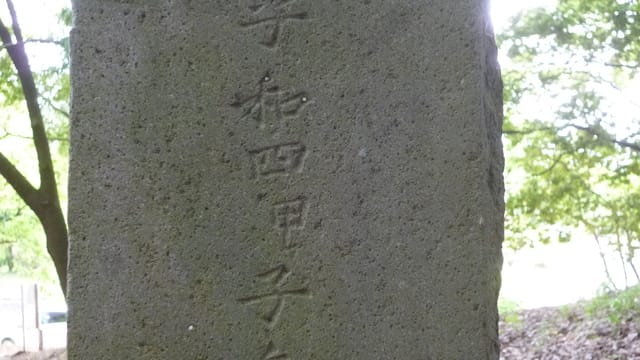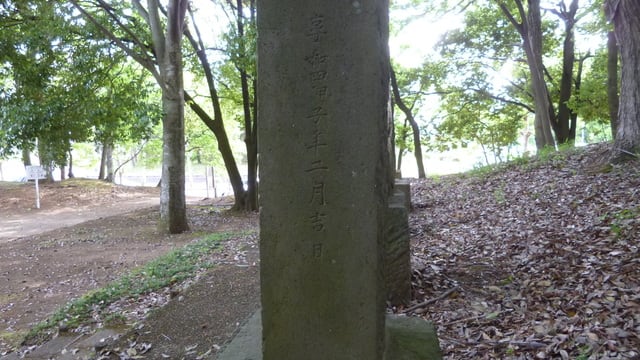雨曇子「三河高浜方言集“じゃんだらりん”見せて頂きありがとうございました」
謙三「方言を集めた岩月三則サは、蒐集途上でノウナラシタモンデ、
遺志を引き継いだ奥さんの三代子さんが自家出版シタダゲナゾン」
雨曇子「ホッカン。立派な装丁でヨウヤラシタナン。題名もかっこいいジャン」
謙三「高浜弁は語尾に“ジャン”“ダラァ”“リン”がヨウ付くだガン」
雨曇子「この辞典を見て、ダチャカン(駄目だ・埒が開かない)タルイ(疲れた・物足りない)タアケ(馬鹿者)
ドッチカテヤァ(どちらかといえば)トットイテクレン(貰っておいて下さい)ナリ(形・恰好)
など、ワシも三河生まれダデ懐かしい言葉か多く目に付いたゾン」
謙三「ホッカネ。ワシも東京に出て長いモンダデ、ふだん三河弁は使わないけれど、
三河弁は体に染み込んでいるみたいダガネ」
雨曇子「お互いに、ホダナン」

(とんこつラーメン店の壁に貼ってあった熊本方言の暖簾)
三河高浜の方言
びり ドベ
お前たち オンシガトウ
たくさん ヨウケ
苦しい エライ
少し チイタア
困る ドオモナラン
早く チャット
欲しいだけ ドイダケデモ
雨曇子「ところで、平昌(ピョンチャン)オリンピック、見トラセタカン」
謙三「毎日、ヨー見トッタガネ」
雨曇子「カーリング娘が連発していた“ソダネー”
三河弁なら“ホゥダネー”ダラー?」
謙三「ホゥダヨ」