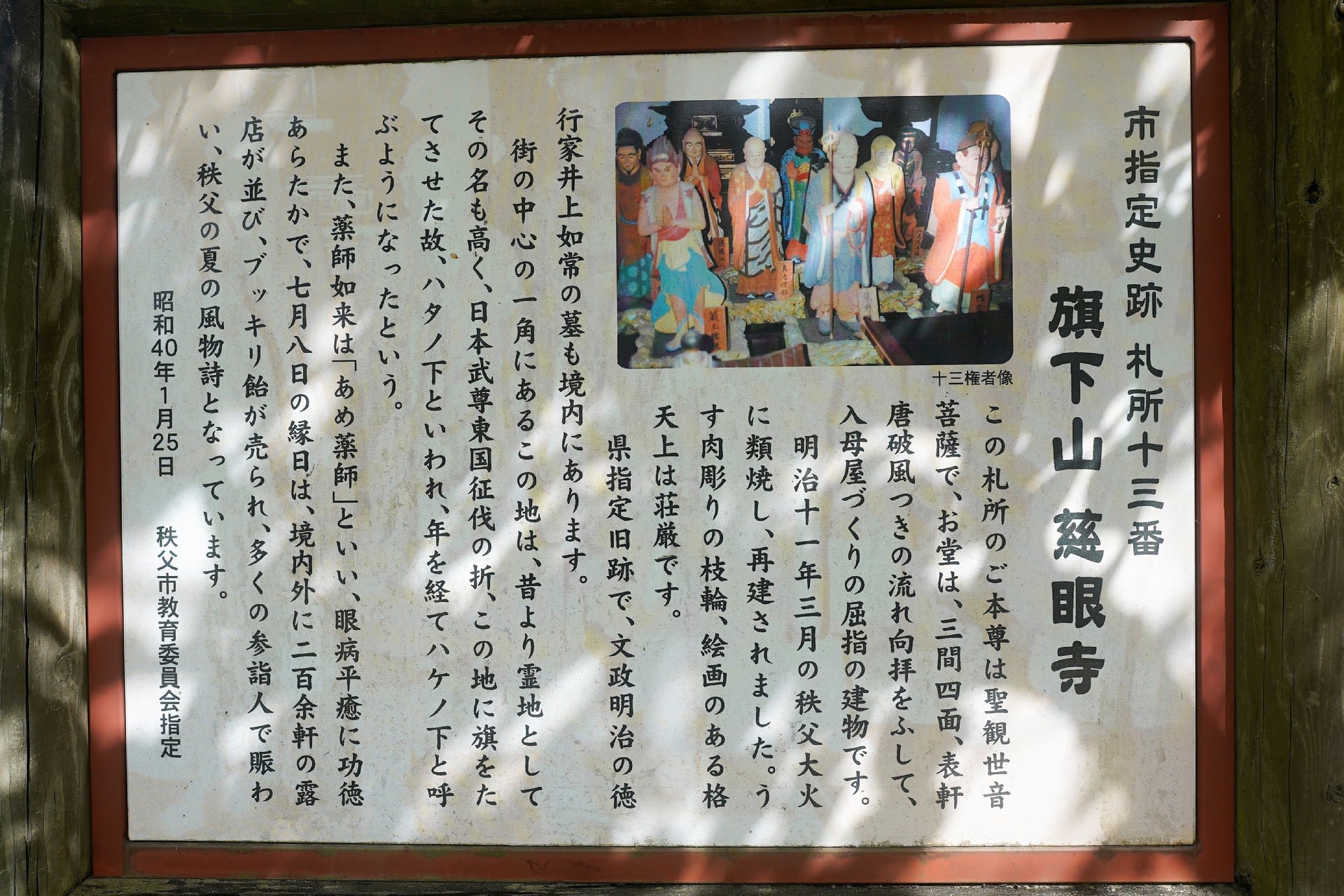寺伝によると、807年、伊予親王(淳輪天皇の弟)の菩提を、
弔うために遍照僧正がこの地の領主に堂宇を作らせたとある。
弔うために遍照僧正がこの地の領主に堂宇を作らせたとある。
旧蒔田村・清水谷の山奥に草創され、花台山と呼ばれ、
915年、村の子供たちの間で疱瘡(天然痘)が流行し、
寺の場所を移すよう観音様からのお告げがあって、
里たちの住むこの場所に移して、
観世音に平癒を願ったら、天然痘は威力を失い、
以来、病魔に犯された子供は、観世音に祈って救われて以来、
以来、病魔に犯された子供は、観世音に祈って救われて以来、
童子堂と呼ぶようになる。
誰が彫ったか、子供にも好かれるフォルムで、仁王像。


👇広い寺域の仁王門の虫食いの柱や、
猫(?)肉球もまた素朴で、
猫(?)肉球もまた素朴で、



好物のネギに挨拶すれば、藤棚、右手に堂宇が。

👇江戸中期・1701年、江戸の田井三右エ門弘祐と、
その女房、お銀が施主となって、
秩父府坂峠の地に再建したもので、
秩父府坂峠の地に再建したもので、
1910年、この土地に移築された、
極彩色豊かにして華麗な、秩父札所22番、童子堂。




天井には、
👇迦陵頻伽(かりょうびんが)の浮彫りが施されていて、
納経所の人影を確認し、周りを見回し、
納経所の人影を確認し、周りを見回し、
1枚だけ撮りたいなァ~・・
でも、やめた ‼
でも、やめた ‼
張り紙がマナー違反を、強烈に戒める ‼





明日は、古河市へ日帰り出張
明日は、陽が射すとなれば、気も晴れ
明日は、陽が射すとなれば、気も晴れ
今夜の寒さの、賄いは
湯豆腐にゴマ入りの高菜漬けをまぶして
湯豆腐にゴマ入りの高菜漬けをまぶして
ちびッと、八海山で一杯・・ッと
・・・・・
のに、豆腐がない
無い 無い
・・・・・
のに、豆腐がない
無い 無い