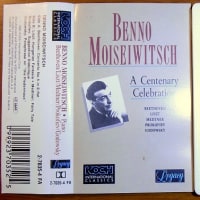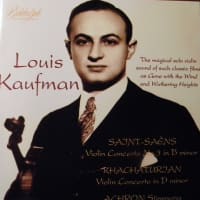ブラームスは晩年に洋琴小曲集を4つ書き残した。合計20曲の小品があるが、作品119-3が僕はとても気に入っている。息の長い独特のうねりを持った旋律、この不思議な魅力に秘められたブラームスの作曲技法の巧みをご紹介しよう。
ブラームスは作品76から作品119までの中で18曲の間奏曲を書いているが、この作品はその最後の1曲である。曲は変則的な3部構成で、主要楽節の反復(第1部)と転調を伴う展開部(第2部)、そして断片的な再現とカデンツ(第3部)から成る。
この作品全体を通じて云えることだが、主旋律は内声部にある。冒頭のE音から13個目までの音符の並びは、音型配合も音階の並びもシンメトリカルな音配列でできていて、再現部で断片が登場する際にもこの部分が使われる。現代のピアノ弾きの多くが、2小節目で区切って3小節目から新たなフレーズとして歌う方法をとっているが、これは明らかに間違いである。この点で、ギーゼキングの解釈は正しい(と僕はブラームスに聞いたかのごとく自信たっぷりに云う)。新しいフレーズは第3小節の第4拍目から始まり、このG音から11個の音配列も先と同様にシンメトリックな構図が発見できる。
ここには詳しく記さないが、シェーンベルクによる音型分類の手法を用いて、この曲を見てみると、鎖状の結合がこの作品のいたるところに散見できる。各小節を音型、動機、楽想の3つの観点で表にすると、一度も縦の直線で区切れる部分がないことに気づく。文法に例えるならば、句読点の無い一文である。うねるやうな息の長い旋律線は、このやうな鎖状の連結法によって生み出されたものであることが分かる。
古典派時代の明快な楽節構造を意識的に回避しようとするブラームスの革新的な態度が窺える。
ブラームスの革新は和声にも見ることができる。ブラームスは、ドミナントの代用にⅢの和音をよく使う。この曲でも第3小節目でⅠからⅢの和音に移ったとき、僕たちはブラームスの憂鬱を感じる。第5小節にもⅢが使われる。そして、もう一つは、トニカの機能をできる限り弱めて使用するといふ注目すべき手法である。
冒頭から12小節の全てのトニカを検証することは無駄ではないと思う。冒頭の堂々としたトニカは、曲全体の不安定な和声進行のためには不可欠なものであるが、これ以降のトニカに注目したい。
第4小節以降に現れるものは次のとおりである。Ⅵ7(Ⅰ7)、経過的なⅥ→Ⅰ、a-mollに転調後のトニカは全て第2展開形といった具合である。このやうに見てみると、句読点の無い旋律線の誕生は、この特殊な和声法と共にあると云へよう。
こういった意味において、ギーゼキングのこの作品で見せる演奏解釈は素晴らしいもので、他のピアノ弾きとは一線を画す。
参考資料は、A.Schonberg「音楽の様式と思想」、Fellinger/Kraus Brahms OP119原典版、音楽芸術:1978-9~12「ロマン派のピアノ曲」、tenten's father「ブラームス ピアノ小品集作品119の分析」、コロムビアLP:ギーゼキング=ブラームス小品集
ブラームスは作品76から作品119までの中で18曲の間奏曲を書いているが、この作品はその最後の1曲である。曲は変則的な3部構成で、主要楽節の反復(第1部)と転調を伴う展開部(第2部)、そして断片的な再現とカデンツ(第3部)から成る。
この作品全体を通じて云えることだが、主旋律は内声部にある。冒頭のE音から13個目までの音符の並びは、音型配合も音階の並びもシンメトリカルな音配列でできていて、再現部で断片が登場する際にもこの部分が使われる。現代のピアノ弾きの多くが、2小節目で区切って3小節目から新たなフレーズとして歌う方法をとっているが、これは明らかに間違いである。この点で、ギーゼキングの解釈は正しい(と僕はブラームスに聞いたかのごとく自信たっぷりに云う)。新しいフレーズは第3小節の第4拍目から始まり、このG音から11個の音配列も先と同様にシンメトリックな構図が発見できる。
ここには詳しく記さないが、シェーンベルクによる音型分類の手法を用いて、この曲を見てみると、鎖状の結合がこの作品のいたるところに散見できる。各小節を音型、動機、楽想の3つの観点で表にすると、一度も縦の直線で区切れる部分がないことに気づく。文法に例えるならば、句読点の無い一文である。うねるやうな息の長い旋律線は、このやうな鎖状の連結法によって生み出されたものであることが分かる。
古典派時代の明快な楽節構造を意識的に回避しようとするブラームスの革新的な態度が窺える。
ブラームスの革新は和声にも見ることができる。ブラームスは、ドミナントの代用にⅢの和音をよく使う。この曲でも第3小節目でⅠからⅢの和音に移ったとき、僕たちはブラームスの憂鬱を感じる。第5小節にもⅢが使われる。そして、もう一つは、トニカの機能をできる限り弱めて使用するといふ注目すべき手法である。
冒頭から12小節の全てのトニカを検証することは無駄ではないと思う。冒頭の堂々としたトニカは、曲全体の不安定な和声進行のためには不可欠なものであるが、これ以降のトニカに注目したい。
第4小節以降に現れるものは次のとおりである。Ⅵ7(Ⅰ7)、経過的なⅥ→Ⅰ、a-mollに転調後のトニカは全て第2展開形といった具合である。このやうに見てみると、句読点の無い旋律線の誕生は、この特殊な和声法と共にあると云へよう。
こういった意味において、ギーゼキングのこの作品で見せる演奏解釈は素晴らしいもので、他のピアノ弾きとは一線を画す。
参考資料は、A.Schonberg「音楽の様式と思想」、Fellinger/Kraus Brahms OP119原典版、音楽芸術:1978-9~12「ロマン派のピアノ曲」、tenten's father「ブラームス ピアノ小品集作品119の分析」、コロムビアLP:ギーゼキング=ブラームス小品集