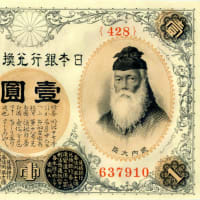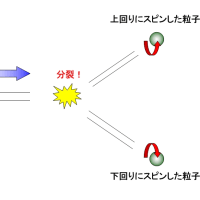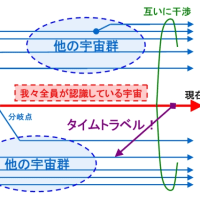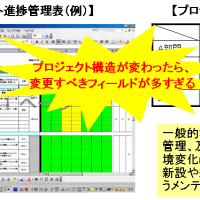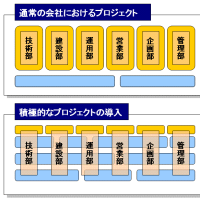「No」と言えない日本。
優柔不断で、言うべきことを言えず、自分をもたずに周りに振り回される。「No」と言えないことは、主体性がないという意味と捉えられてしまい、非常にマイナスに評価され、批判されるものです。
今日、ある人とディズニーランドについて話をしました。どうも、香港のディズニーランドはあまりうまくいっておらず、それは中国人にディズニーキャラクターが浸透していないことが原因らしいのです。中国だけでなく、ヨーロッパもディズニーキャラクターの浸透率は悪く、その人曰く「独自の立派な文化を持っている国で、ディズニーは受け入れられにくいらしい。日本は、主体性がないから、何でも受け入れてしまって、結果としてディズニーがうまくいっているようだ」とのこと。果たして、本当でしょうか。
たしかに日本人は、相手の文化を取り込むことに長けていると思います。しかし、それは主体性がないといったネガティブな意味ではなく、むしろ相手を安易に否定せず、まず認めることから始めているからではないかと思うのです。たとえ、相手が間違っているとしても、頭ごなしに「No」とは言わない。相手を思いやり、相手に気遣う寛大な心を持っているからこそ「No」とは言わないのではないでしょうか。
あるお坊さんから「真理の葛藤」という言葉を聞きました。口にした瞬間、嘘になるから口にはできない。真理でありながら、それを口外した瞬間に嘘になってしまう、ということだそうです。
例えば、ここに寛大な心を持った人がいるとします。その人は、そのことを十分に認識していますが、彼はそのことを決して口にしません。口にしないが真理です。しかし真理だからといって、自分が寛大であると口にした瞬間、結果として相手を狭小だと批判してしまうことになり、自分が寛大でなくなってしまうため、これが真理ではなくなります。
本当のことだが、言った瞬間に本当ではなくなる。これが「真理の葛藤」ということです。
日本人とは、そういう「真理の葛藤」を抱えた人たちではないでしょうか。たとえば日本人の多くは無宗教です。したがって、世界のいろいろな人たちの考え方を聞き入れることができ、それに多少違和感を覚えようが、自分の信念とは若干違っていようが、黙ってそれを聞いてあげられます。立派に寛大な心の持ち主であると思うのです。しかし、自分たちが、そういう人間であるということを自ら口にすることはありません。だから、そうした姿勢に対して、「主体性がない」といったネガティブな評価にも反論せず、黙ってそれを受け入れることができるのです。
こうした相手を受け入れる精神は、例えば城の造りにも表れていると思います。
海外の中世や近世の戦争においては、勝った者が負けた側の人民を皆殺しにしたり、奴隷にするのが一般的です。立て籠もる側は、兵士だけでなく、住民を含めて死に物狂いで抵抗をするから、海外の篭城戦は数年かかるのが当たり前となるのです。長いものになると十年以上かかります。通常、町は城壁の内側にあって、敵に包囲されたら、場内では住民も含めて自給自足をして生活をしながら、抵抗をしていきます。
ところが日本は城下町。お城の下に街が広がっています。篭城といっても、住民を巻き込んで、1年も2年も持ちこたえるような仕組みにはなっていません。勝った側が、住民を皆殺しになどしないため、そのようなことが成り立つのです。即ち、日本での戦争は、海外ほど徹底した敵国殲滅を行っておらず、もともと相手を認める、受け入れることができる素地をもっていたと言うことができると思うのです。
長い歴史のなかで、戦争を繰り返すことはあっても、日本人の考え方の根底、奥底には、このように相手を受け入れるという寛大な精神が宿っており、世界的にみて、そうした点は誇るべきよい点ではないかと思います。
一方でこういうことをもってして、日本人は優れた民族であるなどと言う必要もありません。広く、相手のことを受け入れる。たとえ、自分のことを悪く言う隣人に対しても、耳を貸して黙って聞いてあげる。いろんな価値観を認めてあげているのだから、それだけで十分です。いちいち、口に出して言う必要もありません。
このように、「No」と言えないのは、安易に相手を否定しないという優しさの表れだと思うのです。間違っている相手に対しても、「No」と言わずに、一通り聞き、相手を認める姿勢を示してあげる。それは優柔不断ではなく、積極的に相手を認めようとすることの表れでしょう。
相手をいたわる、察してあげる、言わなくても思ってあげるということは、人間として非常に大事なことです。ただし、このことが「No」と言わないという決まりとして表面化させる場合、このルールでコミュニケーションをするには、「No」と言われなかった側にも、相手をいたわる、察してあげる心を持つことが求められます。
「Noと言われなかったから、自分は正しい」などと思わず、「何故、相手はYesと言わなかったのか」と察する力が求められるわけです。相手が「優しさ」をもって、「No」と言わなかったことに対して、自分も「優しさ」をもって相手の気持ちを察しなければならないのです。
ところが、今の世界では、「Yes」と「No」を明確に言うことがグローバルルールとなってしまっています。日本人が「優しさ」をもって、「No」と言わないことについて、そのことに落ち度があるとされ、そこにつけ込まれてしまうのが、今の社会のルールになってしまっているわけです。何とも寂しい世界ではないでしょうか。
「優しさ」には「優しさ」で返す。「No」と言われなくても、相手の気持ちを察する心を持ち、謙虚に自分を見直していく姿勢を持ち続ける。人間のあり方として、「Yes」と「No」を明確にするのではなく、むしろ「Yes」と「No」をはっきり言わないことの方が大切であり、本来そちらがグローバルルールになるべきではないでしょうか。