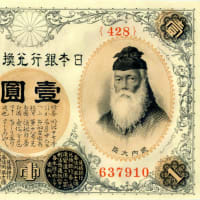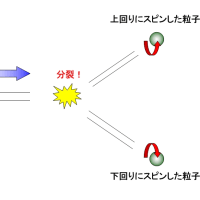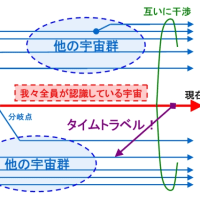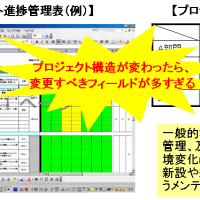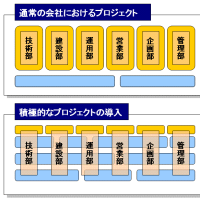報酬は、働いて稼いでいる人にとって労働の証です。したがって、たくさんの報酬を得ている人は、うまく働いている人であるし、裕福な暮らしをできる人でもあります。そしてまた、たくさんの報酬を稼げていると、自分の存在価値をそれだけ多く実感することができるから、その人にとっても自信になります。いい事尽くしです。
しかし、この点ばかりに目を奪われると、本来の報酬の意味を見失います。即ち、報酬は労働の証である前に、感謝や感動の証であるということです。あなたが働いたことによって、それをありがたいと思う人がいて、その人が「ありがとう。これからも頑張ってください」と思うから、お金を出してくれるのであり、その結果が労働の証という名目で、目の前に報酬という現金として現れるのです。
したがって、本来、たくさんの報酬を得ている人は、たくさんの人々に感謝され、多くの人に感動を与える仕事をしている人なのです。これはごく当たり前のことであり、お金や報酬の概念を考える上での原則論とも言えるでしょう。
しかしながら、現実の競争社会ではこの原則論が通じなくなりつつあります。その理由を挙げていったらキリがありません(「人間の優劣と競争社会」、「社会ルールの欠陥」など参照)が、究極的には、この世界が物質世界である以上、人間は目に見えるものに囚われるからと言うことができるでしょう。即ち、自分の存在価値に自信をもつことができない弱い人間は、上述のようにたくさんの報酬を得ていること(さらにそれを数値化し、可視化させること)で安心したがるのです。そこで、原則論を無視した競争が起こるわけです。
多くの人々に感謝されることやたくさんの感動を与えることよりも、他者より多くの報酬を得ることで、自分が優秀であると認められたいという弱い人間の自己防衛と他者攻撃の心理により、競争はさらに激化します。その結果、競争社会で勝ち上がった既得権益者(強者)は自分たちを守るために、自らの手でますます社会システムを硬直化させていくのです。このような社会において、「多くの人々に感謝される仕事」、「たくさんの人々に感動を与える仕事」などと悠長なことを言っている者は、まともな報酬を得ることもできず、たちまち二度と這い上がれない弱者へと転落してしまう恐れがあるわけです。
けれども、この世界は長くは続かないのではないかと思います。労働に携わっている人々は、原則論に立ち返り、必ず「感謝」や「感動」に裏付けられた仕事をしなくてはならなくなるだろうと思うのです。顧客たる消費者を脅すように「この条件を飲まなかったら、仕事はしないぞ」、「この仕事をするから、これくらい払え」というやり方は、通じなくなるでしょう。他に選択肢がないことをいいことに、ある権利やシステムに頼りきったビジネスは、早晩限界を迎え、その有り様を変えていくことになるのではないかと思います。
ひとつの例を挙げましょう。次の一文は、ある音楽業界の関連団体(社団法人私的録音補償金管理協会)が出しているものです。
「今日も私たちが音楽を楽しめるのは、そこに創り手たちの豊かな才能と熱い想いがあるからです。家庭内での「私的な」コピーは一定の条件下で許されていますが、それが全体で膨大な数になればアーティストたちの不利益となり、創作活動を困難にしてしまいます。」
至極、真っ当なことを言っていますが、前提条件として確認しなければいけないのは、今日の高度なデジタル化及びネットワーク化が進んだ現代社会において、音楽ファイルのコピーやその流通を法制度によって統制することは、事実上不可能であるということです。その意味で、上の記述にあるように「それ(コピー)が全体で膨大な数」になることは、時代の潮流であり、避けることはできないと言えるでしょう。
見極めるべき問題の本質は、むしろそういう社会において、創作活動が困難になってしまうアーティストには、そもそも人を感動させる力はないし、その価値もないということです。残酷な言い方になりますが、これからの高度に情報化された社会において、そういうアーティストは沈むべくして、沈むということです。逆の言い方をすれば、才能あるアーティストは、けっして消えることがないでしょう。
素晴らしいアーティストの作品は、それがコピーだろうが何だろうが、人を感動させる力を持っているわけであり、そんなアーティストが創作困難になったということになれば、ファンの人々が募金でも何でもして、そのアーティストに創作活動を続けさせるはずです。また本当に才能あるアーティストに対しては、聞き手側(ファン達)が彼らにきちんと余裕ある(裕福な)暮らしをしてもらいながら、より良い作品を作ってもらいたいと願うでしょう。結果として、より多くの人々にたくさんの感動を与えられるアーティストに潤沢な資金が集まり、彼らが裕福になると同時に、素晴らしい作品を創ってもらえる環境が整っていくのです(問題の本質は、現代の社会システムが、そういう仕組みを用意しきれていないことである)。
ラジオ、テレビ、CD、DVD・・・。こうした媒体から、さまざまなコンピューターとそれらを繋ぐネットワークの発達という大きな環境の変化が起こっているなか、それらの技術を駆使して、きちんと人々に愛される仕事をしているか、感動を与えようとしているかが問われる時代に入ったのだろうと思います。
新しい技術によって、社会の仕組みが大きく変わるとき、人々はそれぞれの労働や報酬の意味を見つめなおすべきではないかと思います。自分が得ている報酬は、労働の価値に対する感謝の証なのか。自分は本当にあらゆる手を尽くして、人々に感動を与える仕事ができているのか。そうした個人個人の問いかけが、次の時代を創る大きな原動力になるのではないかと思うのです