
聴き始めた途端に感じる違和感はコルトレーンのサックスの音がまるで別人のようなリバーブフルな音色に変わっている事だ。瞬間、ミックスの失敗を確認し、聴き進めるのが嫌になった。しかもキーがオリジナルLPと違うように聴こえるのも不自然だ。CDの最初に収録された「dearly beloved」の違和感はこの2枚組アルバムの最後まで続く。コルトレーンのサックスを前面に押し出すミックスがなされ、実際、マッコイ・タイナーがバッキングに回る時の音量がLPより小さくなっていると感じる。何故、このような音処理を施したのか。これまでもコルトレーン諸作品の数々の‘コンプリート’ものをリリースしてきたImpulseが今回、下手を打った。謎だ。クレジットにはHigh-resolutionでマスタリングされた旨のクレジットがあり、元々、ハイレゾになど殆ど関心外な私としてはますます、そのような新技術への不信感が増すだけであった。その違和感はdisc 2のしょっぱなのスタジオでの会話に続く、「ascent」のジミー・ギャリソンのベースソロの音色でも再び顕在化する。ダークでやや籠りがちなトーンの録音が多いギャリソンのベースがここでは中・高音域が強すぎて弦を弾く時に生じている指盤の振動音までクリアに再生されてしまっており、聴き苦しい。粒立ちを強調しすぎた失敗例だろう。もっと音が籠っていても全然、問題ない。むしろそのほうがギャリソンのファットなサウンドに近いと思う。ギャリソンの持ち味はローエッジでグレイトーンとも言うべきその重低音の響きにこそあると思っているので、ミッドが強調された今作でのミックスはギャリソンの実際の演奏とかけ離れていると感じてしまうのだ。その意味で今作『Sun Ship: the Complete Sessions』はもはや、リミックスアルバムといった様相を呈すのである。
アルバムの内容は『Sun ship』録音時(1965.8.26)のドキュメンタリー音源2枚組。例によってレコーディング時の正規収録音源と、セッション音源を網羅した内容だが、国内版が見送られたのは、未発表曲がない事と各テイクの内容が正規音源との差異が少なく商業性に欠けると判断された事がその理由かもしれない。確かに変化に乏しいアレンジによる同一ナンバーを3曲も4曲も羅列されても聴く方としては面白くもなんともない。これを買うのは私のようなコルトレーンマニアだけだろう。
つまりオリジナル『sun ship』(リリースは71年)に収録された「sun ship」「dearly beloved」「amen」「attaining」「ascent」の各曲は異なるアレンジのテイクや違う解釈の演奏は存在せず、ほぼ統一されたイメージの‘ソング’であった事が判明する。従来、楽曲を変形させ、演奏されるたびに全く違う様相を見せる事が多いコルトレーンの録音音源が『sun ship』では各曲がオリジナルとして、外しようのないコンセプト、曲想を用い、そればかりかテーマ後のアドリブ、ソロに於いても似通ったテイクを残している事に、この当時のコルトレーンについて言われるレギュラーカルテットによる創造の限界を仄めかすものが感じられるのも事実だ。或いは一方でこの時のコルトレーンがグループサウンドとしてのイメージが確固として存在し、他のバージョンを成立させる余地がない完成へと向かっていたと考えられなくもないだろう。録音時がバラバラなもので構成される事も多いコルトレーンのアルバムだが、この時のコルトレーンは一つのアルバム制作を前提としたセッションを行った。その意味でオリジナル『sun ship』はコンセプトアルバムであり、神聖感あふれるネームを各曲のタイトルにした統一感を見てもそれは伺える。
‘黄金のカルテット’と呼ばれるレギュラーカルテット(コルトレーン、エルビン・ジョーンズ、マッコイ・タイナー、ジミー・ギャリソン)崩壊への過程、そのメンバーによる最終期の演奏記録とされる同アルバムは、コルトレーンの音楽性がアドリブから即興へと変化する過渡期の記録とされている。これより2ヶ月前、集団即興による『ascension』の録音があった。ただし、留意するべきは「ascension」もクレジットはcomposed by john coltraneとなっており、即興という瞬間運動にもその楽曲性を求めていた点だろう。テーマとは言い難いような四小節ばかりのオクターブによるリフをcompositionとみなすその‘主題性の希薄さ’をしかし、コルトレーンは意識的に当時のフリージャズ・ムーブメントとのぎりぎりの‘相違’として最低ミニマムな主題の存在として残存させたのかもしれない。その継承は『sun ship』のタイトルナンバー「sun ship」や「amen」にも見られるが、一見、ここではテーマ自体がアドリブに移行する為のイントロのような機能になっており、私たちはひたすらその激しいアドリブに身を任せ、テーマの存在、即ち楽曲性を見失うような感慨にとらわれてしまう。しかし考えようによっては、この2曲がコルトレーン独自の祈祷的な雰囲気を醸し出す重厚な歌そのものである「dearly beloved」、「attaining」と共存する事によって、アルバム全体のバランス感覚につながっていると感じられる。このバランス感覚はImpulseでの初スタジオ盤である『coltrane』(62)に実は類似しているとも考えられ、以来、一貫したコルトレーンの静と動という対比が一つの作品でバランスよく配置した時の成功例とも言えるかもしれない。実際、『sun ship』は私の大好きなLPの一つだった。
「コルトレーンは構造的に聴かれず、オーラが聴かれていた」
とは立ち読みした何かの本の中で菊地成孔氏が語っていた言葉だが、私自身もコルトレーンの音楽を構造的に聴いた事はない。と言うか、楽理に弱い私がそもそもそのような聴き方ができる訳がなく、その事が例えばマイケル・ブレッカーのコルトレーンとの近似性という巷で言われる‘常識’にも付いていく事ができず、かなり以前、日本のあるサックスプレイヤー(名前は忘れました)が「『blue train』(57)までのコルトレーンはサックス奏者として完ぺき」と言ったその言葉を俄かに信じがたい気持ちに至った事も同時に思い起こさせるのであった。むしろボブ・ディランにコルトレーンとの類似性を信じて疑わない私の‘オーラ至上主義’から言うとコルトレーンはそのオーラ以外の音楽構造的な視点など、持ちえようのない付属物であると極論しかねないほどのその聴き方は偏ったものであったと言えようか。
しかし『sun ship』に漂うこの霊性というか聖なる神秘的環境を体験すれば、この陶酔の深淵に身を沈める快楽をさて置いて音楽構造的な関心に向かうのは、よほどクールな客観主義者や演奏家か研究者の類だけでしょうと言いたくなるのだが、当のコルトレーン本人の最大の関心事はコード理論を含む音楽の構造的な理解による表現の幅の追及であった。その事はコルトレーンの様々なインタビューでの発言を注意深くみると、はっきりするコルトレーンの特質である。つまり、コルトレーンは決してオーラ主義やコンセプトを先行させないところにこそ、オーラの自発的生成の根っこがあると思われる。
感情表現、精神性、聖性、それらはそれ自体から生まれるものではない。むしろコルトレーンの音楽にいつも感じられる‘精神的な中心性’の 存在を私は彼の音楽至上主義的な性格に由来される特徴とみている。コルトレーンの関心事は尽きない音楽理論への学習であり、それをベースとし、そこにあらゆる‘想い’を演奏のリアルタイムに交差させた結果、何かとてつもないオーラを纏った音楽が創造された。それがコルトレーンミュージックの概観ではないか。
『Sun Ship: the Complete Sessions』に話を戻そう。今作は以前のコンプリート・シリーズに比べ、その内容が乏しいにも関わらず、二枚組という時間の長い作品になっている。従って通して聴くと変化の無さに退屈を覚え、嫌気がさすのが正直な感想で正規採用トラックだけを拾いながら聴くと、改めてオリジナル『sun ship』の素晴らしさの発見がある。
つまりこのアルバムが、「至上の愛a love supreme」(65)に続くコルトレーンによる第二のコンセプトアルバムとして制作されたものだったという事の再発見である。尤も録音時はリリースされず、死後になって初めて明るみに出たのであるが。お蔵入りになった理由は分からないが、少なくとも全トラックが共通のムードを持つ連続されたコンセプトに基つくもので、しかも同日演奏で一気に録音された事から、コルトレーンの意思は個別のトラック録音ではなく、アルバム制作という意識の元にあったと思われる。
「至上の愛a love supreme」(65)以降のコルトレーンのスタジオ録音と正規音源としてリリースされた作品を確認すると「John Coltrane Quartet Plays」(65)、「Kulu Sé Mama」(66)、「Ascension」(66)に続くのが当アルバム「Sun ship」だが、留意しなければならないのはこれが71年までリリースされなかった事だ。「John Coltrane Quartet Plays」や「Kulu Sé Mama」は録音日がまばらなトラック集で、統一されたコンセプトアルバムとしての性格はなかった。或いはこれも録音時はリリースされず、70年にリリースされた「Transition」という素晴らしいアルバムがあるが、「Kulu Sé Mama」と重複するトラックがある、やはり、これも傑作ではあるがオムニバス的なアルバムだった。
その意味で「Sun ship」は「至上の愛a love supreme」で成果を示したコルトレーンによるアルバム単位でのメッセージを発信する第二のコンセプトアルバムであった。ジャズ演奏家の一般意識は演奏に集中され、それがライブアルバムの多さに際立って現れるジャンル的特質だが、コルトレーンの「至上の愛a love supreme」がジャズファン以外の多くのリスナーからの支持を得ているのも、それがロック的なコンセプトアルバムであり、しかも60年代後半以降のアートロックやプログレッシブロックに共通する大作志向を持っている点であったと思う。そして「Sun ship」の内容も全編に祈祷的なムードが漂う神聖な環境と即興演奏の力感が融合された重厚なアルバムとなっている。それは正しく「至上の愛a love supreme」に通じるトータル性を持った力作である。
にも関わらず、このような素晴らしいアルバムが当時、リリースが見送られた。理由は分からないが、Impulse上層部による‘非商業的’という判断、或いはコルトレーン自身に因る作品の完成度への確信の無さだったのか。コルトレーンの中に「Sun ship」によって「至上の愛a love supreme」を超える、或いは異なる特質を得るべく意識があり、果たしてそれを実感できなかったのかもしれない。「至上の愛a love supreme」に続く正規リリース音源は前述と通り、「John Coltrane Quartet Plays」(65)、「Kulu Sé Mama」(66)、「Ascension」(66)であった。それらは「至上の愛a love supreme」とはコンセプトを異にするアルバムでしかも、各々が異なる作風であった。このようにコルトレーンはimpluseから時折、持ちかけられる企画的な制作は除いて、ほぼ一貫して自発的なスタジオセッションによるアルバムの変化と進歩を自らに課していた事が窺える。そのような立場に立つ時、「Sun ship」が「至上の愛a love supreme」と同様な祈祷、信仰をコンセプトを持ちながら類似を避け、差別化を図るなにか異質なもの、進化の証をコルトレーンが自らに課したであろう事は想像に難くない。結論的に言えば、その成果に至らなかった。その事がコルトレーン自身にリリースを躊躇させた。そのような推測も成り立つのではないか。思えばコルトレーンが自ら意識し、また絶えず聴き手を惹きつける大きな要因は、一つの曲、一つの演奏の中で限界を少しずつでも超えようとしてゆくリアルタイムな意思がビリビリ伝わる点であった。コルトレーン以上にその事を感じさせるアーティストはいない。私の推測もつい、そんな高い物差しでコルトレーンを見てしまう結果なのかもしれないがまた、留意すべき点として「Sun ship」がエンジニアであるRudy Van Gelderが録音に参加しなかった唯一のアルバムである事だが、その事がリリースが見送られた事と関係しているのかもしれない。
不可解ながらリリースが見送られた「sun ship」。しかしそこに収められた5つのトラックはそれぞれが素晴らしい輝きを有している事に疑念の余地はない。
サックスによる重厚なテーマで始まる「dearly beloved」はコルトレーンによるメロディの演奏でほぼ、占められ、バンドはフリースタイルにバッキングするという感じ。「attaining」もやはり、神聖なダークトーンに満ちたメロディを朗々と響かせ、途中ピアノ、ドラム、ベースによる疾走するパート、ドラムソロに移行するが、やがてコルトレーンによる重厚な‘歌’に戻る。この2曲に共通するのはいずれもコルトレーンによる即興、ソロパートが存在しない事だ。テーマ、フリーキーなソロ、テーマという常套的パターンがここにはなく、あくまで主題を歌い上げるコルトレーンのメロディプレイが際立っている。祈祷の雰囲気が漂う正にコルトレーンの歌が「dearly beloved」と「attaining」で顕在化した。そしてその味わい深さはメロディを歌いながら、緩やかに変形させる妙技にあるのだが、その点も「至上の愛a love supreme」で完成させた確定されたメロディを起点とする逸脱と反復の即興があると思われる。歌いながらそれを異化させるインプロビゼーション。フリーキートーンに走るだけが即興ではないという事だろう。
逆にアルバムタイトルナンバーである「sun ship」は「dearly beloved」と「attaining」に対する見事な対比を成すハードエッジな即興ナンバー。速いパッセージを持つリフを基点としてバンド全体のゴツゴツした感触の即興演奏が展開される。エルビン・ジョーンズのドラムは規則性からはずれ、ランダムに刻まれるスネアのアクセントによるトラック全体の硬質感を先導するようだ。sun ship=太陽の船というタイトルに遥かアフリカ大陸の太陽信仰のイメージを抱くが、曲調が激しく、むしろ宗教的厳粛さは感じられず、混沌とした異界といった様相を呈するナンバーだ。
ジミー・ギャリソンのベースソロに導かれ始まる「ascent」はギャリソンの自由なソロというよりも8分後に登場するコルトレーンの出だしのテーマを導く同一のフレーズが基調になっており、文字通り、イントロダクションとして機能している。『Sun Ship: the Complete Sessions』(2013)には正規音源の他、同トラックのベースソロの部分を何度もやり直した音源が5つも収録されており、これが謎なのだが、このように繰り返し、演奏を行ったのは5つのテイクになるほど微妙な違いがあるのだが、おそらくは8分後にスタートする全体演奏に対応する主題性を持ちえたか否かというポイントがあったのだろう。<False starts>とケレジットされており、スタートの失敗、即ちコルトレーン、エルビン、マッコイの三人の出だしがつまずいたテイクとして没になったようだが、よく聴くともっと大きな違いがある事にも気がつく。それは正規採用の音源の素晴らしさに感じられるどこか非―情熱的なクールネスに満ちたコルトレーンの演奏なのだ。没テイクはギャリソンのベースによる主題を受け継いでエモーショナルに疾走するコルトレーンの演奏が感じられるのに対し、正規採用音源では素晴らしく客観的理性に満ちた平衡感覚ともいうべき冷静さが伺えるのである。Eフラットから朴訥な表情で上がってゆくこの変哲ないフレーズの平坦なムードが曲全体から醸し出されるこのテイクは素晴らしい。無表情さが曲全体を覆い、その中で演奏者全員がぎりぎりのクライマックス手前までそのエモーションを導き、緊張感を出しているのである。曲はベースのまたしても朴訥なフレーズでストンと終わる。まるで何もなかったかのようなムードを残しながら。
アルバムラストの「amen」は当時、黄金のカルテットの最後期からメンバーチェンジを経て固定化される新クインテット、即ち、コルトレーン、アリス、ファラオ・サンダース、ギャリソン、ラシッド・アリの時代に於ける演奏法の典型である‘短いリフから集団即興へ移行する’というパターンの萌芽とも思えるナンバーである。このあたりは「至上の愛a love supreme」で完成した印象深いメロディを主題に持つ作風に比べ、テーマ性の希薄が感じられるが、その分、即興パートでの重層的なリズムの応酬という全員による意識がより演奏の幅を広げる結果になっていることも見逃せない。エルビン・ジョーンズのドラムの激しさ、そのゴツゴツ感覚はリズムのキープをライドシンバルに基礎を置くタイム感から離れたパーカッシブなものだ。ただ、聴いていて、その心情や如何ばかりかという思いに捉われるのも事実で、コルトレーンの流動的なコンセプトに追いつこうとする必死の姿にも映るのである。そのやけくそパワーとも言いかねないようなやや、無秩序な攻撃性にエルビンの本来の整合性とは乖離した場所へ行こうとするコルトレーンとの僅かな距離を感じる。
1965年8月26日に録音されたアルバム「sun ship」。その一週間後に「first meditation」の録音があり、9月上旬にスタジオでお蔵入りとなる曲「joy」を録音し、これが結果的に黄金のカルテットによる最後の演奏になった。同月、ファラオ・サンダースが加入し、11月にはラシッド・アリがセカンド・ドラマーとして加入。エルビン・ジョーンズはマッコイ・タイナーと共に脱退する。
私は『Sun Ship: the Complete Sessions』を2回、聴いた後、オリジナルLPを聴き直したが、やはりオリジナルの方が優れている。先述した音質面は言うに及ばず、オリジナルの曲順「sun ship」「dearly beloved」「amen」「attaining」「ascent」がやはり絶妙である事に気付く。CDでは「dearly beloved」「attaining」「sun ship」「ascent」「amen」とむちゃくちゃな曲順に配置されており、やはりコンセプトアルバムは曲順をシャッフルしてはいけないという好例になった。
オリジナル『Sun Ship』
これはロックファンをも唸らせる一代コンセプトアルバム。必ずLPで聴く必要がある作品であろう。
2019.1.23



















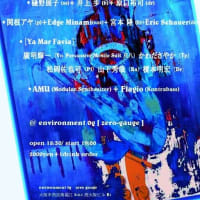






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます