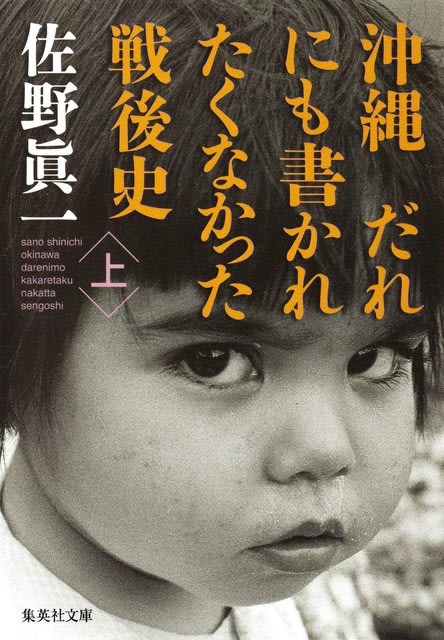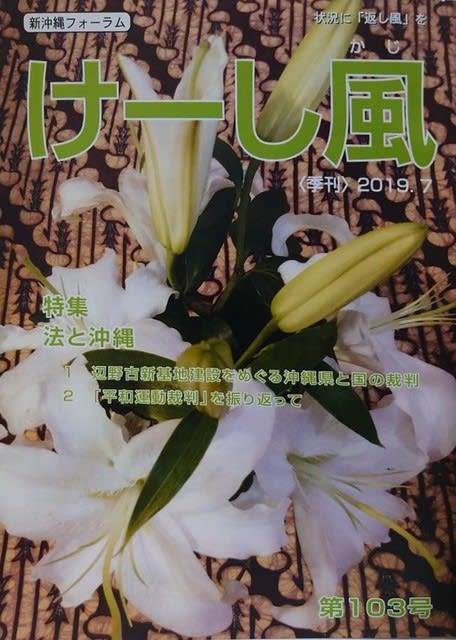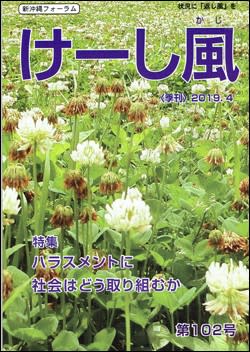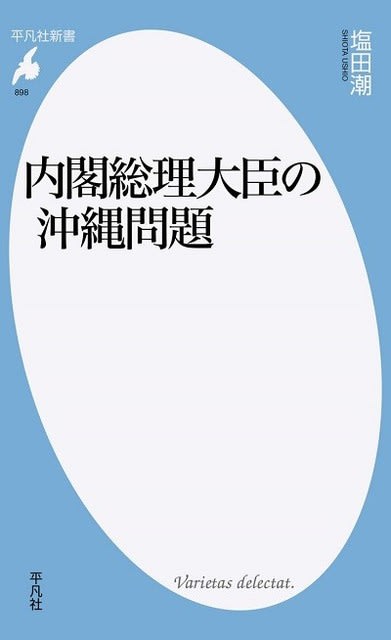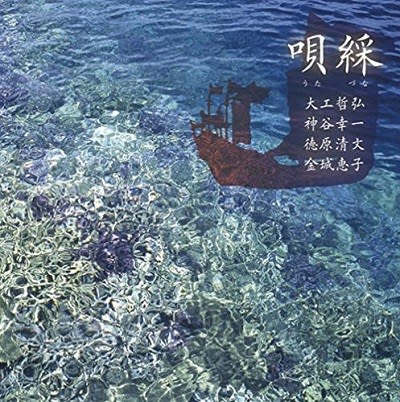NNNドキュメント'20の『封印~沖縄戦に秘められた鉄道事故~』(2020/6/21放送)を観る。

この鉄道とは、1914年から44年まで運営されたケービンこと沖縄県営鉄道の軽便鉄道である(番組では日本語読みを意識したのか主に「けいべん」と発音されていた)。起点はいまの県庁前の那覇バスターミナルにあり、北への嘉手納線、東への与那原線、南への糸満線の3本が走っていた。当時からあった「仲島の大石」は5年前のバスターミナル改築時に撤去されているのだが、その工事の際に、鉄道の向きを回転して変える「転車台」跡が出てきたという。ここで当時を知る方として登場するのが金城功さん。『ケービンの跡を歩く』(ひるぎ社おきなわ文庫、1997年)の著者である(なぜ金城さんも「けいべん」と発音するのだろう)。
ここから何人もの方が登場し、1944年12月11日に起きた鉄道爆発事故について貴重な記憶を証言する。公式な記録は『那覇市史』にしか残されておらず(新聞にも書かれなかった)、それは事故直後から日本軍によって箝口令が敷かれたからだった。同年8月に対馬丸が、また前年12月に湖南丸が米軍により撃沈され、戦争遂行のため情報が出ないよう強制されたように(大城立裕『対馬丸』)。
このドキュメンタリーによれば事故は以下の通りであった。
○犠牲者は221人(『那覇市史』)。うち軍人210人、女学生8人(生存2人)、県鉄職員3人(生存1人)。これは過去最多の犠牲者を出した鉄道事故とみなされてきた西成線脱線火災事故(1940年)の189人を上回る。
○軽便は1943年頃から軍事利用が優先され、一般人はほとんど乗ることができなかった。
○事故が起きた場所は糸満線の稲嶺駅近く、1944年12月11日の15時半~16時半頃。
○6両編成で150人の兵隊を乗せ、嘉手納駅を出発して嘉手納線で南下。那覇駅近くの古波蔵駅で2両が追加され、糸満線に乗り入れてさらに南下する途中のこと。
○煙突から火の粉が出て、それが無蓋車のドラム缶のガソリンに引火し、それが弾薬にも燃え移り、一気に爆発が連鎖した。沿線のさとうきび畑には沖縄戦に備えて弾薬が野積みしてあり、それらも爆発した。積んであった医療品は吹き飛ばされ、巨樹が真っ白になった。なお無蓋車に弾薬を積むことは軍の規制に違反していた。
○100メートルほど先の集落(南風原町神里地区)に人の肉や骨が吹き飛んできた。「戦争が始まった」と勘違いした住民もいた。なお同集落の駐車場には今にいたるまで錆びたレールが放置してあった。
○事故により弾薬等が激減し、「玉砕する他はなき現状」と言った軍の司令官がいた。だがかれも牛島中将と同時(1945年6月22日または23日)に自決した。
○1944年8月の対馬丸撃沈、10月の10・10空襲、1945年4月からの沖縄戦(地上戦)の間に起きた事故であった。
○1983年7月に工事現場から軽便の台車が発見された(説明はなされないが宜野湾市立博物館に展示してあるものだろう)。嘉手納線は今も米空軍嘉手納基地の地下にある。
事実が明らかにされていれば、戦争の行方も世論も変わったかもしれない事故である。このことは今に通じる側面を持っている。
●軽便鉄道
辻真先『沖縄軽便鉄道は死せず』(2005年)
金城功『ケービンの跡を歩く』(1997年)
●NNNドキュメント
『南京事件 II』(2018年)
『南京事件 兵士たちの遺言』(2015年)
『ガマフヤー 遺骨を家族に 沖縄戦を掘る』(2015年)
『9条を抱きしめて ~元米海兵隊員が語る戦争と平和~』(2015年)
『“じいちゃん”の戦争 孫と歩いた激戦地ペリリュー』(2015年)
『100歳、叫ぶ 元従軍記者の戦争反対』(2015年)
『日本地図から消えた島 奄美 無血の復帰から60年』(2014年)
大島渚『忘れられた皇軍』(2014年)
『ルル、ラン どこに帰ろうか タンチョウ相次ぐ衝突死』(2013年)
『狂気の正体 連合赤軍兵士41年目の証言』(2013年)
『活断層と原発、そして廃炉 アメリカ、ドイツ、日本の選択』(2013年)
『沖縄からの手紙』(2012年)
『八ッ場 長すぎる翻弄』(2012年)
『鉄条網とアメとムチ』、『基地の町に生きて』(2008、11年)
『沖縄・43年目のクラス会』(2010年)
『風の民、練塀の街』(2010年)
『証言 集団自決』(2008年)
『ひめゆり戦史』、『空白の戦史』(1979、80年)
『毒ガスは去ったが』、『広場の戦争展・ある「在日沖縄人」の痛恨行脚』(1971、79年)
『沖縄の十八歳』、『一幕一場・沖縄人類館』、『戦世の六月・「沖縄の十八歳」は今』 (1966、78、1983年)