「次何読もうかなぁ」と書棚を見ていたら本書と目が合い読み始めました。
漱石も私の中では読破したい作家の一人ということになっております。

1908年(明治41年)「虞美人草」「坑夫」に続いて朝日新聞に連載した作品です。
初読は思いっきり背伸びしていた小学校高学年時期かも中学生頃だった記憶があります。(そのときも写真の本...だったと思う)
当時は田舎から出てきた大学生を主人公としたビルディングノベル的な理解でそれなりに楽しく読んだ記憶があります。
まったく深く読めていなかったとは思いますが小学生でもそれなりに楽しませるのは漱石の手腕ですかねぇ。
小悪魔的なヒロイン里見美禰子に翻弄される三四郎のラブコメ的読み方もしていたかなぁ。
その当時本作の後に同様な舞台設定(と思われた)鴎外の「青年」を読んでこっちもそれなりに楽しく読めました。
(調べてみたら鴎外は思いっきり「三四郎」を意識して書いたようですね)
その後単純に「三四郎」の続編と思い「それから」に手を出し挫折した記憶があります。
こっちは小学生には厳しかったなぁ….。
最近、「それから」「門」は読んだので、今回本書を読んでこのブログ上漱石の前期三部作制覇です!!
内容紹介(裏表紙記載)
熊本の高等学校を卒業して、東京の大学に入学した小川三四郎は、見る物聞く物の総てが目新しい世界の中で、自由気儘な都会の女性里見美禰子に出会い、彼女に強く惹かれてゆく……。青春の一時期において誰もが経験する、学問、友情、恋愛への不安や戸惑いを、三四郎の恋愛から失恋に至る過程の中に描いて『それから』『門』に続く三部作の序曲をなす作品である。
読後のとりあえずの感想ですが。
「三四郎」中高生の読書感想文の課題図書的に取り上げられていますが、上述したような表面的な読み方はできるでしょうが、一般的な中高生が深く読むには厳しい作品な気がします。
三四郎や美禰子より広田先生的な年になった自分からいろいろ見えてくるものがありました。
小中学生から見ると三四郎他登場人物はみんな年上になるわけでなかなか客観的に見られませんよね。
地方から大学に入ってしばらくは真面目に講義に出て、段々サボりだすというようなところは妙に現代の大学生っぽくてその辺追うだけでも楽しいのですが、多面的に見た方が楽しめる作品な気がしました。
と書いてきて….「まぁ感じ方は好き好きかもしれない」という気もしだしました。
オヤジ視点だと逆に若者に見えてるものが見えないところもあるかと思います。
老若問わず楽しめ、時代を超えているところが漱石の天才性なのかもしれません。
若いうちに読んだ人には是非オヤジ(もしくは淑女?)になっても読んで欲しいものです。
ただ三四郎のあまりのウジウジ感というか自意識過剰ぶりは女性受けしないような気もしますけれど。
ウジウジ感は女の子に声をかけるのにも基本ウジウジする自意識過剰タイプだった私にはとても共感できました。
基本漱石作品の主人公はウジウジ系ですよねぇ、その辺が漱石作品好きな理由の一つかもしれません。
この感想を書いている時点であだち充の漫画を多く読んでいて(「MIX」 1-8)その影響もあり感じたのですが漱石作品の登場人物、シチュエーションもあだち作品同様結構ワンパターンですね。
本作の広田先生と「猫」の苦沙弥先生、「こころ」の先生、「三四郎」の与次郎と「明暗」の小林かなりかぶります…。
美禰子と「坊ちゃん」のマドンナ、野々宮とうらなりなどもかぶっている気がする。
「三四郎」は田舎から都会に出てきて戸惑いますが、「坊ちゃん」は江戸のにおいを残した東京と田舎の伝統社会、赤シャツを代表する近代との間で戸惑う話ですから「坊ちゃん」の裏返し的作品と考えてもいいのかもしれません。
ワンパターンといえば村上春樹も主人公の性格設定など(海辺のカフカ以降の作品は読んでいませんので何ともいえませんが)ほぼ同じキャラのような…。
一つの「形」で多様な世界観を描き出す…才能なんでしょうか?
さて「三四郎」、冒頭の宿屋での女性との一夜からぐっと読者をひきつけます。
絵的にはタッチの上杉達也がはまりそう(笑)、間違いなく草食系ですね。
その後電車の中での広田先生との出会いに(この時は誰だかわかっていない)なりますが、偶然出会ったこの広田先生が三四郎の東京での生活に大きな影響を与える人になります。
現実ではありえない展開なので、自然主義的立場の人たちは怒りそうですが…。
電車の中で広田先生と出会った辺りからこの作品独特の異世界に入り込んでいることを暗示していると理解しました。
電車の中での広田先生の話が全体のモノローグというか予兆として機能している感じです。
恋愛小説的部分は置いて、九州の裕福かつ優秀な青年がそれなりの自負感を持って帝大生として東京に出てくるわけですが、まじめに授業を受けていても何も得ている感じも得られず集団に埋没してしまう感を得てしまう。
それを解決するには余程の才能に恵まれているのでない限り、普通に考えるとコツコツ努力していくしかないわけですが…。(野々宮氏のように)
周りを見ると余程の才能があるわけでもなく、コツコツ努力しているわけでもないのに与次郎や美禰子のように広田先生いわくの「露悪」的に生きることでなにやら自分の位置を確保しているように見える人がいたりもする。(実際に「ある位置」を確保しているのかもしれない)
そんな「露悪」的な人になにやら魅力を感じながらも、九州の地元の「偽善」的文化からも離れられない三四郎は明治の東京で「ストレイシープ」になってしまう。
一方「露悪」的な与次郎・美禰子もどこかで「偽善」的世界から理解や賛美も欲しくて三四郎についついちょっかいを出してしまう…。
また美禰子はコツコツ努力して光の研究で成果を出しそうな野々宮にも惹かれるわけですが、自分の露悪的立ち位置とは相いれないこともわかっていて、野々宮へのあてつけもあり自分のひとことひとことに反応してくれる三四郎にもちょっかいを出してしまう。
それはそれで「ストレイシープ」な状況ですね。
江戸時代的な変化の比較的ゆるやかな時代ならともかく、明治以降の変化の激しい中で価値観がバラバラになっている状況では社会の普遍的な課題といえるのかもしれません。
狂言回したる広田先生は「偽善」から「露悪」への社会の変化を十分認識し分析しているわけですが世の中や人のために動こうという気はありませんし三四郎に対しても「解説」はしていますが、三四郎の行くべき方向は何も示しません….。
冒頭「ビルディングノベル」ということばを出しましたが鴎外の「青年」と違い作品世界を通して「三四郎」はほとんど成長していないように見えます、まぁ「東京」及び近代に戸惑っているだけです。
ただ与次郎・美禰子のように近代世界になんとか折り合いを付け「露悪」していたり、広田先生のように「傍観」しているだけの人より誠実に今を生きているといえる態度のような気はします。
出番は少ないですが、野々宮の妹よし子も「露悪」でも「偽善」でもないある意味企まない「ながれのまま」に生きています。
三四郎もそんなよし子にそこはかとない好意を持っているようにも見えるのですが、美禰子の態度に戸惑い具現化しません。
最終的に美禰子はよし子のお見合い予定の相手と結婚していますので、三四郎だけでなくよし子に対してもなにやらちょっかいを出してしまう気持ちがあったのかもしれません。
同じ「露悪」でも与次郎のそれは陽性ですが、美禰子は何やら陰にこもった闇があるような...。
漱石という男性作家の描く世界ではあるわけですが、意識において性差(善悪・優劣ではない)はあるわけでこの辺も普遍的な課題ですよねー。
「三四郎」いろいろ考えさせてくれる名作です。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
漱石も私の中では読破したい作家の一人ということになっております。

1908年(明治41年)「虞美人草」「坑夫」に続いて朝日新聞に連載した作品です。
初読は思いっきり背伸びしていた小学校高学年時期かも中学生頃だった記憶があります。(そのときも写真の本...だったと思う)
当時は田舎から出てきた大学生を主人公としたビルディングノベル的な理解でそれなりに楽しく読んだ記憶があります。
まったく深く読めていなかったとは思いますが小学生でもそれなりに楽しませるのは漱石の手腕ですかねぇ。
小悪魔的なヒロイン里見美禰子に翻弄される三四郎のラブコメ的読み方もしていたかなぁ。
その当時本作の後に同様な舞台設定(と思われた)鴎外の「青年」を読んでこっちもそれなりに楽しく読めました。
(調べてみたら鴎外は思いっきり「三四郎」を意識して書いたようですね)
その後単純に「三四郎」の続編と思い「それから」に手を出し挫折した記憶があります。
こっちは小学生には厳しかったなぁ….。
最近、「それから」「門」は読んだので、今回本書を読んでこのブログ上漱石の前期三部作制覇です!!
内容紹介(裏表紙記載)
熊本の高等学校を卒業して、東京の大学に入学した小川三四郎は、見る物聞く物の総てが目新しい世界の中で、自由気儘な都会の女性里見美禰子に出会い、彼女に強く惹かれてゆく……。青春の一時期において誰もが経験する、学問、友情、恋愛への不安や戸惑いを、三四郎の恋愛から失恋に至る過程の中に描いて『それから』『門』に続く三部作の序曲をなす作品である。
読後のとりあえずの感想ですが。
「三四郎」中高生の読書感想文の課題図書的に取り上げられていますが、上述したような表面的な読み方はできるでしょうが、一般的な中高生が深く読むには厳しい作品な気がします。
三四郎や美禰子より広田先生的な年になった自分からいろいろ見えてくるものがありました。
小中学生から見ると三四郎他登場人物はみんな年上になるわけでなかなか客観的に見られませんよね。
地方から大学に入ってしばらくは真面目に講義に出て、段々サボりだすというようなところは妙に現代の大学生っぽくてその辺追うだけでも楽しいのですが、多面的に見た方が楽しめる作品な気がしました。
と書いてきて….「まぁ感じ方は好き好きかもしれない」という気もしだしました。
オヤジ視点だと逆に若者に見えてるものが見えないところもあるかと思います。
老若問わず楽しめ、時代を超えているところが漱石の天才性なのかもしれません。
若いうちに読んだ人には是非オヤジ(もしくは淑女?)になっても読んで欲しいものです。
ただ三四郎のあまりのウジウジ感というか自意識過剰ぶりは女性受けしないような気もしますけれど。
ウジウジ感は女の子に声をかけるのにも基本ウジウジする自意識過剰タイプだった私にはとても共感できました。
基本漱石作品の主人公はウジウジ系ですよねぇ、その辺が漱石作品好きな理由の一つかもしれません。
この感想を書いている時点であだち充の漫画を多く読んでいて(「MIX」 1-8)その影響もあり感じたのですが漱石作品の登場人物、シチュエーションもあだち作品同様結構ワンパターンですね。
本作の広田先生と「猫」の苦沙弥先生、「こころ」の先生、「三四郎」の与次郎と「明暗」の小林かなりかぶります…。
美禰子と「坊ちゃん」のマドンナ、野々宮とうらなりなどもかぶっている気がする。
「三四郎」は田舎から都会に出てきて戸惑いますが、「坊ちゃん」は江戸のにおいを残した東京と田舎の伝統社会、赤シャツを代表する近代との間で戸惑う話ですから「坊ちゃん」の裏返し的作品と考えてもいいのかもしれません。
ワンパターンといえば村上春樹も主人公の性格設定など(海辺のカフカ以降の作品は読んでいませんので何ともいえませんが)ほぼ同じキャラのような…。
一つの「形」で多様な世界観を描き出す…才能なんでしょうか?
さて「三四郎」、冒頭の宿屋での女性との一夜からぐっと読者をひきつけます。
絵的にはタッチの上杉達也がはまりそう(笑)、間違いなく草食系ですね。
その後電車の中での広田先生との出会いに(この時は誰だかわかっていない)なりますが、偶然出会ったこの広田先生が三四郎の東京での生活に大きな影響を与える人になります。
現実ではありえない展開なので、自然主義的立場の人たちは怒りそうですが…。
電車の中で広田先生と出会った辺りからこの作品独特の異世界に入り込んでいることを暗示していると理解しました。
電車の中での広田先生の話が全体のモノローグというか予兆として機能している感じです。
恋愛小説的部分は置いて、九州の裕福かつ優秀な青年がそれなりの自負感を持って帝大生として東京に出てくるわけですが、まじめに授業を受けていても何も得ている感じも得られず集団に埋没してしまう感を得てしまう。
それを解決するには余程の才能に恵まれているのでない限り、普通に考えるとコツコツ努力していくしかないわけですが…。(野々宮氏のように)
周りを見ると余程の才能があるわけでもなく、コツコツ努力しているわけでもないのに与次郎や美禰子のように広田先生いわくの「露悪」的に生きることでなにやら自分の位置を確保しているように見える人がいたりもする。(実際に「ある位置」を確保しているのかもしれない)
そんな「露悪」的な人になにやら魅力を感じながらも、九州の地元の「偽善」的文化からも離れられない三四郎は明治の東京で「ストレイシープ」になってしまう。
一方「露悪」的な与次郎・美禰子もどこかで「偽善」的世界から理解や賛美も欲しくて三四郎についついちょっかいを出してしまう…。
また美禰子はコツコツ努力して光の研究で成果を出しそうな野々宮にも惹かれるわけですが、自分の露悪的立ち位置とは相いれないこともわかっていて、野々宮へのあてつけもあり自分のひとことひとことに反応してくれる三四郎にもちょっかいを出してしまう。
それはそれで「ストレイシープ」な状況ですね。
江戸時代的な変化の比較的ゆるやかな時代ならともかく、明治以降の変化の激しい中で価値観がバラバラになっている状況では社会の普遍的な課題といえるのかもしれません。
狂言回したる広田先生は「偽善」から「露悪」への社会の変化を十分認識し分析しているわけですが世の中や人のために動こうという気はありませんし三四郎に対しても「解説」はしていますが、三四郎の行くべき方向は何も示しません….。
冒頭「ビルディングノベル」ということばを出しましたが鴎外の「青年」と違い作品世界を通して「三四郎」はほとんど成長していないように見えます、まぁ「東京」及び近代に戸惑っているだけです。
ただ与次郎・美禰子のように近代世界になんとか折り合いを付け「露悪」していたり、広田先生のように「傍観」しているだけの人より誠実に今を生きているといえる態度のような気はします。
出番は少ないですが、野々宮の妹よし子も「露悪」でも「偽善」でもないある意味企まない「ながれのまま」に生きています。
三四郎もそんなよし子にそこはかとない好意を持っているようにも見えるのですが、美禰子の態度に戸惑い具現化しません。
最終的に美禰子はよし子のお見合い予定の相手と結婚していますので、三四郎だけでなくよし子に対してもなにやらちょっかいを出してしまう気持ちがあったのかもしれません。
同じ「露悪」でも与次郎のそれは陽性ですが、美禰子は何やら陰にこもった闇があるような...。
漱石という男性作家の描く世界ではあるわけですが、意識において性差(善悪・優劣ではない)はあるわけでこの辺も普遍的な課題ですよねー。
「三四郎」いろいろ考えさせてくれる名作です。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










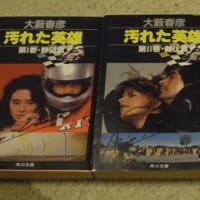
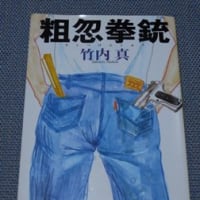
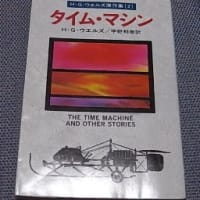
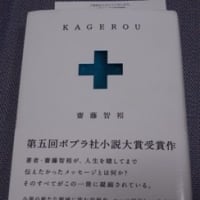
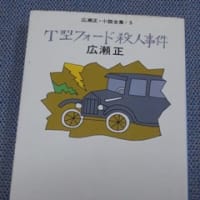
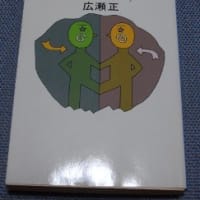


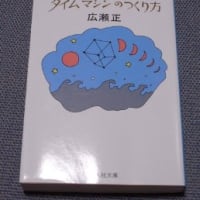
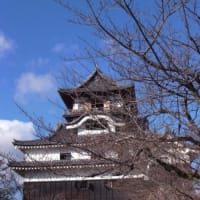
こんばんは!
所帯持ちの書棚ですのでご期待ほど豪快な書棚ではありません(^_^)
昔の本は実家が引っ越すときかなり整理してしまったので随分なくなりましたねぇ…。
今も新しくなった実家の方に昔の本が置いてあったりするので未だに臑齧り感抜けてないかもしれません。
実家には「マーク・トゥェイン自伝」上下など味わい深い本も置きっぱなしな気もしていて気になっていますが妻の眼を考えるとバサッと持ってくるのは厳しいですよねぇ…。