SFが続くと違うものが読みたくなるので本書を手に取りました。
北村薫の「いとま申して三部作」の第二部となります。
第一部の「いとま申して 「童話」の人びと」を読み終わった段階で本書が単行本で発刊されていたのは認識していました。
でも単行本を買うまでの情熱がなくで...文庫が出たら買おうと思いながら忘れていたのですが最近ブック・オフで見かけて購入しました。

購入したのが「無限の境界」を読んでいる最中だったので珍しく入手してから時間空けずにの「読み」となりました。
北村薫作品では「円紫師匠とわたしシリーズ」の「太宰治の辞書」も「文庫出たら買おう」と思っていたのですが、現時点でも未入手なのが気になっています。
(ぼちぼちブックオフで出ていますが新刊で買おうと思っています)
こちらは単行本は新潮からで出ているのに、文庫が創元推理文庫からというのがなんとも北村薫らしいというか....もしくはなにか出版界の事情があるのか....。
また本記事を書くためちょっと調べたら、どうやら4月に「小萩のかんざし-いとま申して3」が出ているようです。
本書を読むのに「いとま申して」を読んでからかなり経っていて(2015年に読んでいたので3年くらい)人間関係などを忘れていて入りこむのに大変だったので「早めに読んだ方がいいかなぁ」とは思うのですが....。
やはり単行本を買うまでには至らないかなぁです。
内容紹介(裏表紙記載)
昭和4年。著者の父・宮本演彦は慶應の予科に通い、さらに本科に進む。教壇に立つのは西脇順三郎や折口信夫。またたびたび訪れた歌舞伎座の舞台には、十五代目羽左衛門、五代目福助が・・・・・・。父が遺した日記は、時代の波の中に浮かんでは消えていく伝説の人々の姿を捉えていた。<本の達人>が描く小さな昭和史。
前述もしましたが前作を読んでしばらく経っいたので家族構成やらなにやら忘れていたので入り込むのに若干苦労しました。
本作単独でもまぁ問題ないとは思いますが「いとま申して」を未読だと入り込むのに苦労するかもしれません。
「いとま申して」の感想にも書きましたが、近親者の日記を基に、周辺情報を調べて書き込んだり、自身(この場合息子として)の所感を書き込んだ形は星新一の「祖父・小金井良精の記」と重なるところがあります。
「業績」中心でなく「生活」の視点から日記を書いた人物の行動やら考えを追っていくスタイルでしみじみ楽しめました。
本書中、”星新一「きまぐれ暦」より引用”という記述もありで、北村薫自身もある程度「祖父・小金井良精の記」を意識はしていたんじゃないかと推察しています。
小中学生時代まだ新作の単行本が発刊され読んでいた「星新一」が時代を帯びてすらりと引用されるということは....自分も年を取ったんだなぁなどと感慨深かったです。
お話の方は弟の死、卒論の苦労など山場の話はありますが、主人公かつ北村薫の父である宮本演彦の慶應本科での昭和初期の学生生活が中心に描かれています。
著者自身も序で書いていますがこんな形でとらえた作品はあまりないかと思うので、昭和初期やら歌舞伎やら民俗学やらが嫌いでない人は楽しめると思います。
私自身、昭和初期も歌舞伎も民俗学も詳しくはないのですが....嫌いではないので楽しめました。
民俗学については本書に登場し名著とされる「花祭」是非読んでみたいものです。
なお民族学に関する個人的所感ですが、最近地元の神社の祭礼の手伝いなどちらちらやっていて思うのですが、祭礼のスタイルやらは「人」につくので移ろいやすいのではないかなぁと思っています。
昭和初期辺りはまだまだ江戸辺りまでのスタイルが残っていたのでしょうが、それがそのまま中世・古代までさかのぼれるのか....疑問な気はします。
その辺は地名も言葉もですが....。(まぁ素人の所管です)
と言って「文書」により現れる「歴史」だけではなく、人々の「暮らし」や「伝承」に着目する民族学の必要性を否定するわけではないのですが...。
そういえば「君の名は。」の三葉の父親も民族学者でしたねぇ。
私も小学生頃民族学にちょろっと憧れ柳田国男の著作「遠野物語」やら「海上の道」などを背伸びして読んだのを思い出しました、当時の私には難しくて苦痛でした...、今読んだらどうなんだろう?
他、「歌舞伎役者」をめぐる考察などは芸談として楽しめますし、卒論のための「吾妻鏡」を古書店を回ってそろえる辺りの考察など、読んでいていろいろなことに思いをはせるような記述もあり楽しめました~。
また比較的「裕福な家庭」であった宮本家が財政的なひっ迫していく様が作品通じて背景として全般に流れており「どうなるのかなー」というはらはら感がありました。
といっても倹約しようとしながらもそれほど倹約するわけでもなく、ガッツリ働くことに現実感のない演彦青年、時代とその当時の裕福な家の青年の気分としてはわかります。
私も、単行本買えないわけではいのですが...ちょっとした倹約で買っていません。
他でずいぶん無駄遣いしているのにねぇ。(笑)
まぁ単行本買わないのはスペースと通勤時の読みやすさの問題もあるのですが。
「小萩のかんざし」は文庫が出たら早めに買おう。
三部通して読みなおしたいような気もします。
↓けちらないで単行本新刊で買えよ!という方も、よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
北村薫の「いとま申して三部作」の第二部となります。
第一部の「いとま申して 「童話」の人びと」を読み終わった段階で本書が単行本で発刊されていたのは認識していました。
でも単行本を買うまでの情熱がなくで...文庫が出たら買おうと思いながら忘れていたのですが最近ブック・オフで見かけて購入しました。

購入したのが「無限の境界」を読んでいる最中だったので珍しく入手してから時間空けずにの「読み」となりました。
北村薫作品では「円紫師匠とわたしシリーズ」の「太宰治の辞書」も「文庫出たら買おう」と思っていたのですが、現時点でも未入手なのが気になっています。
(ぼちぼちブックオフで出ていますが新刊で買おうと思っています)
こちらは単行本は新潮からで出ているのに、文庫が創元推理文庫からというのがなんとも北村薫らしいというか....もしくはなにか出版界の事情があるのか....。
また本記事を書くためちょっと調べたら、どうやら4月に「小萩のかんざし-いとま申して3」が出ているようです。
本書を読むのに「いとま申して」を読んでからかなり経っていて(2015年に読んでいたので3年くらい)人間関係などを忘れていて入りこむのに大変だったので「早めに読んだ方がいいかなぁ」とは思うのですが....。
やはり単行本を買うまでには至らないかなぁです。
内容紹介(裏表紙記載)
昭和4年。著者の父・宮本演彦は慶應の予科に通い、さらに本科に進む。教壇に立つのは西脇順三郎や折口信夫。またたびたび訪れた歌舞伎座の舞台には、十五代目羽左衛門、五代目福助が・・・・・・。父が遺した日記は、時代の波の中に浮かんでは消えていく伝説の人々の姿を捉えていた。<本の達人>が描く小さな昭和史。
前述もしましたが前作を読んでしばらく経っいたので家族構成やらなにやら忘れていたので入り込むのに若干苦労しました。
本作単独でもまぁ問題ないとは思いますが「いとま申して」を未読だと入り込むのに苦労するかもしれません。
「いとま申して」の感想にも書きましたが、近親者の日記を基に、周辺情報を調べて書き込んだり、自身(この場合息子として)の所感を書き込んだ形は星新一の「祖父・小金井良精の記」と重なるところがあります。
「業績」中心でなく「生活」の視点から日記を書いた人物の行動やら考えを追っていくスタイルでしみじみ楽しめました。
本書中、”星新一「きまぐれ暦」より引用”という記述もありで、北村薫自身もある程度「祖父・小金井良精の記」を意識はしていたんじゃないかと推察しています。
小中学生時代まだ新作の単行本が発刊され読んでいた「星新一」が時代を帯びてすらりと引用されるということは....自分も年を取ったんだなぁなどと感慨深かったです。
お話の方は弟の死、卒論の苦労など山場の話はありますが、主人公かつ北村薫の父である宮本演彦の慶應本科での昭和初期の学生生活が中心に描かれています。
著者自身も序で書いていますがこんな形でとらえた作品はあまりないかと思うので、昭和初期やら歌舞伎やら民俗学やらが嫌いでない人は楽しめると思います。
私自身、昭和初期も歌舞伎も民俗学も詳しくはないのですが....嫌いではないので楽しめました。
民俗学については本書に登場し名著とされる「花祭」是非読んでみたいものです。
なお民族学に関する個人的所感ですが、最近地元の神社の祭礼の手伝いなどちらちらやっていて思うのですが、祭礼のスタイルやらは「人」につくので移ろいやすいのではないかなぁと思っています。
昭和初期辺りはまだまだ江戸辺りまでのスタイルが残っていたのでしょうが、それがそのまま中世・古代までさかのぼれるのか....疑問な気はします。
その辺は地名も言葉もですが....。(まぁ素人の所管です)
と言って「文書」により現れる「歴史」だけではなく、人々の「暮らし」や「伝承」に着目する民族学の必要性を否定するわけではないのですが...。
そういえば「君の名は。」の三葉の父親も民族学者でしたねぇ。
私も小学生頃民族学にちょろっと憧れ柳田国男の著作「遠野物語」やら「海上の道」などを背伸びして読んだのを思い出しました、当時の私には難しくて苦痛でした...、今読んだらどうなんだろう?
他、「歌舞伎役者」をめぐる考察などは芸談として楽しめますし、卒論のための「吾妻鏡」を古書店を回ってそろえる辺りの考察など、読んでいていろいろなことに思いをはせるような記述もあり楽しめました~。
また比較的「裕福な家庭」であった宮本家が財政的なひっ迫していく様が作品通じて背景として全般に流れており「どうなるのかなー」というはらはら感がありました。
といっても倹約しようとしながらもそれほど倹約するわけでもなく、ガッツリ働くことに現実感のない演彦青年、時代とその当時の裕福な家の青年の気分としてはわかります。
私も、単行本買えないわけではいのですが...ちょっとした倹約で買っていません。
他でずいぶん無駄遣いしているのにねぇ。(笑)
まぁ単行本買わないのはスペースと通勤時の読みやすさの問題もあるのですが。
「小萩のかんざし」は文庫が出たら早めに買おう。
三部通して読みなおしたいような気もします。
↓けちらないで単行本新刊で買えよ!という方も、よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










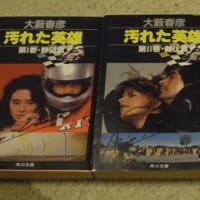
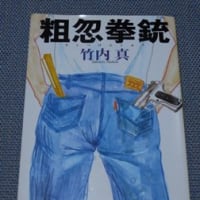
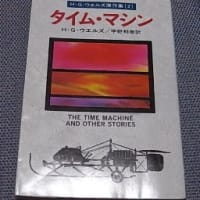
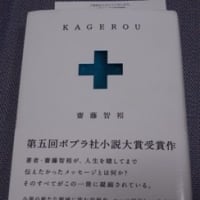
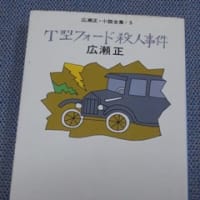
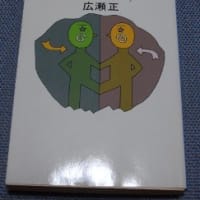


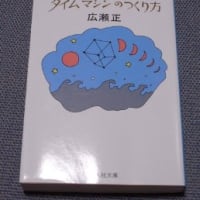
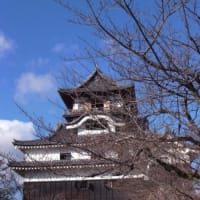
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます