「今ごろ櫻も満開となり花の世となっているでしやう」。茶色く変色したはがきに、きれいな字がつづられている。東洋大4年の小口珠緒さん(25)=東京都文京区=は夏が来ると、特攻隊で戦死した大伯父が家族に残したはがきを読む。ほとんどが家族への思いや近況だ。読むたびに「戦争の悲劇」という抽象的な言葉ではとらえられないものが心に迫る。「特攻隊員の人間味にふれることができるんですよ」(松島京太、写真も)
◆250キロ爆弾を抱えて飛び立った
盆が近づいた10日、小口さんはJR中央線で故郷の長野県諏訪市に着いた。あずさ1号の車窓からは青々と水をたたえた諏訪湖が見えた。同行した記者に「写真でしか知らない大伯父が生きていた証しを確かめたくて、はがきを読むんです」と語った。
大伯父の有賀康男さんは1945年6月20日、250キロ爆弾を抱えた練習機「白菊」で鹿児島県の海軍鹿屋基地を飛び立ち沖縄に向かった。「空母に体当たりす」との無線を最後に、搭乗機からの連絡は途絶えた。19歳だった。
◆「時代が子供でいさせてくれなかったんだ」
有賀さんの生家は今も残っている。小口さんの母の実家で、仏間の欄間に遺影が飾られている。小口さんは「目つきはりりしいけど、ほっぺたはぷっくりして、どこか幼さを感じます」と印象を語った。一方で残されたはがきは大人びた言葉遣いが目立つ。そのギャップに「時代が子供でいさせてくれなかったんだ」と思う。
遺影でしか知らない大伯父のことは「特攻隊員として19歳で戦死した」と幼いころから聞かされていた。実感はなかったが、20歳になった5年前、戸棚の引き出しに入っていた約60枚のはがきを偶然、手にすると人間味あふれる大伯父の姿が浮かび上がった。
「誠一も篤寛も元気に毎日遊んで居ることでしやう」と弟たちを思いやり、「私は元気にやって居ります」と近況がつづられていた。絵を添えて「なかなかうまく書けない。生れつきと思つて許して呉れ」と記したはがきもあった。小口さんは「本当に生きていたんだと実感できた」と初めて読んだときのことを振り返る。
◆「さようなら」に変わった結びの文
78回目の終戦記念日の15日も小口さんは、はがきを手にした。「大伯父は死が近い環境の中でも、気丈に『平気だよ』とふるまっていたのだろう」とその気持ちを推し量る。はがきには直接的に死を覚悟した文面はないが、「では又」と結ばれていた文面が、最後の方は「さようなら」と変わっていた。
小口さんは大伯父が生きていた時代と今を重ね合わせることもある。2年前の夏、コロナ禍の最中に開かれた東京五輪・パラリンピックを振り返り「戦争と同様、国益と命がてんびんにかけられているように感じた」と話す。「一番大切なのは命。そのことを忘れてはいけない」
特攻 太平洋戦争末期、米軍に対して劣勢に陥った日本陸海軍が、戦局打開を狙って考案した航空機などによる体当たり作戦。1944年に海軍の第1航空艦隊司令長官に着任した大西瀧治郎中将が「神風特別攻撃隊」と名付けた部隊を編成し、作戦を開始した。公益財団法人「特攻隊戦没者慰霊顕彰会」(東京都千代田区)によると、特攻による死者は陸海軍で計6418人に上る。


















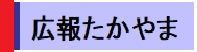












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます