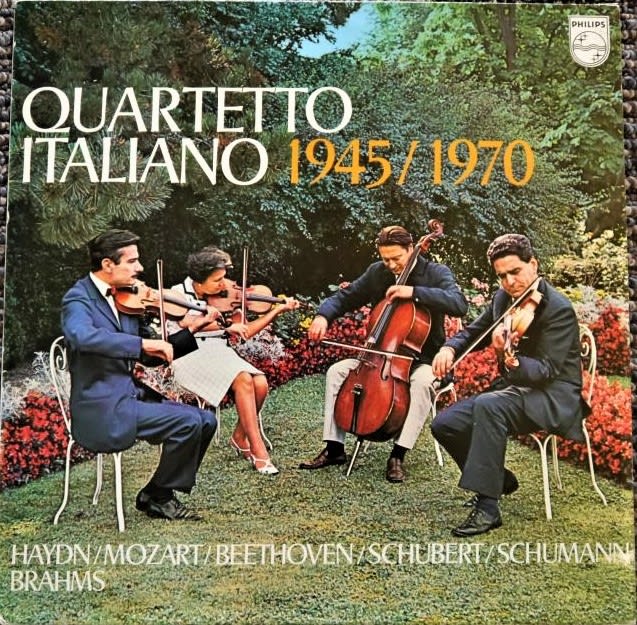少しずつ本格稼働に向かいつつある 雅琴 アンプですが、、、

ようやく最大の課題である イコライザ補正の本質部分に迫ろう という事で、その回路を構成するコンデンサと抵抗をキッチリ数値のモノに換えようという計画
半導体アンプに使用するパーツならば、これまでの経験にて凡その入手ルートは確保しているのですが、こと真空管=球アンプのパーツとなりますとかなり厄介になります。
結局は世の中、需要と供給の関係で成り立っているわけで、極めてニッチな世界である球アンプのパーツ 更に コダワリのパーツともなると圧倒的に需要が少なく、供給も薄くなり 適切価格での入手がなかなかムツカシイわけです。
◎ そんな中ネットで探しまくり、ようやくコダワリのパーツを入手できましたわ~
コンデンサには、その製品により静電容量の誤差範囲が決まっております。今回の改造ではイコライザ補正に使用するには極めて誤差の少ない ±1% すなわち許容誤差ランク=Fクラス が求められております。 一般的な回路で使用しているコンデンサは±5%とか±10% で、だいたい合ってりゃ問題ない といった認識の部品なのですが、、

アチコチ探して、ようやく入手できた 200pF と 8200pF のFクラス コンデンサです!! 上が材料に天然鉱石=雲母ウンモを使用したマイカコンで、下がフィルムコンながら Fクラスの8200pFです(上下2種類で、下は残念ながら±2%でした)

コンデンサは誤差の小さい 精密なモノが少ないのに対して、抵抗は非常に精密なモノも多いので助かります。ただし改造マニュアルにて要求される”抵抗値”が日本国内で一般的に流通しているモノとは少し異なるので なかなか ピッタリ が見当たりません。 たまたま上記のコンデンサを販売する業者さんの抵抗ラインナップに ドンピシャ がありましたので併せて入手したというしだい

本当ならば、もう一種類の抵抗39.2kΩもあれば良かったのですが見つかりませんでした~ 残念
◎ 念願のパーツが入手できたところで、早速パーツ交換作業
マズは LF EQ (マニュアルに左記の表示があったので恐らくは1kHz以下の補正回路)の部分の換装から
比較しやすい様にビフォーアフターですわ
◆ Before

◆ After

お次は HF EQ(同様に恐らくは1kHz以上の補正)の部分の換装
◆ Before

◆ After

とにかく既に改造しているうえに更に無理矢理の改造をするわけですから、かなり困難を極めた作業でした もう、そろそろ中華製基板の限界かもネ・・・
で、で、果たして、、
苦労して入手した精密級パーツの効果は如何に!!
コレは、恐らくは、完全にプラシーボ効果!!? なんじゃないかと思われますが、、、
もの凄くスッキリ 伸びやかなサウンドに成りました~
換装する前は、過去のブログに記載した通り なんか歪っぽい印象のあるサウンドでしたが、その歪っぽさが解消したわけです(あくまで苦労を重ねて作業した挙句の個人的感想です)
イヤハヤ こうなると、なお一層 、シングル球アンプとの組み合わせに期待が高まりますわ~
もはや完全にドロ沼に ドップリと浸かりきりです!! いと 楽し