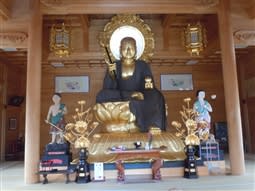三内丸山遺跡を見てきました。6、7年ぶりでしたが、展示物も増え進化していました。ヒスイ製大珠とか平板の土偶など、素人目にもスゴイと思えるのがありました。しかしながら縄文だけが脚光を浴びて、弥生時代はどうしたんでしょうね。


こちらは茅葺住居(復元)。


掘立柱建物と大型竪穴住居(復元)。


三内丸山遺跡の象徴的建造物、大型掘立柱建物(復元)。


れすとらん五千年の星。左上;温かつくねそば680円と縄文古代飯おにぎり1個200円。おにぎりは、古代米(赤米)を栗、ホタテ、山菜で炊き上げられてます。右上;南部初雪茸のおろしうどん780円。


近くに青森県立美術館もありますので、合わせてご覧下さい。「光を描く印象派展」10/10までです。