『警視庁捜査一課刑事』著者:飯田裕久(元捜査第一課殺人犯捜査係担当)2008.11 朝日新聞社刊
◇警察という特殊世界を覘く
長年警察ものを何十冊となく読めば、門前の小僧なんとやらで、知らず知らず警察という世界の仕組みやそこで働く警察官
という人種の習性や文化もわっかてくるものだ。今現在も警察ものを書く作家は少なくないが、多分それぞれが一部の警察官
から内部事情を教わって書いているので、我々読者にはそれなりに違和感もなく状況が伝わってくるが、この度『警視庁捜査
一課刑事』という本物の刑事捜査官が書いた内輪ものを読んで、新たな興奮を覚えた。
これはノンフィクションである。ひとりの青年が何となく警察官になり、多くの警察官があこがれる警視庁捜査一課の刑事に抜
擢されて多くの事件を経験する。その過程で携わった捜査での苦しさ・つらさ・教訓・感動などを綴ったもので、その中で警視庁
と所轄警察の仕組み、警察組織の実態などがかなり細かく明らかにされていく。ある意味個人史的な要素もあるが、係わりを
持った同僚・友人・先輩・上司など、警察という一種特殊な世界で生きる警察官の悩みや苦しみも描かれ、強面の警察官もや
はり人の子か、どんな職業でもそれぞれに辛い現実にもまれているのだなと実感させられる。
とりわけこの本を面白いものにしているのは、現実に起こった事件に主人公飯田裕久が殺人犯捜査係担当刑事として携わ
る中で、どのような捜査をして犯人を追いつめたか、自供をもぎ取ったか、犯人や被害者、被害者の家族との間にどんな感情
的交流があったかなどが綴られていて、話に迫力があることだ。
余談ながら吾輩の三女は、かつて通勤していた地下鉄霞が関駅でサリン事件に遭遇し、駅構内でサリンを吸って体調を崩し
たことがあった。しばらくして「警視庁捜査第一課」から2人の刑事が事情聴取に来たことがあった。娘がその日着ていた衣服
の写真を撮り、車両内の人物確認など根掘り葉掘り聞いていった。その時はるばる柏まで足を運んだのは、何千人という捜査
陣の多分応援部隊の一員だったかもしれないが、今思えば、地道な捜査の積み重ねが彼らの仕事であり、それが確かな結果
を生むということを、この本を読んで改めて実感させられたのである。
著者飯田裕久氏は高卒で警視庁に入り、所轄刑事となったのち本庁刑事部捜査第1課刑事に抜擢された。きっかけは有名
なトリカブト殺人事件。この北海道での何週間にも及ぶ張り込みが結局実を結ぶ。そして地下鉄サリン事件。上九一色村での
オウムの「サティアン」捜索。お受験殺人事件。同期の友の拳銃自殺、親友の過労死、親しくしていた警官の死。
著者飯田氏は平均したら1年間に150件もの死に係わっていたという。25年に及ぶ警察官人生の中で無常観が生まれる。
「人はみな、自分だけは死なないつもりで、一日一日を無駄に生きていることの方が多い。我々はそのような不幸な死を遂げ
た人たちに代わって、「命」というものを尊び、生きていることを感謝しながら、その日その日を全うしなければならないのだ。」
と述懐している。一生の仕事として、人を救い、人から感謝される「刑事」という仕事。最後までやり遂げるか、人生は一度しか
ないことを自覚し、何かを模索するか…。また警察でもキャリアとノンキャリとの差は歴然としている。管理職試験を通らないと
上に行けない。試験勉強などしている暇のない刑事職。
飯田刑事は勤続25年、警部補で退職する。現在は刑事ドラマ等の監修者という新しい人生を歩き始めている。
巻末には「刑事50訓」(これはそのまま人生訓でもある)、「警察隠語集」、「警視庁警察署組織図」、「警視庁捜査一課組織
図」、「警視庁階級構成」などが付けられている。
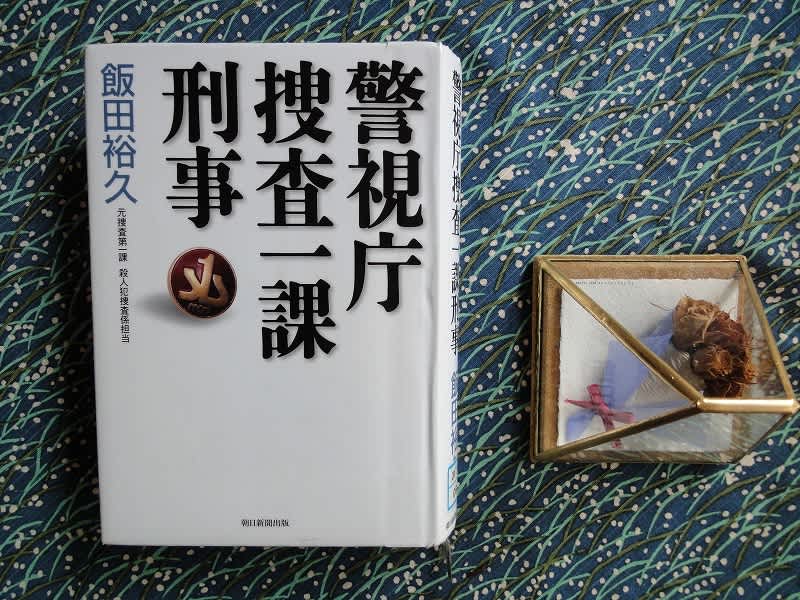
(以上この項終わり)









