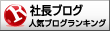人気ブログの池田信夫氏への日本の経済の将来に対するインタビュー記事です。
平成20年度版経済財政白書によれば、2030年までの日本の潜在成長率は年率わずか1%未満に過ぎず、イノベーションを起こせず、現在の産業構造を維持するだけでは、潜在成長率が1%もない超低位安定状態がずっと続く、“失われた40年”に突入すると宣言されたのも同然だ。我々の未来は、沈うつで停滞している。
池田先生は、この内閣府の長期予測に驚き、自分のブログに、「私たちは経済成長を望まず、環境に優しく、穏やかに暮らしていくのがいいのかもしれない」といった内容を、「希望を捨てる勇気」というタイトルで掲載した。もちろん皮肉半分であり、構造的な改革を進めなければならないという思いを込めたのだが、若い読者がブログに殺到し、しかも、同感だという反応が非常に多かったことに戸惑ったそうです。
そこで、本を出版し、潜在成長率の低下をもたらす、ボトルネックを解消し、長期停滞を脱することこそが最重要課題として以下を書かれたとのこと。
彼によると、経済悪化を、短期的異常事態による景気悪化と、長期的なトレンドによる潜在成長率の低下に対し、前者ならマクロ経済政策は一定の痛み止め効果はあるが、後者なら違う対策が必要なのに政府は手を打っていない。
そして、その処方箋として、今の財政支出はやめ、倒産しそうな企業への支援もやめ、一方雇用の流動化を目指すべきだ。という事のようです。
日本の景気不振の最大の原因は、製造業が情報情報通信革命についていけず、競争力、生産性が低下したことに有る。コンピュータ、通信機器、家電等において、主要部品はモジュール化され、主要部品をさまざまなマーケットから買ってきて、組み合わせるだけで一定の品質の製品ができるようになってしまい、製造優位というよりも、製品のコンセプトなどが重要になった事にある。今は強い自動車産業においても流れは同じであり、インドや中国ではモジュール化による低価格自動車が成長するが日本企業は是についていっていない。一見、高付加価値路線は正しいが、新興国においては高級車よりも格安自動車のニーズが圧倒的に高いのに対応できていない。日本の垂直統合モデルの特色である子会社までを巻き込んだ設計、開発、製造等、あらゆる過程における緻密な部品のすり合わせ、組織同士の補完性は必要なくなり、逆に、機動性を欠き、コスト増の原因となっただ。
日本のなかでも国際競争力、生産性が高かったICT産業や自動車産業の衰退が、潜在成長率低下の原因であり、もともと生産性の低かった国内サービス産業もいっこうに改革が進まない。政府は目先の経済対策に追われ、ゾンビ企業を延命し、公共事業投資の拡大によって生産性の低い地方の建設業に労働人口をはりつけた。老朽化した産業構造を再編し、貴重な資源の再配分を行わなければならないのに、逆行する政策ばかりを遂行してきた。
改革すべきは労働市場であり、衰退企業、衰退産業の人材を、需要の増加する産業に移転する。正社員と非正社員の二極化、身分格差の解消を進め、働くことへの意欲を高める。人件費を固定費から変動費に変え、経営者にとって雇用を促進する動機付けをする。優秀な人材の転職を容易にする――こうして労働市場の流動化をはかり、貴重な労働資源を適正に分配する構造を作る必要があるのだ。そのためには、あらゆる労働規制の改革が必要になる。
「労働者を守る」という政府の旧来発想こそが、労働市場の流動化を妨げるということだ。として、現在の雇用確保にかかる法制度を非難されています。
http://diamond.jp/series/tsujihiro/10087/
ことはそう単純か??
2030年には、日本は現在より人口は7-800万人。65歳以下の労働人口が1500万人も減る(マイナス20%)のです。1%の成長を今後続けられるという経済白書の数字のほうが結構楽観的じゃないのかな?
現状の分析はその通りでしょう。過去のことですから。逆にアッセンブリー型の総合電気は駄目ですけど、モジュールを作っている企業は実は日本企業がかなり多く、これらの会社は比較的好調ですよね(今年は影響あるでしょうけど)。
まぁ、政府の短期的政策に対する非難はその通りでしょう。一方雇用対策というのも簡単にはできないですね。人材の流動化はホワイトカラーでは既に発生しています。別にこれ以上流動化するかどうかは政策的な面が多少は影響するでしょうが、さほど期待できないのでは?
人材を流動化して人件費を変動費にする為に派遣社員が増えたのであり、派遣といっても高給の人はいます。コンサルという職業自体も高給な派遣社員に近いでしょう。
問題はブルーカラーです(表面ホワイトカラーのサラリーマンも半分以上は実際には単純作業をしている準ブルーカラーというのが日本企業の実態でしょう)。
日本の課題の一つは格差が無さ過ぎる事。社会主義国はどこもうまく行かず、日本は唯一の成功した社会主義国だった。その限界点に来た。問題は、低所得者の生活できる環境が無い事。東京では家族4人いたら月30万円位最低必要になるでしょう。それが15万円で生活できるなら、格差の問題が起きても深刻さは薄まる筈。アメリカや中国を見ているとそう感じます。
補助金なんて不要なんです。コンビニやスーパーで中国人の子がたくさん働いています。彼らを排斥するわけじゃないですが、多少の給与を得られる仕事があるのに、日本人がその仕事が嫌でやっていないのです。だから在日の子が仕事がある。
おかしいですよ。
政策としては、働かない人を食わせる仕組は撤廃すべき。一方働きたくても働けない人を支援する=保育所をたくさん作りリーズナブルな価格設定にする。高齢者でもバイトクラスの仕事でも応募するなら企業は採用しないと厳しいペナルティを与える。一方働けるのに働かない人間は全く支援しない。それで自殺するならすれば良い。働いても怠ける人には罰を与える。
でも政治は結局人気取りに走るので、今の多くの甘えきった人の票を獲得する方に走るでしょう。
日本は、とことんどん底まで行くべきなんです。ほっといてもそうなるし、そうなった所で改革できるんじゃないでしょうか?その辺は日本人の底力で、多分時期は30年位先だと個人的には楽観視しています。
産業としては何が伸びるでしょうね?成長する産業が何かのアイデアも無いんでしょうね。軍事、航空宇宙関係は今まで日本が手をつけられない分野でしたが、大きな機会があるはずなんですけど。
為替も課題ですよね。何で円がこんなに高い状態がずっと続くのか?もう少し我侭に振舞ってもよいのにしないのは、やはりアメリカの属国だからか。
後、高品質路線はそれで良いのでは?誰でも最初は安いものを買います。日本も昔はまだ未成熟な日本車買っていましたよね。だんだん日本車もよくなりましたが、一方豊かになればドイツやイタリアの車を買うようになりました。日本企業は短期的な浮利に振り回されずに、堅実に今の道を歩み、かつ発展して行けば良いと思いますけど。
何にも束縛されず、国際社会から何言われようと、日本の製造業の技術で国産兵器を開発し防衛体制を整え、その武器を輸出し、為替もアメリカと喧嘩する覚悟で調整し、米国国債なんて脅しに使い。研究開発投資も航空宇宙分野やロボット兵器に費やす。核爆弾があると、お互いに戦争したくても簡単にはできないですし、特に国土の狭い日本から広大な領土を持つアメリカや中国に喧嘩は売れないですよね。やられたら時に主要都市向けに反撃できるだけ。十分でしょそれで。
過激であり、中国っぽいですけど、要は日本がその気になればかなりの事ができる筈なんです。唯、過去のトラウマでできないだけ。世界のパワーバランスがアメリカ一極で無くなったのなら、やりようは幾らでもありそれが政治だと思うんですけどね。
平成20年度版経済財政白書によれば、2030年までの日本の潜在成長率は年率わずか1%未満に過ぎず、イノベーションを起こせず、現在の産業構造を維持するだけでは、潜在成長率が1%もない超低位安定状態がずっと続く、“失われた40年”に突入すると宣言されたのも同然だ。我々の未来は、沈うつで停滞している。
池田先生は、この内閣府の長期予測に驚き、自分のブログに、「私たちは経済成長を望まず、環境に優しく、穏やかに暮らしていくのがいいのかもしれない」といった内容を、「希望を捨てる勇気」というタイトルで掲載した。もちろん皮肉半分であり、構造的な改革を進めなければならないという思いを込めたのだが、若い読者がブログに殺到し、しかも、同感だという反応が非常に多かったことに戸惑ったそうです。
そこで、本を出版し、潜在成長率の低下をもたらす、ボトルネックを解消し、長期停滞を脱することこそが最重要課題として以下を書かれたとのこと。
彼によると、経済悪化を、短期的異常事態による景気悪化と、長期的なトレンドによる潜在成長率の低下に対し、前者ならマクロ経済政策は一定の痛み止め効果はあるが、後者なら違う対策が必要なのに政府は手を打っていない。
そして、その処方箋として、今の財政支出はやめ、倒産しそうな企業への支援もやめ、一方雇用の流動化を目指すべきだ。という事のようです。
日本の景気不振の最大の原因は、製造業が情報情報通信革命についていけず、競争力、生産性が低下したことに有る。コンピュータ、通信機器、家電等において、主要部品はモジュール化され、主要部品をさまざまなマーケットから買ってきて、組み合わせるだけで一定の品質の製品ができるようになってしまい、製造優位というよりも、製品のコンセプトなどが重要になった事にある。今は強い自動車産業においても流れは同じであり、インドや中国ではモジュール化による低価格自動車が成長するが日本企業は是についていっていない。一見、高付加価値路線は正しいが、新興国においては高級車よりも格安自動車のニーズが圧倒的に高いのに対応できていない。日本の垂直統合モデルの特色である子会社までを巻き込んだ設計、開発、製造等、あらゆる過程における緻密な部品のすり合わせ、組織同士の補完性は必要なくなり、逆に、機動性を欠き、コスト増の原因となっただ。
日本のなかでも国際競争力、生産性が高かったICT産業や自動車産業の衰退が、潜在成長率低下の原因であり、もともと生産性の低かった国内サービス産業もいっこうに改革が進まない。政府は目先の経済対策に追われ、ゾンビ企業を延命し、公共事業投資の拡大によって生産性の低い地方の建設業に労働人口をはりつけた。老朽化した産業構造を再編し、貴重な資源の再配分を行わなければならないのに、逆行する政策ばかりを遂行してきた。
改革すべきは労働市場であり、衰退企業、衰退産業の人材を、需要の増加する産業に移転する。正社員と非正社員の二極化、身分格差の解消を進め、働くことへの意欲を高める。人件費を固定費から変動費に変え、経営者にとって雇用を促進する動機付けをする。優秀な人材の転職を容易にする――こうして労働市場の流動化をはかり、貴重な労働資源を適正に分配する構造を作る必要があるのだ。そのためには、あらゆる労働規制の改革が必要になる。
「労働者を守る」という政府の旧来発想こそが、労働市場の流動化を妨げるということだ。として、現在の雇用確保にかかる法制度を非難されています。
http://diamond.jp/series/tsujihiro/10087/
ことはそう単純か??
2030年には、日本は現在より人口は7-800万人。65歳以下の労働人口が1500万人も減る(マイナス20%)のです。1%の成長を今後続けられるという経済白書の数字のほうが結構楽観的じゃないのかな?
現状の分析はその通りでしょう。過去のことですから。逆にアッセンブリー型の総合電気は駄目ですけど、モジュールを作っている企業は実は日本企業がかなり多く、これらの会社は比較的好調ですよね(今年は影響あるでしょうけど)。
まぁ、政府の短期的政策に対する非難はその通りでしょう。一方雇用対策というのも簡単にはできないですね。人材の流動化はホワイトカラーでは既に発生しています。別にこれ以上流動化するかどうかは政策的な面が多少は影響するでしょうが、さほど期待できないのでは?
人材を流動化して人件費を変動費にする為に派遣社員が増えたのであり、派遣といっても高給の人はいます。コンサルという職業自体も高給な派遣社員に近いでしょう。
問題はブルーカラーです(表面ホワイトカラーのサラリーマンも半分以上は実際には単純作業をしている準ブルーカラーというのが日本企業の実態でしょう)。
日本の課題の一つは格差が無さ過ぎる事。社会主義国はどこもうまく行かず、日本は唯一の成功した社会主義国だった。その限界点に来た。問題は、低所得者の生活できる環境が無い事。東京では家族4人いたら月30万円位最低必要になるでしょう。それが15万円で生活できるなら、格差の問題が起きても深刻さは薄まる筈。アメリカや中国を見ているとそう感じます。
補助金なんて不要なんです。コンビニやスーパーで中国人の子がたくさん働いています。彼らを排斥するわけじゃないですが、多少の給与を得られる仕事があるのに、日本人がその仕事が嫌でやっていないのです。だから在日の子が仕事がある。
おかしいですよ。
政策としては、働かない人を食わせる仕組は撤廃すべき。一方働きたくても働けない人を支援する=保育所をたくさん作りリーズナブルな価格設定にする。高齢者でもバイトクラスの仕事でも応募するなら企業は採用しないと厳しいペナルティを与える。一方働けるのに働かない人間は全く支援しない。それで自殺するならすれば良い。働いても怠ける人には罰を与える。
でも政治は結局人気取りに走るので、今の多くの甘えきった人の票を獲得する方に走るでしょう。
日本は、とことんどん底まで行くべきなんです。ほっといてもそうなるし、そうなった所で改革できるんじゃないでしょうか?その辺は日本人の底力で、多分時期は30年位先だと個人的には楽観視しています。
産業としては何が伸びるでしょうね?成長する産業が何かのアイデアも無いんでしょうね。軍事、航空宇宙関係は今まで日本が手をつけられない分野でしたが、大きな機会があるはずなんですけど。
為替も課題ですよね。何で円がこんなに高い状態がずっと続くのか?もう少し我侭に振舞ってもよいのにしないのは、やはりアメリカの属国だからか。
後、高品質路線はそれで良いのでは?誰でも最初は安いものを買います。日本も昔はまだ未成熟な日本車買っていましたよね。だんだん日本車もよくなりましたが、一方豊かになればドイツやイタリアの車を買うようになりました。日本企業は短期的な浮利に振り回されずに、堅実に今の道を歩み、かつ発展して行けば良いと思いますけど。
何にも束縛されず、国際社会から何言われようと、日本の製造業の技術で国産兵器を開発し防衛体制を整え、その武器を輸出し、為替もアメリカと喧嘩する覚悟で調整し、米国国債なんて脅しに使い。研究開発投資も航空宇宙分野やロボット兵器に費やす。核爆弾があると、お互いに戦争したくても簡単にはできないですし、特に国土の狭い日本から広大な領土を持つアメリカや中国に喧嘩は売れないですよね。やられたら時に主要都市向けに反撃できるだけ。十分でしょそれで。
過激であり、中国っぽいですけど、要は日本がその気になればかなりの事ができる筈なんです。唯、過去のトラウマでできないだけ。世界のパワーバランスがアメリカ一極で無くなったのなら、やりようは幾らでもありそれが政治だと思うんですけどね。