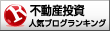| 日米開戦の正体 |
| クリエーター情報なし | |
| 祥伝社 |
日露戦争から真珠湾攻撃までの日本の政治の動きが色々な文献を通して理解ができるという点で良書だと思います。また、著者の見解が昨今の日本の政治、特に安部政権に関してかなり批判的な見解として紹介されています。後者に関しては、個人的には同意しかねる点も多々ありますし、本書内で紹介されている幾つかの統計などを見ると聊か不満を覚えるものもあるのですが、面白い、参考になった点を。
朝鮮併合に関し伊藤博文が反対であった事は認知しておりましたが、満州経営に関しても当然かもしれませんがそうだったこと。韓国が褒め称える安重根義士の暗殺がその後どれだけの災禍をもたらしかと表現されています。まぁ中国はともかく韓国が日本の歴史をちゃんと分析している事は無いでしょうから、そうかなぁと。また安重根の背景に実は日本の右翼がいたという説もあるそうです。でもそちらの方が本当かもしれない。
吉田茂は親英、親米と思っていましたが、実は元々は中国畑出身であり、かつ陸軍に擦り寄っていた事。権力志向が強く外務省に影響を与えたという市で評価されています。そうなの??そして、奉天領事時代に、「自国民の生命や財産を守るために軍事行動をとることは自衛権である」という主張をしたようですね。著者の集団的自衛権に関する懸念材料としてもあげていると思われます。
不満なのは、ロンドン・ワシントン軍縮条約当時の各国のGDP比較を掲示されており、日本のGNPはアメリカの1/10、イギリスの1/3、日露戦争時の日本対ロシアのGDP費は1/8。こういう数字を掲載されていますが、なんで1921年で止めたのかな。ドイツも加え、1937年、1941年の数字も加えれば良いのに。。この辺は元大蔵や通産官僚ご出身の方の書籍と比べると、外務省は昔から2流官庁といわれているけど今でもそうなのかなと思ってしまいます。
ちなみにネットで探してみたら、GDP比で日米は1:5まで狭まっています。日露戦時の日露よりGDPだけ見ると実は差は少ないんですね。著者は意図的に隠したのかな?
1940年 昭和15年
アメリカ 9,308.3
イギリス 3,156.9
フランス 1,641.6
ソ 連 4,200.9
日 本 2,017.7
イタリア 1,520.3
ド イ ツ 2,428.4
付け加えると戦前ルーズベルトが対独船に備えて航空機年間5万機体制を作るように指示したという記載があります。で対戦中の兵器の各国の生産量
航空機 戦車 空母 戦艦
アメリカ 32.5万 7.7万 115 10
イギリス 13.2万 2.3万
ソ 連 15.8万 7.9万
ドイツ 11.7万 3.7万
日 本 7.9万 0.5万 18 2(大和と武蔵)
ドイツと日本は戦争後半は空襲の為に生産能力を大きく阻害されたでしょう。がそもそも違いすぎる。アメリカとソ連が当時からやはり二大強国。ナチがアメリカと中の良い英国に勝ちきれない中、ソ連にに侵攻した時点で敗北は目に見えていたのでは無いでしょうか。日本は日本で中国に勝ちきれない中、資源獲得の為に対米戦。やる前から負けは目に見えている戦争だという事を当時の政府、海軍、陸軍の一部は十分に認識している。陸軍の面子の為に無謀な攻撃をした。その面子も中国侵略における戦死者が起因。
まぁこの本を読むと解りますが、著名な文学者たちが戦争協力をしたと弾劾気味に書かれている一方、対米戦争に反対したそうも非常に多かった。いや、極端にいえば陸軍の一部以外は基本的には反対だったという事が読み取れます。それが暗殺などで陸軍や右翼が政治家などを脅かして実質陸軍軍事政権になってしまい、無謀な戦争に入っていったと。
戦後首相になった石橋湛山の植民地主義反対、国内投資と貿易促進というのは戦後日本の発展をみるとまさにその通りで走っており、こういう意見がつぶされたのは、欧米強国のかっての経済成長のモデル〔植民地獲得、其処からの単一生産、市場確保)にとらわれてからかなと思う反面、日本の戦争が無かった場合、石橋湛山の言うように植民地はいずれ独立したのか、今のようになっていたのかはなんとも判断できないですね。但し、民族主義の勃興していた中国、満州に関しては、どういう経路をとったにしろ今のようになっていただろうとは思います。国家や民族の持っている底力の相違だと思うのです。中国に関しては勝海舟も進出には反対していたようですね。まぁしても飲み込まれていたんだろうな。
興味深いのは、敗戦後の反省からきた様々な方の敗因。ここは今の日本でも通じるものであり、外交その他を考える際には、重視しないといけないところだと思います。そしてこの辺を踏まえてみると、私は著者とは異なる意見になってしまいますが皆さんは如何でしょう。軍人や政治家の当時の反省の弁は実は見るべきものは多くはありません。著書の中では最初の海軍の反省分でしょうか。日本経済が独立性を描いている。海外事情の研究不足、陸軍。を大きく上げています。陸軍系の反省はもう阿呆としか言いようがありません。アメリカの策謀だとか、中国の民族主義を刺激した、戦略なき戦争計画。。。
本質を突いているなと思うのは次の2点。
1.日本国民の常習である妥協・黙従が原因。
日本人が偉大な民族になりたいのなら、個人的な行動で自らの固い信念に基づいた主張をすること。民主主義の政治形態は市民一人一人が良心に対する危機感を強くし個人的な責任を果たす事である。
2.軍需原料の大部分を外国に仰がなければならない国防は、戦争国家としては致命的な弱点を有しており、独力戦争をなす資格に欠ける。どれだけ軍備を増強しても砂上の楼閣に過ぎない〔これ海軍軍人が1929年に書いたそうです)。
陸軍の戦略の無さ、対米戦争をするのに相手を研究していない、その他各論的には山ほど反省点があるでしょうが、やっぱりこの2点でしょう。そしてこの2点は現代日本も全く変わっていない。
さて、何故孫崎氏は安部政権の外交を酷く嫌うのだろうか?そこが良くわからない。
1に関していえば、今も全く変わらないし、長期的に変わるとは思えない。文字通り人口が半減し、移民比率、混血比率が高くなる時代になったら少しはましになるかもしれないという期待しか個人的には持っていない。スポーツ界あたりで少し変化が見られてきているのでは無いでしょうか。
2も同じ。これは解決できない。ということは世界情勢を見て対抗勢力があるのなら少なくともその中で勝ち組になるであろう大国に擦り寄るしかない。元々日露戦争も英米からの資金協力が無ければとても戦えない。まぁそういう背景から石原莞爾は満州侵略で弱点をカバーしようとしたのでしょうが。でもそうであるなら、今の対米追従外交は不愉快でも受け入れざるを得ない。大きな追従の中で自国としての主張をするしかない。まぁ其れが対ソ、対中でも良いんですけど、この3大大国の中でどこを選べといわれたら、個人的にはやはりアメリカしか選択肢は無い。中国に擦り寄る場合、中国及び日本で対米、もしくは対ソの脅威と向き合うことになると思う。日本が中国に必要以上に擦り寄ったらアメリカの対中・対日戦略や外交は物凄く厳しいものになるのでは無いでしょうか。
これ負け犬???でも幾つかスパイスを加えることはできても概ね世界情勢の中でどう生きていくかという点では間違っているとは思わないのだけど。