今年の1月末にこんなディスプレイにしているという記事を書きました。

お正月用のディスプレイにするのもめんどくさいので、
日本酒セットをいろいろ並べて擬似正月的な雰囲気にしてみたという記事です。
そもそもあのときも本格的なディスプレイとしてではなく、
とりあえずその場しのぎのディスプレイとしてあれを飾ってみたわけですが、
なんと、その後まったくあれを新しく陳列し直す余裕のないまま年末を迎えてしまいました。
いつもでしたら毎月とは言わないまでも、季節の変わり目ぐらいには替えていましたし、
雛祭りには雛飾り等、シーズンを感じさせるようなディスプレイにしていたんです、今までは。
ところがこの1年はずーっとプチうつ状態でしたから、
まったくこれを何とかするという気になりませんでした。
というわけで、ほぼ1年間ずっと日本酒セットのままここをほったらかしにしてきました。
しかしながら先日の大掃除で少しだけ生きる気力というか、
部屋の中を片づけたり飾ったりする心の余裕が出てきました。
そこで12月にも入ったことですし、思い切ってクリスマスディスプレイに替えることにしました。
クリスマスディスプレイは雛飾りに比べるとそんなに大変なことではないのですが、
それよりもほぼ1年間ずーっと飾りっぱなしだった日本酒セットを、
次にいつでも実用に供せるようにちゃんと中まで洗っておくことのほうが大変です。
逆に言うとそれが面倒くさいからこれまで飾り替えをやる気になれなかったのかもしれません。
今回は台所もキレイになったばかりでしたので、それに挑戦してみる気になったのでした。
やってみるとやはり大変なのは洗い物のほうで 、
、
ディスプレイの並べ替え自体はあっという間に終わりました。
こんな感じです。

例年、並べるものは同じですのでそんなに目新しい感じにはできません。
ま、クリスマスはこれにあとは部屋の中にクリスマスソングが流れていれば十分ではないでしょうか。
このいつもの階段箪笥だけでなく、一気に玄関もクリスマスにしておきました。

昨年いただいたクリスマスリースです。
このクリスマスリースをぶら下げる用の頂き物のハンティング・トロフィですが、
実際に玄関に飾ってみると思いのほか電池の消費量が激しいです。
LR44という小さいボタン型乾電池を3つも使うのに、
しかもドアの開閉時にしか点灯しないにもかかわらず、1ヶ月くらいで電池が切れてしまいます。
さすがに電力のムダということで、年明け早々電池が切れて以来そのまま放っておきましたが、
せっかくのクリスマスですので、今回1年ぶりに電池も替えて点灯させてみました。
やっぱりこいつが光っているとちょっと雰囲気が違いますね。
しばらくは自宅でもルンルンのクリスマス気分を楽しんでみたいと思います。

お正月用のディスプレイにするのもめんどくさいので、
日本酒セットをいろいろ並べて擬似正月的な雰囲気にしてみたという記事です。
そもそもあのときも本格的なディスプレイとしてではなく、
とりあえずその場しのぎのディスプレイとしてあれを飾ってみたわけですが、
なんと、その後まったくあれを新しく陳列し直す余裕のないまま年末を迎えてしまいました。
いつもでしたら毎月とは言わないまでも、季節の変わり目ぐらいには替えていましたし、
雛祭りには雛飾り等、シーズンを感じさせるようなディスプレイにしていたんです、今までは。
ところがこの1年はずーっとプチうつ状態でしたから、
まったくこれを何とかするという気になりませんでした。
というわけで、ほぼ1年間ずっと日本酒セットのままここをほったらかしにしてきました。
しかしながら先日の大掃除で少しだけ生きる気力というか、
部屋の中を片づけたり飾ったりする心の余裕が出てきました。
そこで12月にも入ったことですし、思い切ってクリスマスディスプレイに替えることにしました。
クリスマスディスプレイは雛飾りに比べるとそんなに大変なことではないのですが、
それよりもほぼ1年間ずーっと飾りっぱなしだった日本酒セットを、
次にいつでも実用に供せるようにちゃんと中まで洗っておくことのほうが大変です。
逆に言うとそれが面倒くさいからこれまで飾り替えをやる気になれなかったのかもしれません。
今回は台所もキレイになったばかりでしたので、それに挑戦してみる気になったのでした。
やってみるとやはり大変なのは洗い物のほうで
 、
、ディスプレイの並べ替え自体はあっという間に終わりました。
こんな感じです。

例年、並べるものは同じですのでそんなに目新しい感じにはできません。
ま、クリスマスはこれにあとは部屋の中にクリスマスソングが流れていれば十分ではないでしょうか。
このいつもの階段箪笥だけでなく、一気に玄関もクリスマスにしておきました。

昨年いただいたクリスマスリースです。
このクリスマスリースをぶら下げる用の頂き物のハンティング・トロフィですが、
実際に玄関に飾ってみると思いのほか電池の消費量が激しいです。
LR44という小さいボタン型乾電池を3つも使うのに、
しかもドアの開閉時にしか点灯しないにもかかわらず、1ヶ月くらいで電池が切れてしまいます。
さすがに電力のムダということで、年明け早々電池が切れて以来そのまま放っておきましたが、
せっかくのクリスマスですので、今回1年ぶりに電池も替えて点灯させてみました。
やっぱりこいつが光っているとちょっと雰囲気が違いますね。
しばらくは自宅でもルンルンのクリスマス気分を楽しんでみたいと思います。













 May your days be merry and bright
May your days be merry and bright 










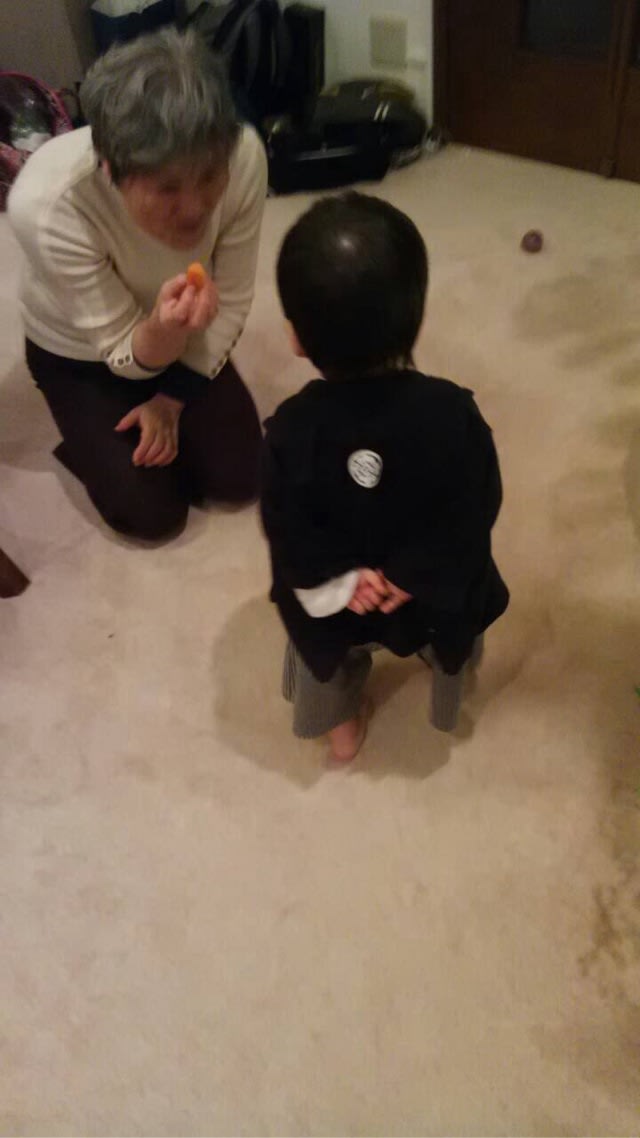




 。
。


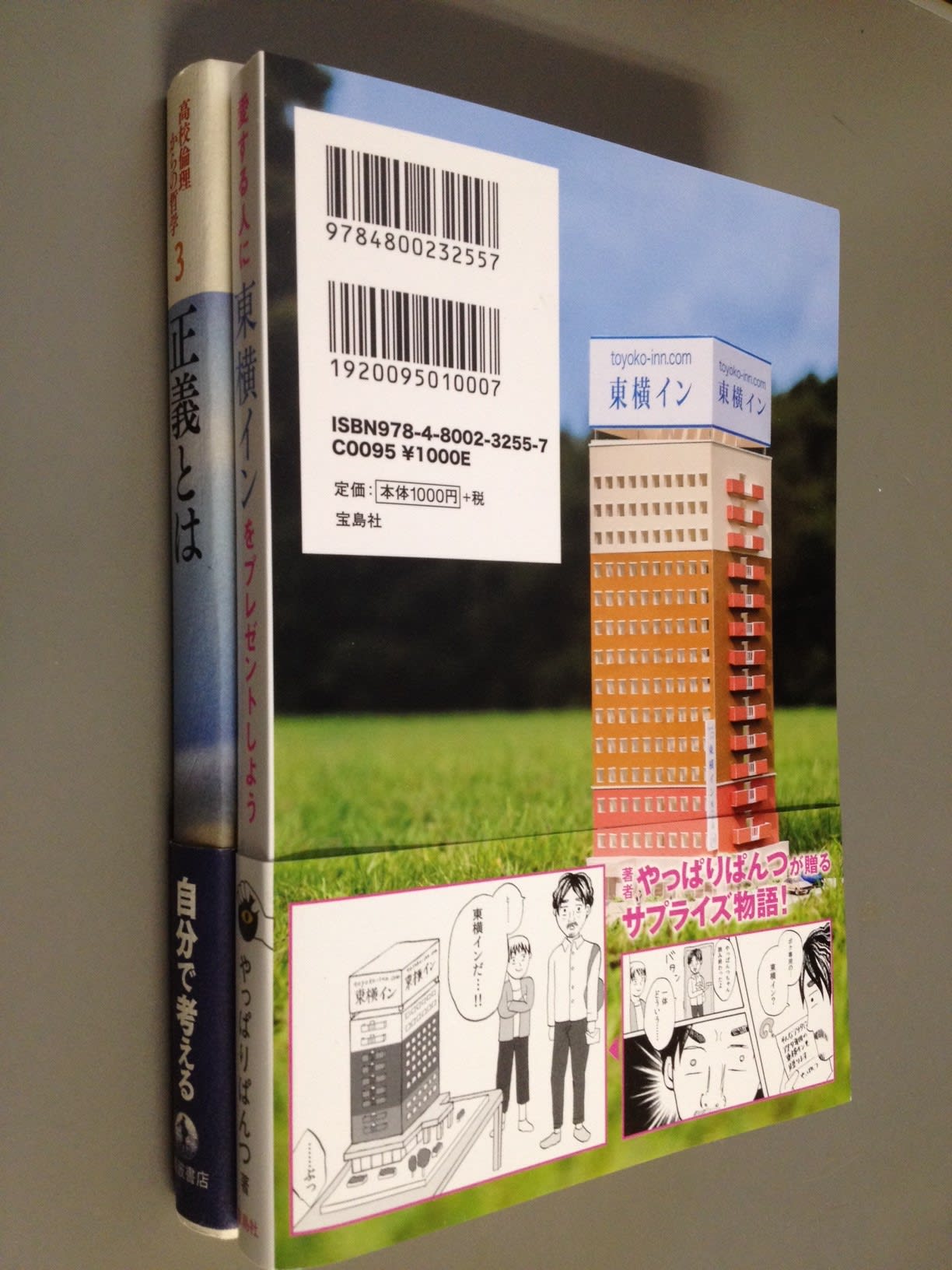
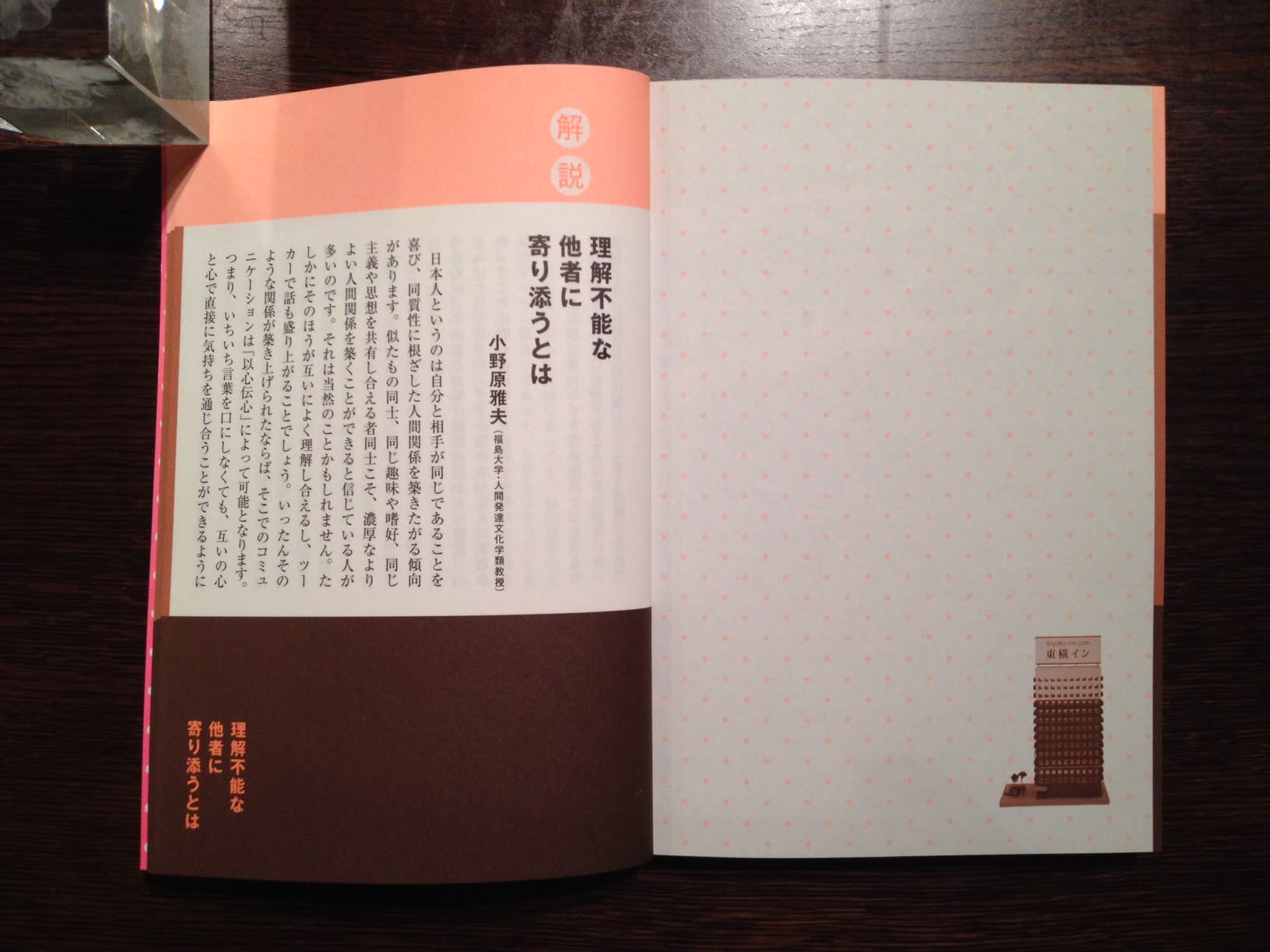

 )
) 。
。