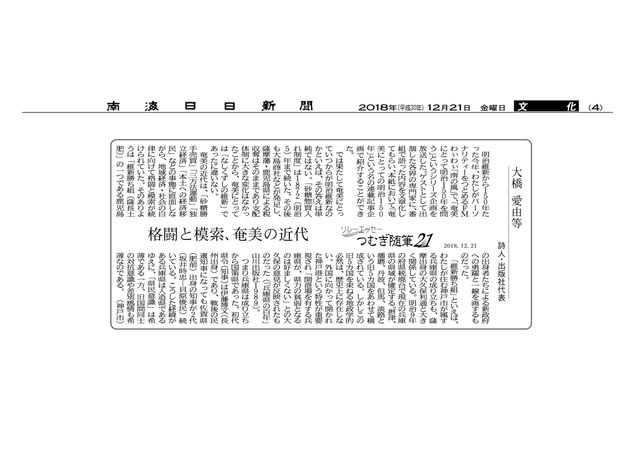2018*12*01/南海日日新聞に連載中の「奄美にとっての明治150年」の4回目は寺尾智史・宮崎大学語学教育センター准教授の文章。寺尾氏との出会いはFMわぃわぃでした。イベリア半島のマイノリティー言語(ミランダ語、アラゴン語)を研究していて、「滅びる言語・滅びない言語」についての考察も深い人。
寺尾智史氏の南海日日新聞への寄稿文は、
https://twitter.com/gunshaku/status/1068643662500745216
2018*12*02/昨日、兵庫県現代詩協会「読書会」が県教育会館で開かれ、詩人の坂東里見さん(右写真の左の人物)が「藤富保男」について講演しました。最後までアバンギャルドであろうとした詩人でありかつ視覚詩(アナグラム)もおおく描いたことで知られています。前衛をつらぬくその姿は評価したい。
読書会の様子(写真)は、https://twitter.com/gunshaku/status/1069029464821063681
2018*12*03/今年最後の詩の会「エクリ」(高谷和幸主宰)が赤穂市の「煉瓦屋」で開かれました。詩人・田村周平氏が経営する店です。第一部読書会は得平秀昌氏が井筒俊彦著「意識の形而上学―大乗起信論の哲学」を取り上げて解説。第二部は詩と川柳の合評会。司会は大西隆志氏が担当。あとは忘年会に。(この会が「煉瓦屋」で開催する最後の赤穂エクリでした)
会の様子は https://twitter.com/gunshaku/status/1074459950150148096
2018.12.04/赤穂といえば塩。わたしはここの塩饅頭と塩羊羹が好きで、赤穂駅構内にある観光物産センターでいつも購入します。とくに塩羊羹は日持ちかするので賞味期限をさほど気にせず楽しめるのが嬉しいですね。赤穂は兵庫県の西端に位置します。詩の会がなければこれほどたびたび訪れたでしょうか。
2018*12*05/神戸日西協会の理事会に出席する。神戸市とバルセロナ市が姉妹都市となっていて神戸から訪問団が赴いた。いまバルセロナと神戸といえば、ヴィッセル神戸に移籍したサッカー選手イニエスタを介して、この二つの都市はいつになく親近度が増していることだろう。スポーツ交流の面白さである。
2018*12*06/神戸は坂の街がいくつかある。まるで迷路のような小坂が多い場所。歩いても歩いても迷ってしまう界隈。小説家の島尾敏雄はこうしたラビリンスのような坂のある場所をこよなく愛した。北野周辺、長田区の山麓地区など神戸には文学が発生する沃野となりそうな小坂の多い場所が点在している。
2018*12*07/アンソロジー「ひょうご現代詩集2018」の編集担当をしている。目標の出稿者数をクリアーして安堵している。出稿内容を見ていると、ようやく今号になって、手書き原稿よりメール出稿の方が多くなった。70歳代以上の会員による手書き原稿の中には味のあるものがあり、とても素敵なのである。
2018*12*08/わたしはまだまだ現役で働いているのだが、拙宅周辺の退職した方々はどこでどのように過ごしておられるのだろう。図書館に毎日「出勤」される方もいらっしゃるが、拙宅近くの図書館分室(かつてはM村の村役場だった)はなくなってしまい区の図書館へ歩いて行くには高齢者は遠すぎるのだ。
2018*12*09/今年最後の「Mélange」例会が神戸・三宮のスペイン料理カルメンで行われました。第一部中堂けいこさんによるソシュール「記号論」の発表には多くの参加者がありました。第二部は詩の合評会。第三部は詩人で小説家の高木敏克氏の小説集『港の構造』(航跡舎)の出版記念会になったのです。
例会の写真と、出版記念会の写真は、https://twitter.com/gunshaku/status/1074832686911377410
2018*12*10/まろうど社の忘年会を大阪・淀屋橋で行いました。参加人数こそ少ないものの、参加者同士、言葉のあえかな交流ができたのです。会場はいつも大阪なのですが、淀屋橋は初めて。小説家で詩人の高木敏克氏の職場が近いので捜してもらいました。大学同窓Sがかつて働いていたオリックスも間近。
2018*12*11/昨日まろうど社忘年会に参加した高木敏克氏が、金里博氏との交誼に触発されて即興詩を作成。これに呼応して里博氏も返詩を作ったのです。こうして詩人たちはあらたに詩友となり言葉と叙情を重ねていくのですね。(辺詩作成の日付は本日ではありませんがあえてこの日の記述としておきます)
高木敏克氏と金里博氏とによる即興詩の交換は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075176189331980288
2018*12*12/兵庫県現代詩協会アンソロジー「ひょうご現代詩集」の編集が佳境。2月刊行予定なので、ぎりぎりといったところか。あとは印刷担当の澪標に頑張ってもらおう。各県に「詩人協会」があるが、あれだけ詩人が多く「山之口貘賞」といった賞もあるのに沖縄には詩人たちの組織がないのは不思議。
2018*12*13/今月は作品締切が多く、原稿執筆をこなすのにあっぷあっぷしている。次に取り組んでいるのは「奔(望月至高個人俳誌)」「吟遊(夏石番矢・鎌倉佐弓代表)」への俳句出稿。私は「豈」を含め3つの俳誌に所属していることに。あいかわらず句会には参加せずもっぱらメディア出稿のみに特化。
2018*12*14/兵庫県現代詩協会の「会報」(年に二回発行)が刷り上がり発送作業。ところが印刷所のミスで表1と表4を逆に組んで印刷している。これはプロの印刷所にすれば基本以前の大チョンボ。協会の担当者にすこし厳しく指摘する。校正もこわいですが印刷はこわいですね。他山の石といたしましょう。
2018*12*15/フラメンコギターの名手・住田政男氏が演奏する本日のスペイン料理カルメンの舞台。相変わらず住田氏のギターは冴えわたり、カンテの鳥居貴子氏も良い。そして今夜は久しぶりに諸藤ふみさんが出演。この人の「ソレア」は何度見てもいい。魂を揺さぶる渾身の踊り。
渾身の踊り・諸藤ふみさんのソレアの動画は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075184906479628289
2018*12*16/俳句とは、自ら作句することと、他人の作品を多く読む(選句する)ということでもあろう。俳句の作句力は選句力に直結するように思えてならない。私は勝手に南海日日新聞「なんかい文芸」に掲載されている俳句を読んで選句しているが、そうした行為も作句力に役立っているのかもしれない。
2018*12*17/「奔」と「吟遊」に出稿する俳句を一気に書きあげ朝にメール出稿。ふたつほど原稿が片付いて安堵している。わたしの作句手法は、書くまでにいくばくかの時間を要する。他人の作品をある程度多く読み込みたいからだ。今回は出口善子さんから送ってもらった俳誌「六曜」も読ませてもらった。
2018*12*18/南海日日新聞に掲載された「奄美にとって明治150年」連載シリーズの5回目。酒井正子・川村女子学園大学名誉教授。テーマは「奄美シマウタの近代」。シマウタは奄美のシマ(集落)という存在が孵卵器のような役割を果たしていたのですが、仕掛け人や、イベントによって変容していくのです。
酒井正子氏の南海日日新聞への文章は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075548948402589696
2018*12*19/「奄美にとって明治150年」(南海日日新聞)連載シリーズのトリを飾るのが、この前利潔氏の文章。奄美の近代史は「本土への経済移民」の歴史でもあるのです。近代という開かれた交通システムが人の移動を促します。本土では島出身者が集住化してエスニシティー集団を形成していくのです。
前利潔氏の南海日日新聞への文章は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075550332279635970
2018*12*20/南海日日新聞に連載している「つむぎ随想」の5回目記事です。神戸市長田区は奄美群島の中でもとくに徳之島出身者が多く住んでいる地域です。今回のコラムでは、ケミカルシューズ業界でミシンを踏み続け、かつウタシャでもある向江登美江さんをインタビューした内容を紹介しているのです。
「つむぎ随想」の5回目記事は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075897909768409088
2018*12*21/「つむぎ随想」(南海日日新聞の連載しているコラム)の11月の記事は、奄美俳句についてです。3年ほど前から、奄美俳句を読み続けています。しばらくこの読みをつづける予定です。本土とも沖縄の俳句とも違った諸相がこの奄美の俳句を読んでいると見えてきます。文芸からみえる景色です。
奄美俳句についての考察は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075899165299769344
2018*12*22/今年最後の「つむぎ随想」の掲載にわたしのコラムを選んでくれました。わたしなりに奄美と兵庫県という視座から〈明治維新150年〉を俯瞰してみたつもりです。ではなぜこの150年にこだわったかというと、次のメルクマールである「明治維新から200年」には生きていないだろうからなのです。
今年最後の「つむぎ随想」は、https://twitter.com/gunshaku/status/1076257470547292160
2018*12*23/クリスマス三連休の真ん中の日。スペイン人スタッフHは二日前、故郷のバルセロナに帰っていきました。スペインを含めたヨーロッパの人たちにとってクリスマスは特別な祭日。キリストの生誕を祝う以上に、家族があつまって家族の絆を深める、いわば日本の正月のような位置づけでしょうね。
2018*12*24/日本もスペインも立憲君主国です。スペインの場合、近代になってなんどか国外に追放されていた時期が長かったせいか、国民との距離を短くしようとする努力が実践されています。20世紀に限っても共和制の時代やそれに続くフランコ総統による長い独裁時代には亡命を余儀なくされていました。
2018*12*25/いよいよ2018年もあとわずか。街なかのディスプレイは早ければ今日から正月の商品やポップに意匠替えされます。神戸・三宮は阪急三宮駅の改修工事で駅周辺の人の流れが変わっています。大阪駅周辺も何年にもわたって工事が繰り返されていましたね。三宮はこれからしばらく混乱が続きます。
2018*12*26/「ひょうご現代詩集2018」の編集は、現在印刷所から兵庫県現代詩協会の会員の皆さんに初校ゲラが届いた状態です。さっそくその返事が編集担当のわたしのもとに帰ってきています。今年設立22周年を迎えた同協会はすこしずつ世代交代が進んでいます。今年になって新しい会員も増えています。
2018*12*27/年賀状の住所を整理しています。物故者あり、住所変更あり。次から出すのをよそうと思う人も。わたしが賀状を出す人はなにがしかの表現をしている人がほとんどなので、会社から退職を機にやめたり、年賀状の終活宣言をする人はいません。生あるかぎり表現を続けようとしているのでしょう。
2018*12*28/年の暮れまでやるべきことが多く、今日はほとんど一日電卓をたたいていました。おもしろいもので、一日数字ばかり相手をしていると、世間の事象がすべて数字に還元されていく、つまりすべてが数値化されて私の前に顕現するのです。〝数字脳〟というのでしょうか。これはこれでまた刺激的。
2018*12*29/今年最後の土曜日。フラメンコライブで締めくくりです。カルメン、満席でした。バイレのみんさんも定期的に踊ることでキャリアが重なっていきます。私はフラメンコを見る時、そのバイレに〝踊りに芯があるかどうか〟を見定めます。ただ先生に習ったとおり上手に踊っていてもダメなのです。
2018*12*30/引っ越しを考えている人がいます。いまより一室多い部屋を選んだそうで、新しい家具を買おうとしています。好みを聞いていると、どうもネオクラシコの家具に興味があるようです。でも現実の選択は「無印良品」的なコンセプトになりそうとのこと。新居に越しても日々の片付けは大切だよね。
2018*12*31/大晦日に奄美から一本の電話。現役最高齢の唄者・森チエさんが逝去されました。百歳近いお年です。奄美の宝でした。瀬戸内町網野集落の出身。これで大島の「民謡大賞」以前のシマウタをしる貴重な唄者がまたいなくなりました。90歳の歌声はこのサイトで聞けます。
森チエさんの歌声が紹介されているサイトを知るには、https://twitter.com/gunshaku/status/1079698468187205632
寺尾智史氏の南海日日新聞への寄稿文は、
https://twitter.com/gunshaku/status/1068643662500745216
2018*12*02/昨日、兵庫県現代詩協会「読書会」が県教育会館で開かれ、詩人の坂東里見さん(右写真の左の人物)が「藤富保男」について講演しました。最後までアバンギャルドであろうとした詩人でありかつ視覚詩(アナグラム)もおおく描いたことで知られています。前衛をつらぬくその姿は評価したい。
読書会の様子(写真)は、https://twitter.com/gunshaku/status/1069029464821063681
2018*12*03/今年最後の詩の会「エクリ」(高谷和幸主宰)が赤穂市の「煉瓦屋」で開かれました。詩人・田村周平氏が経営する店です。第一部読書会は得平秀昌氏が井筒俊彦著「意識の形而上学―大乗起信論の哲学」を取り上げて解説。第二部は詩と川柳の合評会。司会は大西隆志氏が担当。あとは忘年会に。(この会が「煉瓦屋」で開催する最後の赤穂エクリでした)
会の様子は https://twitter.com/gunshaku/status/1074459950150148096
2018.12.04/赤穂といえば塩。わたしはここの塩饅頭と塩羊羹が好きで、赤穂駅構内にある観光物産センターでいつも購入します。とくに塩羊羹は日持ちかするので賞味期限をさほど気にせず楽しめるのが嬉しいですね。赤穂は兵庫県の西端に位置します。詩の会がなければこれほどたびたび訪れたでしょうか。
2018*12*05/神戸日西協会の理事会に出席する。神戸市とバルセロナ市が姉妹都市となっていて神戸から訪問団が赴いた。いまバルセロナと神戸といえば、ヴィッセル神戸に移籍したサッカー選手イニエスタを介して、この二つの都市はいつになく親近度が増していることだろう。スポーツ交流の面白さである。
2018*12*06/神戸は坂の街がいくつかある。まるで迷路のような小坂が多い場所。歩いても歩いても迷ってしまう界隈。小説家の島尾敏雄はこうしたラビリンスのような坂のある場所をこよなく愛した。北野周辺、長田区の山麓地区など神戸には文学が発生する沃野となりそうな小坂の多い場所が点在している。
2018*12*07/アンソロジー「ひょうご現代詩集2018」の編集担当をしている。目標の出稿者数をクリアーして安堵している。出稿内容を見ていると、ようやく今号になって、手書き原稿よりメール出稿の方が多くなった。70歳代以上の会員による手書き原稿の中には味のあるものがあり、とても素敵なのである。
2018*12*08/わたしはまだまだ現役で働いているのだが、拙宅周辺の退職した方々はどこでどのように過ごしておられるのだろう。図書館に毎日「出勤」される方もいらっしゃるが、拙宅近くの図書館分室(かつてはM村の村役場だった)はなくなってしまい区の図書館へ歩いて行くには高齢者は遠すぎるのだ。
2018*12*09/今年最後の「Mélange」例会が神戸・三宮のスペイン料理カルメンで行われました。第一部中堂けいこさんによるソシュール「記号論」の発表には多くの参加者がありました。第二部は詩の合評会。第三部は詩人で小説家の高木敏克氏の小説集『港の構造』(航跡舎)の出版記念会になったのです。
例会の写真と、出版記念会の写真は、https://twitter.com/gunshaku/status/1074832686911377410
2018*12*10/まろうど社の忘年会を大阪・淀屋橋で行いました。参加人数こそ少ないものの、参加者同士、言葉のあえかな交流ができたのです。会場はいつも大阪なのですが、淀屋橋は初めて。小説家で詩人の高木敏克氏の職場が近いので捜してもらいました。大学同窓Sがかつて働いていたオリックスも間近。
2018*12*11/昨日まろうど社忘年会に参加した高木敏克氏が、金里博氏との交誼に触発されて即興詩を作成。これに呼応して里博氏も返詩を作ったのです。こうして詩人たちはあらたに詩友となり言葉と叙情を重ねていくのですね。(辺詩作成の日付は本日ではありませんがあえてこの日の記述としておきます)
高木敏克氏と金里博氏とによる即興詩の交換は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075176189331980288
2018*12*12/兵庫県現代詩協会アンソロジー「ひょうご現代詩集」の編集が佳境。2月刊行予定なので、ぎりぎりといったところか。あとは印刷担当の澪標に頑張ってもらおう。各県に「詩人協会」があるが、あれだけ詩人が多く「山之口貘賞」といった賞もあるのに沖縄には詩人たちの組織がないのは不思議。
2018*12*13/今月は作品締切が多く、原稿執筆をこなすのにあっぷあっぷしている。次に取り組んでいるのは「奔(望月至高個人俳誌)」「吟遊(夏石番矢・鎌倉佐弓代表)」への俳句出稿。私は「豈」を含め3つの俳誌に所属していることに。あいかわらず句会には参加せずもっぱらメディア出稿のみに特化。
2018*12*14/兵庫県現代詩協会の「会報」(年に二回発行)が刷り上がり発送作業。ところが印刷所のミスで表1と表4を逆に組んで印刷している。これはプロの印刷所にすれば基本以前の大チョンボ。協会の担当者にすこし厳しく指摘する。校正もこわいですが印刷はこわいですね。他山の石といたしましょう。
2018*12*15/フラメンコギターの名手・住田政男氏が演奏する本日のスペイン料理カルメンの舞台。相変わらず住田氏のギターは冴えわたり、カンテの鳥居貴子氏も良い。そして今夜は久しぶりに諸藤ふみさんが出演。この人の「ソレア」は何度見てもいい。魂を揺さぶる渾身の踊り。
渾身の踊り・諸藤ふみさんのソレアの動画は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075184906479628289
2018*12*16/俳句とは、自ら作句することと、他人の作品を多く読む(選句する)ということでもあろう。俳句の作句力は選句力に直結するように思えてならない。私は勝手に南海日日新聞「なんかい文芸」に掲載されている俳句を読んで選句しているが、そうした行為も作句力に役立っているのかもしれない。
2018*12*17/「奔」と「吟遊」に出稿する俳句を一気に書きあげ朝にメール出稿。ふたつほど原稿が片付いて安堵している。わたしの作句手法は、書くまでにいくばくかの時間を要する。他人の作品をある程度多く読み込みたいからだ。今回は出口善子さんから送ってもらった俳誌「六曜」も読ませてもらった。
2018*12*18/南海日日新聞に掲載された「奄美にとって明治150年」連載シリーズの5回目。酒井正子・川村女子学園大学名誉教授。テーマは「奄美シマウタの近代」。シマウタは奄美のシマ(集落)という存在が孵卵器のような役割を果たしていたのですが、仕掛け人や、イベントによって変容していくのです。
酒井正子氏の南海日日新聞への文章は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075548948402589696
2018*12*19/「奄美にとって明治150年」(南海日日新聞)連載シリーズのトリを飾るのが、この前利潔氏の文章。奄美の近代史は「本土への経済移民」の歴史でもあるのです。近代という開かれた交通システムが人の移動を促します。本土では島出身者が集住化してエスニシティー集団を形成していくのです。
前利潔氏の南海日日新聞への文章は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075550332279635970
2018*12*20/南海日日新聞に連載している「つむぎ随想」の5回目記事です。神戸市長田区は奄美群島の中でもとくに徳之島出身者が多く住んでいる地域です。今回のコラムでは、ケミカルシューズ業界でミシンを踏み続け、かつウタシャでもある向江登美江さんをインタビューした内容を紹介しているのです。
「つむぎ随想」の5回目記事は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075897909768409088
2018*12*21/「つむぎ随想」(南海日日新聞の連載しているコラム)の11月の記事は、奄美俳句についてです。3年ほど前から、奄美俳句を読み続けています。しばらくこの読みをつづける予定です。本土とも沖縄の俳句とも違った諸相がこの奄美の俳句を読んでいると見えてきます。文芸からみえる景色です。
奄美俳句についての考察は、https://twitter.com/gunshaku/status/1075899165299769344
2018*12*22/今年最後の「つむぎ随想」の掲載にわたしのコラムを選んでくれました。わたしなりに奄美と兵庫県という視座から〈明治維新150年〉を俯瞰してみたつもりです。ではなぜこの150年にこだわったかというと、次のメルクマールである「明治維新から200年」には生きていないだろうからなのです。
今年最後の「つむぎ随想」は、https://twitter.com/gunshaku/status/1076257470547292160
2018*12*23/クリスマス三連休の真ん中の日。スペイン人スタッフHは二日前、故郷のバルセロナに帰っていきました。スペインを含めたヨーロッパの人たちにとってクリスマスは特別な祭日。キリストの生誕を祝う以上に、家族があつまって家族の絆を深める、いわば日本の正月のような位置づけでしょうね。
2018*12*24/日本もスペインも立憲君主国です。スペインの場合、近代になってなんどか国外に追放されていた時期が長かったせいか、国民との距離を短くしようとする努力が実践されています。20世紀に限っても共和制の時代やそれに続くフランコ総統による長い独裁時代には亡命を余儀なくされていました。
2018*12*25/いよいよ2018年もあとわずか。街なかのディスプレイは早ければ今日から正月の商品やポップに意匠替えされます。神戸・三宮は阪急三宮駅の改修工事で駅周辺の人の流れが変わっています。大阪駅周辺も何年にもわたって工事が繰り返されていましたね。三宮はこれからしばらく混乱が続きます。
2018*12*26/「ひょうご現代詩集2018」の編集は、現在印刷所から兵庫県現代詩協会の会員の皆さんに初校ゲラが届いた状態です。さっそくその返事が編集担当のわたしのもとに帰ってきています。今年設立22周年を迎えた同協会はすこしずつ世代交代が進んでいます。今年になって新しい会員も増えています。
2018*12*27/年賀状の住所を整理しています。物故者あり、住所変更あり。次から出すのをよそうと思う人も。わたしが賀状を出す人はなにがしかの表現をしている人がほとんどなので、会社から退職を機にやめたり、年賀状の終活宣言をする人はいません。生あるかぎり表現を続けようとしているのでしょう。
2018*12*28/年の暮れまでやるべきことが多く、今日はほとんど一日電卓をたたいていました。おもしろいもので、一日数字ばかり相手をしていると、世間の事象がすべて数字に還元されていく、つまりすべてが数値化されて私の前に顕現するのです。〝数字脳〟というのでしょうか。これはこれでまた刺激的。
2018*12*29/今年最後の土曜日。フラメンコライブで締めくくりです。カルメン、満席でした。バイレのみんさんも定期的に踊ることでキャリアが重なっていきます。私はフラメンコを見る時、そのバイレに〝踊りに芯があるかどうか〟を見定めます。ただ先生に習ったとおり上手に踊っていてもダメなのです。
2018*12*30/引っ越しを考えている人がいます。いまより一室多い部屋を選んだそうで、新しい家具を買おうとしています。好みを聞いていると、どうもネオクラシコの家具に興味があるようです。でも現実の選択は「無印良品」的なコンセプトになりそうとのこと。新居に越しても日々の片付けは大切だよね。
2018*12*31/大晦日に奄美から一本の電話。現役最高齢の唄者・森チエさんが逝去されました。百歳近いお年です。奄美の宝でした。瀬戸内町網野集落の出身。これで大島の「民謡大賞」以前のシマウタをしる貴重な唄者がまたいなくなりました。90歳の歌声はこのサイトで聞けます。
森チエさんの歌声が紹介されているサイトを知るには、https://twitter.com/gunshaku/status/1079698468187205632