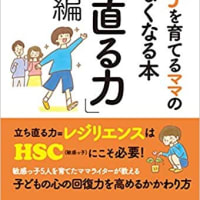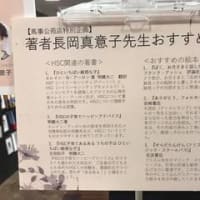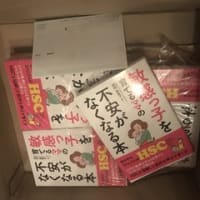「最近落ち着きなく動き回るんだよねー」、
という学齢期前の息子君を持つ友人と、
「異なる特性が存在する」ということを互いに分かりつつ、
(「ごそごそ動いた方が学習効果アップ!ADHDギフテッド舞踏家タイプの子」)
「他にもできること」を模索してみました。
1.スポーツで身体もよく動かしている様子の息子君、
スポーツなど「型にはまった動き」だけでなく、
広場や野原を思いっきり走り回るような「自由な動き」をのびのびできる機会を取り入れる。
2.スケジュールを少しゆったりにしてみる
3.話しかける前に一呼吸おき、しっかり目を見て一言一言少しゆっくりと言葉をかける
私自身、感じてきたのは、
そばにいる私自身が、
「あれもしなくちゃこれもしなくちゃ」と忙しなく動き回ったり、
心ここにあらずで接していると、
如実に落ち着きなくなる子もいるということ。
4.ゆったりと一緒に過ごすのを楽しむ時を持つ
子供って、
「この人、自分と一緒にいること喜んでくれてる」と感じるときに、
最も満たされるんですよね。
5.たっぷり甘えさせ、スキンシップを取る
「虹色教室通信」の
「本当のことを教えてもらえない時代 言ってもらえない時代」という記事をシェア。
「動き回るのは、甘えやスキンシップが足りないのでは?」という指摘、
自らを振り返り、確かにそういう面もあったかなあと思います。
その友人もそうなんですが、
兄弟姉妹も多いと目も手も行き届かず、
その上、友人も私も常に「夢」とか「目標」との葛藤の中で、
試行錯誤で進んでいる状態。
それでも、共に過ごす時間の「長さ」を大幅に変えることはできなくても、
「質」を大幅に高めていくことはできるんですよね。
その子と向き合い、
共にいることを心から喜んでいると示す時を3分でも5分でも日常にちりばめていく。
すると、随分と違ってくると感じています。
6.「私のせい」と責める必要もなく、
「あ、ちょっと注意して接していこう」ぐらいの気持ちで、
変えられることを変えていく
同じ対応をしても全く影響を受けない子もいれば、
すぐに分かりやすく影響を受ける子もいる。
少し水を注げばいっぱいになる器もあれば、
プールを満たすほど注がなければいっぱいにならない器もある。
また同じサイズの器であっても、
注ぐ側に、
蛇口をひねればすぐに水が溢れ出るような装備のある場合もあれば、
バケツをかついで何キロも歩いてようやく井戸にたどり着くような装備しかない場合もある。
だから、「注ぎ方が足りない」というような言葉は、
周りと比べず、ただ自分なりに受け止めればいい。
そして、自分なりにできることに、取り組んでいきたいですね。
異なる特性を持つ子供に関わる方々に、エールを送りつつ!