先日小学校3年生の三女が、学校からこんな通知をもらってきました。
「○○小学校として嬉しいお知らせです!娘さんは、エンリッチメントプログラムに入ることができます!」
以前、この学区の小学校には「ギフテッドプログラム」がないと書いたのですが、この「エンリッチメントプログラム」が「ギフテッドプログラム」とのこと。週に1、2回、30分ほど通常のクラスを抜け、「問題解決能力」を培うための様々なアクティビティーをするのだそうです。
この学区では、小学校3年生と5年生に、教室で一斉に「認知テスト(CogAt: 論理展開能力を測るテスト。IQテストの一部分のようなもの。米国ではこうして「ギフテッドプログラム」の審査に用いられることも多いようです)」が施されます。その結果によって、プログラム入学資格が決まるのだそうです(全国で96パーセンタイル以上)。そしてこの小学生時点でのプログラムへの入学が、その後中学の「ギフテッドプログラム(毎日一時間、次女も羊の脳みそを解剖したりと楽しそうです)」への入学にも繋がるようです。プログラムは3月から始まるとのこと。
今日は、ちょっと特徴のある三女の発達について、シェアさせていただきたいです! 彼女はこれまで、勉強などがすいすいとできてきたタイプでは、決してないんです。
・以前のIQテスト(5歳時)でも今回の認知テストでも、「スピード面」や「言語面」に凹が出ているんですが、情報を処理したり答えをはじき出すのもゆっくりめ。「言語面」では、幼少期から、あれ?と思うことがたびたびありました。
例えば、「バナナ」を「バンダンダン」と言ってました、周りの子が皆さらっと言える年齢になっても。つい最近でも、「アイブラウ(まゆげ)」を「アイブラウン」、「マルティプリケーション(掛け算)」を「マリプリケーション」と言っていたり。細かく聞いているといまだに「微妙に違う」発音がちょこちょこあるんですよね。アラスカ時代も時々お友達に「○○(三女)はちいちゃな子みたいにうまく話せないことがあるのよね」と言われていたようです。
耳が悪いのかなとも思ったのですが、聴覚の検査に引っかかることもなく、端々にあれ?と思うことはあるものの、通常の生活や学習には特に支障がなかったため、ここまできています。我が家は第二外国語として「日本語」を学ぶという立場なのですが、普段あまり使い慣れない他言語の発音の習得も、周りの子に比べ難しそうです。
12と21がこんがらがったり、スペルも母音や子音が順番逆ということも2年生ぐらいまで頻繁にありました。夫のディスレクシアの影響が出ているのかなと様子を見ています。
計算もあまりにものろいので、「早く計算できるパターン」など2年生に上がる頃教えたことがあるのですが、さっぱり呑み込めませんでした。「よく理解できないこと」を暗記するのが苦手のようです。
読書も、これは今でもなんですが、絵がついているものを好みます。
上の娘達も、三女ほどではないのですが、「言語面」に凹が見られ、審査された方々には、両親共に母国語が英語ではないことの影響があるのだろうと分析されたのを思い出します。そして上の娘たちの場合、年を経るにつれ、凹度が減っていきました。
ディスレクシアの遺伝、両親の母国語が英語でない、三女の特徴、が絡み合うなかで、発達を見守っていきたいです。
・個性として気が付くのは、想像遊びが大好きで、石や人形でも何かを手にすると、えんえんと一人でぶつぶつ話していること。手にしたものが物語のキャラクターに変身するようです。車の中でも、家の中でも、こうして一人で話してることが多いです。
・去年ぐらいから、少しずつ、勉強面が伸び始めたようです。こちらでは、リーディングはレベルに合わせ上の学年の内容を受けられるのですが、クラスで一人だけ一学年上のトップレベルに。算数やスペルも、クラスの子達から「分からなかったら○○(三女)に聞け」という扱いを受けているようです。
とはいえ、ぱっぱとできる子という様子ではないようです。去年の担任の先生との懇談会では、「娘さんが答えるのに詰まっている場合は、考え過ぎていることが多いんです。そこまで考えなくていいのよ、と背中を押してやるとすっと答えを書きます」と言われました。
・情緒面では、我が家の子の中では一番穏やか。周りの子や大人の気持ち的なことにも敏感ですが、今のところ毎日ニコニコと楽しそうです。ただ、何かうまくできないと、「ああ私はだめなのよね。うまくないのよね」とすぐに思い込むようなところがあります。
今回のこのプログラム入学への通知も、「クラスで私だけこの手紙をもらったのだけれど、私にはチューターが必要なのね(勉強に遅れている子は通常のクラスから抜けチューターの時間がある)」と残念そうな表情で言っていました(そうではないと説明し納得。今はプログラム開始を楽しみにしています)。今の学校では、周りから「できる」という扱いを受けているんですが、それでも自己評価はすぐに沈んでしまえるようです。
情緒面マインド面を鍛える働きかけの大切さを思います。
・今回の認知テストでは、「非言語での論理展開力」が全体を引き上げていました。視覚的なパズルや図形などの空間認識力などですね。
「スコアの偏り」についての分析では、「非言語的な能力に偏っている場合、学校の成績などとは結びつきにくい場合もある」ともあり、今後勉強面もますます複雑になっていく中で、サポートしていきたいと思っています。
こうして我が家の子供達をみても、これまで出会ってきた「ギフテッドプログラム」の子から放課後スクールのチャレンジングな子をみても、「賢さ」のようなものって、一筋縄ではなかなかくくれないものなんですよね。
全体的によくできる子というのも確かにいます。それでも、我が家のように凸凹のある場合は、凸を見れば「賢い!」ともなり、凹を見るなら「この子ちょっと大丈夫かな」ともなる。本人も、「私は果たしてできるのかできないのか」と、「間」を揺れているようなところがあります。その上、「心理的敏感さ」も手伝い、「ああ、やっぱり私はだめだめなんだ」としゃがみこんでしまったり。
凸を励まし強め、凹を具体的に補足できるスキルを身に着け、マインド面を鍛えていくこと。
それが、我が家の課題であり、同時に、多くの子にも当てはまるのだと思っています。
皆さんの関わる「賢い」子供たちが、伸びていくのを応援しています!










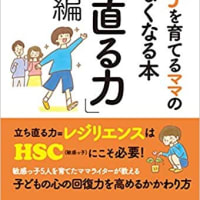





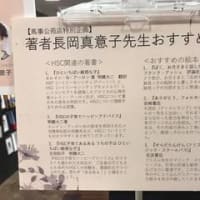

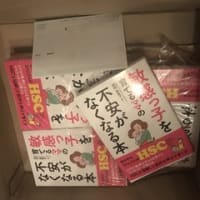

古い記事に失礼します。
我が家の娘がどうもギフテッドらしく、
この凹凸の凹をどうしていくのがいいのか、考えあぐねています…。
難しいです。
満遍なく様々なことを器用にできる「ギフテッド」とされる子もいますが、凸凹のある子も多いのですよね。
この短いコメント欄では、ひとまず一辺倒なことしか言えませんが、凹は、凸で自信や勢いや力をつけていくと、より引き上げていきやすいです。例えば、大好きなプログラミングを通して人との関り方を学んだり、植物への興味からデータ等を整理整頓する力や漢字を書く力を身に着けていったり。
新年へのカウントダウンが始まってますね。ココさんにとって2019年が、最善へと開かれていく年となりますよう祈っています。
2018年最後に良きヒントを頂きました。
どうも、凹凸の凸ばかり見てきてしまったようで、伸びてくるだろうと思っていた心の成長(自己肯定感を自ら下げてしまうようなところが一番気になっています)が思うように伸びてこず、またここへ来て能力の開きが大きく目立ってきたように感じ焦っておりました。
引き上げる視点は正直あまり意識しておりませんでした。
少し、視野を広げてみます。
ありがとうございました。
良いお年を!
凸を観てこられたのですね。それは、娘さんにとって、幸せなことだと思います。
「ギフテッド」とされる子は、学校で一番になって州大会などより大きな大会で3位になったからと、絶望するような子もいます。ですから、なかなか自己肯定感が育ちにくいこともあるかもしれません。
凸凹も取り去ったところで、「ただ普通であるあなたも大好きだよ」と感じられるような時間も過ごせるといいですね。ただただ、ふざけて笑い合ったり、何でもない話をして楽しんだり。
凹面は高望みせず、日常生活に支障のない程度に引き上げていけるといいですね。
2019年、いい年にしましょう!
娘の凹の部分と感じる箇所は、社会性の低さ。幼さです。
そして感情のコントロールの未熟さ。
娘にとっては経験が全て、のような気がします。
なので、ゆっくりいきます。
気になった点がありコメントします。
過度激動、ギフテッド、HSCとの関連性です。
HSCという言葉が広まってきているように思うので。
以前は私も同じことを指していると考えていましたが、どうも違うようなので。
まあでも様々な捉え方があってよし、だとも思ってはおります。
子どもが直面する課題や問題は、「この性質や神経系の特性を持ちながらこれからの社会を生きていくための力とスキルを培いたい!」という子どもからのサイン、そう思います。
中には、時間がかかることもありますが、経験を大切に、ゆっくりと取り組まれるココさんというお母さんが傍にいて、娘さんは本当に幸せです。
ご指摘の「関連性」についてですが、私自身は、過度激動はギフテッドの特徴のひとつとされ、過度激動についてエレイン・アーロン氏が「HSCの敏感さと同じコンセプト」としていると、理解しています。
どんな定義や分類も、子どもがより健やかに伸びていくために、活用していきたいですね。