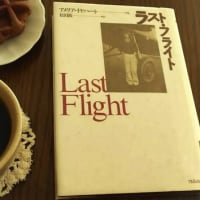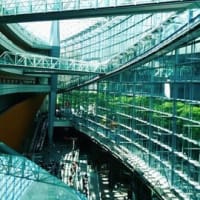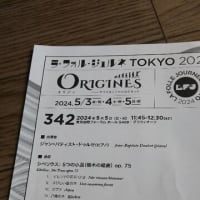3月になりました。
昨夜から今朝は春の嵐が通り抜けていきましたね。 昼前にはもうキラキラ日差しが溢れていましたけれど、 まだ北の方は心配… 被害ありませんように。。


昨日の空…


雨に煙る今朝…
***
ここ数日読んでいた、アルトゥーア・シュニッツラーの短編から、とても興味深いものがあったので、 tweet には載せましたが ちょっとこちらにまとめてみます。
アルトゥーア・シュニッツラー作「死んだガブリエル」という短編。
『夢小説 闇への逃走 他一篇』岩波文庫 に収載されています。
物語の舞台は、19世紀末か20世紀初頭のウィーン。 舞踏会の会場… 社交の場にひと月ぶりに出て来た男… 華やかな舞踏会のホールに向かいながら男はひと月前の出来事を思い出します、、
「…ベッドの中で新聞をひろげて、ガブリエルの自殺を知ったあの朝のこと。そしてひとことも恨みがましいことを言わずに永遠の別れを告げたガブリエルの感動的な手紙を…」(池内紀・訳)
… 読み進めてわかるのは、 同じ女を愛した元学友のふたりの男。。 自分宛ての遺書をのこして 友人ガブリエルは自殺した。 物語はそこから始まる…
、、 この設定、 なんだか、まるで漱石先生の『こころ』のよう…
と思いつつ読んでいたのですが、、 それだけだったら漱石とシュニッツラーの繋がりが? なんて思わなかったのでしょうけれど、、 友人の自殺に関係があるかもしれぬその男は
「…自分には高貴な憂愁というものがあるではないか。…… あの存在の憂愁を、ただにぎやかなだけの愚劣な舞踏会などで台なしにしていいものか…」
、、などと考えるのです、、 まるで『それから』の代助か、 『虞美人草』の甲野さんの感じがしません? 、、そして、、 自殺したガブリエルにも関係のあった女性(女優なのですが) 、、 彼女の描写は、、
「驚きを知らぬ女は、 誰のものになることもない……」
と。。 『虞美人草』のヒロイン 藤尾、、 常に泰然と動じない態度で思うがままに男性を操ろうとしているような女性… その藤尾に対して、 腹違いの兄 甲野が《嘲り》のように呟く場面がある
「驚ろくうちは楽(たのしみ)がある。女は仕合せなものだ」
、、この甲野さんの台詞は 思わせぶりのように、『虞美人草』の中で3回も繰り返されるのですよね、、 どういう意味だろう… と、 ちょっと考えてしまうような言葉、、「驚く女」って? そして、 シュニッツラーの 「驚きを知らぬ女」って…
***
シュニッツラーの「死んだガブリエル」は、 文庫でたった27頁のとても短い作品なのですが、、 これらのイメージによって 読んでいる脳内は、 女優の女は藤尾に、、 学友の自殺のわけを知る男は 代助の態度を持った『こころ』の先生に、、 そんな風に思えてしまって…
以前にもシュニッツラーの短編を読んで、 19世紀末からの、 夏目漱石の同時代の作家だということはわかっていたので、 つい興味で漱石蔵書録を開いて見ると… あったのです Arthur Schnitzler の著書が。。 ドイツ語だったのでどんな本か分からず検索しているうち、、 明治期に シュニッツラーを日本へ紹介したのは 森鴎外(森林太郎)だということもわかり。。
こちらの公開論文を参考にさせていただきました⤵
吉中俊貴「鴎外文庫のシュニッツラー」駒沢大学学術機関リポジトリ
http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/33768/
鴎外先生はシュニッツラーの作品を7篇も翻訳されているそうです。 その中の 鴎外先生が明治41年(1908年)に訳出した「アンドレアス・タアマイエルが遺書」という短編は、 漱石先生の蔵書にも収録されていることがわかりました。 漱石先生が持っていたその短篇集はデジタル書籍のアーカイヴで見ることができます⤵
Dämmerseelen : Novellen by Schnitzler, Arthur
https://archive.org/details/3490869
↑の初版は 1907年ですが、 漱石蔵書にあるのは 1908年版のようです。 だから、なんとなく 鴎外先生が翻訳したのを漱石も読み、 それでシュニッツラーに関心を持って本を入手したのかな、、 などと想像されます。
国立図書館デジタルコレクションで検索すると、 (シュニツレル)シュニッツラーの小説や戯曲が、1910年代~20年代に多く翻訳されていたことがわかります。
***
このような明治・大正期の背景は、 たまたま興味で検索してみたことですが、、 今回読んだ短編 「死んだガブリエル」… とても短い作品なのに、 一切の無駄な説明を廃した心理劇が緻密で、 物語の展開にどきどきするような緊張感を生み出していて、、 描かれているのは、 ウィーンの舞踏会の、社交界の極めて儀礼的な仕草のやりとりや、 真意を隠した上品な会話だけ。 しかし ガブリエルの自殺をめぐる 主人公の男の秘密は暴かれる…
はっきりと書かれていない部分も多く、 ガブリエルの手紙とはどういう内容だったのか、、 そして主人公の男に、 全てをお見通しのように説いてみせる「謎の男」フェルディナンドという名が出てくるのですが、 その人の説明が一切無い、、。 そういう「書かれていない物語」も含めて 不思議なミステリアスな、 そして頽廃的で高踏的な、、 独特の魅力のある作品でした。 だから尚更、 その「書かれていない部分」を想像でひろげていくと、、 『虞美人草』の藤尾みたいな女性が生まれたり、、 『こころ』の先生とKみたいな関係が想像されたりするのかなぁ、、(それは私が勝手に想像することですが) 面白いなぁ、、と。
漱石先生がシュニッツラーをどう読んでいたのかは知りません。 そういう研究がもしあったら、 また興味深く読んでみたいです。
***
もう一つ、、 さきほど「書かれていない部分」… と書きましたけど、 昭和の作家もシュニッツラーブームがあったそうで、、 (何かに書いてあったのですが今、それが見つかりません)
前に、 『椿實全作品』という本について書きましたが(>>)、 その中に収録されている 「月光と耳の話―レデゴンダの幻想―」という作品は、 シュニッツラーの「レデゴンダの日記」を基にしていて、 その「書かれていない部分」を幻想的に創作したような、、 きっと 椿實もシュニッツラー作品に惹かれていたんだろうなぁ、、と想像される 「外伝」みたいな作品です。
シュニッツラーの「レデゴンダの日記」は、 『花・死人に口なし 他7篇』(岩波文庫)に入っています。
・・・話を明治に戻して、、
森鴎外先生が明治41年(1908年)に訳出した「アンドレアス・タアマイエルが遺書」という短編は 青空文庫で読めます。 さきほど読んでみたのですが、、 シュニッツラーは医師だったそうですが、 たぶん医師ならではの関心、 19世紀末の先端医学でもあった(と思う) 遺伝学とか生殖学とかの関心とオカルティックな想像が結びついたような、、 摩訶不思議な短編でした。
医学者である森林太郎先生はきっと興味深かったでしょうし、、 超自然現象好きの漱石先生も きっと面白く読んだことと思います(笑)
、、、 まだ読んでいないシュニッツラー作品、、 いずれまた読みましょう。。 こういう世紀末のミステリアスな雰囲気を持った作品は、 ぜったい古い訳文の方が味わいがありますね。。 古書で探してみよう…
・・・ お雛様 飾りました ・・・

漱石先生の五女は、 3月2日生まれの「ひな子」という名でした。 その雛のような可愛らしいおさな児のことは(悲しい出来事ですが) 『彼岸過迄』の作品の中に書かれていますね、、 かつてそれについては書きました(>>) そんな「ひな子」ちゃんの事も思い出しつつ…
すべての幼な子が 元気で 幸せでありますように…
昨夜から今朝は春の嵐が通り抜けていきましたね。 昼前にはもうキラキラ日差しが溢れていましたけれど、 まだ北の方は心配… 被害ありませんように。。


昨日の空…


雨に煙る今朝…
***
ここ数日読んでいた、アルトゥーア・シュニッツラーの短編から、とても興味深いものがあったので、 tweet には載せましたが ちょっとこちらにまとめてみます。
アルトゥーア・シュニッツラー作「死んだガブリエル」という短編。
『夢小説 闇への逃走 他一篇』岩波文庫 に収載されています。
物語の舞台は、19世紀末か20世紀初頭のウィーン。 舞踏会の会場… 社交の場にひと月ぶりに出て来た男… 華やかな舞踏会のホールに向かいながら男はひと月前の出来事を思い出します、、
「…ベッドの中で新聞をひろげて、ガブリエルの自殺を知ったあの朝のこと。そしてひとことも恨みがましいことを言わずに永遠の別れを告げたガブリエルの感動的な手紙を…」(池内紀・訳)
… 読み進めてわかるのは、 同じ女を愛した元学友のふたりの男。。 自分宛ての遺書をのこして 友人ガブリエルは自殺した。 物語はそこから始まる…
、、 この設定、 なんだか、まるで漱石先生の『こころ』のよう…
と思いつつ読んでいたのですが、、 それだけだったら漱石とシュニッツラーの繋がりが? なんて思わなかったのでしょうけれど、、 友人の自殺に関係があるかもしれぬその男は
「…自分には高貴な憂愁というものがあるではないか。…… あの存在の憂愁を、ただにぎやかなだけの愚劣な舞踏会などで台なしにしていいものか…」
、、などと考えるのです、、 まるで『それから』の代助か、 『虞美人草』の甲野さんの感じがしません? 、、そして、、 自殺したガブリエルにも関係のあった女性(女優なのですが) 、、 彼女の描写は、、
「驚きを知らぬ女は、 誰のものになることもない……」
と。。 『虞美人草』のヒロイン 藤尾、、 常に泰然と動じない態度で思うがままに男性を操ろうとしているような女性… その藤尾に対して、 腹違いの兄 甲野が《嘲り》のように呟く場面がある
「驚ろくうちは楽(たのしみ)がある。女は仕合せなものだ」
、、この甲野さんの台詞は 思わせぶりのように、『虞美人草』の中で3回も繰り返されるのですよね、、 どういう意味だろう… と、 ちょっと考えてしまうような言葉、、「驚く女」って? そして、 シュニッツラーの 「驚きを知らぬ女」って…
***
シュニッツラーの「死んだガブリエル」は、 文庫でたった27頁のとても短い作品なのですが、、 これらのイメージによって 読んでいる脳内は、 女優の女は藤尾に、、 学友の自殺のわけを知る男は 代助の態度を持った『こころ』の先生に、、 そんな風に思えてしまって…
以前にもシュニッツラーの短編を読んで、 19世紀末からの、 夏目漱石の同時代の作家だということはわかっていたので、 つい興味で漱石蔵書録を開いて見ると… あったのです Arthur Schnitzler の著書が。。 ドイツ語だったのでどんな本か分からず検索しているうち、、 明治期に シュニッツラーを日本へ紹介したのは 森鴎外(森林太郎)だということもわかり。。
こちらの公開論文を参考にさせていただきました⤵
吉中俊貴「鴎外文庫のシュニッツラー」駒沢大学学術機関リポジトリ
http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/33768/
鴎外先生はシュニッツラーの作品を7篇も翻訳されているそうです。 その中の 鴎外先生が明治41年(1908年)に訳出した「アンドレアス・タアマイエルが遺書」という短編は、 漱石先生の蔵書にも収録されていることがわかりました。 漱石先生が持っていたその短篇集はデジタル書籍のアーカイヴで見ることができます⤵
Dämmerseelen : Novellen by Schnitzler, Arthur
https://archive.org/details/3490869
↑の初版は 1907年ですが、 漱石蔵書にあるのは 1908年版のようです。 だから、なんとなく 鴎外先生が翻訳したのを漱石も読み、 それでシュニッツラーに関心を持って本を入手したのかな、、 などと想像されます。
国立図書館デジタルコレクションで検索すると、 (シュニツレル)シュニッツラーの小説や戯曲が、1910年代~20年代に多く翻訳されていたことがわかります。
***
このような明治・大正期の背景は、 たまたま興味で検索してみたことですが、、 今回読んだ短編 「死んだガブリエル」… とても短い作品なのに、 一切の無駄な説明を廃した心理劇が緻密で、 物語の展開にどきどきするような緊張感を生み出していて、、 描かれているのは、 ウィーンの舞踏会の、社交界の極めて儀礼的な仕草のやりとりや、 真意を隠した上品な会話だけ。 しかし ガブリエルの自殺をめぐる 主人公の男の秘密は暴かれる…
はっきりと書かれていない部分も多く、 ガブリエルの手紙とはどういう内容だったのか、、 そして主人公の男に、 全てをお見通しのように説いてみせる「謎の男」フェルディナンドという名が出てくるのですが、 その人の説明が一切無い、、。 そういう「書かれていない物語」も含めて 不思議なミステリアスな、 そして頽廃的で高踏的な、、 独特の魅力のある作品でした。 だから尚更、 その「書かれていない部分」を想像でひろげていくと、、 『虞美人草』の藤尾みたいな女性が生まれたり、、 『こころ』の先生とKみたいな関係が想像されたりするのかなぁ、、(それは私が勝手に想像することですが) 面白いなぁ、、と。
漱石先生がシュニッツラーをどう読んでいたのかは知りません。 そういう研究がもしあったら、 また興味深く読んでみたいです。
***
もう一つ、、 さきほど「書かれていない部分」… と書きましたけど、 昭和の作家もシュニッツラーブームがあったそうで、、 (何かに書いてあったのですが今、それが見つかりません)
前に、 『椿實全作品』という本について書きましたが(>>)、 その中に収録されている 「月光と耳の話―レデゴンダの幻想―」という作品は、 シュニッツラーの「レデゴンダの日記」を基にしていて、 その「書かれていない部分」を幻想的に創作したような、、 きっと 椿實もシュニッツラー作品に惹かれていたんだろうなぁ、、と想像される 「外伝」みたいな作品です。
シュニッツラーの「レデゴンダの日記」は、 『花・死人に口なし 他7篇』(岩波文庫)に入っています。
・・・話を明治に戻して、、
森鴎外先生が明治41年(1908年)に訳出した「アンドレアス・タアマイエルが遺書」という短編は 青空文庫で読めます。 さきほど読んでみたのですが、、 シュニッツラーは医師だったそうですが、 たぶん医師ならではの関心、 19世紀末の先端医学でもあった(と思う) 遺伝学とか生殖学とかの関心とオカルティックな想像が結びついたような、、 摩訶不思議な短編でした。
医学者である森林太郎先生はきっと興味深かったでしょうし、、 超自然現象好きの漱石先生も きっと面白く読んだことと思います(笑)
、、、 まだ読んでいないシュニッツラー作品、、 いずれまた読みましょう。。 こういう世紀末のミステリアスな雰囲気を持った作品は、 ぜったい古い訳文の方が味わいがありますね。。 古書で探してみよう…
・・・ お雛様 飾りました ・・・

漱石先生の五女は、 3月2日生まれの「ひな子」という名でした。 その雛のような可愛らしいおさな児のことは(悲しい出来事ですが) 『彼岸過迄』の作品の中に書かれていますね、、 かつてそれについては書きました(>>) そんな「ひな子」ちゃんの事も思い出しつつ…
すべての幼な子が 元気で 幸せでありますように…