支えを作って負担を分散させる方法のヒント、前回のつづきです。
マッサージ用のベッドで治療する時、そのまま立ち続けると、下肢にかかる負担が大きくなって疲労しやすくなります。

そのような時は、膝を少し曲げて大腿部をベッドに預けるようにしてみてください。

すると、セラピストの体重が床方向とベッド方向に分散するので、下肢にかかる負担が和らぎます。
膝蓋骨がベッドに当たるのが不快だったら、膝を深めに曲げて大腿の下部に当てたり、下肢を回旋させて膝蓋骨の内側や外側に当てるようにするとよいでしょう。
膝をベッドに預けた状態と、伸ばした状態を適度に使い分けることで負担が分散できれば、より楽に長時間の作業に耐えられるようになります。
たったこれだけのことなのですがまったく違いますよ!!
それが身体の使い方というものなのですね。
また、身長の高いセラピストが低いベッドで治療する時、体幹の前傾が強くなって腰への負担が大きくなることがあります。
そのような時は片脚をベッドの上に乗せ、反対の膝をやや深めに曲げて腰を落とし、大腿部をベッドへ寄りかかるようにしてみてください。

こうすることで身体の位置が低くなるので、体幹を前傾させる度合いが少なくなり、より楽に操作できるようになります。
必要なら前回ほどお話したように、立てた膝に肘を乗せる、あるいは胸をつけるようにすると、さらに腰への負担を減らすことができます。

こちらは身長の高いセラピスト以外の方にも役立てる方法です。
前回今回と、身体の支えについてその一例をご紹介しました。
はじめのうちは「このような方法があるのかぁ 」と、知識として覚えてから練習してよいでしょう。
」と、知識として覚えてから練習してよいでしょう。
けれども慣れてきたら、その場その場で自分の感覚を頼りに工夫していけるようになるのが理想です。
前回と今回の方法いずれも状況は多少違っていても、似たような発想で支えを作っていたのではないでしょうか。
基本は楽に操作するという「楽操」です。
≪『楽操』のすすめシリーズ≫をご参照ください。
自分の身体の声を聞いて、身体が「しんど操」「つら操」「くるし操」にしていると感じるなら、すぐに修正しなければいけません。
患者さんの身体やテクニックを使うことに気を奪われて、自分の身体をないがしろにしていたら遅かれ早かれ悲鳴を上げるようになります。
とくに教わった方法にハマり込み、考えが固定化されてしまうと、工夫することを忘れて「痛くても仕方がない 」で済ましてしまっている方も少なくありません。
」で済ましてしまっている方も少なくありません。
そうならないためにも、日ごろから自分の身体の状態をよく観察するようにしてください。
まずはご紹介した方法によって比較の対象ができるので、これまで自分が同じ状況で用いていた方法と比べてみましょう。
どちらがより楽かということを実感することによって、少しずつ感覚が養われていきます。
自分にとってより楽な方法を取り入れるようにしてい下さいね。
くれぐれも私の話を鵜呑みにはせず、必ず自分で確認して納得してから取り入れるようにしましょう。
自分にとって何が楽なのか?ということを知るためのヒントとして、今回のお話しが役立てばと思います。
次回は2月14日(土)に更新です。
 大阪セミナーのご案内
大阪セミナーのご案内
はれやかグループさんからのご依頼で、大阪(岸和田市)にてセミナーをさせていただくことになりました。
関西方面で手技療法に興味をお持ちの方、どうぞご参加ください。
テーマ「肘・手部への徒手的アプローチ」
開催日時:2015年03月21日(土) 09:00~17:00
受講料:12,960円(税込)
はれやかセミナー
 寺子屋DVD発売のご案内
寺子屋DVD発売のご案内
手技療法の寺子屋でご紹介しているような手技療法の基本が、医療情報研究所さんよりDVDとして発売されました。
私が大切にしていることを、出来る限りお伝えさせていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。
医療情報研究所
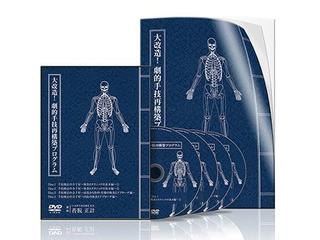
 ☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
手技療法の寺子屋ブログを始めてから今月でまる6年になり、おかげさまで記事も300を越えました。
これだけの量になると、全体をみたり記事を探すのも手間がかかるかもしれません。
そこで、少しでもタイトルを調べやすくできるように、このお休みを使って目次を作ってみました。
手技療法を学ばれている方、興味を持たれている方にご活用いただき、お役に立てれば幸いです。
手技療法の寺子屋ブログ「目次」
今のところまじめに更新中!
手技療法の寺子屋ブログ読者の方の友達リクエスト、歓迎します!!
(どなたかよくわからないときがありますので、メッセージを添えてください)

マッサージ用のベッドで治療する時、そのまま立ち続けると、下肢にかかる負担が大きくなって疲労しやすくなります。


そのような時は、膝を少し曲げて大腿部をベッドに預けるようにしてみてください。

すると、セラピストの体重が床方向とベッド方向に分散するので、下肢にかかる負担が和らぎます。
膝蓋骨がベッドに当たるのが不快だったら、膝を深めに曲げて大腿の下部に当てたり、下肢を回旋させて膝蓋骨の内側や外側に当てるようにするとよいでしょう。
膝をベッドに預けた状態と、伸ばした状態を適度に使い分けることで負担が分散できれば、より楽に長時間の作業に耐えられるようになります。

たったこれだけのことなのですがまったく違いますよ!!
それが身体の使い方というものなのですね。

また、身長の高いセラピストが低いベッドで治療する時、体幹の前傾が強くなって腰への負担が大きくなることがあります。

そのような時は片脚をベッドの上に乗せ、反対の膝をやや深めに曲げて腰を落とし、大腿部をベッドへ寄りかかるようにしてみてください。

こうすることで身体の位置が低くなるので、体幹を前傾させる度合いが少なくなり、より楽に操作できるようになります。
必要なら前回ほどお話したように、立てた膝に肘を乗せる、あるいは胸をつけるようにすると、さらに腰への負担を減らすことができます。


こちらは身長の高いセラピスト以外の方にも役立てる方法です。
前回今回と、身体の支えについてその一例をご紹介しました。
はじめのうちは「このような方法があるのかぁ
 」と、知識として覚えてから練習してよいでしょう。
」と、知識として覚えてから練習してよいでしょう。けれども慣れてきたら、その場その場で自分の感覚を頼りに工夫していけるようになるのが理想です。
前回と今回の方法いずれも状況は多少違っていても、似たような発想で支えを作っていたのではないでしょうか。
基本は楽に操作するという「楽操」です。
≪『楽操』のすすめシリーズ≫をご参照ください。
自分の身体の声を聞いて、身体が「しんど操」「つら操」「くるし操」にしていると感じるなら、すぐに修正しなければいけません。
患者さんの身体やテクニックを使うことに気を奪われて、自分の身体をないがしろにしていたら遅かれ早かれ悲鳴を上げるようになります。
とくに教わった方法にハマり込み、考えが固定化されてしまうと、工夫することを忘れて「痛くても仕方がない
 」で済ましてしまっている方も少なくありません。
」で済ましてしまっている方も少なくありません。そうならないためにも、日ごろから自分の身体の状態をよく観察するようにしてください。
まずはご紹介した方法によって比較の対象ができるので、これまで自分が同じ状況で用いていた方法と比べてみましょう。
どちらがより楽かということを実感することによって、少しずつ感覚が養われていきます。
自分にとってより楽な方法を取り入れるようにしてい下さいね。
くれぐれも私の話を鵜呑みにはせず、必ず自分で確認して納得してから取り入れるようにしましょう。
自分にとって何が楽なのか?ということを知るためのヒントとして、今回のお話しが役立てばと思います。

次回は2月14日(土)に更新です。
 大阪セミナーのご案内
大阪セミナーのご案内
はれやかグループさんからのご依頼で、大阪(岸和田市)にてセミナーをさせていただくことになりました。
関西方面で手技療法に興味をお持ちの方、どうぞご参加ください。
テーマ「肘・手部への徒手的アプローチ」
開催日時:2015年03月21日(土) 09:00~17:00
受講料:12,960円(税込)
はれやかセミナー
 寺子屋DVD発売のご案内
寺子屋DVD発売のご案内
手技療法の寺子屋でご紹介しているような手技療法の基本が、医療情報研究所さんよりDVDとして発売されました。
私が大切にしていることを、出来る限りお伝えさせていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。
医療情報研究所
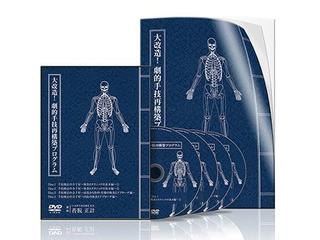
 ☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
☆ブログの目次(PDF)を作りました 2014.01.03☆)
手技療法の寺子屋ブログを始めてから今月でまる6年になり、おかげさまで記事も300を越えました。
これだけの量になると、全体をみたり記事を探すのも手間がかかるかもしれません。
そこで、少しでもタイトルを調べやすくできるように、このお休みを使って目次を作ってみました。
手技療法を学ばれている方、興味を持たれている方にご活用いただき、お役に立てれば幸いです。
手技療法の寺子屋ブログ「目次」
今のところまじめに更新中!
手技療法の寺子屋ブログ読者の方の友達リクエスト、歓迎します!!
(どなたかよくわからないときがありますので、メッセージを添えてください)












 )、胸郭から肩にかけての力が少ないと上肢の支えがツラくなる時があります。
)、胸郭から肩にかけての力が少ないと上肢の支えがツラくなる時があります。

































































 」
」