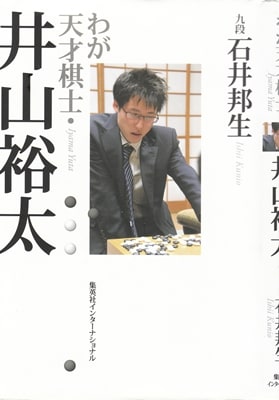紹介が後回しになったMYCOMのもう一冊の新刊、
「淡路流 戦いを極める3つの秘法」。
「3つの秘法」なんていうと、物凄いテクニックに聞こえるが、
その内容はというと「攻めるか守るか」「根拠を奪うか、封鎖するか」
そして「戦いの一段落」を正しく判断して打ちましょうというもの。
普通じゃん!
構成は朴道純。
内容はそれぞれのテーマに沿っての次の一手(選択肢つき)形式。
特に目新しいところはないが、
いざ解いてみると結構間違うことがあり、
自分の攻めの感度が相当落ちているのを実感した。
…実戦不足だしねぇ。
問題図までの手順が掲載されている点や、
わかりやすい解説はこれまでの淡路プロ(朴さん)の本と同様。
尚、根拠を奪うか、封鎖するか」というテーマは、
同時発売された「三村流 布石の虎の巻」とも共通するテーマになっており、
多少の相互補完性があり、併せて読むといいかも…。
尤もそれを狙って同時発売されたわけでもないと思うが…。
「淡路流 戦いを極める3つの秘法」。
「3つの秘法」なんていうと、物凄いテクニックに聞こえるが、
その内容はというと「攻めるか守るか」「根拠を奪うか、封鎖するか」
そして「戦いの一段落」を正しく判断して打ちましょうというもの。
普通じゃん!
構成は朴道純。
内容はそれぞれのテーマに沿っての次の一手(選択肢つき)形式。
特に目新しいところはないが、
いざ解いてみると結構間違うことがあり、
自分の攻めの感度が相当落ちているのを実感した。
…実戦不足だしねぇ。
問題図までの手順が掲載されている点や、
わかりやすい解説はこれまでの淡路プロ(朴さん)の本と同様。
尚、根拠を奪うか、封鎖するか」というテーマは、
同時発売された「三村流 布石の虎の巻」とも共通するテーマになっており、
多少の相互補完性があり、併せて読むといいかも…。
尤もそれを狙って同時発売されたわけでもないと思うが…。