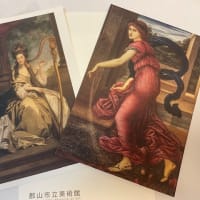今回の旅の目的はローマ「CARAVAGGIO 2025」展と、カラヴァッジョ《聖ルチアの埋葬》の終の棲家となったシラクーサのサンタ・ルチア・アル・セポルクロ聖堂(元々の所蔵先)で「祭壇画」として観ることにあった。特にシラクーサは二十数年ぶりの再訪であり、街や遺跡の様子もかなり変わっていたのが印象的だった。
ということで、まずは仙台から東京へと向かう。最近の東北新幹線は不意のトラブルがあるので、念のため東京(羽田)で前泊することに。昼頃に仙台を出て東京に到着、せっかくの東京なので有効活用として丸の内の静嘉堂文庫に行くことにした。私的には丸の内に移転してから初めての訪問である。
・静嘉堂文庫美術館「黒の奇跡・曜変天目の秘密」展
https://www.seikado.or.jp/exhibition/current_exhibition/

ああ、窯変ではなく曜変だったのだなぁと、ドアの前で立ち止まる 。そのお目当ての(何度見ても魅了される)曜変天目は最後の暗室に鎮座していたが、展覧会では「黒の奇跡」として多様な窯の黒の陶磁器が並んだ。
。そのお目当ての(何度見ても魅了される)曜変天目は最後の暗室に鎮座していたが、展覧会では「黒の奇跡」として多様な窯の黒の陶磁器が並んだ。
はじめに目が惹かれたのは大ぶりの《油滴天目》だった。

《油滴天目》 建窯 南宋時代(12~13世紀)静嘉堂文庫
解説にも「朝顔形の大きな鉢で、器の内外に銀色や虹色に輝く斑文が広がる。...『君台観左右帳記』では、最高評価の「曜変」に次いで評価される種類の天目茶碗である。」とある。
先月、大阪市立東洋陶磁器美術館で観た《油滴天目》とはまた異なる風情であり、漆黒の朝顔の奥底からまるで宇宙が広がるように見える。
黒天目や灰かぶり天目だけでなく、様々な窯の(例えば磁州窯とか)黒色調の陶磁器も展示され、日本の陶磁器も並んでいた。黒茶碗と言えば私的に長次郎茶碗であり、ひときわ寂びた風情で佇んでいた。
日本の陶磁器として仁清の作品ももちろん展示されていたし、茶碗だけでなく交合なども洗練された造形と雅な色合いで魅了する。が、やはり黒の奇跡としてスポットライトが当っていたのは《色絵吉野山図茶壺》であった。

野々村仁清 《色絵吉野山図茶壺》江戸時代(17 世紀)静嘉堂文庫
解説にも「夜景を表したかのような黒を背景に、吉野山に咲きほこる桜の花や金の霞を描いた茶壺。華麗な蒔絵漆器を思わせる。黒い釉薬は、上絵付によるもの。」とある。
静嘉堂文庫《色絵吉野山図茶壺》が夜闇の中でも鮮やかに咲き誇る夜桜を写したものだとすると、福岡市美術館《色絵吉野山図茶壷》は金襴たる霞たなびく山々に燦然と輝く桜を写したものだろう。

野々村仁清《色絵吉野山図茶壷》(江戸時代 17世紀)福岡市美術館
が、而して、私的には福岡の吉野山の方が好ましい 。
。
ということで、最後は暗室に鎮座する唯一無二の稲葉天目の周りをぐるぐる回り、散乱する銀河を彩るその虹彩の不思議さに改めて魅了されるのであった。でもね、以前の世田谷の静嘉堂では陽光の中で鑑賞できたのであり、その青き虹彩の美しさは記憶の中にだけ留まり続けるのだろう。
さて、丸の内の静嘉堂文庫を出た後は、東京駅ロッカーで荷物をピックアップし、羽田に向かったのだった。