国立新美術館で3月24日から開催予定だった「カラヴァッジョ《キリストの埋葬》展」が中止になった!!
https://www.nact.jp/exhibition_special/2020/caravaggio2020/
「この度の新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、バチカンからの作品輸送が困難なため、本展覧会の開催は中止とさせていただくことが決定いたしました。開催を楽しみにしてくださった皆様には、ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。」(国立新美術館サイト)

カラヴァッジョ《キリストの埋葬》(1603-04年)ヴァティカン絵画館
本当に残念だけど、仕方がないと思う... 。
。















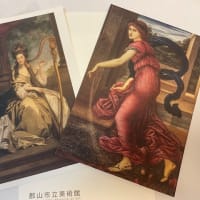




むろさんさんの確認チェックも負けず劣らずディープですね(^^;。「心中天網島」の確認にまで向かうとは!!
昔、篠田正浩監督の映画を見ましたが、面白かったものの、やはり「今日とは違った社会的なモラルや価値の存在」に困惑もしてしまいました(^^;
で、ご紹介の人魚の絵のブログも拝見しました。いやぁ、この方もディープなマニアですねぇ!ラファエル前派の作品を見ていると、ボッティチェッリ好きが多いように思えましたです(^_-)-☆
ということで、むろさんさんのロセッティ作品の捜査が上首尾に行くよう期待しております(^^)
で、今日、ようやく「芸術新潮」をサクッと立ち読みチェックしました(汗)。私的には満谷国四郎《軍人の妻》に、やはり満谷は日本のカラヴァッジェスキではないか?と思ってしまいました(^^ゞ
https://www.kasei-gakuin.ac.jp/wp-tkg-u/wp-content/uploads/2019/03/45H8.pdf
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/48189/mra_034_023.pdf
「道行」の論文の注19にホルマンハント作「イザベラとバジルの鉢」という絵が図像の元になっている可能性が書かれています。ネットでこの絵をさがすと、道行の遊女小春の姿勢と似ています。なお、J.M.ストラドウィックというバーン・ジョーンズの助手をしていたラファエル前派の画家も「イザベラとバジルの鉢」を描いていて、このイザベラの顔はロセッティの描く女性像とよく似ていますが、姿勢は異なります。道行の論文にはロセッティのことは書かれていません。ロセッティの絵はもう少し探してみます。
北野恒富の「道行」の二人の顔、能面のように真っ白で、心中する前からもう死んでいるようです。なお、心中天網島のストーリーが単なる遊女と客の色恋沙汰と叶えられない事を悲観しての死ではなく、客の男の妻が遊女に手を引くよう頼んで身を引いてもらい、その義理により夫婦の全財産で遊女を身請けするという、現代人にはよく理解できないような話(下記URL)なので、これはもう少し近松文学のことを知らないと絵のことも理解できないと思いました。近くの図書館に心中天網島の原文、現代語訳、マンガ版(里中真知子)もあるようなので借りてくるつもりです。東京ステーションギャラリーも緊急事態宣言でしばらく休館するので、再開されるまでに読んでおきます。以前の上記コメントでベルニーニとコスタンツァの石鍋論文に「今日とは違った社会的なモラルや価値の存在」と書かれていることを述べましたが、江戸時代は義理人情や封建社会の制約のためか、ベルニーニの事件よりももっと複雑なようです(ベルニーニの場合は自分の下で働いていた男が、女房コスタンツァをベルニーニに差し出し、そこにコスタンツァとベルニーニの弟ルイージとの浮気も重なって、という分かりやすい構図でしたが)。
http://nanjo-kouki.com/nk5s-22.html
人魚の絵に関しては、下記ブログに多くの作品が出ていて面白い。テーマの「絵」のところをクリックすると、ラファエル前派などの西洋絵画以外もいろいろ見ることができます。フレデリック・レイトンの「漁師とセイレーン」(ブリストル市立美術館)がエロくてよいと思いました。若い漁師の顔もボッティチェリの絵を思わせるようなルネサンスの絵風。解説文も漁師の姿勢が十字架だから信仰の力で耐えているとか、魚籠から魚が落ちているのは「魚=キリスト教信仰の象徴(奇跡のすなどりのこと?)」なので、結局誘惑に負けているとか、…納得です。
https://ameblo.jp/blue-seamade/entry-11287097346.html?frm=theme
https://ameblo.jp/blue-seamade/entry-11299553363.html?frm=theme
「芸術新潮」サイトの目次の下に小さく書いてあるのを見て、むろさんさんはがっかりだろうなぁ、と思っていました。正直、私もです(^^;。来月号(載るのかな?)が楽しみです。
で、まだ5月号をチェックしていませんが、「福富太郎コレクション展」は面白そうですね。むろさんんさん好みの「妖魚」「道行」も、なるほど!ウォーターハウス的な作品ですねぇ。やはりラファエロ前派から影響を受けている可能性があるような気がします。青木繁《わだつみのいろこの宮》なんかもそうですよね。
で、むろさんさんの「ロセッティの絵に似た雰囲気の女性」捜索のご成功を祈っております。見つけたら教えてくださいね(^^)
芸術新潮5月号、本日が発売日なので近くの図書館に行って、ヤマザキマリのリ・アルティジャーニ最終回がどうなったか、私の予想が当たっているかを見てきました。結果は… 残念ながら今月は休載とのこと。最後なので気合を入れて執筆しているためか、締め切りに間に合わなかったようです。お楽しみは来月ということで。
それでせっかくなので、特集記事を読んでいたら、福富太郎コレクションの絵にはまってしまい、特集を全部読んでしまいました。特に鏑木清方の「妖魚」と北野恒富の「道行」には強く惹かれるものがあり、この2点は是非実物を見てみたいと思いました。最近、あやしい絵とか怖い絵が流行っていて、今も東京国立近代美術館であやしい絵展が開かれています。出品リストを見るとこの2点も出ていましたが、前期のみで展示は終わっていました。1~2ヵ月早く特集してくれたら見に行けたのに、ちょっと残念と思ったのですが、ネットで調べていたら、東京ステーションギャラリーで今日から6/27まで「福富太郎の眼」展というのがあり、この2点も出ます(芸術新潮の特集もこの展覧会に連動した企画らしい)。緊急事態宣言で休館になるか気になりますが、6月まで開いているので大丈夫でしょう。
この種の絵は今の言葉でいうと、キモカワイイとかエロイというのでしょうか、上村松園の焔や甲斐庄楠音、岡本神草などの作品も最近よく話題になるようです(見たことがあるのは東博の平常陳列で上村松園の焔ぐらい。六条御息所の怨霊として、着物に描かれた蜘蛛の巣が印象的でした)。近代の西洋美術でもクノップフ(絵だけでなくウィーンにある彫刻VIVIENも)とか、ラファエル前派周辺のミレイ、ウォーターハウス、ドレイパーなどの描くセイレーンや水へ引き込もうとするニンフなど、この種の作品には強く惹かれるので、「妖魚」と「道行」も単なる美人画ではない怖さ、不気味さが心に刺さりました。また、芸術新潮の山下裕二氏解説で「道行の心中しようとする遊女小春については、ロセッティの絵に似た雰囲気の女性がある」とのことなので、何の絵なのか調べてみようと思います。
で、フィレンツェの十字架諸像についても勉強になりました。ありがとうございました!!中でも、ミケランジェロの磔刑像は私的にも一押しだと思っています。確かにS字型のひねりがあり、彫像として見ても魅力的でしたし(*^^*)
で、「ランドゥッチの日記」、やはり私の勘違いです(^^;;。巨人(gigante)の像でしたね!!
実は私も盛期ルネサンスの均整美よりも、初期ルネサンスやヴェネツィア派の方に魅力を感じます。三代巨匠の中ではミケランジェロが好きだし、むろさんさんの好みが良~くわかります(^_-)-☆
ちなみに、マニエリスムのロッソ・フィオレンティーノ《ピエタ》(ルーヴル)を観ると、ボッティチェリ《キリスト哀悼》(ポルディ・ペッツォーリ)をどうしても想起してしまいます。逸脱の美の先駆者なのかもしれませんね。
で、レオナルドは故国フィレンツェではあまり報われませんでしたね。多才ゆえの悲劇かもと思ってしまいます。芸術家は自尊心も強いし、嫉芸術家同士の嫉妬心も理解できるし、でも、やはりレオナルドはボッティチェリに親しみを持っていた故の批判(悪口?)だと思いたいです(;'∀')
また、委員の多くは画家、彫刻家、金工家など物作りをする人ですが、ファイフ(横笛)奏者のジョバンニという音楽家が一人いて、この人はベンヴェヌート・チェリーニの父親だそうです。その意見は「市庁舎の中庭」です。チェリーニの自伝(岩波文庫1993年)を久しぶりに開いてこの父のことを確認したら、興味深いことが出ていました。このチェリーニの父ジョバンニは、1494年のピエロ・デ・メディチ追放までは「メディチ家の真の忠臣」、ソデリーニの時代になってからは「想像できないほどソデリーニに目をかけられた」、メディチ家が復帰してからは「後にレオ10世となる枢機卿(ピエロ・デ・メディチの弟)に大いに目をかけられた」とチェリーニは書いています。ダヴィデ設置場所検討委員会の1504年はソデリーニの時代ですから、まさに「市庁舎の中庭(メディチ家ゆかりのドナテッロのダヴィデをどかして設置)」という反メディチの意見を述べていて、現代の我々から見るとその時々の権力者によって考えを変える節操のない人間に見えますが、音楽家も楽士として雇われる身分なので、美術家同様権力者の意向に沿って生きるのは仕方がないのでしょう。当時の芸術家の実態がよく分かる出来事です。なお、父ジョバンニはレオ10世の即位後に、ローマへ来るよう誘われたことを断ってから、政庁での役職を取り上げられてしまい、また、チェリーニは15歳頃までいやいやながら笛を吹いていて、それから彫金士に弟子入りしたそうです。
前回コメントの訂正です。輪郭に沿って切り抜いた形の板絵十字架像について、フィリッピーノやラファエロも同様の作品を描いていると書きましたが、再確認したら同様の形式ではありませんでした。フィリッピーノの絵(プラートのプレトリオ宮にある市立美術館蔵)は切り抜いていない通常の長方形の絵でした。但し、背景も他の人物も何も描かれていないので、普通の磔刑像とは少し違うようです。現地の美術館で見ているはずですが記憶はありません(来日もしていません)。ラファエロの絵(ミラノのポルディ・ペッツォーリ美術館蔵、1983年に個人から寄贈)は竿の先に取りつけて祭礼で使う行列用の十字架で、47×33cmの小さなもの。キリストは中央部に小さく描かれていて、ジオットやボッティチェリの十字架板絵のように祭壇に飾ったり、堂内の高い場所に掛けて礼拝するものではありません。この絵は2014年の渋谷ブンカムラ、ポルディ・ペッツォーリ美術館展に出たのでその時に見ました。以上2作品の形について訂正します。
また、2016年都美ボッティチェリ展図録のボッティチェリ板絵十字架像解説には、もう少し早い頃(15世紀前半~半ばぐらいか)の同様作品として、フィレンツェ・トルナブオニ通りのサン・ガエターノ教会にある板絵(フィリッポ・リッピの周辺作)を取り上げていますが、下部に聖人が3人いる状態で作られているので、ジオット型の板絵ではありません。このように15世紀後半でジオット型の十字架像板絵はほとんど例がなく、ボッティチェリの板絵(プラートの大聖堂付属美術館蔵)はこの頃としてはかなり珍しいもののようです。同図録解説によればチェッキ氏の説として、サヴォナローラが1496年にプラートで行った説教に関連した作品らしいので、フォッグ美術館の神秘の十字架像よりも少し前に作られたものと思われます。そうであればボッティチェリはまだサヴォナローラ信奉者ではない(信奉者になるのは1498年の処刑から1年後に、処刑首謀者のドッフォ・スピーニから真実を打ち明けられてかららしい)ので、この十字架板絵も単に工房がサヴォナローラ派から注文を受けたので描いただけということになります。ボッティチェリ工房が1496年頃にこのようなジオット風の板絵という古臭い形式の絵を受注したのも、そういう絵を作る工房とみなされていたということかもしれません。また、ミケランジェロは1493年頃(18歳ぐらい)にサント・スピリト教会の全裸の木彫十字架像を作っているので、古臭い形式の板絵を作ったボッティチェリ工房と新しい世代の彫刻家ミケランジェロの新旧差の大きさを感じます(15世紀前半のドナテッロやブルネレスキの木彫十字架像は全裸ではない。ミケランジェロの像は完全な裸体であることと、マニエリスムの先駆的なセルペンティナータ=蛇状の姿勢 が新しい。下記URL)。
https://firenzeguide.net/crocifissi-in-legno-a-firenze/
前コメントで池上氏の本のダヴィデ設置場所検討委員会の部分には誤りがあると書きましたが、全体としてはこの本はレオナルドのことを理解するには良い本だと思います。絵を仕上げることができない理由とか、嫡出子でないことがレオナルドの全生涯にどれほど大きな意味を持っていたのか、鏡文字を使った理由、美術家間のライバル関係のことなど、この本を読んでよく分りました。少し前のコメントで、サルバトール・ムンディのことを知るのに役立つと書きましたが、それ以上の内容です。
また、この本には、レオナルドが何人かの人とダンテについてサンタ・トリニタ教会前の広場付近で話をしていた時にミケランジェロが通りかかったので、ミケランジェロに話を振ったところ、馬鹿にされたと思ったミケランジェロは激高して「一つも作品を完成させることができないくせに偉そうにするな」という意味の言葉(実際の言葉はブロンズの馬の鋳造がデッサンだけで実現できないことについて)を言って立ち去った、そしてレオナルドはそのことが恥ずかしくなったという話が出ています(当時の年代記作者の記述なのでほぼ真実か)。今フェラガモが入っているスピーニ・フェローニ宮の前でこの二人が言い合っていたかと思うと、歴史上の有名人が今も昔もほとんど同じ建物が残っている場所で実際に出合っていたこと(そして旅行中なら自分も実際にそこにいること)に特別な感慨を覚えます。更に、目の前のサンタ・トリニタ教会の中に入れば、ギルランダイオのフレスコ画にそれらの建物が聖フランチェスコの奇跡の場面として描かれているので、現在も変わらない風景であることがより実感できます。この周辺はフィレンツェに行った時はいつも近くのホテルを利用するので、よく歩いていた場所であり、こういう経験はヨーロッパでも国内でも他の場所ではなかなかできないことです(多くの場合、建物はほとんど新しくなっていますから)。やはりフィレンツェという所は凄い町だと思います。
ただ、我々はルネサンス時代というと美術家や美術作品のことを考えますが、ランドウッチの日記では戦争や敵対者間の争い、ペスト、物価上昇、教皇選挙といったことばかりが出てきて、美術家のことはほとんど出てきません。これらが当時の人々の関心事であり、美術家の社会的地位は低く、我々は現代の常識で(ルネサンス時代を美化して)見ているということを常に頭に置いておくべきです。ランドウッチの日記に書かれているダヴィデ像移動の記事は、素晴らしい美術作品というよりも、巨大で重い物を大掛かりな木枠の装置で吊って運んだという見世物的な興味と投石事件という共和制政府とメディチ支持者との政治的対立についての関心から書かれたものと思います。なお、この記事ではジガンテ=巨人と呼んでいて、裸の像とは言っていませんが、当時も公の場に裸の彫刻があることについてはあまり気にならなかったのではないかと思います。1494年から1498年までのサヴォナローラ政権時代という禁欲的生活の時期なら裸体像はみだらであると摘発されたし、1504年頃のラファエロ作コロンナの祭壇画(現NY Met)が女子修道院の注文であるため、幼児キリストが服を着ているとか、敬虔な画僧フラ・アンジェリコの聖母子の幼児キリストもほとんど服を着ていますが、こういう例は少ないようです。
15世紀末頃にはボッティチェリの絵が時代遅れになったとか、今回と次回のリ・アルティジャーニのテーマが新旧ルネサンス美術家の対比だろうと書いてきましたが、見方を変えると、ボッティチェリ晩年の変容は更に先を行っているとも言えます。ボッティチェリの後期の作品(例えば前コメントで書いたレオナルドが批判したと推定されるチェステッロの受胎告知板絵=現ウフィッツィ)について、若桑みどり氏は小学館の世界美術大全集や芸術新潮で、ボッティチェリがマニエリスムの先駆者の一人であり、この受胎告知はその色彩や人物の捻じれた形体がポントルモの絵画の先駆的な作品であることを論じています。ルネサンス以降にマニエリスム、バロックという別の視点から魅力的な作品を残した時代が来ることを我々は知っていますが、当時の三巨匠は自分たちこそ芸術作品の頂点の時代にいると思っていたはずです。私はポントルモ、ロッソ・フィオレンティーノ、カラヴァッジョ、ベルニーニなどの作品の魅力が分かるようになってから、盛期ルネサンス美術、特に三巨匠が自己の様式を確立するようになって以降の作品は理想主義的で完成し過ぎていて、何か白々しいと感じるようになりました。19世紀後半にアカデミーの美術に反発して印象派やクリムト、ラファエル前派が出てきたのと同じような感覚です。ルネサンス美術も15世紀までの方がレオナルド、ミケランジェロの若い頃の作品を含め、自分の好みに合っていると感じています。
レオナルドの手記でのボッティチェリ批判ですが、W.ペイターの「ルネサンス」ではレオナルドの手記で名前が挙げられている唯一の同時代画家(だから一目置いていたという意味?)と書かれていたり、上記の池上氏の本では「『我らがボッティチェッラが言うように』と親しみがなければしない表現をしていて、彼に何度も触れるのは、それだけこの兄貴分の先輩が先に成功したことに対するやっかみや憧れもあったのだろう」としています。レオナルドの手記では当時流行していたパラゴーネ(芸術の優越比較論)を反映して、絵画と彫刻、絵画と詩などを比べ、かなり強引な理屈で絵画の方が優れていると述べていて、彫刻については明らかにミケランジェロを意識して書いていますが、他の画家の絵の手法についてはほとんどが技術的な意味での批判だろうと思います。例えば、ケネスクラーク著レオナルド・ダ・ヴィンチ(法政大学出版局1974)には「(レオナルドは)単なる装飾屋を軽蔑して、『ある種の画家たちは、科学を欠いているために、青色と金色の美しさにたよるほかに道がない。彼らは多額の費用をかけなければ、良い作品は生み出せないというこの上もない愚をおかしている』と述べ、これはピントリッキオのことを言っているにちがいない」としています。確かにヴァチカンのボルジア家の間のフレスコ画を見ると、金箔を貼った円形の盛り上げ装飾を多用しています(ラピスラズリの青が多いかはよく分かりませんが)。ボッティチェリに対してはどうでしょうね。システィーナ礼拝堂の装飾事業ではペルジーノ、ギルランダイオ、ボッティチェリというレオナルドとほぼ同世代の画家が呼ばれたのに対し、レオナルドは(フレスコ画を素早く描けないので当然ですが)外されています。第一次フィレンツェ時代のレオナルドは画家としての大きな成果を挙げていないので、フィレンツェではあまり仕事がなく、ミラノへ移ったということが池上氏の本にも書かれています。1500年前後の第二次フィレンツェ時代もミケランジェロに対するのとは別の意味で、ボッティチェリに対しても複雑な感情があったのは確かだと思います。
>この1504年というのはとんでもなく凄い年だったようです
できるものなら、当時のフィレンツェにタイムスリップしてみたいです!!
>市庁舎前に設置することは最初から決まっていて、一応民主的に専門家の意見を聞いたという実績作り、
現代でも有りがちな話ですね(笑)。委員達の意見も各人の思惑有りというのも興味深いですね(^^;。芸術家のライバル心、確かにありますし。でも、レオナルドのボッティチェリ名指し批判は、もしかして先輩として一目置いていた故、と思いたいですね(^^;
で、「裸の像」ですが、本が手元に無いので確認しようが無いのですが、あれ?!と思った記憶があったのです。でも、もしかして勘違い(覚え違い)の可能性もあるので、悪しからずです(^^;;
今回ダヴィデ設置場所検討委員会のことを確認したのをきっかけとして、同じ年に何があったのかを細かく月単位ぐらいで調べてみたら、この1504年というのはとんでもなく凄い年だったようです。レオナルドがパラッツオ・ヴェッキオの五百人広間にアンギアーリの戦いを描く契約を締結したのが同年5月(実際の着手は翌年)、一方ミケランジェロへのカッシーナの戦いの委嘱は8月、そして同年秋にはラファエロが21歳でフィレンツェにやってきて、翌年3月にミケランジェロがローマへ行くまでの約半年間はこの三巨匠が全員フィレンツェにいたというルネサンス美術史上まれに見る豊かな時期だったわけです。(ラファエロは1504年の多分フィレンツェへ来る前に今ブレラにあるマリアの結婚を描き、フィレンツェへ来てからは聖母子の傑作を次々に描いたことはよく知られている通り。なお、フィリッピーノは1504年4月に亡くなっているので、ラファエロとは顔を合わしていないことになります。)
フィリッピーノが1501年から1504年までに何を描いていたかは前コメントで書いた通りですが、ではボッティチェリは何を描いていたかと言うと、記録があるのは1501年銘があるLNGの神秘の降誕だけ。この絵は当時の人にも難解なギリシャ語で銘文が書かれているので、サヴォナローラの信奉者であることを隠すために描いた個人的な作品という説がある一方で、こういう難解なギリシャ語をボッティチェリが単独で書くのは無理だから、注文者がいるはずという気もします。そして、1503年から1505年までサンルカ画家組合の会費を滞納しているので、時代遅れの画家としてほとんど仕事がなかったようです(これが1510年没時点での多額の負債へとつながる)。1505年にこの組合費を全て納入しているので、これは聖ゼノビウスの奇跡連作(昨年のLNG展に1枚が出品)の代金を組合費返済に充てたという説もあります。このように三巨匠がまさに盛期ルネサンスの幕開けにふさわしい傑作を次々と仕上げている時に、ボッティチェリは宗教的な激情に満ちたゴシック回帰というべき絵や時代遅れの絵を細々と描いていたということになります。2016年の都美ボッティチェリ展にはフォッグ美術館の神秘の十字架像のキリスト磔刑の部分を切り抜いたような板絵の十字架像が出品されていましたが、これなどはまさにチマブーエやジヨットの時代に200年ぐらい時代が遡ったような作品です(もっともフィリッピーノやラファエロも同様の板絵の十字架像を残しているので、これは注文主の要求によるのかもしれませんが)。この頃のフィリッピーノの絵は若い頃の作品とあまり変わらないので、ボッティチェリの変容ぶりはなおさら目につきます。というより、フィリッピーノはストロッツィ礼拝堂フレスコ画のような「マザッチオから遠い地点まで来てしまった作品(ルネサンスの理想から遠く離れてしまったという意味)」(佐々木英也NHK出版のフィレンツェ・ルネサンス4)も同時期に残しているので、フィリッピーノはどんな作品でも描ける柔軟な画家であり、ボッティチェリはサヴォナローラの影響のためか、作風が硬直してしまったということかもしれません。フィリッピーノの柔軟性はカルミネのブランカッチ礼拝堂にマザッチオ・マゾリーノが未完成で残したフレスコ画を仕上げたり、レオナルドが未完成で放棄した東方三博士の礼拝の祭壇画を改めて引き受けてきちんと納品したことからも分かります。一見似たような作風の二人ですが、晩年の様子はかなり違うようです。
次回最終回のリ・アルティジャーニとしては、今回のテーマがレオナルドの聖アンナ画稿の出来栄えに皆が驚く場面なので、次回はミケランジェロのダヴィデ像の出来栄えに驚くシーンとそれに続いて設置場所検討委員会、そしてフィリッピーノやボッティチェリが晩年に見ていた世界と心情という新旧ルネサンス美術家の対比を描いてフィナーレということではないでしょうか。
ダヴィデ設置場所検討委員会のことを少し追加すると、各委員の発言の前に市当局の伝令からの発言として、市政府の意向が述べられています。ここでは市庁舎前のドナテルロ作ユディトが縁起の悪い像(ピサを取り戻せないのはこの像が死を現わすものだから)なのでこれを撤去してダヴィデを置くか、同じくドナテルロ作の(ブロンズの)ダヴィデ像が中庭にあり、後ろの足に欠陥があるのでこれを撤去して置くのが良いという発言をしています。これは2体のドナテルロ作の像がメディチ家ゆかりの作品なので、共和主義政府の意向として反メディチの発言をしているわけで、ランドウッチの日記でミケランジェロのダヴィデ像の移動の時に投石事件があったと書かれているのは、メディチ家支持者の残党の勢力がそれだけ強かったということです。ロッジアに置くべきという意見の中には、28歳の若造であるミケランジェロの作品が市庁舎前という名誉ある場所に置かれることへの反発(レオナルドはこれ)の他に、大理石を雨ざらしにすることへの心配からの発言もあります(これが真意かどうかは不明ですが)。最終結論に至る決定理由は残されていませんが、市庁舎前に設置することは最初から決まっていて、一応民主的に専門家の意見を聞いたという実績作り、アリバイ作りのためにこの委員会を開催したのではないかとも考えられています(現代の政治と変わりませんね)。多数決で決めたわけでもないし、政府責任者のピエロ・ソデリーニと共和主義者のミケランジェロは親しい間柄だったためです。前コメントで書いた美術家の他で名の知られた人の意見としては、コジモ・ロッセルリがボッティチェリと同じ大聖堂の角(この二人はともに60代の老人)、ピエロ・ディ・コジモがフィリッピーノと同じく「作者の意向に従うべき」、ドメニコ・ギルランダイオは10年前にペストで亡くなっているので弟のダヴィッド・ギルランダイオが出席していて、その意見はロッジアに置くべき、となっています。
なお、池上英洋著「レオナルド・ダ・ヴィンチ 生涯と芸術のすべて」筑摩書房2019年 で2ページにわたりダヴィデ設置委員会のことが書かれていますが(P146,7)、「委員でないミケランジェロ本人にも参考意見を述べる機会が与えられた」「フィリッピーノ・リッピ、ピエロ・ディ・コジモ、…らがどの案を支持したかはわかっていない」となっています。出典を上げていないので、この内容をどこから引用しているのかは分かりませんが、ミケランジェロ本人は出席していないし、フィリッピーノ・リッピやピエロ・ディ・コジモの発言内容は残されているので、この部分は誤りだと思われます。前コメントの石鍋氏の論文によれば、この委員会の記録はオペラ・デル・ドゥオモの古文書館にあって1840年に刊行され、また、その原文と英語版が1967年のジーモアのミケランジェロ研究書に収録されていて、石鍋論文もこれに基づいているそうです。池上氏はレオナルドの専門家ですが、ミケランジェロ関係資料の原文やジーモアの研究書、石鍋論文には目を通していないようです(注にもこれらは記載されていません)。
この池上氏の本や芸術新潮2007年6月号(レオナルドの受胎告知来日記念特集)には、レオナルドの受胎告知がウフィッツィに入る前はモンテ・オリヴェートのサン・バルトロメオ教会にあったこと、レオナルドの「絵画の書」に他の画家が描いた受胎告知の絵の大袈裟な身振りを批判する文章が書かれていて、この絵はボッティチェリ作のチェステッロの受胎告知(現ウフィッツィの板絵)と推定されています(原文の日本語訳は斎藤泰弘訳「レオナルド・ダ・ヴィンチ絵画の書」岩波2014)。レオナルドの手記にはボッティチェリを名指しで「絵具を含んだスポンジを投げた時の壁にできた染みと風景」についてボッティチェリを批判することを書いているので、この受胎告知の批判もボッティチェリの絵のことを言っている可能性は高いと思います。これらのことからルネサンス期の美術家間のライバル関係も、カラヴァッジョの時代のように暴力を振るったり、裁判沙汰になるほどではないが、かなり厳しい関係だったことが想像されます。レオナルドやボッティチェリが同性愛の告発を受けているというのもこの種の他人を貶めるためと思われます。なお、モンテ・オリヴェートのサン・バルトロメオ教会という所が前コメントで書いた「鎖の地図を描いた教会」と同じ場所かどうかはまだ確認できていません。
フォッグ美術館のボッティチェリ作神秘の十字架像に描かれた景色については、別冊みずゑのボッティチェリ特集(1967年)で浜谷勝也の「ボッティチェリとメディチ家の人々」に「(この絵の)背景には彼の故郷フィレンツェの荒涼たる遠景が望まれるが、落魄の身を郊外の丘辺に運んだ折心にとどめた風景であろうか。青年時代の栄光の数々やメディチ家の今昔を哀惜する心情がここに定着されているのである。」という文章が書かれています。この文章は世紀の変わり目に、時代に取り残されたボッティチェリが見ていた景色と心情をよく現わしていると思います。
最後に、 <「ランドゥッチの日記」でダビデ像を「裸の像」と書いているのが印象的でした: この「裸の像」とは日記のどの部分に書かれているのでしょうか? (1504年5月14日の移動の記事には裸の像という言葉は出てこないのですが。)
ちなみに「ランドゥッチの日記」でダビデ像を「裸の像」と書いているのが印象的でした(^^;
で、背景のフィレンツェの描き方で、どこから見たのかわかるのも面白いですね。ボッティチェリ晩年には兄との共同所有別荘と借金問題があるのとは...(^^;。むろさんさんの経済状態からの晩年考察に興味津々です!!
リ・アルティジャーニの次回最終回にフィリッピーノを主役にして何か描くとなると、上記委員会とその直後の病死のことぐらいしかないので、ここに師であるボッティチェリとの関係を絡めてくることになると思います。2016年都美ボッティチェリ展図録のネルソン氏(フィレンツェのイ・タッティ教授でフィリッピーノの研究書の著者)の論文によると、ボッティチェリとの関係は「師フィリッポ・リッピの子→弟子→共同制作者→そして最後はライバル」だそうです。1500年頃のイザベラ・デステなどの依頼者に対し、フィレンツェの画家の紹介をしている代理人の手紙によれば、フィリッピーノは仕事で忙しいがボッティチェリは仕事がなくて暇なので、すぐに注文を受けることができる状態だそうですから、ボッティチェリにとっては、かつての弟子の方が売れっ子になっている現状をどのように思っていたか、そして自分より12歳若い弟子が病気で急死した時にどのような気持ちになったのか、この辺を加えて描かれるといいのではないかと思っています。
フォッグ美術館の神秘の十字架像の背景のフィレンツェの街並みですが、ミケランジェロ広場付近から見た風景と比べると、大聖堂とパラッツオ・ヴェッキオの位置関係が左右逆になっていて、別荘のあるベッロズグアルドから描かれた景色だろうと推定されています。有名な「鎖の地図」に描かれた大聖堂とパラッツオ・ヴェッキオもこれとほぼ同様の位置関係ですが、こちらはベッロズグアルドに隣接するモンテ・オリヴェートの頂上にある修道院からの景色だそうで、神秘の十字架像の景色よりも少し高い視点からの景色です。地図上でミケランジェロ広場、ベッロズグアルド、モンテ・オリヴェートから大聖堂やパラッツオ・ヴェッキオに線を引いてみると確かにこのように見えることがよく理解できます。今私は将来のフィレンツェ訪問の準備として、ベッロズグアルドの別荘位置やボッティチェリが多額の負債を残し困窮して亡くなったことと別荘所有との事実関係についていろいろ調べているところです。この辺がはっきりすると晩年のボッティチェリの実態がもう少しよく分るだろうと思っています。(ボッティチェリ没の数年後に別荘共同所有者の兄シモーネが亡くなるまで別荘は持っていたらしいので、ボッティチェリ没時点での多額の負債による相続放棄の事実と相反するように思われる。また、購入価格やシモーネ没後にSMヌオヴァ病院に返却していることから考えると、所有権ではなく定期借地権のようなものだったかもしれない。)
で、「玉眼」は写実表現だとばかり思っていましたが、真の仏様=生身仏を現わすためだったとは...(・・;)
むろさんさんのおっしゃる通り、「ランドゥッチの日記」では、現代人とは違う見方や反応が興味深かったですし、美術品を真に理解するには当時の社会を知る必要が痛感されます。
ヤマザキマリさんが「そろそろ絵筆を置く頃」と言わせて次回が最終回ですから、確かに、ボッティチェッリこそフィレンツェ・ルネサンスを象徴するアルティジャーノだと思っているような気がしますね。
で、《神秘の十字架》はフォッグ美術館で観ているのですが、実は「え?ボッティチェッリ作品なの??」と思った記憶の方が強くて(写真も撮らなかったし)、フィレンツェの街並みが別荘付近からの景観だとは知る由もありませんでした(^^;;
https://seijo.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=3812&item_no=1&page_id=13&block_id=17
日本美術の例で鎌倉時代の仏像の目に水晶を入れる「玉眼」について、以前は写実主義という説明がされていましたが、現在これは否定され、真の仏様=生身仏(しょうじんぶつ)を現わすためと考えられるようになってきました(写実主義というのは近代の美術作品に対する言葉)。私がランドウッチの日記や吾妻鏡に特に魅かれているのも、少しでも当時の人々の考え方や精神生活の実態を理解し、美術作品を正しく理解したいと思っているからです。
ヤマザキマリのリ・アルティジャーニ、連載第1回目は2016年のボッティチェリ展の特集の時(第一特集は江口寿史)、2回目はカラヴァッジョ展の特集の時で、ともにボッティチェリが主役。それから5年、この連載の終わりにまたボッティチェリが主役となって戻ってきました。最初の時はヴェロッキョ工房の協力者だった20代の頃で、レオナルドがキリストの洗礼の天使を描くシーン。少年だったフィリッピーノも登場しています。そして今回は1501年のレオナルドがミラノから戻ってきて、聖アンナ画稿を公開する場面。ボッティチェリはこの時56歳でLNGの神秘の降誕を描いた年。44歳のフィリッピーノに向かってボッティチェリに「そろそろ絵筆を置く頃」と言わせています。その後、1504年にはレオナルド、ボッティチェリ、フィリッピーノはミケランジェロのダヴィデ設置場所検討委員会に出席(フィリッピーノはその年に病気で亡くなります)。ヤマザキマリは若い頃のフィレンツェ留学時からボッティチェリのパラスとケンタウロスが好きだったと何かで読んだことがありますが、この連載の最初と最後にボッティチェリを登場させているので、やはりボッティチェリには特別な思い入れがあるのでしょうね。次回最終回で私が描いて欲しいと思っているのは、この同じ1501年頃にベッロズグアルドの(ボッティチェリと兄シモーネ共有の)別荘付近で、かつての栄光の日々や数年前に処刑されたサヴォナローラのことを思い浮かべながら、フィレンツェの街並みの景色をスケッチしている場面です(これがフォッグ美術館の神秘の十字架像の背景のフィレンツェの街並み)。
特に《マタイの召命》の論考には私も頷けるものがあります。そして、「われわれは意識するにせよしないにせよ、無知と思い込みや偏見に満ちており、見たいように絵を見てしまいがちだということを忘れてはならないだう。」という結びは、美術ド素人の私にも自戒すべき言葉として心に響きました。
「石鍋教授退任に寄せて」では、本当に石鍋先生の「イタリア愛」がわかりますね!! 講演会でのお姿を彷彿しました(^^)
「ありがとうジョット」はかなり前に私も読んでいましたが、2009年の再版の方で読み直してみますね(^^ゞ
むろさんさん、本当にいつも貴重な情をありがとうございます!!
で、「芸術新潮」3月号のフィリピーノ・リッピとマエストロ・ボッティッチェリ登場に、むろさんさんの世界だ!と思いましたです(^^ゞ
石鍋真澄「カラヴァッジョの聖マタイ伝連作をめぐる二、三の考察」成城大学 美學美術史論集 第22輯 2020年3月
https://www.seijo.ac.jp/graduate/falit-grad-school/art-study/academic-journals/jtmo4200000067sk-att/a1592463147282.pdf
https://www.seijo.ac.jp/graduate/falit-grad-school/art-study/academic-journals/
この中で論じられているテーマの一つ、聖マタイ連作の制作順序に関しては、同じ石鍋氏が以前に出した著書「ありがとうジョット」(吉川弘文館1994、再版2009)でも書かれています(既にお読みになっていると思いますが)。今回の論文掲載の「美術史研究者の反省点」などについて、多少のニュアンスの差もありますので、比べてみるとより理解できると思います。
なお、ついでながら上記アドレスの美學美術史論集第22輯には、同大学の喜多崎氏(フランス絵画やラファエル前派など近代絵画史専門)による「石鍋教授退任に寄せて」の一文もあり、石鍋氏の「イタリア愛」がよく分るので、ご興味があれば合わせてどうぞ。また、「ありがとうジョット」は2009年の再版の方が岡田温司氏の後書き「イタリア美術に贈られた感謝状」が追加されていて、石鍋氏のイコノロジーに対する距離感やカラヴァッジョ神話等に対する研究態度を分かりやすく解説しているので、読み直すなら2009年版がお勧めです。
展覧会中止でも、多分、出版されるのではないでしょうか?? 私的には原寸をどのように本に収めるのかが興味津々です。
で、実は昔、私もRizzoli版の四つ折りQuadrifolio(CARAVAGGIO)を持っていたのですよ。(引っ越しで紛失しましたが(^^;)
むろさんさん、小学館版に期待したいですね(^_-)-☆
https://www.shogakukan.co.jp/books/09682359
3/24~に予定されていたキリストの埋葬展に合わせた出版だそうですが、展覧会が中止となっても予定通りの日に発売されるのでしょうか。
日本美術でも原寸大の画集は(仏像も含め)よくありますが、大体は週刊〇〇といった薄っぺらな本が多いようです。今回の本はかなり本格的なもののようなので期待できそうです。小学館の週刊西洋絵画の巨匠38カラヴァッジョ(2009年)には聖マタイの召命の中央の人物2人の顔だけ原寸大で出ていますね。洋書では、Electa QuadrifolioのCARAVAGGIO(Stefano Zuffi、Milano 2000年)という4つ折りの絵を28点収録した本が(原寸かどうかは分かりませんが、)かなり大型の図版を掲載しています(数年前に神田古本祭で千円ぐらいで購入)。Taschenの大型本も一部ですが原寸に近い大きさのようです。これらの図版と比べて、今度の本はどうでしょうか。
中止は本当に残念でしたが、しかたないですよね(>_<)
現状、首都圏に行く困難さは仙台も同じで、なんとか諦めもつきます。
たかさん、コロナ終息後に、またきっと機会がありますとも!!
ただ、こちら長野県から、首都圏へ行くのも難しいので、しょうがないですね。
またの機会があれば、と待っておきます。
本当に悲しいです....(涙)
悲しいです…