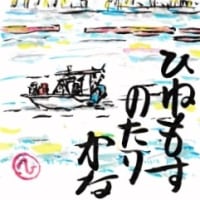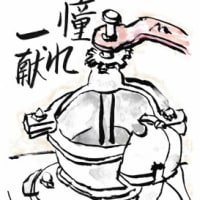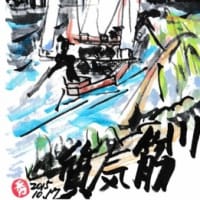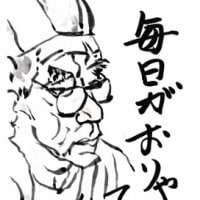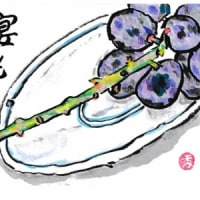絵のタイトルは、「切り株」です。
水が多い時は年輪は太く、逆に少ないとやっと刻む年輪です。
長い年月で、どちらかに必ず傾いてしまう。
環境でしょうか、生き方でしょうか。
下戸どんが 飲まねばならぬ いつの世も
今日のタイトルは、「認める」です。
私の友人たちは、ほとんどの方たちが「馬鹿だね」です。
そこまでやるのかという、形と時間をあるものに没頭する者です。
ほとんどの者が、しっぺ返しに会い反骨精神に火が付いてしまう。
埋没すれば、楽に生きて来られたのにと想像する。
フランシスコ・ザビエルは、没落したとはいえ貴族の出身で、イエズス会に入るまでは、
高僧になり、かつての栄華を取り戻したいと願っていた。
宗教改革(カトリックとプロテスタント)の最中に、イエズス会に入った。
イエズス会が求める、「建物に籠るより、Do it」 を選んだ。
ローマ法王の許可を取り付け、大航海時代の始まりと共にインドに宣教師として行った。
宣教師がいる間はその国での布教活動は成果をあげるが、いなくなると自然消滅する。
ザビエルは、そんな想いを持った。
インドに日本人ナン(?)ジロー(薩摩藩士)が、ザビエルの話が聞きたいと訪ねて来た。
インド南部での布教は、キリスト教国とイスラム教国の入れ替わりが激しく難しかった。
ザビエルは、日本に行こうと決意するが、果たして布教が可能なのかナンジローに尋ねた。
日本で認められるには、二つのことが大切であるとナンジローからアドバイスをもらう。
一つは、語ることが道理にかなっていること。
二つ目は、語ることと行動が重なること。
私は、この二つの言葉に驚いた。
ザビエルは、戦国時代(16世紀)の日本各地(時代背景が影響)で布教活動をした。
日本人は、知識欲が旺盛でまっすぐな気質を持ち合わせていると、手紙で報告した。
二つの言葉が、日本人の魂を表している。
私達は、道理を飛び越え、多くのDoitをしてきた。
時には、破廉恥な間違いも多い。
だが、精神的には常に、二つの言葉に象徴される。
ザビエルは、イエズス会に入る決意を日本で体現したのではないだろうか。
道理は、時代を超越するのか常に問われている。
語るだけなく、行動をしなければならぬことは普遍であろう。
多くの回り道をするけど、我々の心の深奥に刻み付けられている。
なぜかは分からぬが、他を「認める」日本人の根っこのような気がする。
2022年9月29日