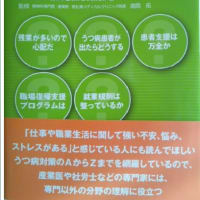ナッジ(nudge)は「そっと後押しする」という意味の英語です。
厚労省は、受診率向上のための施策ハンドブックとして紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000500406.pdf
厚労省HP(小職註;行政の作品にしては、分かりやすく、面白いです)
夏休みの宿題を早めに片付ける子ども、計画を立ててコツコツこなす子ども、2学期が始まる直前にまとめてする子どもがいます。「やらなければ」と思いながらギリギリになってしまうのは、子どもだからでも、怠け者だからでもなく、「人は常に合理的な判断に基づいて行動をするわけではない」という人の性質のためです。この性質を理解して、計画的に宿題をしてもらうためにはどうしたらよいのかというヒントが「ナッジ理論」の中にあります。選択の余地を残しながらもより良い方向に誘導する、または最適な選択ができない人だけをより良い方向に導く、この導きがナッジ(nudge)です。
ナッジ理論の原著の表紙に親子のゾウが描かれています。親のゾウが鼻で子供のゾウをそっと押しながら歩く、これが象徴的なナッジのイメージです。子ゾウを自由に歩かせて、親はそれに注意を払わない、もしくは子ゾウは背中に乗せられ、道を選択する自由がない状態と比較してみて下さい
ナッジ理論を実際の現場で使いやすい手法のフレームワークが「EAST」(Easy, Attractive, Social, Timely)です。
・Easy;簡単に、意思決定のプロセスを減らして、楽にしてあげましょう。“選ばなくていい”は、最強の選択肢。
・Attractive;正しいインセンティブを、ご褒美(インセンティブ)は結果に対してではなく、事前に渡すのがよいでしょう
・Social;正しい行動を示して 周囲の人々に影響されやすいのは自然なことです
・Timely;タイムリーに 気になる時に、気になることを伝えましょう
(参照)
1.日本証券業協会HPより
https://www.jsda.or.jp/gakusyu/edu/web_curriculum/images/mailmagazine/Vol.176_20210624.pdf
2.青森県立保健大学/行動経済学者 竹林正樹先生
実践者のナッジ 【基本編】DVD【ダイジェスト版】
https://www.youtube.com/watch?v=u86TeQxeN8c