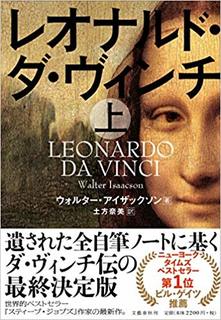
ダ・ビンチが、ルドヴィーコ・スフォルツァの宮廷から声がかかったのは、建築家や技術者でも、勿論、画家でもなく、余興のプロデューサー、すなわち、宮廷付きの演劇プロデューサーだった。
それに、初めてスフォルツァ宮を訪れたのは、外国使節団の楽師であって、自ら製作したヴァイオリンのように弾くタイプのリラを優雅に弾いて、即興で、自作自演の歌を披露したと言う。
この演劇プロデューサーの仕事の一環として、ヤギと鳥がついたヴァイオリン様の楽器や、金属製の鐘に二本のハンマーと振動を抑えるダンパーが四本ついた楽器や、ヴァイオリンとオルガンを掛け合わせた「ビオラ・オルガニスタ」等々、新しい楽器を考案した。
また、主に、朗読などの余興のために、動物やモノを擬人化した勧善懲悪ものの動物寓話などの文芸作品を作ったり、「デカメロン」スタイルのファンタジー小説の草稿も残している。
偉大なダ・ヴィンチが、束の間の娯楽に時間と想像力を費やしたのは無駄のように思えるが、舞台のデザイン、衣装、背景、音楽、舞台装置、舞踊の振り付け、シナリオ、自動機械や小道具の制作など、芸術と技術の両面において様々なスキルが求められる仕事に、ダ・ヴィンチは、そのすべてに想像力を刺激された。と言う。
当時、フィレンツェやミラノでも、宮廷で催される様々な催しは、極めて重要で、ダ・ヴィンチなどプロデューサーは、一目置かれていたようで、アイデア・フェスティバルでは、科学の実験、様々な芸術形態の比較論、独創的装置の展示など、その後の啓蒙時代にもてはやされた科学論や道徳論の片鱗が見られたと言うから、ダ・ヴィンチの芸術遍歴には貴重な時でもあったのであろう。
当時のフェスティバルや祭りなど、見たいと思うが、フランコ・ゼフィレッリのように、ダ・ヴィンチが、オペラなどを演出したりプロデュースしたりしたら、どのように素晴らしい舞台になるか、非常に興味を感じている。
オペラや演劇は、まさに、総合芸術であり、催し物やフェスティバルともなれば、もっと、総合性に富んだ芸術・美術の融合した華であり、ダ・ヴィンチは、総合的プロデュースを統括したのみならず、自ら、楽器まで自分で作り演奏し、自作の歌を限りなく感動的に朗詠したと言うのであるから、凄いタレント魂の爆発である。
尤も、レオナルドは1482年から1499年まで、ミラノ公国で活動したのだが、この間、現在ロンドンのナショナル・ギャラリーにある「岩窟の聖母」や、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の壁画「最後の晩餐」を描いており、画家としても活躍していたのである。
もう一つ興味深いのは、ダ・ヴィンチは、同性愛者であったこと。
ミラノで、ダ・ヴィンチが、人気を博したのは、美しい容姿、筋骨たくましい体格、そして、穏やかな性格で、人を惹きつける素晴らしく魅力的な人格を備えた人で、何時も、華やかでダンディな装いをしていたと言うことで、女性には持てたはずだが、女性には関心がなかった。
それに、動物愛が嵩じて、ノミ一匹殺せない性格で、動物を犠牲にして作られた衣服を避け、リネンを好んで身に着けると言う状態で、菜食主義者でもあった。
ヴェロッキオ工房に居た頃、男色事件で逮捕寸前まで行ったことがある程だったが、ミラノ近郊のオノレ村の貧しい農家の10歳の少年ジャン・ジャコモを、弟子か助手か分からない状態で手元に置いて、この小悪魔みたいな性悪な美少年を「サライ(小悪魔)」と呼んで、恋人として、ダ・ヴィンチが、亡くなるまで、ほとんどの時期を一緒に過ごしたと言う。
このサライは、人のモノを平気で盗んだり、宴会をぶっ壊したり、悪さをして、ダ・ヴィンチを、随分困らせたと言うのだが、ひたすら彼の罪を許して、記録し続けたと言うのである。
これは、プラトンの時代には、パイデラスティアー(paiderastia、少年愛)が一般的に見られた現象だと言うのだが、これと同じで、プラトン自身も、ダ・ヴィンチ同様に同性愛者であった。
プラトニックラブは、肉体的な欲求なり結びつきを離れた精神的な恋愛のことと解釈されているのだが、ウイキペディアによると、
プラトンは『饗宴』の中で、男色者として肉体(外見)に惹かれる愛よりも精神に惹かれる愛の方が優れており、更に優れているのは、特定の1人を愛すること(囚われた愛)よりも、美のイデアを愛することであると説いた。 と言うことで、もっと、哲学的な意味合いの表現なのである。
いずれにしろ、同性愛など、私の埒外の世界で、全く理解を越えているのだが、プラトンやダ・ヴィンチと言った凄い偉人が子孫を残さなかったと言うことは、惜しいことだとは思うのだが、やはり、偉大な業績を残す人物は、どこか、常人とかけ離れた性行なり資質を持っていると言うことであろうか。
それに、初めてスフォルツァ宮を訪れたのは、外国使節団の楽師であって、自ら製作したヴァイオリンのように弾くタイプのリラを優雅に弾いて、即興で、自作自演の歌を披露したと言う。
この演劇プロデューサーの仕事の一環として、ヤギと鳥がついたヴァイオリン様の楽器や、金属製の鐘に二本のハンマーと振動を抑えるダンパーが四本ついた楽器や、ヴァイオリンとオルガンを掛け合わせた「ビオラ・オルガニスタ」等々、新しい楽器を考案した。
また、主に、朗読などの余興のために、動物やモノを擬人化した勧善懲悪ものの動物寓話などの文芸作品を作ったり、「デカメロン」スタイルのファンタジー小説の草稿も残している。
偉大なダ・ヴィンチが、束の間の娯楽に時間と想像力を費やしたのは無駄のように思えるが、舞台のデザイン、衣装、背景、音楽、舞台装置、舞踊の振り付け、シナリオ、自動機械や小道具の制作など、芸術と技術の両面において様々なスキルが求められる仕事に、ダ・ヴィンチは、そのすべてに想像力を刺激された。と言う。
当時、フィレンツェやミラノでも、宮廷で催される様々な催しは、極めて重要で、ダ・ヴィンチなどプロデューサーは、一目置かれていたようで、アイデア・フェスティバルでは、科学の実験、様々な芸術形態の比較論、独創的装置の展示など、その後の啓蒙時代にもてはやされた科学論や道徳論の片鱗が見られたと言うから、ダ・ヴィンチの芸術遍歴には貴重な時でもあったのであろう。
当時のフェスティバルや祭りなど、見たいと思うが、フランコ・ゼフィレッリのように、ダ・ヴィンチが、オペラなどを演出したりプロデュースしたりしたら、どのように素晴らしい舞台になるか、非常に興味を感じている。
オペラや演劇は、まさに、総合芸術であり、催し物やフェスティバルともなれば、もっと、総合性に富んだ芸術・美術の融合した華であり、ダ・ヴィンチは、総合的プロデュースを統括したのみならず、自ら、楽器まで自分で作り演奏し、自作の歌を限りなく感動的に朗詠したと言うのであるから、凄いタレント魂の爆発である。
尤も、レオナルドは1482年から1499年まで、ミラノ公国で活動したのだが、この間、現在ロンドンのナショナル・ギャラリーにある「岩窟の聖母」や、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の壁画「最後の晩餐」を描いており、画家としても活躍していたのである。
もう一つ興味深いのは、ダ・ヴィンチは、同性愛者であったこと。
ミラノで、ダ・ヴィンチが、人気を博したのは、美しい容姿、筋骨たくましい体格、そして、穏やかな性格で、人を惹きつける素晴らしく魅力的な人格を備えた人で、何時も、華やかでダンディな装いをしていたと言うことで、女性には持てたはずだが、女性には関心がなかった。
それに、動物愛が嵩じて、ノミ一匹殺せない性格で、動物を犠牲にして作られた衣服を避け、リネンを好んで身に着けると言う状態で、菜食主義者でもあった。
ヴェロッキオ工房に居た頃、男色事件で逮捕寸前まで行ったことがある程だったが、ミラノ近郊のオノレ村の貧しい農家の10歳の少年ジャン・ジャコモを、弟子か助手か分からない状態で手元に置いて、この小悪魔みたいな性悪な美少年を「サライ(小悪魔)」と呼んで、恋人として、ダ・ヴィンチが、亡くなるまで、ほとんどの時期を一緒に過ごしたと言う。
このサライは、人のモノを平気で盗んだり、宴会をぶっ壊したり、悪さをして、ダ・ヴィンチを、随分困らせたと言うのだが、ひたすら彼の罪を許して、記録し続けたと言うのである。
これは、プラトンの時代には、パイデラスティアー(paiderastia、少年愛)が一般的に見られた現象だと言うのだが、これと同じで、プラトン自身も、ダ・ヴィンチ同様に同性愛者であった。
プラトニックラブは、肉体的な欲求なり結びつきを離れた精神的な恋愛のことと解釈されているのだが、ウイキペディアによると、
プラトンは『饗宴』の中で、男色者として肉体(外見)に惹かれる愛よりも精神に惹かれる愛の方が優れており、更に優れているのは、特定の1人を愛すること(囚われた愛)よりも、美のイデアを愛することであると説いた。 と言うことで、もっと、哲学的な意味合いの表現なのである。
いずれにしろ、同性愛など、私の埒外の世界で、全く理解を越えているのだが、プラトンやダ・ヴィンチと言った凄い偉人が子孫を残さなかったと言うことは、惜しいことだとは思うのだが、やはり、偉大な業績を残す人物は、どこか、常人とかけ離れた性行なり資質を持っていると言うことであろうか。























