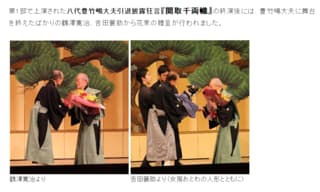今月の国立劇場の文楽は、文楽鑑賞教室「解説・文楽の魅力/曽根崎心中」(他に社会人/外国人)が主体のような感じで、私が観た恒例の5月文楽公演の方は、「絵本太功記」ながら、少し寂しい感じであった。
しかし、初日の舞台を観て、改めて、文楽の「絵本太閤記」の良さを実感し、補助金問題や人間国宝の引退等で弱体化が危惧されていた文楽界の層の厚さとその素晴らしい実力に感じ入ったのである。
本来なら15日に行く予定が、私用でダメになり、両プログラムとも、早くから、チケットがソールドアウトで諦めていたのだが、直前に、国立劇場チケットセンターのHPを叩いていたら、いくらかチケットが出て、幸いにも、鑑賞の機会を得たのである。
さて、「太閤記」の主人公は、本来なら当然太閤豊臣秀吉だが、文楽「絵本太功記」の主人公は、悲劇の智将明智光秀となっている。
我々が、良く観る舞台は、歌舞伎で言う太十、十段目「尼ヶ崎の段」で、逆賊の汚名を着た光秀が、秀吉だと見誤って自分の母親を刺し殺し、戦場で深手を負って瀕死の状態で帰還してきた息子から、味方の敗北を伝え聞き、最愛の二人に先立たれると言う切羽詰まった悲壮感に満ちたシーンなので、余計に、光秀の悲劇が強調されてくる。
平成15(2003)年4月と5月の桐竹勘十郎の「襲名披露狂言」で、この「絵本太閤記」の夕顔棚と尼崎の段が上演された。
武智光秀は、当然、桐竹勘十郎だが、武智十次郎に吉田玉男、嫁初菊に吉田簑助、妻操に吉田文雀、母さつきに桐竹紋壽、
そして、尼ケ崎の段の浄瑠璃と三味線は、切 豊竹嶋大夫 鶴澤清介 奥 豊竹咲大夫 豊澤富助、
と言う文楽界挙げての錚々たる演者による舞台が実現している。
その後、平成19(2007)年 5月に、この国立劇場で、通し狂言が実現しているので、私は、2度、素晴らしい文楽「絵本太閤記」の舞台を鑑賞したことになる。
平成12(2000)年5月の公演にも、行っている筈だが、全く記憶にないのだが、歌舞伎でも、太十は、何回か観ているので、この夕顔棚と尼ケ崎の段は、かなり、印象に残っている。
この舞台を鑑賞しながら、いつも思うのだが、母さつき(玉也)が言うように、光秀(玉志)を、主に弓引いた悪逆な謀反人として糾弾するのが正しいのか、光秀の説くように、天命を失った暴虐な独りよがりの天下人を討って革命を起こすのが正しいのか、と言う疑問で、この段では、当然ながら、その両者の主張がかみ合わずに、「また、改めて、山崎の天王山で」で終わっていることである。
史実とは異なっているので、何とも言えないのだが、そう言う疑問を感じて舞台を観ていると、私など、明智光秀謀叛の理由はともかく、どちらかと言えば、光秀の方が正しいと思っているので、母さつきや妻操(簑二郎)の言い分の方が、女の短慮と言うか理不尽のように思えて、悲劇の本質が全く変わってしまうのである。
親子の愛情を身に染みて感じながら慟哭する光秀の思いは、それを越えた正義の貫徹への挫折、天命に見放された苦悶苦痛の方が色濃い筈であろうと思う。
そう思えば、この舞台の主役は、母さつきと言うよりも、光秀の方にもっと比重が行くのだが、この太十に関しては、母さつきの立場と、光秀の立場になったつもりで、思いを切り替えながら観ている。
さて、大詰は「大徳寺焼香の段」で、武智光秀が、天王山の戦いで真柴久吉に敗れて逝った後、春永の法要が営まれて、春長の孫・三法師丸を伴って現れた久吉が、柴田勝家に屈辱を味わわせて、後日の対決を意図して終わっている。ので、一応、「太閤記」なのであろう。
失礼な話だとは思っているのだが、私など未熟者は、どうしても素人考えが先に立って、人形についても、スター人形遣いの舞台に注目が行くのだが、今回、さつきを遣っている玉也を筆頭に、人形遣いの人々は、素晴らしい舞台を演出していて、感激の一言であった。
珍しくも、早々に、チケットが完売するのも、当然と言うことであろう。
ところで、いつも、どうしても人形にばかり集中するのだが、今回は、席が上手側にあって床が斜め正面に見えていた所為もあって、特に、浄瑠璃と三味線に、注目して鑑賞させてもらった。
シェイクスピア戯曲を聴くと言うのと同じで、本来は、浄瑠璃を聴くと言うのが本筋であろうが、いつも、演劇や歌舞伎を見るのと同じ感覚で、芝居を観ると言う姿勢になってしまうのである。
客席後方で、引退された嶋大夫が観劇されていたのだが、浄瑠璃と三味線は、妙心寺の段の奥の、呂勢大夫と錦糸、尼ケ崎の段の、文字久大夫と藤蔵、津駒大夫と清介をはじめ、素晴らしい熱演で、改めて、浄瑠璃を、三業でパーフォーマンス・アーツとして創り上げた日本芸術の素晴らしさに感じ入っていた。

しかし、初日の舞台を観て、改めて、文楽の「絵本太閤記」の良さを実感し、補助金問題や人間国宝の引退等で弱体化が危惧されていた文楽界の層の厚さとその素晴らしい実力に感じ入ったのである。
本来なら15日に行く予定が、私用でダメになり、両プログラムとも、早くから、チケットがソールドアウトで諦めていたのだが、直前に、国立劇場チケットセンターのHPを叩いていたら、いくらかチケットが出て、幸いにも、鑑賞の機会を得たのである。
さて、「太閤記」の主人公は、本来なら当然太閤豊臣秀吉だが、文楽「絵本太功記」の主人公は、悲劇の智将明智光秀となっている。
我々が、良く観る舞台は、歌舞伎で言う太十、十段目「尼ヶ崎の段」で、逆賊の汚名を着た光秀が、秀吉だと見誤って自分の母親を刺し殺し、戦場で深手を負って瀕死の状態で帰還してきた息子から、味方の敗北を伝え聞き、最愛の二人に先立たれると言う切羽詰まった悲壮感に満ちたシーンなので、余計に、光秀の悲劇が強調されてくる。
平成15(2003)年4月と5月の桐竹勘十郎の「襲名披露狂言」で、この「絵本太閤記」の夕顔棚と尼崎の段が上演された。
武智光秀は、当然、桐竹勘十郎だが、武智十次郎に吉田玉男、嫁初菊に吉田簑助、妻操に吉田文雀、母さつきに桐竹紋壽、
そして、尼ケ崎の段の浄瑠璃と三味線は、切 豊竹嶋大夫 鶴澤清介 奥 豊竹咲大夫 豊澤富助、
と言う文楽界挙げての錚々たる演者による舞台が実現している。
その後、平成19(2007)年 5月に、この国立劇場で、通し狂言が実現しているので、私は、2度、素晴らしい文楽「絵本太閤記」の舞台を鑑賞したことになる。
平成12(2000)年5月の公演にも、行っている筈だが、全く記憶にないのだが、歌舞伎でも、太十は、何回か観ているので、この夕顔棚と尼ケ崎の段は、かなり、印象に残っている。
この舞台を鑑賞しながら、いつも思うのだが、母さつき(玉也)が言うように、光秀(玉志)を、主に弓引いた悪逆な謀反人として糾弾するのが正しいのか、光秀の説くように、天命を失った暴虐な独りよがりの天下人を討って革命を起こすのが正しいのか、と言う疑問で、この段では、当然ながら、その両者の主張がかみ合わずに、「また、改めて、山崎の天王山で」で終わっていることである。
史実とは異なっているので、何とも言えないのだが、そう言う疑問を感じて舞台を観ていると、私など、明智光秀謀叛の理由はともかく、どちらかと言えば、光秀の方が正しいと思っているので、母さつきや妻操(簑二郎)の言い分の方が、女の短慮と言うか理不尽のように思えて、悲劇の本質が全く変わってしまうのである。
親子の愛情を身に染みて感じながら慟哭する光秀の思いは、それを越えた正義の貫徹への挫折、天命に見放された苦悶苦痛の方が色濃い筈であろうと思う。
そう思えば、この舞台の主役は、母さつきと言うよりも、光秀の方にもっと比重が行くのだが、この太十に関しては、母さつきの立場と、光秀の立場になったつもりで、思いを切り替えながら観ている。
さて、大詰は「大徳寺焼香の段」で、武智光秀が、天王山の戦いで真柴久吉に敗れて逝った後、春永の法要が営まれて、春長の孫・三法師丸を伴って現れた久吉が、柴田勝家に屈辱を味わわせて、後日の対決を意図して終わっている。ので、一応、「太閤記」なのであろう。
失礼な話だとは思っているのだが、私など未熟者は、どうしても素人考えが先に立って、人形についても、スター人形遣いの舞台に注目が行くのだが、今回、さつきを遣っている玉也を筆頭に、人形遣いの人々は、素晴らしい舞台を演出していて、感激の一言であった。
珍しくも、早々に、チケットが完売するのも、当然と言うことであろう。
ところで、いつも、どうしても人形にばかり集中するのだが、今回は、席が上手側にあって床が斜め正面に見えていた所為もあって、特に、浄瑠璃と三味線に、注目して鑑賞させてもらった。
シェイクスピア戯曲を聴くと言うのと同じで、本来は、浄瑠璃を聴くと言うのが本筋であろうが、いつも、演劇や歌舞伎を見るのと同じ感覚で、芝居を観ると言う姿勢になってしまうのである。
客席後方で、引退された嶋大夫が観劇されていたのだが、浄瑠璃と三味線は、妙心寺の段の奥の、呂勢大夫と錦糸、尼ケ崎の段の、文字久大夫と藤蔵、津駒大夫と清介をはじめ、素晴らしい熱演で、改めて、浄瑠璃を、三業でパーフォーマンス・アーツとして創り上げた日本芸術の素晴らしさに感じ入っていた。