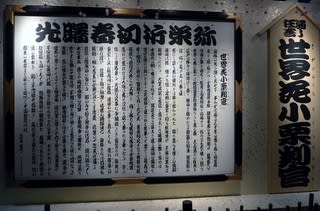今回の文楽では、織太夫襲名公演の「摂州合邦辻」は、先月、大阪の文楽劇場で鑑賞していたので、近松門左衛門の「心中宵庚申」と「女殺油地獄」に期待して出かけた。
今回のこの文楽「心中宵庚申」の舞台は、原作の中の巻からの話で、
半兵衛(玉男)の妻のお千世(勘十郎)は、これまでに2度嫁入りしたものの、半兵衛とは3度目の縁組みで、今度こそ、夫と添い遂げたいと願っていたのだが、半兵衛の義母である姑(文司)は、お千世のことを良く思わず、半兵衛の留守中に、懐妊中のお千世を実家へ帰す。
お千世の実家・山城国上田村では、お千世の姉・おかる(清十郎)夫婦が、病気で寝込んでいる老父・島田平右衛門(玉也)と暮らしていて、老父は、姑に戻されて来たお千世の身の上を案じながらも温かく迎え入れる。
そこへ、半兵衛が、浜松からの帰りがけに訪ねてきて、事情を聞かされて恥じ入り、どんなことがあっても、お千世と添い遂げることを誓う。喜ぶ老父は、娘が二度と実家に戻らぬことを願って見送り半兵衛夫婦は大坂に戻る。
お千世を連れ帰った半兵衛は、自分に財産を譲り跡を継がせようとしている義母の顔が立つように、一旦お千世を家に戻し、改めて自分から離縁を言い渡して、お千世を家の外に追い出す。半兵衛は、夫婦2人でこの家を「去る」のだと言い聞かせ、庚申詣りの人込みに紛れて、生玉神社へ向かう。
お腹の子を思いながら、半兵衛はお千代を刺し、辞世の句を詠んで、切腹して果てる。
この浄瑠璃は、近松門左衛門の最晩年の心中物で、
大坂新靫の八百屋の養子半兵衛と、姑のために離縁された女房の千世とが宵庚申の夜、生玉の大仏勧進所で心中した事件を脚色したもの。だと言う。
何故、姑がお千代を嫌うのか分からないが、この舞台では、徹底的な嫌味ばばあで、自分では生き仏だと言っているところが愛嬌だが、血のつながった甥ではなく、血縁も何もない養子の半兵衛に身代そっくり譲り渡すと言う心境との落差が、面白い。
私など、心中しなくても、いくらでも、家を出て生きる道はあると思うのだが、そこか、当時の庶民の義理と人情に生きる生き様であったのであろうか。
お千代は、2度結婚していて、1度目は夫の破産で生き別れ、2度目は死別しているので、半兵衛とは3度目だが、この文楽では、真面な相思相愛の夫婦であって、姑だけが、悪者で横車を押しており、旦那の方は、能天気で無関心と言う事らしい。
実話通りに、生玉神社境内の東大寺再建の勧進所での心中である。
念仏を唱えた後、半兵衛は、お千代に切っ先を向けるが、あれは自分のための祈りで、お腹の子どもの供養がしたいと涙を流し、半兵衛も唱和して涙にむせぶシーンが、実に切なくて悲しい。
明日はあの世で夫婦になる、別れはしばらくのことと思い定めて、元は武士の半兵衛は、大切に持っていたのであろう刀で、後ろ振りに仰け反るお千世を刺す。お千代は激しく痙攣しながら息絶え、そして、半兵衛は、辞世の歌を詠み、武士のしきたりどおりに切腹し、心中を遂げる。
半兵衛が息絶えるまでに、かなり間があるのだが、今回、勘十郎は、横向きに倒れたお千代の首をシッカリと、最後まで握りしめて支えており、玉男の半兵衛が、抱きついて倒れかけるのに応えていた。
普通は、亡くなった人形は、そのまま、舞台において、人形遣いは、去って行くのだが、勘十郎の温かさを感じて感動。
玉男の半兵衛、勘十郎のお千代は、東西一の名コンビで、感動の一語。
真面目一方で人情に篤い娘思いの老長けた玉也の老父、そして、実に優しくて甲斐甲斐しく妹を愛しむ清十郎のおかる、絶品であった。
文字久太夫と東蔵、千歳太夫と富助、三輪太夫・團七ほかの、義太夫と三味線、とにかく、ぐいぐい、胸を締め付ける、流石に近松の浄瑠璃は凄い。
余談だが、私が初めて人形の心中シーンを見たのは、もう、30年ほど前の、ロンドンでのジャパンフェスティバルの「曽根崎心中」。
初代玉男の徳兵衛、文雀のお初。
同じような後ろ振りのお初を、徳兵衛が抱きかかえるようにして、崩れ折れる壮絶なシーンであった。
私など、心中する勇気もその思いもないが、大変なことだと思っている。
今回のこの文楽「心中宵庚申」の舞台は、原作の中の巻からの話で、
半兵衛(玉男)の妻のお千世(勘十郎)は、これまでに2度嫁入りしたものの、半兵衛とは3度目の縁組みで、今度こそ、夫と添い遂げたいと願っていたのだが、半兵衛の義母である姑(文司)は、お千世のことを良く思わず、半兵衛の留守中に、懐妊中のお千世を実家へ帰す。
お千世の実家・山城国上田村では、お千世の姉・おかる(清十郎)夫婦が、病気で寝込んでいる老父・島田平右衛門(玉也)と暮らしていて、老父は、姑に戻されて来たお千世の身の上を案じながらも温かく迎え入れる。
そこへ、半兵衛が、浜松からの帰りがけに訪ねてきて、事情を聞かされて恥じ入り、どんなことがあっても、お千世と添い遂げることを誓う。喜ぶ老父は、娘が二度と実家に戻らぬことを願って見送り半兵衛夫婦は大坂に戻る。
お千世を連れ帰った半兵衛は、自分に財産を譲り跡を継がせようとしている義母の顔が立つように、一旦お千世を家に戻し、改めて自分から離縁を言い渡して、お千世を家の外に追い出す。半兵衛は、夫婦2人でこの家を「去る」のだと言い聞かせ、庚申詣りの人込みに紛れて、生玉神社へ向かう。
お腹の子を思いながら、半兵衛はお千代を刺し、辞世の句を詠んで、切腹して果てる。
この浄瑠璃は、近松門左衛門の最晩年の心中物で、
大坂新靫の八百屋の養子半兵衛と、姑のために離縁された女房の千世とが宵庚申の夜、生玉の大仏勧進所で心中した事件を脚色したもの。だと言う。
何故、姑がお千代を嫌うのか分からないが、この舞台では、徹底的な嫌味ばばあで、自分では生き仏だと言っているところが愛嬌だが、血のつながった甥ではなく、血縁も何もない養子の半兵衛に身代そっくり譲り渡すと言う心境との落差が、面白い。
私など、心中しなくても、いくらでも、家を出て生きる道はあると思うのだが、そこか、当時の庶民の義理と人情に生きる生き様であったのであろうか。
お千代は、2度結婚していて、1度目は夫の破産で生き別れ、2度目は死別しているので、半兵衛とは3度目だが、この文楽では、真面な相思相愛の夫婦であって、姑だけが、悪者で横車を押しており、旦那の方は、能天気で無関心と言う事らしい。
実話通りに、生玉神社境内の東大寺再建の勧進所での心中である。
念仏を唱えた後、半兵衛は、お千代に切っ先を向けるが、あれは自分のための祈りで、お腹の子どもの供養がしたいと涙を流し、半兵衛も唱和して涙にむせぶシーンが、実に切なくて悲しい。
明日はあの世で夫婦になる、別れはしばらくのことと思い定めて、元は武士の半兵衛は、大切に持っていたのであろう刀で、後ろ振りに仰け反るお千世を刺す。お千代は激しく痙攣しながら息絶え、そして、半兵衛は、辞世の歌を詠み、武士のしきたりどおりに切腹し、心中を遂げる。
半兵衛が息絶えるまでに、かなり間があるのだが、今回、勘十郎は、横向きに倒れたお千代の首をシッカリと、最後まで握りしめて支えており、玉男の半兵衛が、抱きついて倒れかけるのに応えていた。
普通は、亡くなった人形は、そのまま、舞台において、人形遣いは、去って行くのだが、勘十郎の温かさを感じて感動。
玉男の半兵衛、勘十郎のお千代は、東西一の名コンビで、感動の一語。
真面目一方で人情に篤い娘思いの老長けた玉也の老父、そして、実に優しくて甲斐甲斐しく妹を愛しむ清十郎のおかる、絶品であった。
文字久太夫と東蔵、千歳太夫と富助、三輪太夫・團七ほかの、義太夫と三味線、とにかく、ぐいぐい、胸を締め付ける、流石に近松の浄瑠璃は凄い。
余談だが、私が初めて人形の心中シーンを見たのは、もう、30年ほど前の、ロンドンでのジャパンフェスティバルの「曽根崎心中」。
初代玉男の徳兵衛、文雀のお初。
同じような後ろ振りのお初を、徳兵衛が抱きかかえるようにして、崩れ折れる壮絶なシーンであった。
私など、心中する勇気もその思いもないが、大変なことだと思っている。