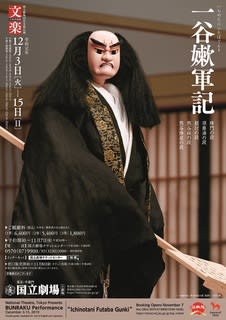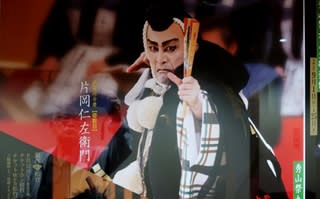錣太夫襲名披露狂言『傾城反魂香』土佐将監閑居の段の前に、「菅原伝授手習鑑」の車曳きから桜丸切腹の段が上演された。
「桜丸切腹の段」は、大阪に出かけて、2014年4月の通し狂言で住大夫引退狂言という記念すべき公演を観劇して、私は、次のように書いている。
住大夫と錦糸の浄瑠璃に乗って、浮世の未練をすべて清め捨て去って、従容と死に赴く桜丸を簑助が、悟りきれなくて号泣し続ける八重を文雀が、生身の役者以上に生き生きと人形を遣って演じ切っており、そのまわりを実直そうな白大夫のかしらをつけた玉也の父・白大夫が、撞木と鐘を打ちながらうろうろ右往左往する・・・正に、哀切極まりないこの世の終わりの光景であり、観客を忍び泣かせて、場内は水をうった様に静寂の極致。
今回は、浄瑠璃は千歳太夫と富介、同じく簔助が感動的な桜丸を遣い、八重を勘十郎、白大夫を和生と言う非常に充実したキャスティングで素晴らしい舞台を見せて魅せてくれた。
さて、冒頭の車曳きの段で、三つ子の兄弟である梅王丸、松王丸、桜丸が登場するのだが、三つ子であるから、同じようなものであるはずだが、長幼の序は、この順である。
菅丞相の肝いりで、梅王丸は菅丞相の、松王丸は時平の、桜丸は斎世親王の、それぞれの牛飼いの舎人となっている。
桜丸夫妻の取り持ちで斎世親王と菅丞相の娘苅屋姫の密会を実現させたのだが、これが、政敵の藤原時平に陰謀だと姦計を弄されて、菅丞相は、九州・大宰府に流罪になってしまい、この時点で、梅王丸と桜丸は、扶持離れすなわち浪人となっていて、その腹いせもあって、時平の牛車を襲って乱暴狼藉を働こうとしたのである。
桜丸は、菅丞相の讒言の原因を作ったその責任を感じて、既に切腹を決意していており、その後の佐太村の舞台で、父親白大夫の喜寿の賀に三つ子の兄弟とその妻たちが帰って来て祝うのだが、皆が集う前にやってきた桜丸が、その決意を父に語っている。
尤も、文楽では、この部分は暗示されているだけで、桜丸は、賀の祝いが終わって皆が退散した後で舞台に登場して切腹する。
この伏線があって、固い覚悟を知らされた父白太夫も悩み抜き、何か助ける手はないか必死になって考えるのだが、氏神詣の神籤でも凶ばかりが出て、帰ってきたら兄たちの喧嘩で桜の枝が折れてしまって凶と出ており、運命と諦めて、わが子の切腹を認める。
親としてしてやれることは撞木と鉦を打ちならすことだけだと悟るも、切腹する桜丸の周りを右往左往するばかりで、妻八重は、切腹を止めさせようと、桜丸にしがみ付いて必死に懇願して説得するが、それも叶わず、桜丸は切腹を遂げる。
この哀切極まりない愁嘆場が、この桜丸切腹の段である。
簔助の桜丸は、運命を従容と受けて立ち何の迷いもなく腹に刀を当てる、匂い立つような気品と様式美の美しささえ感じさせる迫真の芸で、どうしても桜丸の命を助けたい一心で縋り付いて断腸の悲痛を訴える勘十郎の八重の、寄り添って必死に耐える二人の姿が、儚くも輝いていて、実に美しくも悲しい舞台である。
この劇は、菅原道真の絶対善と藤原時平の絶対悪の対立抗争が主題であるから、どうしても、松王丸が悪玉のような感じになって、ワリを食っていて、この佐太村の舞台で、白大夫が、松王丸の差し出した勘当願いはあっさりと認めて、主人の時平と敵対する親兄弟を心置きなく討つためではないかと非難さえして、松王丸の菅丞相への恩義を返したいという健気な心の内を理解できずに、早々に追い返す。
この逆転劇を展開するのは、終幕に近い「寺子屋の段」。
重要なテーマは、「梅は飛。桜はかるる世の中に。何とて松のつれなかるらん。」
松王丸が、一子小太郎を管秀才の身替りに差し出して、武部源蔵に討たせた後で、いろは送りの前に、「管丞相には我が性根を見込み給ひ「何とて松のつれなからうぞ」との御歌を「松はつれないつれない」と世上の口に、かかる悔しさ。・・・」苦しい胸の内を吐露しながら、管丞相に恩を返す劇的な結末の述懐であり、
さらに、管丞相の奥方御台所を救出して管秀才に対面させ、一気に、善玉として脚光を浴びる。
松王丸は、この段で、小太郎の死を重ね合わせながら、桜丸の死を追悼して涙に暮れている。
三つ子の父親白大夫は、三つ子の兄弟に対して、「生ぬるこい桜丸が顔つき。理屈めいた梅王丸が人相。見るからどうやら根性の悪そうな松王が面構え」と言っている。
これを反映してかどうかはともかく、主役の桜丸は、一番若く見えて前髪立ちの童姿で、歌舞伎では女形が演じている。
序段の「加茂堤の段」で、加茂川の堤に、桜丸が斎世親王の牛車を乗り入れ、妻八重が苅屋姫を連れてきて、二人を車の中に押し込んで愛の交歓をさせるのだが、刺激された桜丸が、”女房たまらぬたまらぬ”と身悶えし、”追っ付けお手水がいろうぞよ”水汲んでこいと言った調子の子供じみた夫婦で、思慮分別のある貴人の逢い引きの仲立ちとも思えないアクションだから、当然、露見しても不思議ではない。
今回、しみじみと、桜丸を思う機会を得たが、この浄瑠璃、三つ子の兄弟のキャラクター一つとっても良くできた作品であると思う。
天神さんの浄瑠璃であったが、今、国立劇場の前庭の3本の梅が、きれいに咲いていて舞台を荘厳している。




「桜丸切腹の段」は、大阪に出かけて、2014年4月の通し狂言で住大夫引退狂言という記念すべき公演を観劇して、私は、次のように書いている。
住大夫と錦糸の浄瑠璃に乗って、浮世の未練をすべて清め捨て去って、従容と死に赴く桜丸を簑助が、悟りきれなくて号泣し続ける八重を文雀が、生身の役者以上に生き生きと人形を遣って演じ切っており、そのまわりを実直そうな白大夫のかしらをつけた玉也の父・白大夫が、撞木と鐘を打ちながらうろうろ右往左往する・・・正に、哀切極まりないこの世の終わりの光景であり、観客を忍び泣かせて、場内は水をうった様に静寂の極致。
今回は、浄瑠璃は千歳太夫と富介、同じく簔助が感動的な桜丸を遣い、八重を勘十郎、白大夫を和生と言う非常に充実したキャスティングで素晴らしい舞台を見せて魅せてくれた。
さて、冒頭の車曳きの段で、三つ子の兄弟である梅王丸、松王丸、桜丸が登場するのだが、三つ子であるから、同じようなものであるはずだが、長幼の序は、この順である。
菅丞相の肝いりで、梅王丸は菅丞相の、松王丸は時平の、桜丸は斎世親王の、それぞれの牛飼いの舎人となっている。
桜丸夫妻の取り持ちで斎世親王と菅丞相の娘苅屋姫の密会を実現させたのだが、これが、政敵の藤原時平に陰謀だと姦計を弄されて、菅丞相は、九州・大宰府に流罪になってしまい、この時点で、梅王丸と桜丸は、扶持離れすなわち浪人となっていて、その腹いせもあって、時平の牛車を襲って乱暴狼藉を働こうとしたのである。
桜丸は、菅丞相の讒言の原因を作ったその責任を感じて、既に切腹を決意していており、その後の佐太村の舞台で、父親白大夫の喜寿の賀に三つ子の兄弟とその妻たちが帰って来て祝うのだが、皆が集う前にやってきた桜丸が、その決意を父に語っている。
尤も、文楽では、この部分は暗示されているだけで、桜丸は、賀の祝いが終わって皆が退散した後で舞台に登場して切腹する。
この伏線があって、固い覚悟を知らされた父白太夫も悩み抜き、何か助ける手はないか必死になって考えるのだが、氏神詣の神籤でも凶ばかりが出て、帰ってきたら兄たちの喧嘩で桜の枝が折れてしまって凶と出ており、運命と諦めて、わが子の切腹を認める。
親としてしてやれることは撞木と鉦を打ちならすことだけだと悟るも、切腹する桜丸の周りを右往左往するばかりで、妻八重は、切腹を止めさせようと、桜丸にしがみ付いて必死に懇願して説得するが、それも叶わず、桜丸は切腹を遂げる。
この哀切極まりない愁嘆場が、この桜丸切腹の段である。
簔助の桜丸は、運命を従容と受けて立ち何の迷いもなく腹に刀を当てる、匂い立つような気品と様式美の美しささえ感じさせる迫真の芸で、どうしても桜丸の命を助けたい一心で縋り付いて断腸の悲痛を訴える勘十郎の八重の、寄り添って必死に耐える二人の姿が、儚くも輝いていて、実に美しくも悲しい舞台である。
この劇は、菅原道真の絶対善と藤原時平の絶対悪の対立抗争が主題であるから、どうしても、松王丸が悪玉のような感じになって、ワリを食っていて、この佐太村の舞台で、白大夫が、松王丸の差し出した勘当願いはあっさりと認めて、主人の時平と敵対する親兄弟を心置きなく討つためではないかと非難さえして、松王丸の菅丞相への恩義を返したいという健気な心の内を理解できずに、早々に追い返す。
この逆転劇を展開するのは、終幕に近い「寺子屋の段」。
重要なテーマは、「梅は飛。桜はかるる世の中に。何とて松のつれなかるらん。」
松王丸が、一子小太郎を管秀才の身替りに差し出して、武部源蔵に討たせた後で、いろは送りの前に、「管丞相には我が性根を見込み給ひ「何とて松のつれなからうぞ」との御歌を「松はつれないつれない」と世上の口に、かかる悔しさ。・・・」苦しい胸の内を吐露しながら、管丞相に恩を返す劇的な結末の述懐であり、
さらに、管丞相の奥方御台所を救出して管秀才に対面させ、一気に、善玉として脚光を浴びる。
松王丸は、この段で、小太郎の死を重ね合わせながら、桜丸の死を追悼して涙に暮れている。
三つ子の父親白大夫は、三つ子の兄弟に対して、「生ぬるこい桜丸が顔つき。理屈めいた梅王丸が人相。見るからどうやら根性の悪そうな松王が面構え」と言っている。
これを反映してかどうかはともかく、主役の桜丸は、一番若く見えて前髪立ちの童姿で、歌舞伎では女形が演じている。
序段の「加茂堤の段」で、加茂川の堤に、桜丸が斎世親王の牛車を乗り入れ、妻八重が苅屋姫を連れてきて、二人を車の中に押し込んで愛の交歓をさせるのだが、刺激された桜丸が、”女房たまらぬたまらぬ”と身悶えし、”追っ付けお手水がいろうぞよ”水汲んでこいと言った調子の子供じみた夫婦で、思慮分別のある貴人の逢い引きの仲立ちとも思えないアクションだから、当然、露見しても不思議ではない。
今回、しみじみと、桜丸を思う機会を得たが、この浄瑠璃、三つ子の兄弟のキャラクター一つとっても良くできた作品であると思う。
天神さんの浄瑠璃であったが、今、国立劇場の前庭の3本の梅が、きれいに咲いていて舞台を荘厳している。