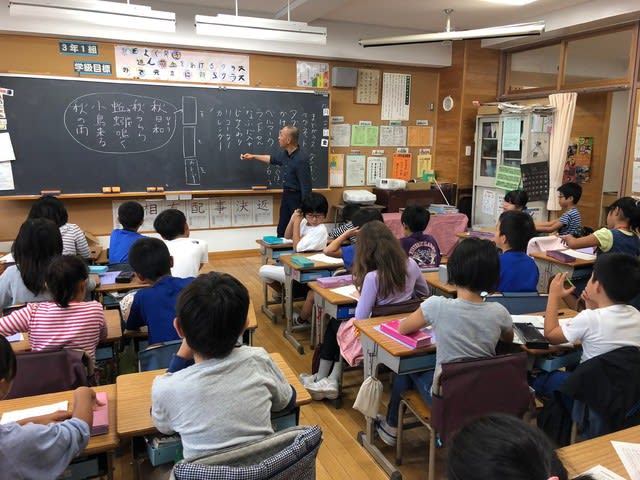何でこんなに多いのかと思ったら、「正月の俳句」である。
学校でおそらく俳句の宿題が出たのであろう。
ヒットするのがこのプログに2010年に書いたお正月俳句の作り方だ。
今だったら、この作り方を推奨しない。9年間の俳句の授業の積み重ねで、指導法もいくらか上達している。このままだと申し訳ないので、今だったらどうするか、さわりを書いておく。
1番の違いはどこか。
2010年には、まず上五にお正月とおくと書いているが、今なら下五にお正月と置かせる。
これだけで俳句になる。
思い出すには上五の方がいいのだが、上五にお正月と置くと、最後が動詞になりやすい。つまり散文になる。もっと言えば楽しいなで終わる。
下五にするだけで、こうした点を回避できる。
では、上五をどうするか。
基本は我が家ではである。自分の体験を書くことだ。
しかし、我が家といちいち書く必要はない。
最初のうちは書いて考えるとわかりやすい。
我が家ではみんな集まるお正月
誰が来るか考えてみる。
じいちゃんもおじちゃんも来るお正月
我が家のお正月を一渡り作ったら、ばあちゃんちや田舎のお正月を考えても良い。
田舎では何にもないけどお正月
である。
風の音川のせせらぎお正月
かもしれない。
こんな風に広げていくといろいろできていく。
同じようにして、初詣やせち料理、年賀状など正月にまつわるいろいろな季語を用いてお正月俳句を作ってみたらどうだろう。