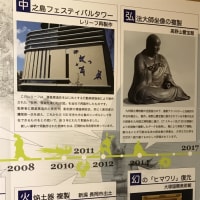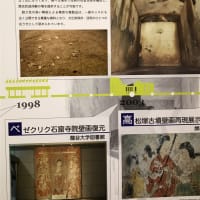従来日本の経済政策はグローバル企業を中心に考えられていたが、日本経済全体にグローバル経済でのプレイヤーの占有率は3割程度、雇用にいたっては2割程度に過ぎない。残り7割のローカル経済圏が復活してこそ、日本経済は成長軌道に乗ることができる。そのためにはグローバル経済のプレイヤー(Gの世界)への施策とローカル経済(Lの世界)への施策を分けて共に進めなければならない、という主張。
グローバル企業の業績が良くなってもトリクルダウンは起きない、Lの世界はサービス業が中心のため規模の経済よりは「密度の経済」が働く、など、Gの世界とLの世界の特性とそれぞれに必要な施策を整理している。
Gの世界とLの世界の比較対照表はこちら。

著者はGの世界とLの世界には優劣はなく、選択の問題だという。
そしてGの世界で日本が勝ち抜くには、より熾烈な競争に生き残るべく企業統治や雇用関係も見直す必要があると説く。
個人としてもリスクを取って頂点を目指す人材が求められるので、今までのように大企業に就職すれば安泰、という選択肢はなくなるわけだ。
なので、「普通にできる」人にとってはまさに選択の問題になる。
そして、Lの世界では労働生産性がポイントになり、労働生産性の低い古い企業が退場し、新しい企業が参入できるしくみが必要だと説く。
つまり企業も長期的にはGの世界で勝負するかLの世界で勝負するかが問われるし、それぞれの世界でがんばらないといけない。この、常に尻をたたき続けるところが冨山節の聞かせどころである。
ご指摘の通りだと思う。
現在はGの規律とLの規律が混在していて、企業経営者も従業員も「いいとこどり」をしているがそれは長期的には成り立たないよ、というのはその通りだと思う。
かといって、大企業がすぐに舵を(特にGの方に)切れるかというとそこは慣性が働くので難しいというのも、日本経済の課題の一つである。
個人的には大量のリテール店舗と人員を持った「メガバンク」という存在がどうなるのか興味がある(本書では一応Gの世界に入っていたが)。
実家がベタなLの世界の町工場だったので、本書でいうLの世界では雇用の流動性が高い云々は認識していたし、またLの世界では一律給料が安いかというと、自営業者や歩合の営業マンは下手な大企業のサラリーマンより羽振りがいいのも知っているので、Gの世界とLの世界は選択の問題であるというのも理解できる。
ただ、Lの世界の問題は、同族での事業承継にこだわる経営者が多く、新陳代謝が行われにくいという点。筆者はここについては地方金融機関のデットガバナンスに期待しているがここもハードルがけっこう高そうではある。
ただ、今の日本は既得権の賞味期限が見えつつあるので、変われるチャンスかもしれないとも期待している。