
There's a dragon in each and every single one of us.
Dragons feed on experiences.
It becomes stronger and stronger over the years.
We must always be in control of that dragon.
(ブータン国王の相馬市桜ヶ丘小学校でのスピーチから)
今年もよろしくお願い申しあげます。

There's a dragon in each and every single one of us.
Dragons feed on experiences.
It becomes stronger and stronger over the years.
We must always be in control of that dragon.
(ブータン国王の相馬市桜ヶ丘小学校でのスピーチから)
今年もよろしくお願い申しあげます。
貴族階級は決してその権力の絶頂にはおらず、抑圧だの搾取だのといった直接の原因はもはやまったく存在しなかったからである。一見したところ、まさに誰の眼にも明らかな権力喪失が民衆の憎悪をかきたてたのだ。
ハンナ・アーレントの『全体主義の起源』で紹介されている、トクヴィルのフランス革命の初めに突然堰を切った貴族階級に対する民衆の憎悪についての分析。(孫引きの孫引きですが)
絶対的な権力が絶対的でないとわかったとき、憎悪を抑制するものがなくなり、一気に攻撃が加速するということです。
思い返すと2011年はさまざまな場面でこの現象が見られた年だったと思います。
長期独裁政権が覆しうるとわかった瞬間にアラブ諸国で革命の動きが連鎖しました。
一方で苛烈な弾圧を続けているシリアのアサド大統領は、そのメカニズムを知っているからこそ強権行使以外の選択肢を持ち得ないのだと思います。
絶対的な権力をアピールし続けるという点では、北朝鮮の政権承継も、そしてある意味ロシアのプーチンも同じ状況にあるのかもしれません。
日本でも、小泉政権以降の現政権の不人気というのも同じメカニズムなのかもしれません。
橋下大阪府知事の強引なスタイルは、既存の権力を攻撃する側に回るという戦略と同時に、少しでも弱みを見せると危ないと自覚しているのかもしれません。
政治だけでなくでも、原発事故以来安全神話が崩壊し、電力会社に対して責任の追及や発送電分離の動きなどが起こっています。
そして大王製紙やオリンパス事件によって、企業経営者や監査法人も非難の対象になっています。
そのうち「第三者委員会」や「社外役員」もたいしょうになるかもしれません。
そして、権力ではないものの震災・原発事故で様々な安全神話が崩壊したことが、被災地の復興と津波リスク、原発事故に伴う被曝リスクや食の安全、原発の運転再開について過剰な不安や逆に判断停止を生んでいるように思います。
権力・権威が喪失した時に起きる攻撃は往々にして過剰な攻撃を生んで生産的でない結果を生み出します。
一方で、別のものを妄信したり判断停止してしまっては単なる先祖返りです。
今ある権力・権威を検証し続け、一方で自らの反応が過剰でないかをチェックし、そして代替の権力・権威についても妄信せずに検証し続けることが2012年には求められると思います。
難しいですけど。
2011年はホントにいろんなことがあったが、カダフィ、ビン・ラディンの死亡につづいて年末の大トリで金正日。
ただ、他の二人に比べれば病死というだけましなのかもしれない。
北朝鮮の体制も同時に崩壊したわけではないし。
一方で独裁政権を倒したエジプトも民政に移行できてはいないし、リビアも部族間の対立もあり、単純には行かない。
民主主義国の代表格であるEU諸国も、財政問題によって国内政治とEUの枠組みとの綱引きが行なわれているし、金融危機の解決のめどは立っていない。
そして来年は中国の首脳部の交代もある。
今年が「激動の2011年」ですむのか、始まりに過ぎなかったのか、来年になるとはっきりしてくるかもしれない。
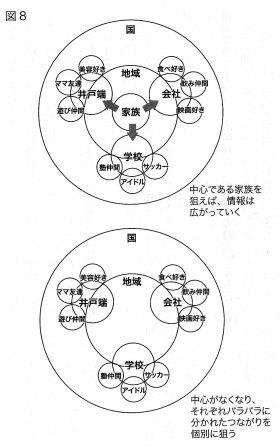
国民総幸福(GNH)で話題のブータン国王夫妻が来日しています。
でも、国民の幸福というのは為政者に期待する当然のことのはずです。
なのになぜここまで話題になるのか、ちょっと考えてみました。
・日本人は「不幸」から出発したがる
日本で首相が同じことを提唱したら、「幸福の定義とは?」「どのように計測するんだ」などという批判が続出すると思います。
一方でブータンの人々はそんなことを言わずに、現状をポジティブに考えて「そうかそれはいいことだ」と思うような国民性なのではないでしょうか。
一方、日本人にとっては、幸福というのは不幸な現状を克服した先にあるもの、達成すべき目標というとらえ方をしているように思います。
「最小不幸社会」を標榜して不評だった首相がいますが、それはネガティブなメンタリティを正面きって指摘したから不評だっただけで、ポピュリストとしてはいい勘をしていたのかもしれません。
・遠いものへの羨望と近いものへの嫉妬
もし「県民総幸福」の向上を目標にした県があったとすると、マスコミはよってたかってあら捜しをするんじゃないかと思いますし、他県の人も批判的な態度をとるのではないでしょうか。
遠い人が幸せそうにしているとあこがれる反面、身近な人が幸福そうにしていると何かしら嫉妬心が芽生えがちなので、外国という距離感も大事なんだと思います。
・でも、今の生活にはそこそこ満足している
ではブータンのGNHをうらやましがる人の多くも、ブータンに一度旅行に行こうかというレベルで、移住まで考える人はほとんどいないと思います。
「日本の生活レベル・利便性を維持しながら、ブータンの人々のような幸福感を感じたい」というところが多くの人の本音ではないでしょうか。
同様に、上の例が県でなく、過疎の村が「村民総幸福」の最大化を謳っていたとするなら、逆にほのぼのとした話題として取り上げられるのではないかと思います。
幸福になるには、まずこういうメンタリティから脱却する必要があるような気がします。
といっても貸金業法の問題ではありません。
言わば「街金」でなく「国金」の話。
NHKBSの世界のドキュメンタリーで ギリシャ 財政破綻への処方箋 ~監査に立ち上がる市民たち~という番組をやってました(本日再放送があったようですね)
NHKのサイトによると、この番組の生い立ちはつぎのとおり。
この作品は市民から寄付を募り、約85万円という低予算で制作され、最初はウェブ上で発表されましたが、金融関連報道で「豚」呼ばわりされたギリシャ、スペイン、ポルトガルなどの民衆の共感を集め、難しい経済の話ながら各地で上映されました。
ここで取り上げられていたのが「不当債務」という概念 。
元は1927年にアレクサンダー・サックという学者によって提唱された概念で、
① 政府が国民の認識と承認なしに融資を受けた場合
② その融資が国民の利益にならない活動に使われた場合
③ 貸し手がこの状況を知っていたにもかかわらず見て見ぬふりをした場合
の3条件を満たす場合国家は「不当債務」として返済を拒否できるとするものです。
サックの提唱前の19世紀末、アメリカはスペインとの戦争によってキューバを保護国にした際に、同様の理屈によって400年間にわたるスペインの植民地支配時代のキューバに対する累積した膨大な金額の債務の返済を拒否しています(Wikipediaの "Odious debt"の項目によると、この史実が不当債務の概念の下敷きになっているようです)
番組では、2002年12月のイラク侵攻計画の中でアメリカ国務省はこの概念を使ってイラクの債務(フランスやロシアからの数十億ドルの武器購入にあてたものなど)を免除しようという計画を立てたものの、この概念を途上国が主張しだすとパンドラの箱を開けることになってしまう(たとえばキブツ政権下のコンゴ、マルコス政権下のフィリピン、アパルトヘイト時の南ア・・・)ので、債権国はイラクに対する債務を自主的に80%削減するという大人の解決をしたと指摘しています。
そして、この概念を使って最近債務の削減に成功した例としてエクアドルを取り上げます。
エクアドルは石油資源があるにもかかわらず、インフラ投資などにかかる先進国からの融資がふくれあがり、2005年度では国家予算の半分の30~40億ドルを返済にまわす状態でした。
しかし、これらの債務は、過去の政権が先進国の企業と癒着して行なったものであり、投資は先進国の企業に発注されて回収され、後には無用の長物と借金だけが残っている。そしてエクアドルの石油輸出代金は債務返済という形で先進国に吸い上げられ、国民には何も残らない。(この途上国を借金漬けにする手法は「エコノミック・ヒットマン」と言われています。 エコノミック・ヒットマンの仕事については下の動画をご参照ください(ちょっと長いですけど))
本来エクアドルの石油はエクアドルの国民のために使われるべきだと新たに選出されたコレア大統領は主張します。
そしてコレア大統領は就任早々に世界銀行・IMFの指導を拒否し、過去の債務を調査する委員会を立ち上げます。
そして大統領は調査の結果を国民に公開し、過去の政権の負った債務の70%の支払いを停止すると宣言します。
エクアドルが巧妙なのはその後で、この宣言の結果投資家があわてて売りに出して暴落したエクアドルの債券を、エクアドル政府は陰でこっそり買い集め、その結果30億ドル分の債務を8億ドルで清算できたといいます(相場操縦風ですけど)。
番組は、ギリシャの債務においても不当債務が多いと主張します。
2001年には有利な為替レートを適用することで債務隠しをする(為替スワップか何かでしょうか)ことにゴールドマン・サックスが加担し、その後も元ゴールドマン社員がギリシャの債務削減の担当者に就任していたこと、独仏は金融支援の見返りとして戦闘機や潜水艦の購入を申し入れてきたことなどをあげます。
そして、ギリシャもエクアドル同様、国の債務を監査し、不当債務があれば弁済拒否をすべきだ、とまとめます。
今回「不当債務」という概念は初めて知りました。
独裁政権と結託して借金漬けにする経済支配の手法に対しては有効な主張のように思います。
ただ、番組の主張についてはギリシャって民主主義国家だったんじゃないの?という疑問はありますし、イタリアやスペインあたりがこれを言い出したら収拾つかなくなりそうです。
これはギリシャの人の主張ということで。
また、一部特権階級だけが恩恵をこうむって、借金は国民全体が負担していることに 不満が渦巻いているのは事実のようです。
エコノミック・ヒットマンが語るアメリカ帝国の秘史 前編
エコノミック・ヒットマンが語るアメリカ帝国の秘史 後編
上の動画でインタビューに応じている「元エコノミ・ヒットマン」が書いた本
(動画で取り上げられている本の前著。日本語訳がでているのはこれだけみたいです。)
読んでみようと思います。
ひきつづきTPPについて。
nikkei bp netの大前研一氏のTPPは「国論を二分する」ほどの問題ではない
大前氏らしい冷静(冷ややかな)言い回しですが、今のところいちばんまともな意見のように思えます。
長めの引用ですが備忘録代わりに。
・・・他の参加国には少なからず自国に有利な戦略的なねらいがあることだ。それに対して日本は、「交渉参加が自分たちにとって損か、得か」のレベルでもめているように見える。何とも「滑稽」な話ではないか。少なくとも日本がTPPに参加する以上は「何を達成したいのか」を明確にする必要がある。
・・・日本の財界はおしなべて賛成意見を持っているようだ。私は今まで40年にもわたって経営コンサルタントとして企業のグローバル化を手伝ってきたが、貿易障壁があって経営戦略に支障を来した国はTPP交渉参加9カ国では一度もなかった。だから、これらの国とどんな障害をどのように取り除いていこうとしているのか、政府あるいは財界には明確に説明してもらいたい、と思っている。
「新たな開国」というフレーズはなんとなくかっこいいですが何を意味しているのかわからないし、議論を曖昧にしているように思います。
また、少なくとも経団連に加盟しているような企業がTPP参加国に対して参入障壁があって困っているということもないように思うのですが。
ひょっとすると民主党と経団連の仲直りのための握手代わりのような感じも。
一方の反対派の多くは「情緒に流されているだけ」のように見える。
・・・交渉を始めたら最後、「奈落の底まで突き落とされるぞ!」という恐怖の物語はあまりにも主体性のない脅し、と映る。
これは同感だけど、上の政府の主体性のなさとあわせると漠然と不安も持っている、という人も僕も含めて多いのではないでしょうか。
で、大前氏らしさが出るのがこのあと。
「滑稽」と言えば、TPP交渉参加国である米国もそうだ。米国がTPPでねらうのは「対アジア輸出の拡大」「自由貿易圏の拡大」だ。もちろん「その心は?」と問えば、米国内での雇用拡大である。
しかし過去30年間、米国はこの手の貿易交渉の結果、貿易を拡大させたことがあったろうか? 雇用を増大させたことがあっただろうか? 私の記憶では一度もない。
(米国は)日本との交渉は政治的にうまみがある(雇用につながるかもしれないという期待がある)のでしっかりやるが、次の国が台頭してくる頃には米国側の当該産業界に強いロビー勢力が消えており、政治的に興味を失ってしまっている。こういうパターンはこの40年間、いっこうに変わっていない。
もう一つ面白い現象がある。米国が門戸開放をした市場に当初の予定通り、米国企業が「進軍してきた」ケースはほとんどない、ということである。
米国は軍・宇宙などの半導体が主力であるため、またインテル社やテキサス・インスツルメンツ社のように強いメーカーはすでに日本で生産していたため、日本が必要としている民生用の半導体を輸入することはできなかった。日本企業はやむを得ず韓国にノウハウを与えて無理に20%分の生産を委託し、「輸入実績」を作ろうとした。当時はこれが名案のように思われていたのだろうが、結局これが命取りとなって、世界最強を誇っていた日本の民生用半導体の主導権を韓国に奪われる悲惨な結果に終わっている。
つまり米国は過去40年間、「輸入自由化を相手国に飲ませます。輸出の拡大によって米国の景気や雇用は改善します」と米国民に対して言い続けてきたが、結局のところは景気も雇用も改善したわけではなかった。
米国は貿易相手国に門戸を開かせるまでは熱心だが、その後は続かない。いつも「漁夫の利」を得るのは他の国なのだ。これを「滑稽」と言わずして、何と言おう。
・・・仮に日本がTPPに参加して環太平洋で自由貿易圏が確立したとしても、米国の雇用も経済もほとんど改善することはないだろうと私は見ている。肝心の米国企業にその気がないからである。つまり、米国の強い企業は世界の最適地で生産し、魅力ある市場で勝負している。「米国国内に雇用を創出しよう」などと考えている殊勝なグローバル企業はない。だからこそ、この期に及んでも米国企業は好決算、米国の景気や雇用は停滞という対照的な状況になっているのである。
そう言われてみれば確かにそうだよな、という話。
カーター政権のときのピーナッツ問題で千葉の落花生農家が崩壊したわけではないとか、日米繊維交渉が長引いた結果日米共に東南アジア諸国に負けてしまったなどの実例をあげています。
こういう話があるのにけっこう忘れっぽいんだよなぁと自省。
米国が欲しいのは雇用であって「市場開放」ではない。ましてやEU並みの国家資格の相互認証など米国はまったく考えてもいないだろう。米国が考えてもいないことを想定して煙幕を張り、日本が世界に誇り、世界がまた日本をうらやむ「国民皆保険」を人質にとって「それが崩壊してもいいのか!」と脅す医師会も、もう少し冷静になってもいいのではないか?
日本に対して市場開放を迫る米国の農業も、オーストラリアと一本勝負すれば負ける。補助金のないオーストラリア農業は、補助金で支えられた米国農業よりも圧倒的に強いのだ。
今回の9カ国メンバーにオーストラリアが入っているということは、「例外」を設けるに違いないというヒントでもある。
これは僕も思っていて、「例外はまったくない」というのを鵜呑みにするのはナイーブ過ぎるし、国民の安全のための規制はなんと言われようと非関税障壁ではない、と断固として言い返すのが政府の仕事だと思う。
そして、相前後しますが気になるフレーズ
・・・対外交渉の下手な政府は米国の言いなりとなるが、その被害者には税金で応分の負担をしましょう、というやり方を用いるのである。今回も野田首相は早速このお家芸を持ち出し、万一農家などに被害が及べば補償はしっかりやります、などと交渉の始まる前から「鎮静剤の散布」を提案している。
結局「焼け太り」狙いかよ、と思われるのは、農業の発展を目指す人々にとってもプラスではないように思います。
日経ビジネスonlineの記事「農業の守り方を間違った」元農水次官の告白
共感できる部分もあり、できない部分もあり。
(以下抜粋の部分は若干前後します)
何しろ「原則関税撤廃」というのが大きな誤解だ。撤廃する品目もあるが、そこは正に交渉して決まる話だ。米国は米豪FTA(自由貿易協定)で砂糖などを関税撤廃の例外にしている。TPPでも米豪FTAの内容は変えないというのが米国の基本姿勢だ。若干は変えるところがあるとしても、基本は絶対に守るだろう。
日本がどうしてもコメを守りたいならば、早く交渉に入って、我々はコメ問題をこう考えると主張するべきだ。米韓FTAでコメを例外にした韓国が、もしTPPに入ってくれば、当然コメを例外にするよう主張する。日本が先に入り、WTO(世界貿易機関)のドーハラウンド(多角的通商交渉)でそうしたのと同じように、韓国と一緒にコメを守ればいい。
情報がないのが問題なら、まず交渉に参加しろということだ。交渉に参加して情報を取り、日本の強み、弱みを踏まえて交渉する。協定の中に自分たちの考えを反映させるよう、一番国益に沿うものを勝ち取る。そして協定の形ができあがったら、批准するかしないかはまさに国会の役割だ。
このへんは共感できます。
交渉する前にどうこう言っても仕方ないし、交渉に入ったら負ける前提のところがそもそもまずいと思います。
ただ、今までの各国とのEPA・FTA協議でも農水省の人はNOの一点張りだったという話も聞いたことがあるので、実際にできるかどうかはちと心配。
一方で内容はともかく調印することが目的、という省庁の人もいるようで、TPPに参加するのなら国・官僚組織としての交渉力を磨く必要がありそうですし、交渉過程を(事後的にでも)きちんと示すべきだと思います。
さらに野田政権はG20で他国の関心がないのに消費税10%とか言うし、それを「国際公約」といかいうマスコミもいるのでなおさら心配です。
ただ、それ以外のところは今ひとつよくわかりません。
農業で言えば、小沢さんがかつて言ったように、戸別所得補償を導入すれば日米FTAも乗り切れるはずだった。2009年のマニフェストにもそう書いてある。農村の振興と国際化は両立させる、というのはそういう意味だ。そういう政策目的をもっていたはずなのに、マニフェストと全く関係ないことをやってしまっているのは、政策目的なき、究極のバラマキと言わざるを得ない。
「戸別所得補償を導入すれば日米FTAも乗り切れる」というのは、戸別補償は「補助金」ではないから非関税障壁じゃない、というロジックでFTAに抵触しないだけで、日本農業の発展にプラスになるのでしょうか?
戸別補償は日米FTAとセットだというなら、なぜ小沢グループはTPPに反対しているのでしょうか。(このへん私の理解不足かもしれませんが)
私の原点となる主張は、農業経営は総合産業ということだ。経営資源は農地、人、技術であり、作物を加工し、付加価値をつけて販売、マーケティングする。そういう意味では製造業と何ら変わらない。今は「6次産業化」という言葉を使っているが、先進的な農業者は前からみんなそうしている。
私はそういう経営体を「持続的農業経営体」と呼んでいる。すでに存在している経営体を点から面へと広げていく。既存の制度の壁を取り払うため、持続的農業経営体の総合支援法を作り、そこで農地の問題、新規参入も含めた人の問題、技術の問題を取り扱い、企画力や販売力を高めていく支援体制をどう作るか考える。
今の農地制度を廃止するぐらいまでやればいい。それは経過措置を取ればいいし、持続的農業経営体支援法のなかに使いやすい簡単な農地制度として入れてもいい。今の農地法の特例法をその中に書くやり方もある。要するにやる気になればいろんなことができるはずだ。
この「原点」っていつのことなんでしょう?
事務次官のときにやっていれば今更反省はしなかったはずだし、経歴を拝見すると事務次官を2001年に退官後は農林中金総合研究所理事長、農林漁業金融公庫総裁を歴任。2007年からNPO(特定非営利活動法人)日本プロ農業総合支援機構副理事長、とあり、少なくとも農林中金総合研究所理事長や農林漁業金融公庫総裁のときに主張されればもっと影響力があったのでは?
事務次官経験者って退官後、天下りで十分利食ったあとにNPO法人の理事長とか大学教授とかになって宗旨替えする人が多いように思うのですが、「今までは間違っていた」と言われてもどうしても色眼鏡で見てしまいますね。
それに、この人は先進的な取り組みの人を例に挙げているだけで、結局自ら何か規制を突破したとか、少なくとも先進的な取り組みの人を支援したというわけでもないようです。
せっかく反省するのなら、現役のときにそういうことができなかった背景にある官僚組織や政治家の関わり方の問題点などを掘り下げて欲しかったと思います。
やはり人間は生身だから、保身もあるし、出世欲もあるし、いろんな思いがごちゃごちゃにある。そういう中で、政治というものがどっちを向くのか気になる人たちもいる。改革を始める時は、ほとんどがその改革を理解していないか、改革に反対か、改革に消極的だ。改革をする時、組織の中に信念を持った人間が1%いればいい、と私は言ってきた。
農業関係者は、とかく排除の論理に陥りやすい。農政のことは、俺たちだけしかわからない、俺たちが一番わかっているんだ、となると、内輪でしか通用しない用語ができてくる。そうした用語を理解しない人たちは全部わかってない連中ということになる。
NHKの「激論TPP」というTPP問題についての解説委員による討論を見ていて思ったこと。
・「 今TPPの交渉に参加しないと、枠組みの決定に参加できず、日本の主張も反映できない」という主張
これは僕もそう思うので、「交渉に参加」はした方がいいんじゃないかと漠然と思っています。
Wikipediaで拾った「環太平洋戦略的経済連携協定 (TPP) の概要と意義」( 亜細亜大学 国際貿易投資研究所)を見ると「サービス貿易の自由化約束についてネガティブ・リスト方式を採用している」とか「競争法の適用除外分野はannex で提示されている」など、枠組みが決まってからだと不利になる可能性のありそうなところとか「地理的表示については、TRIPs 協定第22 条によるチリのワインおよびスピリッツについての地理的原産地の表示の保護が規定されている」というように、早めに言っておけば日本の主張も反映できそうなところなどもありそうなので。
ただ一番の心配事は、日本政府の交渉力。
よくあるパターンとして「交渉に入る、入らないの議論は盛り上がるが、一度交渉に入ると決まると、次は「交渉に入った以上妥結する」ことが至上命題になってズルズル譲歩を繰り返してしまう。」というのがあります。
いつの間にか政治家の面子や交渉担当の官僚の成果測定の問題になってしまうパターンです。
(企業間の交渉もそういうケースもあるし、逆に相手をそういう方向に持っていくというのもテクニックの一つではありますが)
現状の議論が「交渉をする=相手の言い分を飲む」という風になってしまっているのがとても気になります。
和平交渉ではないのだから、冷静かつ粘り強く交渉して、結局国として利益にならないと判断したら調印しなければ言いだけの話だと思うのですが。
もっとも「普天間問題で怒らせてしまったアメリカへのお土産」などという主張もあるそうで、そういう動機があるのだとしたら交渉に入らないほうがいいと思います。
・ 日本の農業はどうなる
専門知識がないので物品貿易が完全自由化されると日本の農業が壊滅してしまうのか、競争力を持つように生まれ変わるのかはよくわかりません。
ただ、議論で気になったのは、「安全でおいしい農産物を作れば競争力が持てるし輸出もできる」という論調。
この前提として「安全でおいしい農産物」は高級品として品質で勝負するのか、価格競争力で勝負するのかを整理したほうが良かったと思います。
たぶん「安全でおいしい農産物を輸入食品と同程度の価格で」というのは難しいと思うので、国際競争力を持つのは「安全・高品質な高級品」になるはずです。
そしてそれは「お金のある人は安全・高品質な食品を食べて、お金のない人は輸入原材料による安価な加工食品やファストフードを食べる」という今のアメリカと同じ状況をもたらすのではないでしょうか。
それは避けたい。
そうすると、農業問題は、安全で高品質な農産物を適正な価格で食べられるくらいに国民の所得レベルを維持向上させることができるのか、という経済政策とも関連してきます。
企業が労働力をコストとしてのみ考えると、労働分配率が減り総需要が減少するという合成の誤謬の指摘もありますし、一方で労働政策で対応しようとすると既得権のある(僕らの年代以上の)年寄りの抵抗も予想されます。
そのへんが自分としてはいまひとつ整理できていない感じでした。
野田首相とか経産省とか経団連はどう考えているのかにも興味があります。
<追記>
そのあとBSで「キング・コーン-とうもろこしの国を行く-」というアメリカのドキュメンタリーを見ました。
アメリカのトウモロコシはほとんどが牛の飼料や高果糖コーンシロップ、コーン油など食品や添加物の原料として使われている。
それは1970年代に食料補助金制度を増産にインセンティブを与えるように変えて、安価に大量のトウモロコシが供給されるようになったことによる(この既存の米国の農業補助金がTTP上どうなるんでしょうか)。
そのため栽培されているトウモロコシは収穫量とデンプン量を最大にするように品種改良されたいわば工業品であり、直接の食用には適さない。
逆にアメリカ人の摂取する食品の80%がトウモロコシを飼料や原料にしていて、それが糖尿病などの成人病を引き起こす原因になっている。
というような内容です。
(本来穀物を食べるようにできていない牛の飼料にすることの弊害や糖尿病の問題については『フードインク』でも指摘されてました。)
つまり、デンプンを安価に供給できれば、何もトウモロコシ(や場合によっては農業自体)に頼る必要はないわけです。
ここからは思考実験。
たとえばトウモロコシよりもデンプンを採取するのに高効率な穀物がどこか(中央アジアとかアフリカの奥地とか)で発見され、その遺伝子特許を日本企業が取得して、たとえばオーストラリアとかで大量に生産することになった場合、TPPではアメリカは関税をかけられない一方で日本の特許は保護されることになります。
そのときにアメリカは自国の農業の衰退を座して待っているだろうか。TPPの例外規定を作るとか、脱退をほのめかすとかするのではないでしょうか。
日本が交渉に参加するのであれば、そういう連中と交渉する、そしてこちらも同じくらいの振る舞いをする覚悟が必要なんだろうと思います。
個人的にはそこのところが一番心配・・・
サラリーマンNEO シーズン6の総集編を録画で観ていたら、「NEOビジネススクール」という東進ハイスクールのCMのパロディ5連発のなかに表題のテーマがあった。
曰く
a=声がやたら大きい
b=酒が強い
c=左利き
d=雑学
1つを除いてすべてあてはまるw
旧ソ連時代のこのジョークのようなオチになったりして、とふと思った次第。
衆議院のサーバーに不正侵入判明
(10月25日 17時55分 NHK)
ことし8月、衆議院のネットワークのサーバーが、外部から不正に侵入を受け、内部の情報にアクセスできる状態になっていたことが分かりました。衆議院事務局は「今のところ情報の流出は確認されていない」としていますが、詳しい調査を始めました。