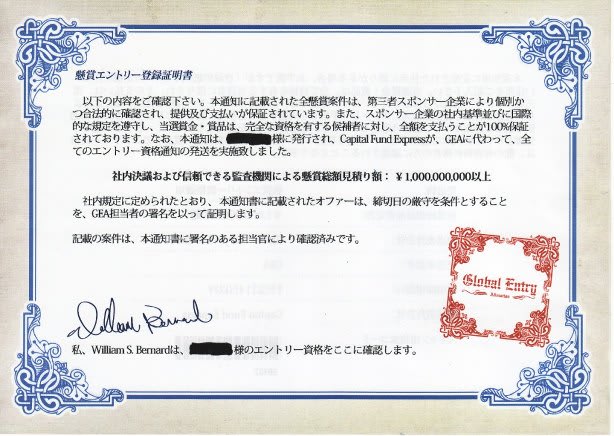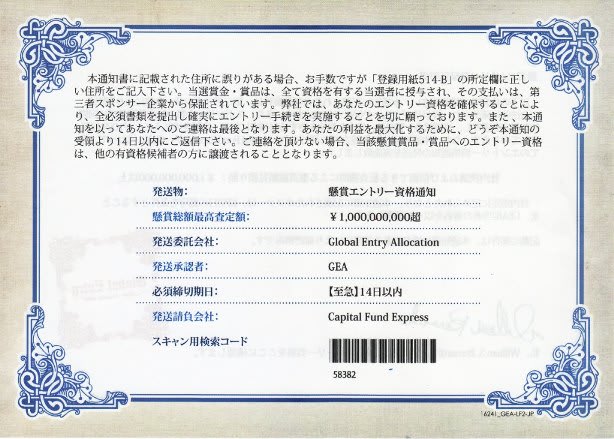酒席でオセロの中島の話になった。
あいかわらず芸能ネタに弱いのだが、ここのところ朝のテレビ番組でも散々とりあげられているのでいやでも耳に入ってくる。
一方で占いが好きという人は結構多いようだ。
オセロ中島と霊能師の関係を取り上げた直後に「今日の星座ランキング」のコーナーが来るのがいい証拠。
要するに気分転換とかちょっとした参考にするのはいいが、過度の依存はロクなことにならない、というのが世間の相場なのだろう。
ところが、どうも依存というのは知らないうちに深くなるようだ。
大学の学園祭で占いの出店をやったことがあるが、どう見てもちょっとかじっただけの素人(無料だったし)に対しても、深刻な相談を持ちかけてくる人がいて驚いたことがある。
企業経営者でも占いに凝っていて、事務所移転に方角を気にする人というのは耳にすることがある。
もともと高島易断の創設者である高島嘉右衛門がそうだ(
参照)。
女性関係のトラブルを相談しているうちにその女性占い師とデキてしまったという話を聞いたこともある。
などと考えたのだが、そんな月並みな話では会話は盛り上がらないし、固有名詞を出すのははばかられるので、もっぱら聞き役に回る。
一方で報道を聞いて気になったのが、家主の本木雅弘は借主の中島に対して契約解除明渡請求訴訟を提起したようだが、同時に占有移転禁止の仮処分を申し立ててはいないらしいということ。
貸主が勝訴しても借主が立ち退かない場合強制執行を行なうことになるが、強制執行はあくまでも借主を対象にしかできない。
執行官が現地に行ったときに霊能師の親族などが適法な賃借人(転借人)の地位を主張した場合には二度手間になるように思うのだが。
そんなことを言ったらますます会話が盛り上がらなくなるので、井上陽水がどうこう、という話をふんふんと聞いていた。
個人的には占いにはほとんど興味がないのだが、それは幸いにも深い悩みがない能天気な人生を送ってこられたことに感謝すべきなのかもしれない。