てつがくカフェ@ふくしま特別編4の翌日は、立て続けに本deてつがくカフェ番外編が開催されました。
課題図書は、アルベール・カミュの『ペスト』。
この企画は、この春に福島を離れる方と「読書会をしよう!」という話が盛り上がったついでに、本deてつがくカフェで扱うことになったものです。
その意味で「番外編」とさせていただいたのですが、参加者は予想以上に集まり10名の方々にお出でいただきました。
しかも、今回は、まさに「読書会の不可能性」を探求する場となりました。
というのも、まず、読書会であるにもかかわらず、課題図書を読み切ってきた参加者がほとんどいません。
1ページすら読んでいない方もいます。
つまり、ほとんどの人が結末を知らないまま読書会が進行したわけです。
さらに、読み切った人がほとんどいないということは、会の性質上、ネタバレのオンパレードになります。
これについては小野原がブログで書いています(ネタバレ本deカフェ)。
果たして、これが読書会と言えるのか?
しかし、そこはてつがくカフェ@ふくしまです。
ネタバレもお構いなしに対話がくり広げられました。
ここから読まれる方はネタバレ覚悟でお読みください。
ちなみに、今回の報告は特に発言メモを取らなかったので、皆さんの意見や議論を聞きながら渡部が再解釈してまとめた内容になっています。
さて、カミュの『ペスト』のあらすじ等についてはウィキペディアを参照して下さい。
それを読んだとしても、本書自体のおもしろさは、やはり実際にお読みいただくしかありませんが、それを前提にカフェで触れられた内容について書き連ねていきましょう。(以下、青字は新潮文庫版・宮崎嶺雄訳『ペスト』からの引用)
しばしば『ペスト』は、〈3.11〉の「フクシマ」の状況と重ねて語られます。
私自身もとりわけ前半部分なんかは、原発事故直後に福島市内が放射能汚染されつつあった状況をリアルに思い出させられました。
たとえば、
「肝心なことは」と、カステル[医師]はいった。「こう言う議論の仕方がいいとかなんとかいうことじゃない。それを聞いて、みんながよく考えてみるということです」(p72)とか、
「我々はあたかも市民の半数が死滅させられる危険がないかのごとく振る舞うべきではない、と。なぜなら、その場合には実際そうなってしまうでしょうから」(p76)とか、
「自分[知事]にはそうする権力がないっていう返事なんです。僕の意見では、こいつ[ペスト]、勢いを増してきますよ」(p92)とか、
知事:「総督の命令を仰ぐことにしましょう。」
リウー(医師)「命令なんて!それこそよっぽど頭を働かせなきゃならない時なんだが」(p94)とか、
「この病疫の無遠慮な侵入は、その最初の効果として、この町の市民に、あたかも個人的な感情などもたぬようにふるまうことを余儀なくさせた、といっていい。」(p97)とか、
これらの言葉は、実際に被災現場にいた私たちが口にしたり耳にしたりしたものです。
「仮に我々の中の一人が、ふとしたはずみで、自分の感情上の何かのことを打ち明け、あるいは話そうと試みたとしても、相手のそれに対する返事は、どんな返事であろうと、たいていの場合、彼の心を傷つけるのであった。彼はそこで、その話し相手と自分とは、同じことを話していなかったことに気がつくのである」(p109)なんて、放射能に対する温度差に悩んだ経験を思い出さずにはいられません。
これらの言葉の数々は、あの放射能汚染が広まる中、なかなか自分で考え判断できない、自分で責任をとってよいのか迷う現場の状況下における行政側の対応と葛藤に響きあうのではないでしょうか。
参加者の中には行政職に携わる方もいらっしゃいましたが、彼に思わず問い質してしまう場面も生まれ、申し訳ないことをしてしまいました。
話題はいろいろなページにわたって繰り広げられますが、やはり登場人物の生きざまに注目が集まります。
まずは、ペストが発生したオランの外部から来訪した記者であるランベール。
彼は、閉鎖された町の外に愛人(妻)を残しており、彼女に会うために必死に脱出を画策します。
が、ことごとく失敗するさまは、まるでカフカの『審判』の世界です。
そんな理不尽さにうんざりしたランベールが言った一言がこれです。
「僕はもう観念のために死ぬ連中にはうんざりしているんです。僕はヒロイズムは信用しません。僕はそれが容易であることを知っていますし、それが人殺しを行うものであったことを知ったのです。僕が心惹かれるのは、自分の愛するもののために生き、かつ死ぬということです」(p244)
状況としては、オランがペストの蔓延を防ぐために市門を閉鎖して住民を外部から隔離したのに対し、福島の場合は放射能汚染のために居住区域から追放された点で、正反対の状況とも言えます。
しかし、「世界からの追放」という意味では、同じであるとも言えるのではないでしょうか。
その場合、「世界」とは自分に慣れ親しんだもの、愛したものたちに囲まれた環境そのものを指します。
すると、「自分の愛するもののために生き、かつ死ぬということ」とは、単に実存主義の態のいい定義とだけ解釈すべきではないでしょう。
「愛するもの」とは、その土地かもしれないし、ペットかもしれないし、自分に慣れ親しんだもの全般を指します。
あるいは、未だ発見されぬ津波の犠牲となった愛すべき存在者かもしれません。
この「愛するもの」と隔絶された内/外部の壁にもがき苦しむランベールの苦悩は、世界からの追放と読む限りにおいて福島と縁遠い話ではないわけです。
これに対して、医師であり主人公であるリウーの答えは、こうです。
「今度のことは、ヒロイズムなどと言う問題はないんです。これは誠実さの問題なんです。こんな考え方は笑われるかもしれませんが、しかしペストと闘いう唯一の方法は、誠実さと言うことです」(p245)
「誠実さ」とは何か?
彼によれば、「僕の場合には、つまり自分の職務を果たすことだと心得ています」とのことです。
彼の医師としての職務とは、自分の死を省みずに目の前の患者を救うことに只管邁進することでしょう。
まるで野口英世のようです。
この「誠実さ」という言葉に、参加者それぞれが自分の立場でものを考えさせられます。
ジャーナリストとして、果たして誠実な報道をしているか…
あのとき、予定通り入学式を挙行し、子どもたちを被ばくの危険にさらしたのは教師としての「誠実さ」だったのだろうか…
しかし、そうはいっても先述したオランの知事や行政官だって、自分の職務を全うしていたとも言えるんじゃないだろうか?
いったい「職務」の遂行と「誠実さ」はイコールなのか?
それとも「職務」の遂行が「誠実さ」を伴うとはいかなることなのか?
2次会で話題に上った登場人物の一人に作家志望の下級役人グランがいます。
彼等は、ひたむきに自分のできる行政職の仕事に従事しますが、彼の市政はアイヒマンそのものだとみる参加者がいました。
ただし、「アイヒマン」という言葉が象徴するような無思考の犯罪者というよりも、あの家中の中で黙々と自分の仕事に従事する人々がいて成り立っている側面に注意を促します。
グランはその点でまさに「誠実さ」をもって行政職に従事する人物だったと評価できると思いますが、それとアイヒマンの境目とはなんだったのか?
アイヒマンは「誠実」だったのか?
このヒントは、終盤、流れ者のタルーが自らの出自を告白する中でふれられる「聖者」というものにつながるのではないかという話題になります。
「第三の範疇―つまり、本当の医師という範疇が、当然あっていいだろうが、しかし事実として、そういうのにはそう多くは出くわさないし、まず困難なことというものだろう。まぁ、そういうわけで、僕は、災害を限定するように、あらゆる場合に犠牲者の側に立つことにきめたのだ。彼らの中にいれば、僕はともかく探し求めることはできるわけだ―どうせすれば第三の範疇に、つまり心の平和に到達できるかということをね」(p378-379)
タルー:「僕が心を惹かれるのは、どうすれば聖者になれるかという問題だ」
リウー:「だって、君は神を信じてないんだろう」
タルー:「だからさ。人は神によらずして聖者になりうるか―これが、今日僕の知っている唯一の具体的な問題だ」(p379)
タルーによれば、この世は天災と犠牲者というものがあり、万一自分が天災になるようなことがあるとしても、自分は決してそれに同意せず、「敗者の方にずっと連帯感を感じる」と言います。
この部分はなかなか複雑な告白内容で、彼が天災=ペストと名指すものは、実は死刑という殺害が正当化された社会に生きている人間に潜む病魔だと考えています。
いくら戦争や殺人を批判的であろうとしても、社会的に合法化された死刑を無意識に認めている限り、彼に言わせれば、間接的に死刑という殺害に加担していることは否定できません。
そして、それを容認する限り「やむを得ない殺人」は際限なく繰り広げられることを止めることはできません。
「やむを得ない」犠牲を容認するもの、これこそが人間の中に潜む「ペスト」性だというわけです。
タルーは、いかに死刑が社会にとって必要悪だという合理化されようとも、そんな「理性的な殺人者」に加担したくはないと言います。
加害者になるくらいなら犠牲者の側に。
しかし、ここで「天災(加害者側)」と「犠牲者」のみならず、それとは異なる「第三の範疇」としての「本当の医師」という存在が要請されるわけです。
この場合、医師は只管患者の治療にあたるわけですが、それは一方では病としてのペストを治すものであり、他方は死刑に同意する人々を治癒しようとするものでしょう。
いずれも不可能なものへ挑むものとして「聖者」としてタルーは考えます。
しかも、「神」という救済の存在もなしに、ただ救われる望みもなく挑み続けるもの。
自分の罪深さから、オランの部外者であるタルーがペスト撲滅にまい進する姿は、まさにこの「聖者」にならんとしているかのようです。
そして、その姿はペストと戦い続けるリウーにこそ見出されるのではないか、という意見が出されました。
たぶん、「神によらずしてなる聖者」とは、この終息が見えない病魔との戦いを継続するものであり、その戦いがほとんど報われるとは思えないにもかかわらず、しかも自分もまたいつ感染するかわからないにもかかわらず、只管挑むものなのでしょう。
ここに原発事故の終息が見えない廃炉作業に携わる人々の姿が重なります。
ただし、これを「聖者」と解釈して「犠牲」に供する存在の意味に解消しては決してならないはずですが。
が、しかし、まさにこの小説がカミュの作品たるゆえんは、このタルーがペスト終息宣言が出された直後にペストで死んでしまう場面です(一同驚愕)!
ペストも終息を迎えますが、それは決して医師たちの努力によるものではありません。
人々の努力が実を結んだわけでもなく、しかも努力した人間がペストの終焉とともにペストによってほとんど犬死同然に死んでしまうという不条理!
人は希望があるからこそ努力できる、という目的論はまったく通用しないことに愕然とさせられるほどです。
さて、カフェの議論でふれられた他の登場人物についても見てみましょう。
序盤からコタールという絶望に駆られた男が登場します。
彼は精神的に病んでいて自殺未遂を犯すわけですが、その背景には彼が犯した犯罪が発覚することへの恐れがありました。
ところが、一連のペスト騒動はその事実を有耶無耶にし、彼にとって何でもありの、ある種の祝祭感を与えます。
明日は我が身。いつ果てるともない生のちっぽけさに裏打ちされた祝祭性は、ある種のリセット願望と一致したのかもしれません。
「要するに、ペストは彼にとってうってつけのものである。孤独な、しかも孤独であることを欲しない一人の男を、ペストは一個の共謀者に仕立てた」(p287)
街の静けさと対照的に妙にハイテンションにふるまう彼の行動は、しかし震災直後に現れた「災害ユートピア」ともいうべき状況を彷彿とさせます。
ふだんは関係の悪い職場の人間関係も、あの震災対応に追われる中でみたことのない協働性を発揮したという経験談が挙げられながら、人とつながるにある種の陶酔感を覚えた人もいたのではないでしょうか。
他方、こうしたリセット願望は「孤独」や「孤立」といったキーワードと結びつきながら、この世界が破滅するか自分自身を破滅させるかのどちらかを欲望せざるをえない人々を想い起させます。
これに関して、『黒子のバスケ』著者に対する連続脅迫事件の裁判で、被告が「こんなクソみたいな人生やってられないから、とっとと死なせろ」と述べた一言が頭を離れません。
自殺未遂を冒したコタールにとって、ペストに侵された世界とは自分を救う新世界だったのかもしれません。
図らずも、ペスト終息後、彼は住居に立て籠り、銃で警官を殺害したことで警察隊に射殺されてしまいます……
彼にとって日常の回復は死を意味したのでしょうか。
それから、このペストと死が蔓延する中で説教を説くイエズス会の神父パヌルーです。
彼はとても説得的で学識豊かな神父として、この状況を神学的に解釈し説教しますが、それはまさに「天罰論」ともいうべきものです。
「今日、ペストがあなたがたにかかわりをもつようになったとすれば、それはすなわち反省すべき時が来たのであります。心正しき人はそれを恐れる必要はありえません。しかし邪なる人々は恐れ戦くべき理由があるのであります。世界という宏大な穀倉の中で、仮借なき災厄の殻竿は人類の麦を売って、ついにわらが麦粒から離れるまで打ち続けるでしょう」(p139)
これがあの「3.11」の震災直後、この天災を「津波をうまく利用して、我欲をうまく洗い流す必要がある。積年にたまった日本人の心の垢を。これはやっぱり天罰だと思う」としたある政治家の発言を想い起すことは容易でしょう。
このペストによってオトンの息子が死にますが、パヌルーはその出来事も「それが我々の尺度を超えたことだからです。しかし、おそらく我々は、自分たちに理解できないことを愛さねばならないのです」(p322)と述べます。
これに対して医師リウーは、何の罪もない「子供たちが責めなまされるようにつくられたこんな世界を愛することなどは、死んでも肯んじません」と反論します。
我々の理解の尺度を超えたものを想定し、「自然」とか「神」とか理解を超えたものに原因を期することは一つの不条理を納得する仕方かもしれません。
しかし、リウーはそうした理解の方法を拒絶します。
そんな不条理な世界を、いくら理解を超えていようとも「愛すること」などできるはずもないのです。
福島に生きる者にしてみれば、まして原発事故という人為の責任を「天」や「神」に帰する論理など到底受け入れられないでしょう。
こうしたリウーの考えに触発されたのか、このあと、パヌルーは天罰論と無垢な死をどのように解釈すべきか、ぎりぎりまで突き詰めていく論題の説教を試みます。
子どもの苦しみをまったく問題としない天罰論者にでもなく、ペストの苦痛に対する恐怖に圧倒される者としてでもなく、「みなさん、私どもは踏みとどまるものとならねばなりません」。「善を為そうと努めることだけを為すべきである…しかし、…子どもの死さえも、神のみ心に任せ、そして個人の力に頼ろうなどとしないようにすべきである」、「中間などと言うものはない」。
だが、パヌルーはこういいながらも、自身そのはざまで不安に苛む様子がうかがえます。
「司祭が医者の診察を求めるとしたら、そこには矛盾がある」(p339)と、彼が語った事実を若い助祭は語りました。
タルーは、リウーからその説教の話を聞きながら、戦争中に罪なき者が目をつぶされる姿を見て信仰を捨てた司祭の話を引き合いに、
「罪なき者が目をつぶされるとなれば、キリスト教徒は、信仰を失うか、さもなければ目をつぶされることを受け入れるかだ。パヌルーは信仰を失いたくない。とことんまで行くつもりなのだ。」と解釈します。
ところが、パヌルー自身、その直後にペストによって死亡してしまいます。
果たして、彼の死は信仰の犠牲に自らを供したものなのか、それともまったくの無意味で不条理な死にすぎなかったのか?
いずれにせよ、タルーといいパヌルーといい、その「誠実さ」と結果とのあまりのギャップに、この本を読んでいない参加者から「結局この本はペシミスティックなわけ?」という問いが発せられました。
しかし、読破した参加者は一様に「そうでもない。むしろなぜか希望的なものすら感じる」という意見が出されました。
それはなぜなのか?
リウーのように、ほとんど徒労にもかかわらず、ただ「健康」のために医療行為に従事する姿は、ある意味でカミュの著作でもある「シーシュポスの神話」を想い起させます。
ギリシア神話においてシーシュポスは、神々の怒りを買ってしまい、大きな岩を山頂に押して運ぶという罰を受けるのですが、山頂に運び終えたその瞬間に岩は転がり落ちてしまい、ひたすら同じ動作を何度繰り返しても、結局は同じ結果にしかならないという無意味さの苦しみを繰り返します。
この無意味な不条理さにいったい、ペシミズム以外に何があるのでしょうか。
これについて、ある参加者は、この小説がある種の報告書、証言の形式になっていることに注目します。
そして、この無意味で無価値であるにもかかわらず、そこにたしかにペストをめぐって格闘したり、悩んだり、逃げたり、苦しんだ人々を書き記そうとすることそれ自体に、何かポジティブなものを感じるというわけです。
ペスト終息宣言が出された後、街では祝賀の花火があがり歓声がわきます。
「コタールもタルーも、リウーが愛し、そして失った男たち、女たちも、すべて、死んだ者も罪を犯した者も、忘れられていた。爺さんの言った通りである。― 人々は相変わらず同じようだった。しかし、それが彼らの強み、彼らの罪のなさであり、そしてその点においてこそ、あらゆる苦悩を超えて、リウーは自分が彼らと一つになることを感じるのであった」(p457)
「忘れる力」とは、先日の特別編4のテーマでしたが、まさにそのことを指し示しているかのような一文です。
「その時医師リウーは、ここで終わりを告げる物語を書き綴ろうと決心したのであった―黙して語らぬ人々の仲間に入らぬために、これらペストに襲われた人々に有利な証言を行うために、彼らに対して行われた非道と暴虐の、せめて思い出だけでも残しておくために、そして、天災のさなかで教えられること、すなわち、人間の中には軽蔑すべきものよりも賛美すべきものの方が多くあるということを、ただそうであるというだけ言うために」
「しかし、彼はそれにしてもこの記録が決定的な勝利の記録ではありえないことを知っていた。それはただ、恐怖とそのあくなき武器に対して、やり遂げねばならなかったこと、そしておそらく、すべての人々―聖者たりえず、天災を受け入れることを拒みながら、しかも医者となろうと努めるすべての人々が、彼ら個々自身の分裂にもかかわらず、さらにまたやり遂げねばならなくなろうであろうこと、についての証言でありえたにすぎないのである」(p457~458)
歴史を作り上げてきた人々とは、歴史に名を残せない大多数の人々であって英雄ではありません。
その歴史に刻まれなかった人々は沈黙のうちに忘却という死に晒されるでしょう。
いわば、敗北の歴史というべきものです。
あの震災・原発事故ののさなかに、自分自身を引き裂きながら個々の状況に葛藤し、選択肢、戦った人々は無数に存在しました。
聖者どころか、負い目を追ってしまう人も多数いたことでしょう。
逃げるように、この地を離れた人もいたでしょう。
しかし、それらがすべて無意味であるとか正しい/間違っているといった、わかりやすい物差しで評価されること自体憚れることです。
その出来事の渦中で、個々人が経験したこと、行為したこと、苛まれたこと、これらのことを書き記す証言を残すこと自体が、不条理ともいえるペストに対抗できるポジティブな何某かだということではないでしょうか。
それが、もしかしたら「救い」なのかもしれません。
忘却から存在が救われた、という意味での。
実は、最後にこの記録者がリウー自身だったことが明かされるわけですが、彼はその戦いの中で生まれた「友情」というものに惹きつけられます。
あれほど市外へ脱出したがっていたランベールも、脱出の土壇場で共に戦ってきたこの地を離れるわけにはいかないと決断します。
「もし自分が発って行ったら、きっと恥ずかしい気がするだろう。そんな気持ちがあっては、向こうに残してきた彼女を愛するのにも邪魔になるには違いないのだ。」
「しかし、自分一人が幸福になるということは恥ずべきことかもしれないんです。」
「僕はこれまでずっと、自分はこの街には無縁の人間だ、自分には、あなた方は何のかかわりもないと、そう思っていました。ところが、現に見た通りのものを見てしまった今では、もうたしかにこの町の人間です、自分でそれを望もうと望むまいと。この事件は我々みんなに関係のあることなんです」(p307)
これが避難せずに現地へとどまった人々の行為を正当化するものとして読み込めば陳腐なものとなるでしょう。
しかし、オランという街に関わりのないエトランジェ(よそもの)であるランベールが、出来事に巻き込まれるうちに自分と無関係ではないと納得していく過程は、その中で邂逅した人々との戦いがあったからでしょう。
その中で生じた「友情」なるものは、やはり否定しがたく自分のぎりぎりの選択を規定するに余りある経験だったのだと思います。
これを「戦友」と名付けることが許されるとすれば、やはり「よそもの」であったタルーとの友情も同様でしょう。
こうした友情など、歴史に刻まれるはずもありません。
しかし、そのことを証言することは後世に役立つとかそんな功利的意義を超えて、それ自体として不条理の中に「記憶」という一つの光をもたらすように思われるのです。
「彼[リウー]はタルーの傍らで暮してきて、そしてタルーは今夜、二人の友情が本当に生きられるひまもないうちに、死んでしまったのだ。タルーは勝負に負けたのであった―自分でいっていたように。しかし、彼、リウーは、いったい何を勝負にかちえたであろうか?彼がかちえたところは、ただ、ペストを知ったこと、そしてそれを思い出すということ、友情を知ったこと、そしてそれを思い出すということ、愛情を知り、そしていつの日かそれを思い出すことになるということである。ペストと生とのかけにおいて、およそ人間が勝ちうることのできたものは、それは知識と記憶であった。おそらくこれが、勝負に勝つとタルーが呼んでいたところのものなのだ!」(p431)
さて、今回の本deてつがくカフェは、冒頭で申しましたように、この春、福島から離れる参加者から「読書会をしよう」との要望があったことに端を発しています。
まさに、彼らはエトランゼ的存在でもあったわけですが、しかし、わずかな時間であっても、こうした知的な遊びの空間を共有していただいたり、また福島の問題をともに共有し、戦っていただけたという点で、無限の友情を感じないわけにはいきません。
その点でも『ペスト』を選書したことは彼らとの友情を描き刻むにうってつけの機会だったのではないでしょうか。
福島を離れられるKさん、Fさん、そしてもうひとりのFさんには、益々ご活躍くださることをお祈り申し上げます。
また、お会いできる日を楽しみにしています。
最後に、リウーの患者であった爺さんの意味深な言葉を引用して終えましょう。
「一番いい人たちが行っちまうんだ。それが人生ってもんさ……だが、いったい何かね、ペストなんて?つまりそれが人生ってもんで、それだけのことさ」(p454)
課題図書は、アルベール・カミュの『ペスト』。
この企画は、この春に福島を離れる方と「読書会をしよう!」という話が盛り上がったついでに、本deてつがくカフェで扱うことになったものです。
その意味で「番外編」とさせていただいたのですが、参加者は予想以上に集まり10名の方々にお出でいただきました。
しかも、今回は、まさに「読書会の不可能性」を探求する場となりました。
というのも、まず、読書会であるにもかかわらず、課題図書を読み切ってきた参加者がほとんどいません。
1ページすら読んでいない方もいます。
つまり、ほとんどの人が結末を知らないまま読書会が進行したわけです。
さらに、読み切った人がほとんどいないということは、会の性質上、ネタバレのオンパレードになります。
これについては小野原がブログで書いています(ネタバレ本deカフェ)。
果たして、これが読書会と言えるのか?
しかし、そこはてつがくカフェ@ふくしまです。
ネタバレもお構いなしに対話がくり広げられました。
ここから読まれる方はネタバレ覚悟でお読みください。
ちなみに、今回の報告は特に発言メモを取らなかったので、皆さんの意見や議論を聞きながら渡部が再解釈してまとめた内容になっています。
さて、カミュの『ペスト』のあらすじ等についてはウィキペディアを参照して下さい。
それを読んだとしても、本書自体のおもしろさは、やはり実際にお読みいただくしかありませんが、それを前提にカフェで触れられた内容について書き連ねていきましょう。(以下、青字は新潮文庫版・宮崎嶺雄訳『ペスト』からの引用)
しばしば『ペスト』は、〈3.11〉の「フクシマ」の状況と重ねて語られます。
私自身もとりわけ前半部分なんかは、原発事故直後に福島市内が放射能汚染されつつあった状況をリアルに思い出させられました。
たとえば、
「肝心なことは」と、カステル[医師]はいった。「こう言う議論の仕方がいいとかなんとかいうことじゃない。それを聞いて、みんながよく考えてみるということです」(p72)とか、
「我々はあたかも市民の半数が死滅させられる危険がないかのごとく振る舞うべきではない、と。なぜなら、その場合には実際そうなってしまうでしょうから」(p76)とか、
「自分[知事]にはそうする権力がないっていう返事なんです。僕の意見では、こいつ[ペスト]、勢いを増してきますよ」(p92)とか、
知事:「総督の命令を仰ぐことにしましょう。」
リウー(医師)「命令なんて!それこそよっぽど頭を働かせなきゃならない時なんだが」(p94)とか、
「この病疫の無遠慮な侵入は、その最初の効果として、この町の市民に、あたかも個人的な感情などもたぬようにふるまうことを余儀なくさせた、といっていい。」(p97)とか、
これらの言葉は、実際に被災現場にいた私たちが口にしたり耳にしたりしたものです。
「仮に我々の中の一人が、ふとしたはずみで、自分の感情上の何かのことを打ち明け、あるいは話そうと試みたとしても、相手のそれに対する返事は、どんな返事であろうと、たいていの場合、彼の心を傷つけるのであった。彼はそこで、その話し相手と自分とは、同じことを話していなかったことに気がつくのである」(p109)なんて、放射能に対する温度差に悩んだ経験を思い出さずにはいられません。
これらの言葉の数々は、あの放射能汚染が広まる中、なかなか自分で考え判断できない、自分で責任をとってよいのか迷う現場の状況下における行政側の対応と葛藤に響きあうのではないでしょうか。
参加者の中には行政職に携わる方もいらっしゃいましたが、彼に思わず問い質してしまう場面も生まれ、申し訳ないことをしてしまいました。
話題はいろいろなページにわたって繰り広げられますが、やはり登場人物の生きざまに注目が集まります。
まずは、ペストが発生したオランの外部から来訪した記者であるランベール。
彼は、閉鎖された町の外に愛人(妻)を残しており、彼女に会うために必死に脱出を画策します。
が、ことごとく失敗するさまは、まるでカフカの『審判』の世界です。
そんな理不尽さにうんざりしたランベールが言った一言がこれです。
「僕はもう観念のために死ぬ連中にはうんざりしているんです。僕はヒロイズムは信用しません。僕はそれが容易であることを知っていますし、それが人殺しを行うものであったことを知ったのです。僕が心惹かれるのは、自分の愛するもののために生き、かつ死ぬということです」(p244)
状況としては、オランがペストの蔓延を防ぐために市門を閉鎖して住民を外部から隔離したのに対し、福島の場合は放射能汚染のために居住区域から追放された点で、正反対の状況とも言えます。
しかし、「世界からの追放」という意味では、同じであるとも言えるのではないでしょうか。
その場合、「世界」とは自分に慣れ親しんだもの、愛したものたちに囲まれた環境そのものを指します。
すると、「自分の愛するもののために生き、かつ死ぬということ」とは、単に実存主義の態のいい定義とだけ解釈すべきではないでしょう。
「愛するもの」とは、その土地かもしれないし、ペットかもしれないし、自分に慣れ親しんだもの全般を指します。
あるいは、未だ発見されぬ津波の犠牲となった愛すべき存在者かもしれません。
この「愛するもの」と隔絶された内/外部の壁にもがき苦しむランベールの苦悩は、世界からの追放と読む限りにおいて福島と縁遠い話ではないわけです。
これに対して、医師であり主人公であるリウーの答えは、こうです。
「今度のことは、ヒロイズムなどと言う問題はないんです。これは誠実さの問題なんです。こんな考え方は笑われるかもしれませんが、しかしペストと闘いう唯一の方法は、誠実さと言うことです」(p245)
「誠実さ」とは何か?
彼によれば、「僕の場合には、つまり自分の職務を果たすことだと心得ています」とのことです。
彼の医師としての職務とは、自分の死を省みずに目の前の患者を救うことに只管邁進することでしょう。
まるで野口英世のようです。
この「誠実さ」という言葉に、参加者それぞれが自分の立場でものを考えさせられます。
ジャーナリストとして、果たして誠実な報道をしているか…
あのとき、予定通り入学式を挙行し、子どもたちを被ばくの危険にさらしたのは教師としての「誠実さ」だったのだろうか…
しかし、そうはいっても先述したオランの知事や行政官だって、自分の職務を全うしていたとも言えるんじゃないだろうか?
いったい「職務」の遂行と「誠実さ」はイコールなのか?
それとも「職務」の遂行が「誠実さ」を伴うとはいかなることなのか?
2次会で話題に上った登場人物の一人に作家志望の下級役人グランがいます。
彼等は、ひたむきに自分のできる行政職の仕事に従事しますが、彼の市政はアイヒマンそのものだとみる参加者がいました。
ただし、「アイヒマン」という言葉が象徴するような無思考の犯罪者というよりも、あの家中の中で黙々と自分の仕事に従事する人々がいて成り立っている側面に注意を促します。
グランはその点でまさに「誠実さ」をもって行政職に従事する人物だったと評価できると思いますが、それとアイヒマンの境目とはなんだったのか?
アイヒマンは「誠実」だったのか?
このヒントは、終盤、流れ者のタルーが自らの出自を告白する中でふれられる「聖者」というものにつながるのではないかという話題になります。
「第三の範疇―つまり、本当の医師という範疇が、当然あっていいだろうが、しかし事実として、そういうのにはそう多くは出くわさないし、まず困難なことというものだろう。まぁ、そういうわけで、僕は、災害を限定するように、あらゆる場合に犠牲者の側に立つことにきめたのだ。彼らの中にいれば、僕はともかく探し求めることはできるわけだ―どうせすれば第三の範疇に、つまり心の平和に到達できるかということをね」(p378-379)
タルー:「僕が心を惹かれるのは、どうすれば聖者になれるかという問題だ」
リウー:「だって、君は神を信じてないんだろう」
タルー:「だからさ。人は神によらずして聖者になりうるか―これが、今日僕の知っている唯一の具体的な問題だ」(p379)
タルーによれば、この世は天災と犠牲者というものがあり、万一自分が天災になるようなことがあるとしても、自分は決してそれに同意せず、「敗者の方にずっと連帯感を感じる」と言います。
この部分はなかなか複雑な告白内容で、彼が天災=ペストと名指すものは、実は死刑という殺害が正当化された社会に生きている人間に潜む病魔だと考えています。
いくら戦争や殺人を批判的であろうとしても、社会的に合法化された死刑を無意識に認めている限り、彼に言わせれば、間接的に死刑という殺害に加担していることは否定できません。
そして、それを容認する限り「やむを得ない殺人」は際限なく繰り広げられることを止めることはできません。
「やむを得ない」犠牲を容認するもの、これこそが人間の中に潜む「ペスト」性だというわけです。
タルーは、いかに死刑が社会にとって必要悪だという合理化されようとも、そんな「理性的な殺人者」に加担したくはないと言います。
加害者になるくらいなら犠牲者の側に。
しかし、ここで「天災(加害者側)」と「犠牲者」のみならず、それとは異なる「第三の範疇」としての「本当の医師」という存在が要請されるわけです。
この場合、医師は只管患者の治療にあたるわけですが、それは一方では病としてのペストを治すものであり、他方は死刑に同意する人々を治癒しようとするものでしょう。
いずれも不可能なものへ挑むものとして「聖者」としてタルーは考えます。
しかも、「神」という救済の存在もなしに、ただ救われる望みもなく挑み続けるもの。
自分の罪深さから、オランの部外者であるタルーがペスト撲滅にまい進する姿は、まさにこの「聖者」にならんとしているかのようです。
そして、その姿はペストと戦い続けるリウーにこそ見出されるのではないか、という意見が出されました。
たぶん、「神によらずしてなる聖者」とは、この終息が見えない病魔との戦いを継続するものであり、その戦いがほとんど報われるとは思えないにもかかわらず、しかも自分もまたいつ感染するかわからないにもかかわらず、只管挑むものなのでしょう。
ここに原発事故の終息が見えない廃炉作業に携わる人々の姿が重なります。
ただし、これを「聖者」と解釈して「犠牲」に供する存在の意味に解消しては決してならないはずですが。
が、しかし、まさにこの小説がカミュの作品たるゆえんは、このタルーがペスト終息宣言が出された直後にペストで死んでしまう場面です(一同驚愕)!
ペストも終息を迎えますが、それは決して医師たちの努力によるものではありません。
人々の努力が実を結んだわけでもなく、しかも努力した人間がペストの終焉とともにペストによってほとんど犬死同然に死んでしまうという不条理!
人は希望があるからこそ努力できる、という目的論はまったく通用しないことに愕然とさせられるほどです。
さて、カフェの議論でふれられた他の登場人物についても見てみましょう。
序盤からコタールという絶望に駆られた男が登場します。
彼は精神的に病んでいて自殺未遂を犯すわけですが、その背景には彼が犯した犯罪が発覚することへの恐れがありました。
ところが、一連のペスト騒動はその事実を有耶無耶にし、彼にとって何でもありの、ある種の祝祭感を与えます。
明日は我が身。いつ果てるともない生のちっぽけさに裏打ちされた祝祭性は、ある種のリセット願望と一致したのかもしれません。
「要するに、ペストは彼にとってうってつけのものである。孤独な、しかも孤独であることを欲しない一人の男を、ペストは一個の共謀者に仕立てた」(p287)
街の静けさと対照的に妙にハイテンションにふるまう彼の行動は、しかし震災直後に現れた「災害ユートピア」ともいうべき状況を彷彿とさせます。
ふだんは関係の悪い職場の人間関係も、あの震災対応に追われる中でみたことのない協働性を発揮したという経験談が挙げられながら、人とつながるにある種の陶酔感を覚えた人もいたのではないでしょうか。
他方、こうしたリセット願望は「孤独」や「孤立」といったキーワードと結びつきながら、この世界が破滅するか自分自身を破滅させるかのどちらかを欲望せざるをえない人々を想い起させます。
これに関して、『黒子のバスケ』著者に対する連続脅迫事件の裁判で、被告が「こんなクソみたいな人生やってられないから、とっとと死なせろ」と述べた一言が頭を離れません。
自殺未遂を冒したコタールにとって、ペストに侵された世界とは自分を救う新世界だったのかもしれません。
図らずも、ペスト終息後、彼は住居に立て籠り、銃で警官を殺害したことで警察隊に射殺されてしまいます……
彼にとって日常の回復は死を意味したのでしょうか。
それから、このペストと死が蔓延する中で説教を説くイエズス会の神父パヌルーです。
彼はとても説得的で学識豊かな神父として、この状況を神学的に解釈し説教しますが、それはまさに「天罰論」ともいうべきものです。
「今日、ペストがあなたがたにかかわりをもつようになったとすれば、それはすなわち反省すべき時が来たのであります。心正しき人はそれを恐れる必要はありえません。しかし邪なる人々は恐れ戦くべき理由があるのであります。世界という宏大な穀倉の中で、仮借なき災厄の殻竿は人類の麦を売って、ついにわらが麦粒から離れるまで打ち続けるでしょう」(p139)
これがあの「3.11」の震災直後、この天災を「津波をうまく利用して、我欲をうまく洗い流す必要がある。積年にたまった日本人の心の垢を。これはやっぱり天罰だと思う」としたある政治家の発言を想い起すことは容易でしょう。
このペストによってオトンの息子が死にますが、パヌルーはその出来事も「それが我々の尺度を超えたことだからです。しかし、おそらく我々は、自分たちに理解できないことを愛さねばならないのです」(p322)と述べます。
これに対して医師リウーは、何の罪もない「子供たちが責めなまされるようにつくられたこんな世界を愛することなどは、死んでも肯んじません」と反論します。
我々の理解の尺度を超えたものを想定し、「自然」とか「神」とか理解を超えたものに原因を期することは一つの不条理を納得する仕方かもしれません。
しかし、リウーはそうした理解の方法を拒絶します。
そんな不条理な世界を、いくら理解を超えていようとも「愛すること」などできるはずもないのです。
福島に生きる者にしてみれば、まして原発事故という人為の責任を「天」や「神」に帰する論理など到底受け入れられないでしょう。
こうしたリウーの考えに触発されたのか、このあと、パヌルーは天罰論と無垢な死をどのように解釈すべきか、ぎりぎりまで突き詰めていく論題の説教を試みます。
子どもの苦しみをまったく問題としない天罰論者にでもなく、ペストの苦痛に対する恐怖に圧倒される者としてでもなく、「みなさん、私どもは踏みとどまるものとならねばなりません」。「善を為そうと努めることだけを為すべきである…しかし、…子どもの死さえも、神のみ心に任せ、そして個人の力に頼ろうなどとしないようにすべきである」、「中間などと言うものはない」。
だが、パヌルーはこういいながらも、自身そのはざまで不安に苛む様子がうかがえます。
「司祭が医者の診察を求めるとしたら、そこには矛盾がある」(p339)と、彼が語った事実を若い助祭は語りました。
タルーは、リウーからその説教の話を聞きながら、戦争中に罪なき者が目をつぶされる姿を見て信仰を捨てた司祭の話を引き合いに、
「罪なき者が目をつぶされるとなれば、キリスト教徒は、信仰を失うか、さもなければ目をつぶされることを受け入れるかだ。パヌルーは信仰を失いたくない。とことんまで行くつもりなのだ。」と解釈します。
ところが、パヌルー自身、その直後にペストによって死亡してしまいます。
果たして、彼の死は信仰の犠牲に自らを供したものなのか、それともまったくの無意味で不条理な死にすぎなかったのか?
いずれにせよ、タルーといいパヌルーといい、その「誠実さ」と結果とのあまりのギャップに、この本を読んでいない参加者から「結局この本はペシミスティックなわけ?」という問いが発せられました。
しかし、読破した参加者は一様に「そうでもない。むしろなぜか希望的なものすら感じる」という意見が出されました。
それはなぜなのか?
リウーのように、ほとんど徒労にもかかわらず、ただ「健康」のために医療行為に従事する姿は、ある意味でカミュの著作でもある「シーシュポスの神話」を想い起させます。
ギリシア神話においてシーシュポスは、神々の怒りを買ってしまい、大きな岩を山頂に押して運ぶという罰を受けるのですが、山頂に運び終えたその瞬間に岩は転がり落ちてしまい、ひたすら同じ動作を何度繰り返しても、結局は同じ結果にしかならないという無意味さの苦しみを繰り返します。
この無意味な不条理さにいったい、ペシミズム以外に何があるのでしょうか。
これについて、ある参加者は、この小説がある種の報告書、証言の形式になっていることに注目します。
そして、この無意味で無価値であるにもかかわらず、そこにたしかにペストをめぐって格闘したり、悩んだり、逃げたり、苦しんだ人々を書き記そうとすることそれ自体に、何かポジティブなものを感じるというわけです。
ペスト終息宣言が出された後、街では祝賀の花火があがり歓声がわきます。
「コタールもタルーも、リウーが愛し、そして失った男たち、女たちも、すべて、死んだ者も罪を犯した者も、忘れられていた。爺さんの言った通りである。― 人々は相変わらず同じようだった。しかし、それが彼らの強み、彼らの罪のなさであり、そしてその点においてこそ、あらゆる苦悩を超えて、リウーは自分が彼らと一つになることを感じるのであった」(p457)
「忘れる力」とは、先日の特別編4のテーマでしたが、まさにそのことを指し示しているかのような一文です。
「その時医師リウーは、ここで終わりを告げる物語を書き綴ろうと決心したのであった―黙して語らぬ人々の仲間に入らぬために、これらペストに襲われた人々に有利な証言を行うために、彼らに対して行われた非道と暴虐の、せめて思い出だけでも残しておくために、そして、天災のさなかで教えられること、すなわち、人間の中には軽蔑すべきものよりも賛美すべきものの方が多くあるということを、ただそうであるというだけ言うために」
「しかし、彼はそれにしてもこの記録が決定的な勝利の記録ではありえないことを知っていた。それはただ、恐怖とそのあくなき武器に対して、やり遂げねばならなかったこと、そしておそらく、すべての人々―聖者たりえず、天災を受け入れることを拒みながら、しかも医者となろうと努めるすべての人々が、彼ら個々自身の分裂にもかかわらず、さらにまたやり遂げねばならなくなろうであろうこと、についての証言でありえたにすぎないのである」(p457~458)
歴史を作り上げてきた人々とは、歴史に名を残せない大多数の人々であって英雄ではありません。
その歴史に刻まれなかった人々は沈黙のうちに忘却という死に晒されるでしょう。
いわば、敗北の歴史というべきものです。
あの震災・原発事故ののさなかに、自分自身を引き裂きながら個々の状況に葛藤し、選択肢、戦った人々は無数に存在しました。
聖者どころか、負い目を追ってしまう人も多数いたことでしょう。
逃げるように、この地を離れた人もいたでしょう。
しかし、それらがすべて無意味であるとか正しい/間違っているといった、わかりやすい物差しで評価されること自体憚れることです。
その出来事の渦中で、個々人が経験したこと、行為したこと、苛まれたこと、これらのことを書き記す証言を残すこと自体が、不条理ともいえるペストに対抗できるポジティブな何某かだということではないでしょうか。
それが、もしかしたら「救い」なのかもしれません。
忘却から存在が救われた、という意味での。
実は、最後にこの記録者がリウー自身だったことが明かされるわけですが、彼はその戦いの中で生まれた「友情」というものに惹きつけられます。
あれほど市外へ脱出したがっていたランベールも、脱出の土壇場で共に戦ってきたこの地を離れるわけにはいかないと決断します。
「もし自分が発って行ったら、きっと恥ずかしい気がするだろう。そんな気持ちがあっては、向こうに残してきた彼女を愛するのにも邪魔になるには違いないのだ。」
「しかし、自分一人が幸福になるということは恥ずべきことかもしれないんです。」
「僕はこれまでずっと、自分はこの街には無縁の人間だ、自分には、あなた方は何のかかわりもないと、そう思っていました。ところが、現に見た通りのものを見てしまった今では、もうたしかにこの町の人間です、自分でそれを望もうと望むまいと。この事件は我々みんなに関係のあることなんです」(p307)
これが避難せずに現地へとどまった人々の行為を正当化するものとして読み込めば陳腐なものとなるでしょう。
しかし、オランという街に関わりのないエトランジェ(よそもの)であるランベールが、出来事に巻き込まれるうちに自分と無関係ではないと納得していく過程は、その中で邂逅した人々との戦いがあったからでしょう。
その中で生じた「友情」なるものは、やはり否定しがたく自分のぎりぎりの選択を規定するに余りある経験だったのだと思います。
これを「戦友」と名付けることが許されるとすれば、やはり「よそもの」であったタルーとの友情も同様でしょう。
こうした友情など、歴史に刻まれるはずもありません。
しかし、そのことを証言することは後世に役立つとかそんな功利的意義を超えて、それ自体として不条理の中に「記憶」という一つの光をもたらすように思われるのです。
「彼[リウー]はタルーの傍らで暮してきて、そしてタルーは今夜、二人の友情が本当に生きられるひまもないうちに、死んでしまったのだ。タルーは勝負に負けたのであった―自分でいっていたように。しかし、彼、リウーは、いったい何を勝負にかちえたであろうか?彼がかちえたところは、ただ、ペストを知ったこと、そしてそれを思い出すということ、友情を知ったこと、そしてそれを思い出すということ、愛情を知り、そしていつの日かそれを思い出すことになるということである。ペストと生とのかけにおいて、およそ人間が勝ちうることのできたものは、それは知識と記憶であった。おそらくこれが、勝負に勝つとタルーが呼んでいたところのものなのだ!」(p431)
さて、今回の本deてつがくカフェは、冒頭で申しましたように、この春、福島から離れる参加者から「読書会をしよう」との要望があったことに端を発しています。
まさに、彼らはエトランゼ的存在でもあったわけですが、しかし、わずかな時間であっても、こうした知的な遊びの空間を共有していただいたり、また福島の問題をともに共有し、戦っていただけたという点で、無限の友情を感じないわけにはいきません。
その点でも『ペスト』を選書したことは彼らとの友情を描き刻むにうってつけの機会だったのではないでしょうか。
福島を離れられるKさん、Fさん、そしてもうひとりのFさんには、益々ご活躍くださることをお祈り申し上げます。
また、お会いできる日を楽しみにしています。
最後に、リウーの患者であった爺さんの意味深な言葉を引用して終えましょう。
「一番いい人たちが行っちまうんだ。それが人生ってもんさ……だが、いったい何かね、ペストなんて?つまりそれが人生ってもんで、それだけのことさ」(p454)










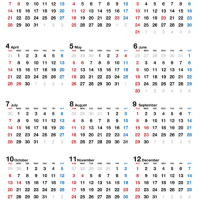









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます