思い出のキリマンジャロ登頂
今を去る10年前の登頂紀行
~~~~~
A社ツアーに参加する
2000年2月10日~20日
《乗り物》
2月10日 関西空港(機乗 12時間)
2月10日 オランダ・アムステルダム空港 15:00(ホテル泊)
2月11日 アムステルダム空港(機乗 12時間)
⇒タンザニア・キリマンジャロ空港
↓送迎 40分
アリューシャ・デイクデイクホテル(泊)
2月12日 デイクデイクホテル
↓送迎 2時間
登山口・マラングゲート(標高1900m)
《歩行》
2月12日 マンダラハット山小屋(標高2,690m)で第一夜
登山口・マラングゲート(標高1900m)で
ポーター30名の役割分担が決まるのを、気長に待つ。
ポレポレ~~ 悠長迫らない。
ランチをもらい、超スローペースで歩き始める。
ポーターは荷物(登山者が山小屋で使うシュラフ等、個人装備)を頭にのせて
運んでくれる。
ガイドE君が、草むらのカメレオンを見つける。
E君の指に止まり、ゆったりかまえている。
とかげに、そっくりだ。
ポーターのフセインが赤く熟した野苺を摘んでくれる。
フセインは、私のリュックを持ってくれているのだ。
登頂を是が非でも成し遂げるため、依頼したもの。
従って、私は手ぶらで歩く。
休憩の都度、ポーターが温かいテイを配ってくれる。
頻繁な水分補給は高山病対策でもある。
樹林帯の緩い登り坂、陽射しがきついので傘をさして歩く。
歩くこと4時間で、1番目の小屋マンダラハットに到着する。
テイの用意がととのっている。
紅茶・コーヒー・ビスケット・ポップコーンがお替り自由。
テイの後、小屋から15分歩いたところにあるマウンデイクレーター
(火口原)を見物に行く。
マツムシソウ・エリカ・テガタチドリ・ハハコグサが咲いている。
夕食メニュー、スープ・肉&魚ステーキ・温野菜・デザート。
少し離れたキッチンから人海戦術で運んでくる。
料理を配る順番はレデイファーストをしっかり守る。
熱々のステーキの時は、メンバー注視のなか、最初に配るトップの2人だけ
お皿にかぶせたキャップをジャーンと持ち上げるセレモニーをやる。
第1夜は食堂2階の20人部屋になる。
ベッドで明日の用意をしていると、誰か南十字星を知っている人はいない?
との呼びかけ。
ニュージーランドで見た星を思い出しながら、夜空を見上げる。
見つけられない。
オリオン座が見える。
明け方前には、天の川がくっきり見えた。
小屋の外も寒くない。
=======
2月13日 山小屋(ホロンバハット標高3750m)で第二夜
朝、ポーターが湯を満たした洗面器を配る。
モーニングテイもサービスしてくれる。
高山病予防に水分を多量摂取するよう、添乗員からクレグレも言われている。
配られる度にせっせと飲む。
9時、ホロンバハットへ向けて出発。
下山してくる日本人ツアー客に出会う。
ピークまで登った人と握手し、元気をもらう。
わずかに頭痛をかんじるが、いつのまにか忘れている。
プロテイア・セネシア(イソギンチャクのような形)
トムソンソーニア(槍状で橙と黄色のツートンカラー)
などが花盛り。
ホロンバハットに15時40分到着。
小屋の床下を鼠がチョロチョロ動き回っている。
背中に縦縞が3本ある。
第二夜は4人部屋である。
小屋の配置が判りづらくて、夜中ヘッドランプを灯し、さまよう。
よその小屋を通りかかると、中に居る外人が入口の扉を開けてと、
必死の形相で私に訴える。
どうして中から開かないのか、訳が判らなかったが、自分の小屋で同じ状況が出現
して納得する。
外からだと押しただけで開く。
ガタピシ扉を間違ってキッチリ閉めようものなら「引き手」がとれて無くなっているから
明朝、モーニングテイまで小屋から出られなくなること必定。
夜中、激しい風がしばらく続く。
低気圧でも通過したのかしら。
========
2月14日 高度順応日(ホロンボハット3750m泊)
高度順応のため、このハットでもう1泊する。
小鳥のさえずりで目が覚める。
昨夜の風がうそのような上天気。
小屋のそばにある川で、洗面している人もいる。
洗面器のお湯(サービス)で洗うよりも、気持ちが良いのは確かだ。
マウエンジ峰(5149m)の麓を、スローペースで登る。
デイクデイク(鹿)が人を見て、姿を隠す。
ゼブラロックを通り過ぎ、4200m地点に着いたのは、ちょうど正午。
急に曇り始め、雷鳴が聞こえる。
小屋に戻ったのは13時、すぐ昼食。
食欲がない、消化のよさそうな野菜・果物をつまむ。
午後はポーターも時間にゆとりがある。
胸に名札をつけたウエイター達が寄ってきて、オハヨウ・コンニチワなど挨拶語を
教えてと言う。
メモ用紙に、GOOD NIGHT = OYASUMI
など、7単語ほど書いて3人に渡す。
彼らはそれを正確にものにした。
夕食はキツネドンベエ、美味しい。
明け方、ベッドに寝たままで、地平線上の北斗七星をみる。
北極星は見えない。
=======
2月15日 キリマンジャロ直下の小屋:キボハット(4740m)へ
ホロンボハット(3750m) 8時45分出発、
キボハット(4740m) 14時30分到着
歩くのが辛そうな人が出始める。
20人の足並みがそろわない。
全員、キボハットへ辿りつくも、Hさんは一休みする間もなく、ホロンバハットへ引き返す
羽目になる。
高度を下げたら、ケロッと元気回復するそう。
ガモウバッグに入ったものの血中酸素濃度がアップしないFさんは、明朝ホロンボハットへ
下山することになる。
添乗員2人は、パルスオキシメーターで全員の血中酸素濃度を何度も計って回る。
ガモウバッグに何人も入ってもらったり、てんてこ舞いだ。
18時、夕食にアルフア米が出る。
23時、起床・軽食。
24時、いよいよ頂上へのアタック開始。
=======
2月16日 キリマンジャロ頂上をめざす
キボハット(4740m)を午前0時 スタート。
私のポーター・アルフレッドは傍らに付き添って歩いてくれる。
真っ暗闇で誰が前を歩いているか、全く分からない。
登り始めてまもなく、私のすぐ前を行く人がフラフラよろけだし、少し歩いては立ち止まる。
ガイドは休憩をかなり長くとる。
寒さに縮こまりながら、満天の星空を見上げる。幸運にも、流れ星を見る。
はるか下方ではヘッドランプの灯が動いている。
隊列が長く伸びる。
高度をかせぐにつれ、眠気が猛烈に襲ってくる。
半分、眠りながら歩く、初体験だ。
息づかい激しい、心臓は、はちきれんばかり。
口が喘ぐ、鼻から口から息を吸う。
延々とザレ道が続く。
一歩進んでは、半歩ズリ落ちる。
靴の長さ(23.5c)2分の1がやっとの一歩・一歩を20歩数えては、立ち止まり岩に寄りかかる。
一歩も前に進みたくなくなる。
星が輝く稜線に、中々近づかない。
こんな辛い登山は初めてだ、申し込んだことを後悔する。
6時20分、稜線に出る手前で日の出を迎える。
まばゆい黄金色をチラと見やるのが精一杯。
感激する余力すら、残っていない。
6時40分 ギルマンズポイント(5685m)到着。
皆の顔が判別できる明るさになる。
写真を撮っている間に呼吸が落ち着く。
ウフルピーク(5892m)を目指す勇気も湧いてくる。
緩やかな登りだが、息苦しいのは変わらない。
火口の縁をトラバースする。
ところどころ雪渓がある。
何組ものパーテイがウフルピークを目指している。
ウフルピーク(5892m) 8時45分到着
ここまで到達しないと見られない氷河を写真に収める。
何層にもなった万年氷河である。
9時、下山開始。
ギルマンズポイント(5685m) 10時に戻りつく。
ここからキボハット(4740m)までは砂走りだ。
ポ-ターのアルフレッドが腕をくんでくれる。
おかげで、2時間でキボハット小屋まで走り下りる。
キボハット(4740m) 12時、帰着。
疲れているがキボハットには、次の登山者が入るので、部屋を明け渡さねばならない。
シュラフや荷物を大急ぎでザックに詰め込む。
ウエーターが卵料理の希望をききにくる。
昼食もそこそこに、三々五々、ホロンボハット(3750m)へ戻り始める。
道すがら、ポーターのフセインとカタコト英語で会話する。
彼は、登山客から貰ったであろうブランド服を着ている。
ホロンボハット(3750m)15時30分到着
夕食時、眠かった。
月光はこうこうと明るい。
夜中でもヘッドランプが要らない。
=======
2月17日 ウサ ロッジへ
5日ぶりのシャワー
ホロンボハット(3750m)小屋、食堂のテーブルは、満杯。
これから上へ登る客優先なのか、 朝食が1時間遅れる。
ホロンボハット(3750m) 10時 出発
早足で歩く。
道はカラカラに乾ききっているので、前を歩く人の砂埃をもろに受ける。
マスクが必需品だ。
病人を乗せた三輪車が通り過ぎる。ポーター3人掛かりで下っていく。
多分、高山病にかかった人であろう。
登山口のマラングゲート(1900m) 16時30分到着
カメレオンが、再び姿を見せる。
頭をもたげる様子や、細い緑色の足指を興味深く、観察する。
ポーター達とは、ここでお別れだ。
フセインのアドレスをメモする。
ウサロッジまで車で1時間。
5日間の汗と埃を、シャワーで流す。
夕食は生バンド演奏を楽しみながら、頂く。
オイルフオンデュに舌づつみ、至福の時が流れる。
黒人シンガーの歌声に聴き惚れる。
登頂の喜びをはがきにしたため、ホテルで投函する。
=======
2月18日 サフアリを楽しむ
アリューシャ国立公園
キリンは遠くからでもそれと見分けられる。
天敵にも狙われやすいのではないだろうか。
猿、バッフアロ、鹿etc
中でも、フラミンゴの大群は圧巻だ。
湖をピンク色に染め尽くすフラミンゴが一勢に飛び立つ様は
見もの。
しかし、赤道直下のきつい陽射しが私には耐えがたく、楽しめない一日だった。
ホテルへ帰る車中から、メルー山(4565m)が青空にクッキリ聳え立つ
雄姿を見る。
ホテルでデイナーのあと、キリマンジャロ空港へ向かう。
=======
2月19日~20日 帰国
アムステルダム空港では 乗り継ぎ便を6時間待つ。
この時間を利用し、アムステルダム市内見物へでかける人もいる。
一世一代の挑戦を終えて、関西空港へ帰り着く。
THE END
今を去る10年前の登頂紀行
~~~~~
A社ツアーに参加する
2000年2月10日~20日
《乗り物》
2月10日 関西空港(機乗 12時間)
2月10日 オランダ・アムステルダム空港 15:00(ホテル泊)
2月11日 アムステルダム空港(機乗 12時間)
⇒タンザニア・キリマンジャロ空港
↓送迎 40分
アリューシャ・デイクデイクホテル(泊)
2月12日 デイクデイクホテル
↓送迎 2時間
登山口・マラングゲート(標高1900m)
《歩行》
2月12日 マンダラハット山小屋(標高2,690m)で第一夜
登山口・マラングゲート(標高1900m)で
ポーター30名の役割分担が決まるのを、気長に待つ。
ポレポレ~~ 悠長迫らない。
ランチをもらい、超スローペースで歩き始める。
ポーターは荷物(登山者が山小屋で使うシュラフ等、個人装備)を頭にのせて
運んでくれる。
ガイドE君が、草むらのカメレオンを見つける。
E君の指に止まり、ゆったりかまえている。
とかげに、そっくりだ。
ポーターのフセインが赤く熟した野苺を摘んでくれる。
フセインは、私のリュックを持ってくれているのだ。
登頂を是が非でも成し遂げるため、依頼したもの。
従って、私は手ぶらで歩く。
休憩の都度、ポーターが温かいテイを配ってくれる。
頻繁な水分補給は高山病対策でもある。
樹林帯の緩い登り坂、陽射しがきついので傘をさして歩く。
歩くこと4時間で、1番目の小屋マンダラハットに到着する。
テイの用意がととのっている。
紅茶・コーヒー・ビスケット・ポップコーンがお替り自由。
テイの後、小屋から15分歩いたところにあるマウンデイクレーター
(火口原)を見物に行く。
マツムシソウ・エリカ・テガタチドリ・ハハコグサが咲いている。
夕食メニュー、スープ・肉&魚ステーキ・温野菜・デザート。
少し離れたキッチンから人海戦術で運んでくる。
料理を配る順番はレデイファーストをしっかり守る。
熱々のステーキの時は、メンバー注視のなか、最初に配るトップの2人だけ
お皿にかぶせたキャップをジャーンと持ち上げるセレモニーをやる。
第1夜は食堂2階の20人部屋になる。
ベッドで明日の用意をしていると、誰か南十字星を知っている人はいない?
との呼びかけ。
ニュージーランドで見た星を思い出しながら、夜空を見上げる。
見つけられない。
オリオン座が見える。
明け方前には、天の川がくっきり見えた。
小屋の外も寒くない。
=======
2月13日 山小屋(ホロンバハット標高3750m)で第二夜
朝、ポーターが湯を満たした洗面器を配る。
モーニングテイもサービスしてくれる。
高山病予防に水分を多量摂取するよう、添乗員からクレグレも言われている。
配られる度にせっせと飲む。
9時、ホロンバハットへ向けて出発。
下山してくる日本人ツアー客に出会う。
ピークまで登った人と握手し、元気をもらう。
わずかに頭痛をかんじるが、いつのまにか忘れている。
プロテイア・セネシア(イソギンチャクのような形)
トムソンソーニア(槍状で橙と黄色のツートンカラー)
などが花盛り。
ホロンバハットに15時40分到着。
小屋の床下を鼠がチョロチョロ動き回っている。
背中に縦縞が3本ある。
第二夜は4人部屋である。
小屋の配置が判りづらくて、夜中ヘッドランプを灯し、さまよう。
よその小屋を通りかかると、中に居る外人が入口の扉を開けてと、
必死の形相で私に訴える。
どうして中から開かないのか、訳が判らなかったが、自分の小屋で同じ状況が出現
して納得する。
外からだと押しただけで開く。
ガタピシ扉を間違ってキッチリ閉めようものなら「引き手」がとれて無くなっているから
明朝、モーニングテイまで小屋から出られなくなること必定。
夜中、激しい風がしばらく続く。
低気圧でも通過したのかしら。
========
2月14日 高度順応日(ホロンボハット3750m泊)
高度順応のため、このハットでもう1泊する。
小鳥のさえずりで目が覚める。
昨夜の風がうそのような上天気。
小屋のそばにある川で、洗面している人もいる。
洗面器のお湯(サービス)で洗うよりも、気持ちが良いのは確かだ。
マウエンジ峰(5149m)の麓を、スローペースで登る。
デイクデイク(鹿)が人を見て、姿を隠す。
ゼブラロックを通り過ぎ、4200m地点に着いたのは、ちょうど正午。
急に曇り始め、雷鳴が聞こえる。
小屋に戻ったのは13時、すぐ昼食。
食欲がない、消化のよさそうな野菜・果物をつまむ。
午後はポーターも時間にゆとりがある。
胸に名札をつけたウエイター達が寄ってきて、オハヨウ・コンニチワなど挨拶語を
教えてと言う。
メモ用紙に、GOOD NIGHT = OYASUMI
など、7単語ほど書いて3人に渡す。
彼らはそれを正確にものにした。
夕食はキツネドンベエ、美味しい。
明け方、ベッドに寝たままで、地平線上の北斗七星をみる。
北極星は見えない。
=======
2月15日 キリマンジャロ直下の小屋:キボハット(4740m)へ
ホロンボハット(3750m) 8時45分出発、
キボハット(4740m) 14時30分到着
歩くのが辛そうな人が出始める。
20人の足並みがそろわない。
全員、キボハットへ辿りつくも、Hさんは一休みする間もなく、ホロンバハットへ引き返す
羽目になる。
高度を下げたら、ケロッと元気回復するそう。
ガモウバッグに入ったものの血中酸素濃度がアップしないFさんは、明朝ホロンボハットへ
下山することになる。
添乗員2人は、パルスオキシメーターで全員の血中酸素濃度を何度も計って回る。
ガモウバッグに何人も入ってもらったり、てんてこ舞いだ。
18時、夕食にアルフア米が出る。
23時、起床・軽食。
24時、いよいよ頂上へのアタック開始。
=======
2月16日 キリマンジャロ頂上をめざす
キボハット(4740m)を午前0時 スタート。
私のポーター・アルフレッドは傍らに付き添って歩いてくれる。
真っ暗闇で誰が前を歩いているか、全く分からない。
登り始めてまもなく、私のすぐ前を行く人がフラフラよろけだし、少し歩いては立ち止まる。
ガイドは休憩をかなり長くとる。
寒さに縮こまりながら、満天の星空を見上げる。幸運にも、流れ星を見る。
はるか下方ではヘッドランプの灯が動いている。
隊列が長く伸びる。
高度をかせぐにつれ、眠気が猛烈に襲ってくる。
半分、眠りながら歩く、初体験だ。
息づかい激しい、心臓は、はちきれんばかり。
口が喘ぐ、鼻から口から息を吸う。
延々とザレ道が続く。
一歩進んでは、半歩ズリ落ちる。
靴の長さ(23.5c)2分の1がやっとの一歩・一歩を20歩数えては、立ち止まり岩に寄りかかる。
一歩も前に進みたくなくなる。
星が輝く稜線に、中々近づかない。
こんな辛い登山は初めてだ、申し込んだことを後悔する。
6時20分、稜線に出る手前で日の出を迎える。
まばゆい黄金色をチラと見やるのが精一杯。
感激する余力すら、残っていない。
6時40分 ギルマンズポイント(5685m)到着。
皆の顔が判別できる明るさになる。
写真を撮っている間に呼吸が落ち着く。
ウフルピーク(5892m)を目指す勇気も湧いてくる。
緩やかな登りだが、息苦しいのは変わらない。
火口の縁をトラバースする。
ところどころ雪渓がある。
何組ものパーテイがウフルピークを目指している。
ウフルピーク(5892m) 8時45分到着
ここまで到達しないと見られない氷河を写真に収める。
何層にもなった万年氷河である。
9時、下山開始。
ギルマンズポイント(5685m) 10時に戻りつく。
ここからキボハット(4740m)までは砂走りだ。
ポ-ターのアルフレッドが腕をくんでくれる。
おかげで、2時間でキボハット小屋まで走り下りる。
キボハット(4740m) 12時、帰着。
疲れているがキボハットには、次の登山者が入るので、部屋を明け渡さねばならない。
シュラフや荷物を大急ぎでザックに詰め込む。
ウエーターが卵料理の希望をききにくる。
昼食もそこそこに、三々五々、ホロンボハット(3750m)へ戻り始める。
道すがら、ポーターのフセインとカタコト英語で会話する。
彼は、登山客から貰ったであろうブランド服を着ている。
ホロンボハット(3750m)15時30分到着
夕食時、眠かった。
月光はこうこうと明るい。
夜中でもヘッドランプが要らない。
=======
2月17日 ウサ ロッジへ
5日ぶりのシャワー
ホロンボハット(3750m)小屋、食堂のテーブルは、満杯。
これから上へ登る客優先なのか、 朝食が1時間遅れる。
ホロンボハット(3750m) 10時 出発
早足で歩く。
道はカラカラに乾ききっているので、前を歩く人の砂埃をもろに受ける。
マスクが必需品だ。
病人を乗せた三輪車が通り過ぎる。ポーター3人掛かりで下っていく。
多分、高山病にかかった人であろう。
登山口のマラングゲート(1900m) 16時30分到着
カメレオンが、再び姿を見せる。
頭をもたげる様子や、細い緑色の足指を興味深く、観察する。
ポーター達とは、ここでお別れだ。
フセインのアドレスをメモする。
ウサロッジまで車で1時間。
5日間の汗と埃を、シャワーで流す。
夕食は生バンド演奏を楽しみながら、頂く。
オイルフオンデュに舌づつみ、至福の時が流れる。
黒人シンガーの歌声に聴き惚れる。
登頂の喜びをはがきにしたため、ホテルで投函する。
=======
2月18日 サフアリを楽しむ
アリューシャ国立公園
キリンは遠くからでもそれと見分けられる。
天敵にも狙われやすいのではないだろうか。
猿、バッフアロ、鹿etc
中でも、フラミンゴの大群は圧巻だ。
湖をピンク色に染め尽くすフラミンゴが一勢に飛び立つ様は
見もの。
しかし、赤道直下のきつい陽射しが私には耐えがたく、楽しめない一日だった。
ホテルへ帰る車中から、メルー山(4565m)が青空にクッキリ聳え立つ
雄姿を見る。
ホテルでデイナーのあと、キリマンジャロ空港へ向かう。
=======
2月19日~20日 帰国
アムステルダム空港では 乗り継ぎ便を6時間待つ。
この時間を利用し、アムステルダム市内見物へでかける人もいる。
一世一代の挑戦を終えて、関西空港へ帰り着く。
THE END






























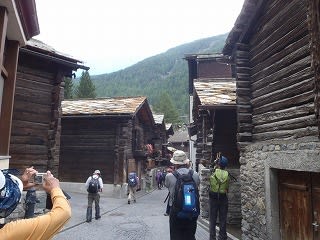

































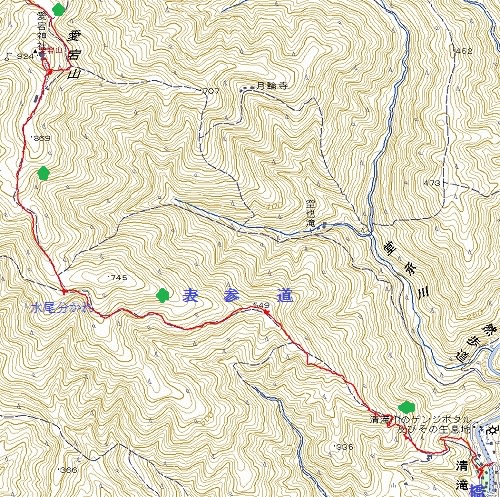




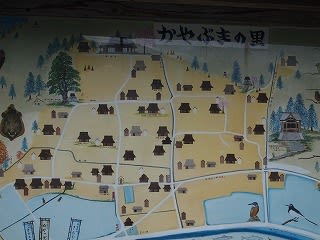



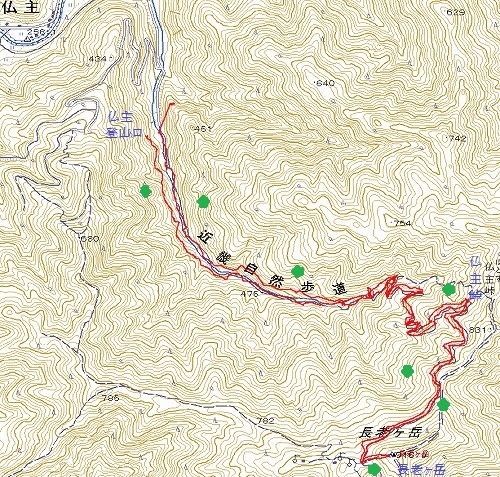



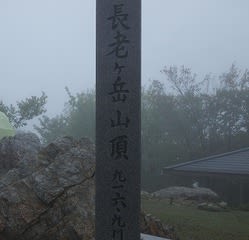

















 が掘り返した穴ぼこが延々と続く。
が掘り返した穴ぼこが延々と続く。

 の若者5人が一休みがてら、談笑している。
の若者5人が一休みがてら、談笑している。









































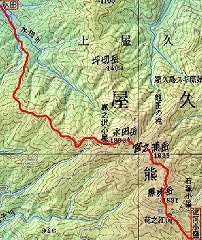















 ⇒宝塚駅 04:00
⇒宝塚駅 04:00 




























