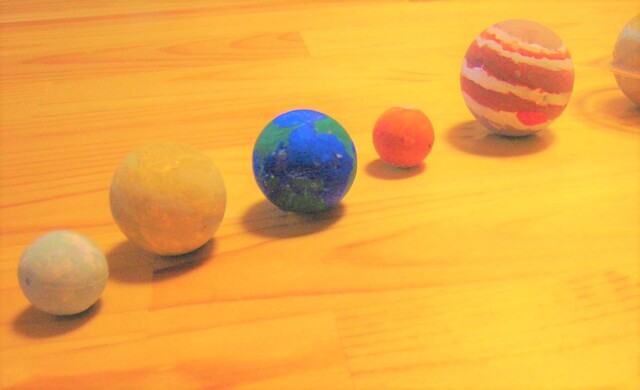ご覧いただきありがとうございます。
gooブログがサービス終了するため(2025年11月)
アメブロへお引越ししていますので、こちらもよろしくお願いいたします。
https://ameblo.jp/kodomonoie-aiai/

この写真のとおり、やっと息子が一人で滑れるようになりました^^
昨年は、失敗してしまい、息子は、「スキーこわいからヤダ」と言うし、
今年に入ってから、1度行ったのですが、うまくできず、
カマクラづくりで終わってしまいました(T_T)
今度こそ、失敗したくない!という(親の)強い思いで、
体調もなんとか整え(本調子ではなかったけれど)、
ゲレンデに行かないことには始まらないので、
なんとかなだめすかし、連れて行きましたが、
今回は、うまく行き、自信もついて、自分から
「リフトに乗って、山の上から滑りたい」と、うれしい言葉。
少し心配もしましたが、こわがることなく、
転びながらも、自分で起き上がり、下まで降りてくることができました。
回数券だっため、この後、2回リフトに乗って、降りましたが、
「もっとやりたかった」と言っていました。
そのあと、また、やはりカマクラ作ってましたけど^^ゞ
●今回成功した要因●
1.行く前に、家で、グローブをはめて、
ストックを手首にかけることができるようにしておいた。
2.ブーツを履いて、板に自分ではめることができるようにしておいた。
3.板をつけた状態で、横歩きができるようにしておいた。
(傾斜をのぼるとき、使えます)
4.ゲレンデを変えた。
何人かの初心者ママたちに聞いたら、私たちがいつも行く
ゲレンデは、コワイと言うので、よく行くゲレンデを聞いて、
そちらに変えてみました。
このゲレンデが、息子に合っていたようでした。
広々とした緩やかな坂があり、ベルコン(ベルトコンベア)で、
板をつけたまま上がっていくことができました。
何度も「自分でできる」というのが、よかったようです。
親は、交代で、付き添っているだけで、あまり教えることはなかったです。
他には、雪が滑りにくいガサガサの雪だったことも、よかったかも。
親は、新雪だったりすると、いい雪!とうれしくなりますが、
初心者には、滑りすぎないほうがいいでしょうね。
夫は、滑りやすいように板にワックスを念入りに塗ってくれるのですが、
息子の板にも塗っていたらしい・・・。
まだエッジもうまく使えないのに、それは、コワかったでしょう・・・(苦笑)
ボーゲンの仕方ですが、よく「ハの字」と教えられますが、
三角と教えるとわかりやすいようですよ。
「とがった三角にすると滑る」「広がった三角にすると止まる」
と教えました。
天気がよかったことも大きいと思います。
慣れないうちは、お天気がよい日に行くといいですね。
最近は、暖かい日も多くなってきました。
スキーシーズンも、あと少しかな?