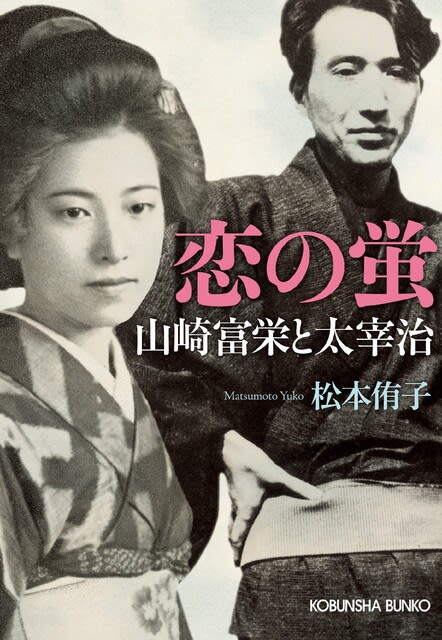琵琶と語りで聞く平家物語〜俊寛
平家物語は、日本という国の権力にまつわる物語であるが故に、
勝者、敗者、ともに数々のドラマがあり、笑う人、泣く人も数多くいました。
勝者の中にあっても泣く人はいたし、敗者でありながら笑う人もいました。
そういった中で、この俊寛という坊さんは、
悲劇、憐れの極致を演じた人物ではないでしょうか。

1177年、京都郊外の鹿ケ谷で、ある事件が起こりました。
世に「鹿ケ谷の陰謀」と言われた事件です。
ここには俊寛の別荘がありました。
そこには毎晩、打倒平家を叫ぶ輩が集まって密談をしていました。
平清盛率いる平家は、「平家に非ずば人に非ず」と豪語し、
まさに「我が世の春」を謳歌しまくっていたのです。
それを心よく思わない人達が居ない筈はありません。
平家じゃない奴は人間じゃないなどと言われて楽しい筈はありません。
天皇家である後白河上皇もそうでした。
貴族でもない平家ごときが、いい加減にしろと彼も怒っていたのです。
打倒平家の話の輪に加わっていた人達の中に、
それほどでもない人がいて、彼は「これが発覚したらエライ事になる」と、
これを清盛に密告しました。
誰だって、どっちに付けば損か得かの、損得勘定をするのが人間。
彼だって生き永らえ、勝ち組になりたいのです。
その報告を受けた清盛の怒りは激しく、ただじゃ済ませませんでした。
死刑にする奴は死刑にし、その時は死刑にならなくても、流刑になる人もいました。
流刑(要するに島流し)ですね。
で、何処に島流しになったのか?


九州の遥か南、奄美黄島の右側あたりにいくつかの島々があり、
その中の(硫黄島)ではないかと言われています。
ハッキリとした確証は無いのですが、平家物語の文献からそうではないかと言われています。
そこに流されたのは、俊寛、平康頼、藤原成経の3人でした。
平家物語によると、
舟は滅多に通わず、人も稀である。
住民は色黒で、毛が濃く、話す言葉も理解できず、
農夫はおらず穀物の類は無く、衣料品も無い。
島には高い山があり、常時火が燃えており、硫黄が沢山ある。
そういった島であり、京の都の住民から見れば、まさに絶海の孤島だったのでしょう。
彼等が鬼界が島に流刑になった翌年、
清盛の次女徳子(建礼門院)が懐妊した事に喜んだ清盛は、
流刑となった者達に恩赦を発しました。
清盛の命令書を携えた者が、鬼界ヶ島へ向かいました。
しかし、その書面には2人の名前しか書いてありません。
平康世、藤原成経。
俊寛は、何かの間違いだ、自分の名前だけが無いなんてそんな筈が無いと、
何度も何度も封筒の裏表を調べますが、彼の名前は何処にも無いのです。

舟は無情に去って行きます。
俊寛は「京の都までとは言わないが、せめて九州まで乗せていってくれ」と船べりにすがります。
しかし、水面は腰から胸と深くなるばかり、
遂に俊寛は諦めざるを得なくなり、海岸に突っ伏し泣き伏します。
何と無情な事でしょう。
その時の俊寛の絶望くらい、真の絶望はなかったと思います。
二人の死刑囚が居て、明日は死刑執行になるとします。
彼等は「俺達は二人で明日は一緒に逝こうな」と語り合っていました。
所が死刑執行当日になって、一人だけに恩赦が下って助かります。
残された片割れは、その瞬間「そんな馬鹿な、そんな不公平はあるかッ」と、
怒り狂い昨日までの平常心は吹き飛んでしまいます。
俊寛にしても、昨日までは3人で「京の都に帰るまでは」と、
共に語り合っていたであろう3人だったのに、
2人だけが京に帰り、自分一人だけが島に置き去り。
もう何が何だか判らなく自暴自棄、半狂乱になった自分がそこに居たのです。
その時の彼の心を思うと、ゾッとします。
俊寛が一人残された半年後、
かつて都で面倒を看ていた有王という童が俊寛を探しに島にやって来ました。
そして、俊寛の妻も息子も不遇の中で既に亡くなった事を伝えます。
今は娘だけが伯母様の下に暮らしていると告げ、
娘から預かってきた手紙を俊寛に渡しました。
妻子にもう一度逢いたいと、それだけを支えに生き永らえてきた俊寛は、
全ての望みを失い、以後、一切の食べ物を口にせずに餓死したのです。
俊寛37歳でした。
平家物語は、日本という国の権力にまつわる物語であるが故に、
勝者、敗者、ともに数々のドラマがあり、笑う人、泣く人も数多くいました。
勝者の中にあっても泣く人はいたし、敗者でありながら笑う人もいました。
そういった中で、この俊寛という坊さんは、
悲劇、憐れの極致を演じた人物ではないでしょうか。

1177年、京都郊外の鹿ケ谷で、ある事件が起こりました。
世に「鹿ケ谷の陰謀」と言われた事件です。
ここには俊寛の別荘がありました。
そこには毎晩、打倒平家を叫ぶ輩が集まって密談をしていました。
平清盛率いる平家は、「平家に非ずば人に非ず」と豪語し、
まさに「我が世の春」を謳歌しまくっていたのです。
それを心よく思わない人達が居ない筈はありません。
平家じゃない奴は人間じゃないなどと言われて楽しい筈はありません。
天皇家である後白河上皇もそうでした。
貴族でもない平家ごときが、いい加減にしろと彼も怒っていたのです。
打倒平家の話の輪に加わっていた人達の中に、
それほどでもない人がいて、彼は「これが発覚したらエライ事になる」と、
これを清盛に密告しました。
誰だって、どっちに付けば損か得かの、損得勘定をするのが人間。
彼だって生き永らえ、勝ち組になりたいのです。
その報告を受けた清盛の怒りは激しく、ただじゃ済ませませんでした。
死刑にする奴は死刑にし、その時は死刑にならなくても、流刑になる人もいました。
流刑(要するに島流し)ですね。
で、何処に島流しになったのか?


九州の遥か南、奄美黄島の右側あたりにいくつかの島々があり、
その中の(硫黄島)ではないかと言われています。
ハッキリとした確証は無いのですが、平家物語の文献からそうではないかと言われています。
そこに流されたのは、俊寛、平康頼、藤原成経の3人でした。
平家物語によると、
舟は滅多に通わず、人も稀である。
住民は色黒で、毛が濃く、話す言葉も理解できず、
農夫はおらず穀物の類は無く、衣料品も無い。
島には高い山があり、常時火が燃えており、硫黄が沢山ある。
そういった島であり、京の都の住民から見れば、まさに絶海の孤島だったのでしょう。
彼等が鬼界が島に流刑になった翌年、
清盛の次女徳子(建礼門院)が懐妊した事に喜んだ清盛は、
流刑となった者達に恩赦を発しました。
清盛の命令書を携えた者が、鬼界ヶ島へ向かいました。
しかし、その書面には2人の名前しか書いてありません。
平康世、藤原成経。
俊寛は、何かの間違いだ、自分の名前だけが無いなんてそんな筈が無いと、
何度も何度も封筒の裏表を調べますが、彼の名前は何処にも無いのです。

舟は無情に去って行きます。
俊寛は「京の都までとは言わないが、せめて九州まで乗せていってくれ」と船べりにすがります。
しかし、水面は腰から胸と深くなるばかり、
遂に俊寛は諦めざるを得なくなり、海岸に突っ伏し泣き伏します。
何と無情な事でしょう。
その時の俊寛の絶望くらい、真の絶望はなかったと思います。
二人の死刑囚が居て、明日は死刑執行になるとします。
彼等は「俺達は二人で明日は一緒に逝こうな」と語り合っていました。
所が死刑執行当日になって、一人だけに恩赦が下って助かります。
残された片割れは、その瞬間「そんな馬鹿な、そんな不公平はあるかッ」と、
怒り狂い昨日までの平常心は吹き飛んでしまいます。
俊寛にしても、昨日までは3人で「京の都に帰るまでは」と、
共に語り合っていたであろう3人だったのに、
2人だけが京に帰り、自分一人だけが島に置き去り。
もう何が何だか判らなく自暴自棄、半狂乱になった自分がそこに居たのです。
その時の彼の心を思うと、ゾッとします。
俊寛が一人残された半年後、
かつて都で面倒を看ていた有王という童が俊寛を探しに島にやって来ました。
そして、俊寛の妻も息子も不遇の中で既に亡くなった事を伝えます。
今は娘だけが伯母様の下に暮らしていると告げ、
娘から預かってきた手紙を俊寛に渡しました。
妻子にもう一度逢いたいと、それだけを支えに生き永らえてきた俊寛は、
全ての望みを失い、以後、一切の食べ物を口にせずに餓死したのです。
俊寛37歳でした。