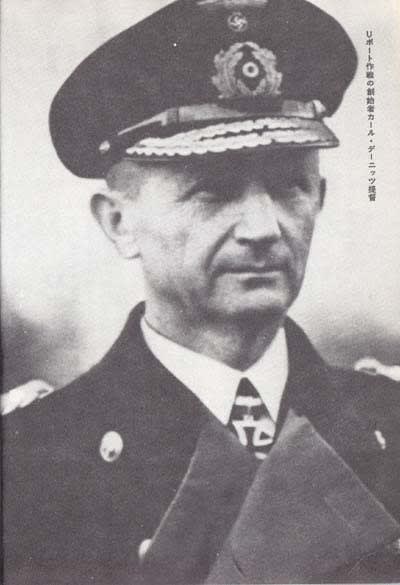ドーリットル空襲は1942年(昭和17年)4月18日。
日本本土がアメリカ軍により初めて受けた空襲でした。
前年1941年12月8日に日本軍がハワイ・真珠湾を攻撃して太平洋戦争が勃発。
開戦後は日本の潜水艦9隻がアメリカ本土周辺の貨物船、タンカーなど5隻を撃沈し、
艦砲射撃によるアメリカ本土攻撃も行い、
それはアメリカ国民に非常に大きな衝撃を与えました。
ルーズベルト大統領は、真珠湾攻撃から2週間後の時点で、
日本本土空襲の可能性を研究させていました。
これに対し、ロー海軍大佐が、空母からの空襲のプランを思いつきます。

選ばれた空母はホーネット。
排水量2万トン。全長247メートルです。
今までの空母艦載機では、飛行機が小型すぎて日本までの航続距離が足りません。
また爆弾搭載量も少なくて空襲の意味がありません。

いくつかの爆撃機の中から可能性の最も高かったのが、B-25爆撃機でした。
空母という狭くて限られたスペースから飛び立つには、様々な制約があります。
大型の爆撃機では空母からの発艦は無理です。
といってあまり小型でも空襲の役目は果たせません。
B-25は日本本土空襲の為にいくつかの改造を施します。
アメリカ本土からひたすら日本を目指しまっしぐら。
日本軍に発見される前に、太平洋の真っただ中から飛び立ち、
空母に戻る事はしないで、日本を飛び越えて中国に着陸するのが計画です。
それには長大な航続距離が求められます。
B-25は機体の軽量化と共に、予備のガソリンタンクを搭載したのです。


空襲を指揮するのは、ジミー・ドーリットル中佐。
爆撃機は全部で16機。
一機あたり5名が乗り組むので総勢80名です。

ホーネットの甲板には16機のB-25が所狭しとその時を待っています。


そして4月18日。
これ以上は日本には近づけないという地点から、
一機、また一機と16機のB-25は一時間をかけて飛び立って行きました。
空母から爆撃機が飛び立ったのは、これが初めてでした。
目指すは日本本土。
その内、10機は東京。横浜が2機。横須賀1機。名古屋1機。神戸1機。大阪1機でした。
爆撃の為に日本では死者87人。重傷者151人。
家屋の全壊、全焼は180戸でした。
被害そのものは大した事ではなかったのですが、
日本軍と日本国民に与えた衝撃は極めて大きかったのです。
日本本土への空襲を終えた爆撃隊は、
空母から発艦13時間後に中国に達しました。
航続距離は3600キロに及んでいました。
彼等は全員が同じ飛行場に着陸とはいかず、
それぞれが、てんでんばらばら状態で、
パラシュート降下などで降り立ったので、機体の15機は全損でした。
その中でも8名が日本軍の捕虜になり、
その中の3人は後に死刑となります。
80名のうち71名は6月にアメリカに帰国する事ができ、
彼等は英雄として称えられます。
この作戦が果たして成功だったのか、失敗だったのかは意見が分かれますが、
とに角、アメリカが勝ち誇った状態の日本に冷水を浴びせた事は間違いなく、
そういった意味では成功だったのかも知れません。
戦争というのはワンサイドゲームなんて殆どあり得ないのですから、
死刑にまでなってしまった兵士は気の毒だし、
まして、青天の霹靂で亡くなってしまった日本の一般市民はもっと気の毒ですね。
日本本土がアメリカ軍により初めて受けた空襲でした。
前年1941年12月8日に日本軍がハワイ・真珠湾を攻撃して太平洋戦争が勃発。
開戦後は日本の潜水艦9隻がアメリカ本土周辺の貨物船、タンカーなど5隻を撃沈し、
艦砲射撃によるアメリカ本土攻撃も行い、
それはアメリカ国民に非常に大きな衝撃を与えました。
ルーズベルト大統領は、真珠湾攻撃から2週間後の時点で、
日本本土空襲の可能性を研究させていました。
これに対し、ロー海軍大佐が、空母からの空襲のプランを思いつきます。

選ばれた空母はホーネット。
排水量2万トン。全長247メートルです。
今までの空母艦載機では、飛行機が小型すぎて日本までの航続距離が足りません。
また爆弾搭載量も少なくて空襲の意味がありません。

いくつかの爆撃機の中から可能性の最も高かったのが、B-25爆撃機でした。
空母という狭くて限られたスペースから飛び立つには、様々な制約があります。
大型の爆撃機では空母からの発艦は無理です。
といってあまり小型でも空襲の役目は果たせません。
B-25は日本本土空襲の為にいくつかの改造を施します。
アメリカ本土からひたすら日本を目指しまっしぐら。
日本軍に発見される前に、太平洋の真っただ中から飛び立ち、
空母に戻る事はしないで、日本を飛び越えて中国に着陸するのが計画です。
それには長大な航続距離が求められます。
B-25は機体の軽量化と共に、予備のガソリンタンクを搭載したのです。


空襲を指揮するのは、ジミー・ドーリットル中佐。
爆撃機は全部で16機。
一機あたり5名が乗り組むので総勢80名です。

ホーネットの甲板には16機のB-25が所狭しとその時を待っています。


そして4月18日。
これ以上は日本には近づけないという地点から、
一機、また一機と16機のB-25は一時間をかけて飛び立って行きました。
空母から爆撃機が飛び立ったのは、これが初めてでした。
目指すは日本本土。
その内、10機は東京。横浜が2機。横須賀1機。名古屋1機。神戸1機。大阪1機でした。
爆撃の為に日本では死者87人。重傷者151人。
家屋の全壊、全焼は180戸でした。
被害そのものは大した事ではなかったのですが、
日本軍と日本国民に与えた衝撃は極めて大きかったのです。
日本本土への空襲を終えた爆撃隊は、
空母から発艦13時間後に中国に達しました。
航続距離は3600キロに及んでいました。
彼等は全員が同じ飛行場に着陸とはいかず、
それぞれが、てんでんばらばら状態で、
パラシュート降下などで降り立ったので、機体の15機は全損でした。
その中でも8名が日本軍の捕虜になり、
その中の3人は後に死刑となります。
80名のうち71名は6月にアメリカに帰国する事ができ、
彼等は英雄として称えられます。
この作戦が果たして成功だったのか、失敗だったのかは意見が分かれますが、
とに角、アメリカが勝ち誇った状態の日本に冷水を浴びせた事は間違いなく、
そういった意味では成功だったのかも知れません。
戦争というのはワンサイドゲームなんて殆どあり得ないのですから、
死刑にまでなってしまった兵士は気の毒だし、
まして、青天の霹靂で亡くなってしまった日本の一般市民はもっと気の毒ですね。