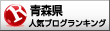フローラは2015年から環境システム科に移籍することになります。
ここで発表しているのは園芸科学科最後のメンバー。
2011年に活動を始めたサクラソウの救出活動は、
その後、自生地の保全活動へと舵を切っていました。
彼女たちは保全生態学の権威である当時東大の鷲谷先生や
筑波大学の先生方からアドバイスをいただき精力的に活動を推進。
その活動が青森県に認められ、日本で初めて開催されたアジア国立公園会議での
発表を依頼されます。もちろん唯一の高校生発表者。それも英語での発表です。
さらに農業クラブでは、この活動をプロジェクト発表と意見発表の2つで披露。
いずれも青森県大会で最優秀。大活躍しました。
確か東北大会の会場となった仙台にフローラは
2〜3年生全員12名ぐらいの大所帯で乗り込んだのを覚えています。
これには理由があります。翌年、環境システム科に完全移籍することになっていたチームは
3年生は園芸科学科、2年生は環境システム科という不思議なメンバー構成。
そのため園芸科学科時代に作り上げた「やるなら楽しく精一杯」という流儀を
この大会を通してバトンタッチしたいという願いがあり
学科こそ違いますが、春から同じ目標に向かって一緒に活動してきたからです。
園芸科学科最後のフローラにとって有終の美を飾るにふさわしい活動でした。
なおここで説明している園芸科学科最後の女子メンバーは筑波大学に進学。
フローラ2人目の筑波大生誕生となりました。
このように園芸科学科時代は頼もしいお姉さんが多く、
グイグイ引っ張ってくれたものです。
ここで発表しているのは園芸科学科最後のメンバー。
2011年に活動を始めたサクラソウの救出活動は、
その後、自生地の保全活動へと舵を切っていました。
彼女たちは保全生態学の権威である当時東大の鷲谷先生や
筑波大学の先生方からアドバイスをいただき精力的に活動を推進。
その活動が青森県に認められ、日本で初めて開催されたアジア国立公園会議での
発表を依頼されます。もちろん唯一の高校生発表者。それも英語での発表です。
さらに農業クラブでは、この活動をプロジェクト発表と意見発表の2つで披露。
いずれも青森県大会で最優秀。大活躍しました。
確か東北大会の会場となった仙台にフローラは
2〜3年生全員12名ぐらいの大所帯で乗り込んだのを覚えています。
これには理由があります。翌年、環境システム科に完全移籍することになっていたチームは
3年生は園芸科学科、2年生は環境システム科という不思議なメンバー構成。
そのため園芸科学科時代に作り上げた「やるなら楽しく精一杯」という流儀を
この大会を通してバトンタッチしたいという願いがあり
学科こそ違いますが、春から同じ目標に向かって一緒に活動してきたからです。
園芸科学科最後のフローラにとって有終の美を飾るにふさわしい活動でした。
なおここで説明している園芸科学科最後の女子メンバーは筑波大学に進学。
フローラ2人目の筑波大生誕生となりました。
このように園芸科学科時代は頼もしいお姉さんが多く、
グイグイ引っ張ってくれたものです。