2008年5月27日(火曜日)
まだ、車の運転をしちゃいけないので、
夫の運転する横で、おとなしくちょこんと座っています・・・
座っていますの後になぜ「・・・」なのか・・・
自分の行きたい時に、行きたい所へ、ひとりで行けないのが
不便で、窮屈で、いろいろと気を使わなければならなくて・・・
そう! いろいろと気を使うのがいやだ! という心が
「・・・」に現われているのです。
あ~あ、わたしってやっぱり、相当わがままなんだということを
思い知って、というか思い知らされてもいます。
(曰、今頃何を! あんたのわがままは筋金入りだ! そうです)
相手を気遣うという思いやりの心が相当、欠如しているのは
その相手が夫だからでしょう・・・
とも言える・・・
でも、わたし以上に夫もたいそうな気の使いよう!
(あんたは使っていない! んだそうです)
絶対一人ででかけるな!
遠くに散歩に行くな!
健さま、ほんとうにありがたいことでございます・・・
と、ここにも「・・・」がつくのでございます・・・
さて、入院中、しかも手術のその日に、載った
朝日新聞のリレーエッセー「あしたは晴れ」の最終便。
今日初めて、13日の新聞で実物にご対面。
(ちなみに13日の紙面は、四川省の大地震が1面トップでした)
いや~・・・今頃、この言い回しはちょっと変! と
気づいても遅すぎる! けどね・・・
(はずかしい・・・わたしです)
その最後のエッセーをアップします。
http://mytown.asahi.com/fukui/news.php?k_id=19000110805130001
【聖火が広めたチベット問題】
2008年05月13日
長野の聖火リレーの中継を見た。
中国の赤い国旗が画面を覆い尽くしていた。
「ワン・チャイナ!」の叫びがわたしの心をヒンヤリさせる。
聖火リレーは、ヒトラー率いるナチスが
ベルリンオリンピックで初めて取り入れたものだ。
ナチスの国家権力とドイツ民族の優秀さを誇示するためだったといわれる。
大戦を知らないわたしでも、今回の聖火リレーにおける中国の
「愛国心」を前面に出しての意気込みは、ナチス・ドイツを思い起こさせる。
政治とオリンピックは別、と言いながらナチス以来の様式を
継承した聖火リレーは、中国という国の様々な側面を世界中に見せつけた。
聖火リレーが世界にチベットの問題を広めたとも言われている。
中国の唐丹鴻(タン・タンホン=詩人・映画監督)のエッセーを読んだ。
「チベットは消滅しつつある。美しい平和なチベットを
作っている精神も消滅しつつある。チベットは中国になりつつある。
チベットがそうなりたくないと願うものになりつつなるのである」
「そう、わたしはチベットを愛する。……チベットが自由意思を持つ限り、
わたしはチベットを愛する漢人だ。……わたしは歓迎される漢人として
チベットに戻りたいと痛切に願う。対等な隣人として、
あるいは家族の一員として、真の友情をはぐくむために」
このエッセーはわたしを少しだけ、ほっとさせてくれた。
中国を嫌いにならずに済んだから。
そして唐丹鴻が愛してやまないチベットには、
ダライ・ラマ法王が92年に作った自由チベット民主憲法
(亡命チベット人憲章)がある。
「暴力ならびに武力使用の放棄」や「すべての国民が法の前に平等であり、
性別・民族・言語・宗教・肌の色・身分さらに僧俗の別に関係なく
法が定める権利を享受することができる」と書かれている。
2年前に出版された井上ひさし氏の
「子どもにつたえる日本国憲法」を読み返した。
日本の憲法のすばらしさを再認識しながら、
「フリー・チベット」と声に出しているわたし……。
このエッセーの後には、ちゃんと
リレーエッセー「あしたは晴れ」は今回で終わります。
ご愛読ありがとうございました。
と書かれていました。
終わってみると、やっぱりさびしい・・・










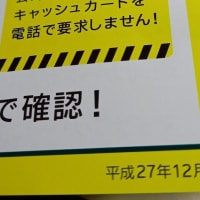
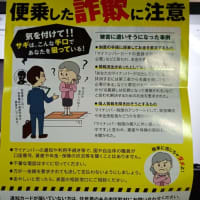
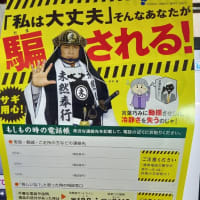

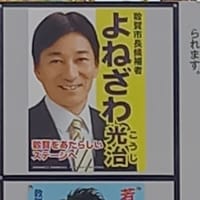











別れもね。
さびしさを噛みしめて、新しい出会いに出会うんだよね。
やっと、コメントに書き込めるようになったはるみです。
リレーエッセーから生まれた出会いも数々あって、
思い出深い2年間でした。