
風流間唯人の女災対策的読書・第64回 ジェンダー大戦「男性差別」→「弱者男性」→「男性復権」
メインテキスト:赤木智弘『若者を見殺しにする国』(双風社平成19年。加筆訂正した朝日文庫平成23年)
J.D.ヴァンス/関根光宏・山田文訳『ヒルビリー・エレジー~アメリカの繁栄から取り残された白人たち~』(原著は2016年刊。光文社未来ライブラリー平成29年)
私一個の都合でだいぶ遅れましたが、本年3月23日の言語哲学研究会の折、兵頭新児さんの発表で採り上げた「弱者男性」の問題について、私の見地からまとめておこうと思います。
まずずいぶん昔の話のように感じられる、赤木智弘が思い出された。赤木はこの国で、最初ではないかも知れないが、最初のうちに「弱者男性」を術語として使った人物の一人だ。
強者男性・弱者男性・強者女性・弱者女性、の四象限の中の一つで、安定した職や収入がなく、しかもその状態が改善される見込みもない、いわゆる社会的弱者としての男性、という意味である。
彼のメジャーデビュー作「『丸山真男』をひっぱたきたい ー 三一歳フリーター。希望は、戦争。」は朝日新聞社が出していた月刊誌『論座』平成19(2007)年1月号に出た。
それまでちょこちょこ文章を投稿していた赤木に編集者の一人が声をかけて実現したとのこと。一応は話題となり、「赤木問題」とまで言われたのだから、うまく当てた企画と言ってよい。
ポイントの第一はもちろん戦争。大東亜戦争後日本の最高の国是は反戦平和である。これだけは公然と疑ってはならないはずだった。
それが、戦争によって最も酷い目に合うはずの一般庶民、それも底辺と言える人が、日本を代表する論壇誌(それも左派の)の一つで、「希望だ」と言ってのけたのだ。
左翼人士としては、実際はどれくらいの衝撃を受けたかはともかく、訊かれたら無関心に「知らねえよ」と言うわけにはいかないわけだ。
赤木の主張は。
かつての日本企業は高度成長期からバブル期まで、日本型とも呼ばれる終身雇用制度でやってきた。それも経済成長が目に見えて右肩上がりだったからで、それが鈍った結果、既に社会に出ている旧世代の既得権益としての生活の安全(できれば収入が年々上がること、最悪でも困窮を感じるほど下がらないこと)を守るために、以前ほどの稼ぎは期待できなくなった企業をスリム化することにした。
具体的には、人件費を削るのが一番てっとり早い。しかし現社員は守られねばならない。勢い、新入社員を絞るので、結果としてその被害は若い世代に負わせることになる。
かくして、1990年代半ばから就職氷河期を迎え、そのための応急措置として非正規雇用が促進された。昭和60(1985)年に成立した労働者派遣法が改正(改悪?)され、それまで特殊技能を要する少数業種に限られていた派遣対象を、逆に少数の業種以外は受け入れ可能としたのが平成11(1999)年、小渕内閣の時。
これによって、赤木のように、高校を不登校で中退し、中卒の学歴しかない者が安定した正社員の職に就くことは絶望的になった。
それはつまり、バブル経済を現出して崩壊させた旧世代の尻拭いをさせられている、ということではないか。それなのに、年長者たちは、「近頃の若者は、勤労意欲やら組織への忠誠心が足りない」だの、「指示待ちだ、ゆとりだ」のと、すべての責任をこちらに押しつけようとする。卑劣としか言いようがない、と。
それでどうして戦争なのかというと、このような欺瞞的な社会構造を根本的に変える可能性があるからだ。
大東亜戦争の最中、丸山真男は三十歳で召集され、二等兵として送られた平壌で旧制中学にも進んでいないであろう一等兵に執拗にいじめられたという。こういう際でなければ、丸山のような超エリートを最底辺の庶民がひっぱたくなどあり得ないことだ。
持てる者にとってこそ戦争は最悪の厄災以外ではないが、持たざる者には希望があるかも知れない。後のほうは思い違いだとしても、失うものなどどうせ何もないのだ。
このような赤木の言は、暴論ではあっても妄説ではない。平和で安定した時代には、先進国では富裕層と貧困層が交代することは原則として、ない。そしてその差は開く一方である。
20世紀前半には変動が見られたが、それは二度の世界大戦に依る。戦争だけが、社会の富をめぐる競争をある程度初期状態に戻すことができると言ってよい。これがトマ・ピケティが膨大なデータを整理して『21世紀の資本』で実証したことである。
赤木言説への左翼人士達の対応は、同じ『論座』4月号にまとめられた。
だいたいは、戦争になれば赤木のような弱い立場の者が真っ先に犠牲になり、命を失うのに、そんなことも知らないとは、哀れなもんだ、というような調子だった。
これに対する再反論。なるほど、そうかも知れない。しかし、今の平和が続いたところで、自分はバイトで月10万ぐらいしか稼げないし、今後この現状を変える方途も見つからない。今は実家にいるからなんとかなっているが、やがて親も死ねば、ホームレスになるか首をくくるしかない。
それはこの世の誰も知らない、興味も持たれない死だ。ならば、戦争で死んで「名誉の戦死」とされたほうがまだましではないか、と。
個人的に一番面白かったのは、「こんな世の中にした現体制に対して、一緒に戦いましょう」という福島みずほへの返しだ。
戦うって、例えばデモ行進か。よろしい、日当をくれるなら、参加しよう。警官隊や右翼とぶつかった場合の危険手当と、交通費を含めて、一日一万円くれ、と。
懐かしのフレーズ「同情するなら金をくれ!」が思い出される。いや、冗談ではない。バイトで日銭を稼いで生活している者にとって、政府への抗議活動のために何日か仕事を休むことは、死活問題に直結する。
それは福島たち革新側も知らないわけはない。知っているからこその抗議行動なのだと言うだろう。しかし、それによって悪化する底辺の者たちの現在はどうする?
そう訊かれても……だろう。もともと革新の目指すものは「未来」なのだ。「現在」のケアは現在の政府の仕事だ。
これが、革新派が現政権になかなか勝てない理由なのである。現在が救われないのに、輝かしい未来なんてあるわけがない。だいたい、それが来る前に死んでしまうじゃないか!?
「いやいや、それは話がおかしい。今の政府がちゃんとしているなら、もともと、そんな『最底辺』は生じなかったはずじゃないか」とおっしゃいますか。
まあ、その通りでしょう。しかしとりあえず現政府は、「現在」について責任があるとされ、だから非難もされる。
「明日」を見ている反体制の革新には、そんな責任はない、感じていない。むしろ、社会全体の未来のために、個々人の現在は犠牲にするヒロイズムが暗黙の前提になっているようだ。だから「そう訊かれても……」なのだ。
このように、自分たち弱者男性の現状を、誰もちゃんとは見ていない。それが問題の核心だ、と赤木は言う。
何よりもキツイのは、そうした私たちの苦境を、世間がまったく理解してくれないことだ。
空前の人手不足だと言われ、人材派遣会社自体に人が集まらないので次々と倒産している令和の現在でも、この無理解は構造としては続いている。それも、日本だけの話ではない。
たとえば私の父は、懸命に働くことの価値をけっして否定するような人ではなかったが、それでも、生活を向上させるはっきりとした道のいくつかを信用していなかった。私がイェール大学のロースクールに進学すると知ったとき、父は私に、「黒人かリベラルのふりをしたのか」と言ったものだった。白人労働者の将来に対する期待値は、これほどまでに低いのである。こうした態度が広まっていることを考えれば、生活をよくするために働こうという人が少なくなっても、なんら不思議ではない。
以上は現米国副大統領J.D.ヴァンスが32歳のときに出版した自伝の一節である。
彼の家族は白人だがWASP(White Angro-Saxon Protestant。最も早く英国から移り住んだ人種で、ほぼ米国の支配階層と同義)ではなく、18世紀に東海岸の、カナダから米国に跨がるアパラチア山脈周辺に住み着いたアイルランド系移民の子孫で、彼自身はオハイオ州のラストベルト(錆びついた工業地帯)に属する町で育った。
そこの白人男性たちの一般的な意識は、上の引用文のようなものだ。しかし、そこから脱出し、今時珍しくアメリカン・ドリームを実現したヴァンスは、赤木智弘と違って、それを外部のせいだけにはしない。
彼の同輩達は確かに怠け者と呼ばれるに相応しかった。学校ではこつこつ勉強するなんて女々しいなんて思い込みが支配的で(日本の田舎でも、私の子ども時分にはそういう雰囲気があった)、仕事では簡単で比較的恵まれている職場でも長続きせず、人生のごく早い段階でセックスに耽り、時には麻薬に手を出す。うまく生活保護を受給できるようになると、自分や自分の生活を向上させるための一切の努力を放棄し、ますます自堕落な生活を送る。
彼らに対する社会のケアが足りないのか、彼らのほうがケアに値しないのか、はそれこそ卵―鶏関係だ。確かに言えるのは、期待されないから努力しない←→努力しないから期待しない、の悪循環が果てしなく繰り替えされ、出口が見えないということである。
そこでヴァンスの父の言葉だが、黒人やリベラルのほうが恵まれているかどうかは知らない。ただ、彼らは、他人や公的・半公的(NPOなど)機関に気にかけてもらえる度合いが高い。少なくともその思い込みはある。
黒人、とは少し前の時代の、社会的少数者・弱者の象徴である。そこに現在、米国国内の少数民族、LGBTQ+、ハンディキャップ、そして女性、が急速に加わった。Diversity(多様性)の尊重の名の下に、彼らの救済を叫ぶのがリベラルの存在価値になっている。
健康な白人男性への救済措置はない、それ以前に存在が認められていない。少なくともその思い込みはある。
いや、実際より主観的な思い込みのほうが強いとしても、この分断は深刻だろう。差別というのは、黒人なら黒人が目の前にいて、そこで感情が動くことから始まる。目の前にいないなら、あるいはいても少しも感情が動かず、無視してしまえるなら、それは差別であると気づかれることもない。だから、問題視されることも、反省されることもない。
例えば昨年の9月、人気トーク番組「オプラ・ウィンフリー・ショー」を模した民主党のイベントで、ゲストのメリル・ストリープがハリス(当時)副大統領に「ハリス大統領」と呼びかけ、そのあとわざとらしく「あっ、ごめんなさい」と続けたパフォーマンスは、会場を湧かせた。それを報じた日本のTVでも、大統領選でのハリスの優勢を伝えた。
ただしあくまで東西海岸の知識層、大手メディア、ハリウッドのスターたち、などの間では、とは言われなかった。実際に気づいていなかったのだろう。
一方大統領選挙後のネット上の記事CNN business11月6日は、ある大手TV局幹部の言葉として、「国民の半分がトランプが大統領になる資格があると決断したのなら、彼らはこのようなメディアは全然読んでいないということだ。そして我々はこのような視聴者を完全に失ったのだ」というのを伝えている。
民主党の政治家も、彼らを支持する大手マスコミも、インフレや不法移民や行きすぎたポリコレに苦しむ一般民衆の姿を、ほとんど見ていなかった。だから彼らの報道には民衆は登場しない。
民衆の側では、そんな報道は読まないし、見ないし、そこで立派なことを言うだけは言っている政治家を全く信用しない。それが米国のトランプ現象と呼ばれるものの底流にあり、またヨーロッパの、マスコミには「極右」などと呼ばれる保守勢力の台頭をももたらしたものだろう。
もう言われ尽くしたことだが、カマラ・ハリス候補は女性でアフリカ系というだけで、ポリコレの目指すequality(平等)の象徴として相応しい人物だ。これに対して弱者男性の視点は、現在の国民意識の深い断絶を測る指標になりそうだ。
どうして弱者男性が無視されがちなのか? 答えはもう出ているように感じられるのだが、どうですか?
男は弱者であることが許されないからだ。「俺は弱者だ」なんぞと自認して、そういう観点から世間の注目やら同情やらを買おうとする男は、許しがたい裏切り者なのだ。
つまり、男とは最も広い意味の外部からの脅威から、女・子どもを守るべき存在だ。あるいは、守るようなふりをして、女・子どもを圧迫し、支配しようとする存在だ。それ以外であっては困る。
社会の多くの人が実際にそう思っているのか、そう思われているだろうと思う男が多いので自分の首を絞めているのか、などと考えるのは無駄である。それは卵鶏関係でもない、同じものの表裏の関係なのだから。
社会的弱者の明確なしるしのない所謂普通の男は、苦境に陥ってもなかなかそうとは認めてもらえないし、自分の方でも認めてもらいたくない様子をしていることが多い。
フェミニズムから派生した男性学は、そのような従来からの男女の役割分担、そこを言語化した「男らしさ・女らしさ」の規範は、女性のみならず、男性をも不自由で不幸にしているのだから、できるだけ軽減して、もっと個々別に「自分らしく」、自由に生きることを勧めている。
しかしもちろん、そう簡単にはいかない。自分一人の生き方や考え方を変えるだけでなんとかなることではないからだ。他人にとって自分がどういう存在であるかが、決定的に大きい領域の話なのである。たぶんそんなことはフェミニストも百も承知で、自分たちの運動を進めるための便法として「男性にも理解を示す」だけなのだろう。
例えば専業主夫の存在。
政府の取り組みもあって、戦後一貫して女性の社会進出は進んだ。今は女性も、少なくとも一時期は働くのが当り前である。男女の賃金格差は依然としてあるが、それはマスコミで「是正されるべき」だという社会問題扱いされている。
一方で金を稼がず、専ら家事に従事している専業主婦は、減っているとは言え、全世帯の三割ぐらいはいる。その役を男性が引き受けようとすると。
赤木智弘は、著書『若者を見殺しにする国』の第二章を「私は主夫になりたい」とした。女性も働くのが当り前の世の中になっても、専業主婦の存在が許されているなら、専業主夫がいてもいいはずなのだ。しかし彼が調べた厚生年金第3号被保険者(会社員や公務員の配偶者として扶養されている人々)のうち、男性の割合は1%に過ぎなかった。
因みに、厚労省が発表した令和5年度の資料から筆者が計算したところでは、この割合は1.9%になっていた。赤木の時代から15年ほど経て、倍増したわけだ。ここに人々の意識の変化が見られる……わけはないか。
また因みに、著書『若者を見殺しにする国』で、赤木智弘は自分のウェッブサイト(ホームページか?)で自分を主夫として養ってくれる女性を募集したそうだ。女性からは非難と批判しか浴びなかったそうで、まあそうだろうな、とすぐに思えてしまうところが一番問題のような……いや、配偶者をネットで公募するのは、どちらにしろ非常識ではあるんだけどね。
それでもまあ、尋常な婚活をしたところで、赤木のような弱者男性は、国と同様、女性も救ってはくれないことは確かなようである。
と言うと、では女性は救われると言うのか? と詰問されそうだが、そこは我が国では傾向としてはっきりした相違が認められる。
だいたい、働かなくても/働けなくても、専業主婦になる道はまだ残っている。結婚せず、生業にもつかずに「家事手伝い」で、四十代を過ぎてもずっと実家で暮らしている女性、ネットスラングで言う「こどおば」←「子ども部屋おばさん」は、「こどおじ」よりずっと多い。
この状態の者に対する家人及び世間からの風当たりは、男性のほうがずっと強いからだ。
などなどの結果、自殺者のうち男性の数は女性の二倍近くになり、男性ホームレスの割合は女性のざっと二〇倍近くにのぼるとも言われる。
いやそれは、路上生活者になった場合、女性のほうが軽く二〇倍は危険な目に合う可能性が高いだろうから、そこに社会的なケアが働くのは当然だと言える。そのこと自体は。
問題は、ここを進めて、男性対女性の構図を描き、それを強引に進める勢力があることだ。男性は加害者で女性は被害者、もっと言えば男性は悪。こう唱えるフェミニズムこそ、今日最も強力に男女差を際立たせ、両性の協力関係を妨げているのは見やすい事実である。
ここのところを突っ込んで、「弱者男性はフェミが作ったのだ」などと論じているのが兵頭新児さんなので、これ以上の考察は冒頭に紹介したものを初めとする彼の動画シリーズ「風流間唯人の女災対策的読書」をご覧下さい。
申し訳ない話ながら、私にはここでどういう解決策が有効かわかっていない、だけではなく、一般的な解決策なんてあるのかどうかもわからない。社会風潮は強力であるにしても、結局は個々の男女がどれくらい満足し、幸福になれるかが一番重要なのだから、その積み重ねで、言わば民主的に、世の中が動いていくことが一番いいのであろう。
そのためにも、何しろ、弱者男性という「問題」が、現代社会にも存在する、目をそらすのはまずい。この理解をすすめるのが先決だ、というだけで、今はお許し願うしかありません。
【ロン・ハワード監督「ヒルビリー・エレジー」(1920)は、ヴァンスの原作を、ヤク中の母親中心に編集した脚本だからそう思えるわけなんでしょうけど、彼は少年期から青年期にかけてずっと女性に支えられてきていて、それだけでもラッキーだし、おかげで弱者男性にならなくてすんだのだな、自然に納得されます。肝っ玉母さんのおばあちゃん(演:「危険な情事」の不死身の女グレン・クローズ)に、聡明なお姉さんに、優しい秀才であるインド系の恋人。お母さん(演:「魔法にかけられて」のこちら側のお姫様エイミー・アダムス)だけが困りもののようですが、この人に可愛がられたり殺されかかったりしながらJ.D.の自我が形成されていったわけでして。その後彼女が薬物を絶って立ち直り、少なくともこの映画の発表時には健在だったっていうのは救いになります。】














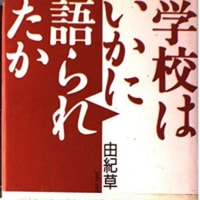
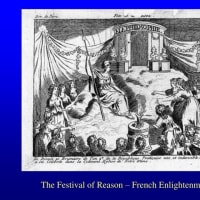










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます