7/26
古事記の世界解釈に構造主義を利用できないかと考えてみる。すでにフランソワ・マセさんの著作があり、その焼き直しでは面白くはないが、スッキリとした神話解釈を自分自身でしてみたいと思う。
そのための道具として構造主義というものをとらえなおす必要があり、正しい運用をしたいなどと、つい思ってしまう。
こう考えることはすでに負け組の発想で、勝ち組なら自分流の構造主義手法を適当に作り出し、自分流の古事記解釈をまずやるだろう。
そういう才能はないので構造主義をとりあえず知る必要があると思い、そのテキストとして「はじめての構造主義」を選んだ。その中に構造主義のルーツは遠近法で数学を媒介にして、構造主義に発展するとある。遠近法とは、見え方と在り方のことをいっているのだろうが、よくはわからない。
構造主義を考えているとシステム分析にあるオブジェクト指向という考え方に似ているようにも思える。案外、この手法を推し進めることが構造主義の近道かもしれないなどと思う。つまり、オブジェクトの存在(在り方)、オブジェクト相互の関係、オブジェクトの作り出す秩序、オブジェクト間の通信、ユーザーインタフェース(見え方)、システムテスト等を分析することにより、現実世界のある部分を射影するのである。
最新の画像[もっと見る]










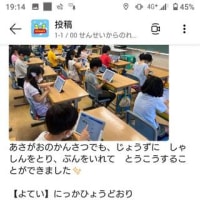
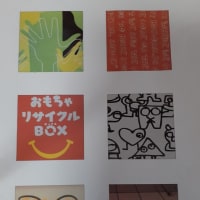








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます