一年を通して日本全国の各市町村で何らかのお祭りが必ずあります。
故郷を思うとき、まず思い出されるのが祭りではないでしょうか?
ただ世の中には、地元の人には普通で真剣なんだけれど、
外部の人から見ると摩訶不思議な世界に見えてしまう祭りがあります。
これを世の人は「奇祭」と呼びます。
奇祭とは、独特の習俗を持った、風変わりな祭りのことと解説されています。
これを、人によっては「とんまつり(トンマな祭)」
「トンデモ祭」とも呼んでいるようで、
奇祭に関する関連書物も数多く出版されています。
よく取り上げられるのは、視覚的にインパクトがある祭り
(性器をかたどった神輿を担ぐ祭りなど)がよく話題になりますが、
ほかにも火を使った祭りや裸祭り、地元の人でさえ起源を知らない祭りや、
開催日が不明な祭りなど、謎に包まれた祭りはたくさんあるようです。
これから数回に渡って奇祭を特集していきます。
その多彩さに驚くとともに、祭りは日本人の心と言われるゆえんが、
祭りの中に詰まっていることが理解できるでしょう。
特に言う必要はないと思いますが、
以下にふざけて見えようと馬鹿にしているように見えようと、
れっきとした郷土芸能であり、
日本の無形民俗文化財だということは間違いありません。
今回は、山梨県富士吉田市の吉田の火祭りの第8回目です。
吉田の火祭り(北口本宮冨士浅間神社:山梨県富士吉田市)
松明の消化
夜も更けて午後9時頃になると、松明はかなり燃え尽きて崩れています。
大松明はおよそ4時間以上燃え続けるといわれていますが
、今日では午後10時15分頃、一斉に消化命令が出され、
神社側で用意した重機やトラックを使って、
その日のうちに火の後片付けが行われます。
燃え残った松明の残骸を崩し、放水を行って完全に消化し、
灰はスコップなどでかき集めてトラックで運び出します。
最後の仕上げに路上に水を撒いて、完全に流し終わると作業終了となります。
これら後片付け作業はは消防団員によって行われ、
午後11時までに完了し、午後11時30分には交通規制が解除されます。
すすき祭り(27日)
火祭りの2日目、浅間神社へ還幸する2台の神輿を、
参詣者らがススキの玉串を持って、ついて行き、
境内の高天原をぐるぐると回ります。これをすすき祭りと呼んでいます。
御旅所発輿祭と金鳥居祭
 金鳥居
金鳥居
吉田の火祭り2日目の祭礼は、
午後2時前頃から御旅所内で行われる御旅所発輿祭から始まります。
これは2台の神輿を上吉田の氏子地域での巡行に向かうための神事です。
出席者一同は2台の神輿の前に整列し、雅楽の奏でられる中、
神職によるお祓い、献饌、玉串奉献など一連の神事の後、
世話人がセコたちに神輿担ぎ出しの掛け声をかけ出発となります。
2台の神輿は御旅所より下手にあたる、
主に上吉田の北側の氏子地域を巡回していきますが、
休憩を挟みながら同じ場所を行ったり来たり、複雑な経路を巡行していきます。
やがて午後3時30分頃から始まる金鳥居祭での神事のため、
2台の神輿は金鳥居の下に集結します。
明神神輿は金鳥居北側の山梨中央銀行前の道路上中央、
御山神輿はやや北側の金鳥居交差点の中央に安置され、
明神神輿のみ四方に忌竹が設置され注連縄で囲まれます。
神職らによる一連の神事が執り行われると再び神輿の出発となります。
御鞍石祭・神輿の還幸
金鳥居での神事を終えた2台の神輿は、
再び2手に分かれて上吉田地区氏子地区内を
複雑な経路でそれぞれ巡行していきます。
御旅所を再び経由し、浅間諏訪の両社を目指して坂を登っていきます。
途中、前日と同様に西念寺僧侶による神輿送りを受けながら、
御鞍石の聖地を目指します。
御鞍石とは諏訪神社の旧鎮座地といわれる聖地で、
諏訪神社南方の森の中に馬の鞍の形をした巨石があり、
その上に神輿を安置して神事を行います。
午後6時30分頃、神輿行列は御鞍石に到着し、
明神神輿は御鞍石の上に東向きに安置され、
御山神輿はそのかたわらの地上に南向きに置かれます。
御鞍石と明神神輿の周囲は4本の忌竹で囲われ注連縄が張られます。
宮司の手で祝詞が読み上げられると、
いよいよ浅間神社境内への最後の下向となります。
高天原・着輿祭
 揃いの法被姿の世話人
揃いの法被姿の世話人
日が暮れてすっかり暗くなった浅間神社境内では、
2台の神輿を迎え待つ多くの参詣者らで埋め尽くされていて、
参詣者らは手にススキで作った玉串を持っています。
午後7時過ぎ、最初の明神神輿が浅間神社の境内に戻ってくると、
待ち構えていた参詣者らは一斉に神輿の背後について、
手に持ったススキの玉串を高く掲げ、遅れて到着した御山神輿も合流し、
高天原の周囲を2台の神輿と参詣者らは合計7周回ります。
参詣者は浴衣姿の女性が多く、
これは婦人が神輿を担いではならないというしきたりがあるためで、
神輿を担げないなら、その代わりにせめて神輿の還幸時に
背後について行列に加わりたいという思いによるものであるといいます。
2台の神輿は高天原の周囲を7周回ると、
高天原の中央部に安置され、高天原神事が行われます。
御山神輿は再び地上に3回ドスンドスンと景気よく落とされます。
世話人14人は叫びながら駆け出し、セコらは明神神輿、
御山神輿をそれぞれ諏訪神社拝殿下まで運び安置すると、
セコらは一斉に神輿から離れ、神職らによる御霊移しの儀式が始まります。
境内の照明はすべて消灯され、闇の中で御絹垣によって神輿は隠され、
諏訪・浅間両社の御神体が取り出され再び諏訪神社本殿に戻されます。
午後7時30分過ぎ頃、諏訪神社還幸祭の神事が行われ、
その後、浅間神社での御霊移しの儀式が行われ、
御絹垣に隠されたそれは宮司の手によって大切に抱かれて
浅間神社の本殿へと動座します。
午後8時、御霊移しの神事が終了すると境内に再び電灯が灯され、
浅間神社拝殿内で本殿還幸祭が行われます。
これをもって火祭りに関わる祭礼はすべて終わり、
世話人、セコ、氏子らは解散となります。
14人の世話人は最後に社前に一拝し、
セコや多くの参詣者たちの拍手を浴びながら提灯を高く掲げ退場していく際、
すべての任務を務め上げたことの開放感、
困難な仕事をやり遂げたことの感動が胸をよぎり、
14人の世話人は感極まって涙を流します。
祭礼以外の関連行事
火祭りの祭礼が終わった翌8月28日には、
世話人、氏子総代らによって御旅所・神楽殿の解体、
神社境内での神輿の清掃、担ぎ棒の解体などが行われます。
浅間神社から出される鎮火祭の神札も、氏子総代の手で各戸に配られます。
その数は上町で1200体、中町で650体、下町・中曽根で1200体にも達します。
また、世話人たちは祭りの後に残される巨額の支払いを決済します。
祭りのために調達されたあらゆる物資、資材、
飲食物などは全てを現金決済していき、
各所への挨拶回りも並行して行っていきます。
火祭りの残務処理がすべて片付いた11月になると、
14名の世話人は静岡県の秋葉山本宮秋葉神社への秋葉詣などを行い、
12月には次年度の世話人の選出に携わります。
次年度世話人が決まり、
年が明けた小正月の道祖神祭りでの新旧世話人交代式をもって、
1年間に及ぶ世話人の任務はすべて終了する事になります。
調査活動と文化財指定
吉田の火祭りは、
富士山と地域の歴史的な結び付きや、
富士山信仰を背景とした文化遺産価値の高いものであり、
文化庁により2000年(平成12年)12月25日に
選択無形文化財として選択されました。
富士吉田市教育委員会では国および山梨県から補助金などの支援を受け、
2003年に吉田の火祭り調査委員会を組織し
「吉田の火祭り民族文化調査事業」を発足させました。
同事業は各分野の研究者から構成される調査委員3名、
調査員9名、地元調査員2名、調査補助員20名からなり、
同年から2年間をかけ、吉田の火祭りの多角的な調査考察を行いました。
これらの調査をもとにして2012年3月8日に、
山梨県内では3例目となる国の重要無形民俗文化財に指定されました。
2012年現在、富士山は世界遺産登録の暫定リストに掲載されており、
山梨県では静岡県とともに富士山の世界遺産登録の活動が行われています。
富士山の世界遺産の構成資産リストには、
北口本宮富士浅間神社や御師の家などが挙げられており、
山梨県教育委員会学術文化財課や富士吉田市関係者らは、
これら構成資産に密接に関連した吉田の火祭りの重文指定は、
富士山の世界遺産登録に向けた機運の醸成にもつながるものとしています。
【交通アクセス】
電車:富士急行線「富士山」駅下車、徒歩3分。
車 :中央自動車道「河口湖IC」から県道138号線経由で10分。
駐車場:無料約300台。
いかがでしたか。
祭りには底知れない魅力と気分を高揚させる何かがあります。
長年にわたって受け継がれてきた祭りには、
理屈では割り切れない人々の思いが詰まっているように思います。
たかが祭り、されど祭りといったところでしょうか?










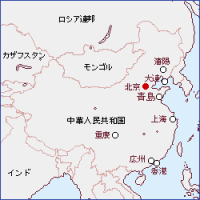
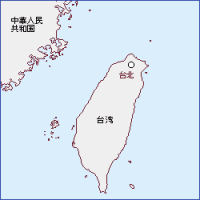
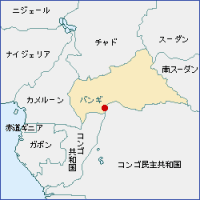
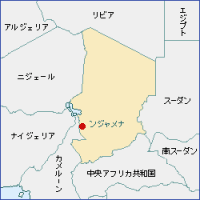
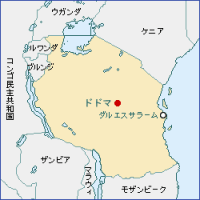
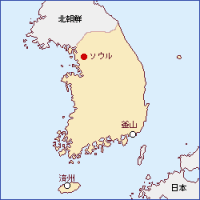

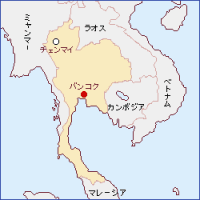
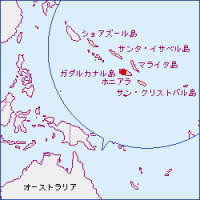
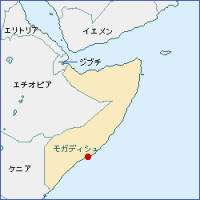
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます