15日(金)。われらが阪神タイガースの兄貴・金本知徳の連続試合出場記録が今日途切れた。今日の対中日第1戦の8回裏二死一塁で投手の代打として途中出場したが、打席中に一塁走者が盗塁失敗してイニングが終了、打席未完了のまま真弓監督が9回表に金本に代えて投手を出したため、連続出場記録が1,776試合で途絶えた。テレビで見ていたが、実にあっけない幕切れだった。これは歴代第2位の記録で、第1位は広島カープの衣笠祥雄の2215試合である。今日途切れていなければ、これを抜く可能性は限りなく高かったのではないか。なお、今日の試合は阪神が中日を5対4で下した。
彼はすでに連続試合フルイニング出場1492試合(1999年7月21日~2010年4月17日)の世界記録、連続イニング出場13,686イニング(同)を達成している。
1968年4月生まれの金本は、広島の広陵高校~東北福祉大学~広島東洋カープ(1992-2002)~阪神タイガース(2003-)という経歴の持ち主である。今年満43歳である。しかし彼に年齢は関係ない。
阪神タイガースが日本一に輝いた1985年、日本シリーズの観戦のため2度西部球場に通った。目の前で吉田監督の胴上げを見た。あの時はバース、掛布、岡田、真弓の強力打線によって日本一になった。あの頃からのタイガースファンであるが、3~4年前までは子供たちを連れて、時には神宮球場へ、時には横浜スタジアムへ、ハッピとメガホンを片手に阪神の応援に駆けつけたものだ。残念ながらまだ甲子園球場へ行ったことはない。これは私の小さな夢だ。
もともと私のラッキーナンバーは6なのだが、金本選手の背番号が6であることから、縁起をかついでメルアドの中にも6を入れている。

彼はすでに連続試合フルイニング出場1492試合(1999年7月21日~2010年4月17日)の世界記録、連続イニング出場13,686イニング(同)を達成している。
1968年4月生まれの金本は、広島の広陵高校~東北福祉大学~広島東洋カープ(1992-2002)~阪神タイガース(2003-)という経歴の持ち主である。今年満43歳である。しかし彼に年齢は関係ない。
阪神タイガースが日本一に輝いた1985年、日本シリーズの観戦のため2度西部球場に通った。目の前で吉田監督の胴上げを見た。あの時はバース、掛布、岡田、真弓の強力打線によって日本一になった。あの頃からのタイガースファンであるが、3~4年前までは子供たちを連れて、時には神宮球場へ、時には横浜スタジアムへ、ハッピとメガホンを片手に阪神の応援に駆けつけたものだ。残念ながらまだ甲子園球場へ行ったことはない。これは私の小さな夢だ。
もともと私のラッキーナンバーは6なのだが、金本選手の背番号が6であることから、縁起をかついでメルアドの中にも6を入れている。














 ので紹介します。題して「AKB48は、なぜ、売れたのか?」
ので紹介します。題して「AKB48は、なぜ、売れたのか?」 。今ヒットしているものはすべて過去だ。今の流れを読んでひらめくというよりは、周りと関係なく、自分でこれが面白いと思うものが見つけられるかどうかだ。止まっている時計は、日に2度正確な時刻を示す
。今ヒットしているものはすべて過去だ。今の流れを読んでひらめくというよりは、周りと関係なく、自分でこれが面白いと思うものが見つけられるかどうかだ。止まっている時計は、日に2度正確な時刻を示す 。ところが周りを見ながら合わせようとするとなかなか合わない。世間で流行しているものとは関係なく、自分が”これは絶対に面白い”と思い、それを全力でやり続けることが大事ではないか。今はインフラや技術が急速に進歩しているので、コンテンツを考える時にもメディアミックスをどうするかといった”器”から入りたがる人が多いが、料理
。ところが周りを見ながら合わせようとするとなかなか合わない。世間で流行しているものとは関係なく、自分が”これは絶対に面白い”と思い、それを全力でやり続けることが大事ではないか。今はインフラや技術が急速に進歩しているので、コンテンツを考える時にもメディアミックスをどうするかといった”器”から入りたがる人が多いが、料理 がおいしければ、どんな皿に盛っていても食べたいと思う。器の形に関係なく、自分は何が面白いのかというところから始めたほうがいい」
がおいしければ、どんな皿に盛っていても食べたいと思う。器の形に関係なく、自分は何が面白いのかというところから始めたほうがいい」 をエンターテインメントの世界にデビューさせて成功させるのは非常に困難でしょう。でも一辺に48人まとめてデビューさせれば「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」ではないけれど、そのうちの何人かはヒットするのではないか。少女たちを集めて歌
をエンターテインメントの世界にデビューさせて成功させるのは非常に困難でしょう。でも一辺に48人まとめてデビューさせれば「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」ではないけれど、そのうちの何人かはヒットするのではないか。少女たちを集めて歌 と踊り
と踊り を仕込んでデビューさせる。そして人気投票をやってお互いの競争意識を高めて全体のレベルアップを図る。それが彼の仕掛けでした。
を仕込んでデビューさせる。そして人気投票をやってお互いの競争意識を高めて全体のレベルアップを図る。それが彼の仕掛けでした。 」と言う人は”運がない”のではなく、”運を引き寄せる努力をしていない”から、運がやってきた時に逃してしまうのだと思います。日ごろから広くアンテナを張って情報を収集することも大事なような気がします。
」と言う人は”運がない”のではなく、”運を引き寄せる努力をしていない”から、運がやってきた時に逃してしまうのだと思います。日ごろから広くアンテナを張って情報を収集することも大事なような気がします。 が、「わかった
が、「わかった 案外簡単じゃん
案外簡単じゃん 」と言って、解説してくれた。「西暦の誕生年の下2桁と今年の満年齢を足すと下2桁が11になるということだけど、誕生年をゼロとして、つまり0歳と考えて、それに今年の満年齢を加えれば2011年になるから、だれもが11になるはずだよ」。これには納得せざるを得ない
」と言って、解説してくれた。「西暦の誕生年の下2桁と今年の満年齢を足すと下2桁が11になるということだけど、誕生年をゼロとして、つまり0歳と考えて、それに今年の満年齢を加えれば2011年になるから、だれもが11になるはずだよ」。これには納得せざるを得ない 。やむを得ず「正解
。やむを得ず「正解 11に因んだものをあげるよ
11に因んだものをあげるよ 」と言うと「やったぁ
」と言うと「やったぁ 何だって11万円くれるの
何だって11万円くれるの うれしいなぁ
うれしいなぁ 」と大幅に勘違いしている。こっちは5月11日にいたチョコ11枚でもあげればいいと思っていたのに・・・・このギャップをどうやって埋めればいいのか・・・・・・これから厳しい春闘交渉が始まりそうだ
」と大幅に勘違いしている。こっちは5月11日にいたチョコ11枚でもあげればいいと思っていたのに・・・・このギャップをどうやって埋めればいいのか・・・・・・これから厳しい春闘交渉が始まりそうだ


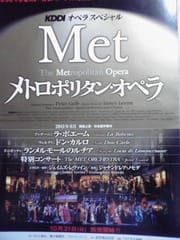
 することになり、上野駅構内でコーヒーショップを探しました。スタバもあったのですが、「もっと広いところがいいね」ということで「ハードロック・カフェ」なるお店に入りました。店内はかなり広く、壁にはエレキギターやロック歌手のゴールドディスクのレプリカらしきものや、ビートルズの写真などが飾られており、TVモニターはロック歌手の映像を流し店内いっぱいその音
することになり、上野駅構内でコーヒーショップを探しました。スタバもあったのですが、「もっと広いところがいいね」ということで「ハードロック・カフェ」なるお店に入りました。店内はかなり広く、壁にはエレキギターやロック歌手のゴールドディスクのレプリカらしきものや、ビートルズの写真などが飾られており、TVモニターはロック歌手の映像を流し店内いっぱいその音 が溢れていました。Aさんの話では横浜にも同じ店があるとのことでした。
が溢れていました。Aさんの話では横浜にも同じ店があるとのことでした。 にしよう」と意見が一致したのですが、セットはないといいます。メニューにチーズケーキがあったので、Aさんはアイス・コーヒーを私はアイス・アップルティーを選び、それぞれチーズケーキを注文しました。
にしよう」と意見が一致したのですが、セットはないといいます。メニューにチーズケーキがあったので、Aさんはアイス・コーヒーを私はアイス・アップルティーを選び、それぞれチーズケーキを注文しました。 聞いてみると普通の1.5倍
聞いてみると普通の1.5倍 あるといいます。ココナッツのツブツブが入っていてすごく美味しかったのですが、小柄で少食なAさんは完食するのに四苦八苦していました。それはそれは見ていて気の毒
あるといいます。ココナッツのツブツブが入っていてすごく美味しかったのですが、小柄で少食なAさんは完食するのに四苦八苦していました。それはそれは見ていて気の毒 なくらいでした。
なくらいでした。 。この店の従業員はどういう教育を受けているのでしょう? その上、頻繁に追加注文を聞きにくるのです。「別のお飲み物はいかがですか?」「お皿を片付けてもいいですか?」。落ち着いて話もできません。
。この店の従業員はどういう教育を受けているのでしょう? その上、頻繁に追加注文を聞きにくるのです。「別のお飲み物はいかがですか?」「お皿を片付けてもいいですか?」。落ち着いて話もできません。 ですが、私の場合はそれほどでもないので、せめてBGMはもう少し静かめな曲を選んでほしかったと思います。「だったら最初からハードロック・カフェという名前のショップに来るなよな!
ですが、私の場合はそれほどでもないので、せめてBGMはもう少し静かめな曲を選んでほしかったと思います。「だったら最初からハードロック・カフェという名前のショップに来るなよな! 」という声が聞こえてきそうですが・・・・・・あいにく私には1.5倍の寛容さがないのです。ゴメンなさい
」という声が聞こえてきそうですが・・・・・・あいにく私には1.5倍の寛容さがないのです。ゴメンなさい
 」という番組企画がありました。オーケストラがある曲の出だしの部分を演奏して、指揮者やコンマスや作曲家などのゲストが、早押しクイズ形式で曲名を当てるというものでした。
」という番組企画がありました。オーケストラがある曲の出だしの部分を演奏して、指揮者やコンマスや作曲家などのゲストが、早押しクイズ形式で曲名を当てるというものでした。 」と有頂天になりました。しかし、後で冷静になってよく考えてみると、ほとんど音楽について無知だからこそ答えられたのではないか
」と有頂天になりました。しかし、後で冷静になってよく考えてみると、ほとんど音楽について無知だからこそ答えられたのではないか と思うようになりました。というのは、回答者のような音楽のプロはあまりにも多くの曲を知っているからこそ、あれでもない、これでもない、と考え過ぎてしまい、なかなか回答できなかったのではないか。逆に知っているオペラの数が限られている素人にとっては、知っている曲が少ないだけに、すぐに曲を絞り込めたのではないか。そう思い直したのでした
と思うようになりました。というのは、回答者のような音楽のプロはあまりにも多くの曲を知っているからこそ、あれでもない、これでもない、と考え過ぎてしまい、なかなか回答できなかったのではないか。逆に知っているオペラの数が限られている素人にとっては、知っている曲が少ないだけに、すぐに曲を絞り込めたのではないか。そう思い直したのでした
 こともあって1週間がすごく長く感じた。昨日も飲んだし
こともあって1週間がすごく長く感じた。昨日も飲んだし 。
。 が目に飛び込んできたのです。この人がどういうピアニストかまったく知らないけれど”名演に違いない”と直感的に思ったのです。2枚組みCDで2,000円、迷わず買ったのですね。直感はかなりの確立で当たります。多くのCDを聴いた経験があると”CDが呼ぶ”のです。すると、そこに残して帰るわけにはいかなくなります。その結果が4000枚です
が目に飛び込んできたのです。この人がどういうピアニストかまったく知らないけれど”名演に違いない”と直感的に思ったのです。2枚組みCDで2,000円、迷わず買ったのですね。直感はかなりの確立で当たります。多くのCDを聴いた経験があると”CDが呼ぶ”のです。すると、そこに残して帰るわけにはいかなくなります。その結果が4000枚です (本当はもっと繰り返し聴かなければ、良さがわからないのですが)。しかし、2枚目の第4番と第5番はサン=サーンスらしい魅力に溢れていてとても気に入りました
(本当はもっと繰り返し聴かなければ、良さがわからないのですが)。しかし、2枚目の第4番と第5番はサン=サーンスらしい魅力に溢れていてとても気に入りました 。とくに第5番の協奏曲は「エジプト風」というタイトルが付けられており、エキゾチックな雰囲気がただよっていて、まさしく「エジプト風」なのです。耳に残るメロディー
。とくに第5番の協奏曲は「エジプト風」というタイトルが付けられており、エキゾチックな雰囲気がただよっていて、まさしく「エジプト風」なのです。耳に残るメロディー が少なくないような気がします。もっとサン=サーンスの音楽が聴かれてもいいと思います。
が少なくないような気がします。もっとサン=サーンスの音楽が聴かれてもいいと思います。



