よき治療家 生く可きを生かし 死ぬ可きを死なしむ。
殺す可きに会はず。
治るべきを治らしめ、治らざるに会はず。
常に楽々悠々 いつもすらすら動いて自づから静か也。
気張らず 努めず 焦ること無く
その息乱れること無き也。
ー野口晴哉 『治療の書』よりー
殺す可きに会はず。
治るべきを治らしめ、治らざるに会はず。
常に楽々悠々 いつもすらすら動いて自づから静か也。
気張らず 努めず 焦ること無く
その息乱れること無き也。
ー野口晴哉 『治療の書』よりー
私が独立して歩み始めた頃、1996~7年位に初めて『治療の書』を読みました。
その時、最も印象に残った部分です。
この書によって、自分がこれから立とうとしている処がどういう処なのか、教えられました。
「生く可きを生かし 死ぬ可きを死なしむ」…この一節は、今でも私の心に折に触れ浮かび上がってきます。
「整体」というと、ごく一般的な認識では「腰の痛みを改善する」「肩凝りを楽にする」というイメージを抱かれていることでしょう。
そして、そこに従事している、あるいは仕事とすべく奮闘努力している方々の、おそらくほとんどはこのような意識でいることと思います。
私の認識も、当初はそういうものでした。
人体への興味、普遍的神秘への興味…それが、初めの動機といえば動機になるでしょう。
しかし、より根源的には、何度か死にかけている経験もあってか、「生と死」、に関心があったようにも、思います。
そして、出会ったのは『身体均整法』(以下、「均整」)。
愛媛県・松山市の亀井進師範(故人)によって創始された、手技的体育療法でした。
「均整」は、日本の整体におけるひとつの極点と専門誌でも評されるほどの豊富な内容と体系を含み、人体のほぼ全領域に渡る手技が伝えられています。
最初にこの「均整」に出会えたことは、いまにしても幸運であったな、と思っています。
そこには、「均整」創立当時の最新のアメリカやヨーロッパの手技療術のエッセンスが散りばめられていましたし、同時に日本で脈々と伝えられる武術の活法的な見方や技術の一端も、書として遺されていました。
それはすなわち、「生死」を対象とする技術の一端がそこにはあったということ、です。
解剖的知識や生理学に単に立脚するのではなく、実際の生きた人間の営みからそれらを眺めるような見地に最初から立てたのは、やはり「均整」を学べたことが大きいと思います。
1996年、独立。
ほどなく、縁あって「整体」に出会います。
…そこで私は、先ず、死ぬか死なないかということを観ます。
そのために、一番早く変化する場処を見つけました。
私の一番最初に知ったのはそれなのです。
死ななければ治る。
死なない者は生きている。
生きていればよくなる。
駄目な者は死ぬ。
それなら、生きていることと死ぬことのどこに差があるだろうか。
ー『整体法の基礎』ー
そのために、一番早く変化する場処を見つけました。
私の一番最初に知ったのはそれなのです。
死ななければ治る。
死なない者は生きている。
生きていればよくなる。
駄目な者は死ぬ。
それなら、生きていることと死ぬことのどこに差があるだろうか。
ー『整体法の基礎』ー
私は、開業当初は、いわゆる難病ウンヌンという方々によく出会わせていただきました。
世間的な常識と現実はこれほどに違うのだと、自らの浅学非才を嘆く場面も、多々経験させていただきました。
いわゆる「キレイゴト」は、木っ端微塵に打ち砕かれました。
相手の方に同情したり、「してあげたい」という欲求のままに技術を施す。
こうしたことの、いかに愚かなことかを、この頃に経験として学びました。
治療するの人 相手に不幸を見ず 悲しみを見ず 病を見ず。
ただ健康なる生くる力をのみ見る也。
…病もまた同じ。
のり超える力導く者の前には 病も老いることも また無き也。
あるはただ生命の溌剌とした自然の動きあるのみ。
その故に治療する者は生命を見て病を見ず、活き活きとした働きを感じて苦しむを見ず。
苦しむを見 悲しみを見 病めるを見るは、それをのり超える力を喚び起こすこと出来ぬ為なり。
ー『治療の書』ー
ただ健康なる生くる力をのみ見る也。
…病もまた同じ。
のり超える力導く者の前には 病も老いることも また無き也。
あるはただ生命の溌剌とした自然の動きあるのみ。
その故に治療する者は生命を見て病を見ず、活き活きとした働きを感じて苦しむを見ず。
苦しむを見 悲しみを見 病めるを見るは、それをのり超える力を喚び起こすこと出来ぬ為なり。
ー『治療の書』ー
相手の事を慮る…。
慈しみの眼で見つめる…。
これらは、確かに大切なことだと思います。
けれど、「本当に」そうであるのと、「そういうつもり」であるのは、全く違う。
他者の不幸への同情のなかに、自らへの憐れみを見ていないだろうか…。
さすれば、それは一体、「誰のための」慈しみなのだろうか…。
「導く者」であろうとするのであれば、その点を常に留意すること。
それはすなわち、基本的な「嗜み」であるように、思います。
私にとっての「整体」というのは、こういう立脚点に立っています。
また、こういうものでもない限り、興味も関心も持てず早々と飽きてしまったことでしょう。
また、一般的なイメージから「お客様」的な意識で来られる方も当然おられますし、それはそれで必要なければかまわないとも思っています。
そういう方は、実際「あんまり困っていない」ことが多いですし、強いてこちらが「先生」然とするのも必要も感じませんし、そういう態度も好きではないので。
ただ、根本的に、私は「導く者」であるのであって、「召し使える者」ではありません。
相手の方の言いなりになって、それでその方のなかに何が生まれるのでしょう。
この点をはき違えないこと大切かと、思います。
「病」とは、その心にこそ潜んでいるのですから…。。。
…以上、「指南塾三期生」募集の前に、ちょっとだけ書いておこうとメモ代わりに

ここまで読んでいただき、ありがとうございました



















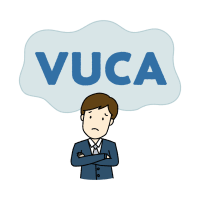
雷が鳴ると臍を隠すから♪
つまり。
何かによって何かが起こるのだけど、何かは既に存在していて、何かが起こったから、何かが現れただけで、すでに根はあったのだということですね♪
昨日、近江八幡の賀茂神社へいきました。
ご祭神、ごぞんじですか?
賀茂別雷命
火雷命
の二柱のカミサマのことをいっているのでしょうか
賀茂建角身命
賀茂玉依比賣命
と共に、主祭神として祀られていますね
いつもあろがとうございます。