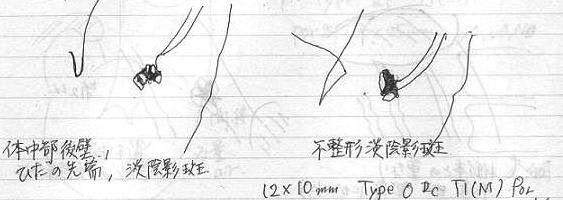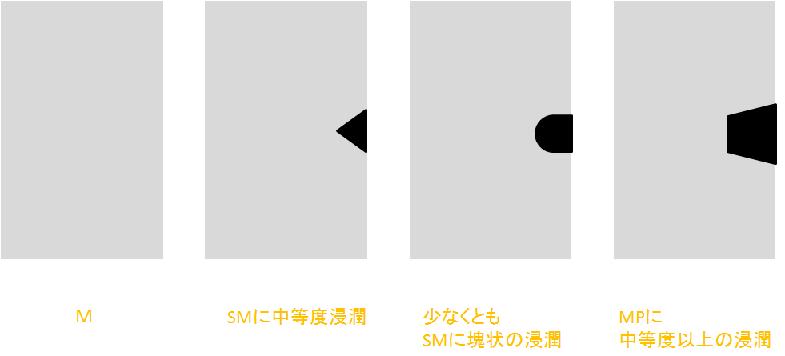こんばんは。
今日は、胃透視をしていると、耳にする用語のひとつをご紹介します。
急性胃粘膜病変、AGML(acute gastric mucosal lesion)です。
急性胃粘膜病変は、突発的な腹痛や消化管の出血などの腹部症状を伴い、内視鏡検査で、胃粘膜に異常の所見を認めるものとされています。
AGML...。胃透視の紹介後で行った内視鏡結果の診断書をみたときにも、たまに見かけます。
今日は、胃透視をしていると、耳にする用語のひとつをご紹介します。
急性胃粘膜病変、AGML(acute gastric mucosal lesion)です。
急性胃粘膜病変は、突発的な腹痛や消化管の出血などの腹部症状を伴い、内視鏡検査で、胃粘膜に異常の所見を認めるものとされています。
AGML...。胃透視の紹介後で行った内視鏡結果の診断書をみたときにも、たまに見かけます。