
間章(あいだあきら)の「時代の未明から来たるべき者へ」(82年)、「非時と廃墟、そして鏡」(88年)は何れもその死後、発刊されたものであり、私は愛読していた。彼の著作は長尺で何れも内面発露的な散文調のエッセーも交えた自身の音楽哲学を展開するもので、対象批評でありながらその本質は自己表現にあった。従って音楽作品や演奏家に対し過度な思い込みを反映しすぎるきらいはあるが、それでも私は間章の文体が好きであった。己の観念、その肥大する想念に辟易する場面に遭遇してもどこか、美を感じさせる力が文章にあり、知らず知らずにうちに惹き込まれてゆく。とどのつまり間章の音楽批評とは壮大な‘詩’であっただろう。その一方で、情報として機能するかなり客観的な対象批評もあり、そのバランスの上に成立する事でエンターティメント性も十分、存在した。音楽の聴きこみ方が半端ではないので、誰もが見落としがちな観点も数多く提示し、それは私が音楽を聴くにあたっての参考にもなり得た。そんな間章とは、象徴主義的詩人のようでありながら、客観批評を行う職業的評論家でもある事で音楽を媒体とした著述家という意味では稀有の存在であったと言えるかもしれない。
彼は評論家でありながら数々のイベントを主宰し、即興音楽を中心とするシーンを国内に根付かせるべく奔走した活動家でもあった。阿部薫の盟友であり、その阿部や高柳昌行、吉沢元治等と‘ジャズを契機とする闘争集団’(年譜による)(すごい‘集団’だ)「JRJE」(日本リアルジャズ集団)を組織している。また、フリージャズに見切りをつけた後(「ジャズの死滅へ向けて」というエッセーがあった)、デレク・ベイリー、スティーブ・レイシー、ミルフォード・グレイブスの招聘を赤字を出しながら断行、数々のレコーディングも行っている。その強い意志は自らの観念過剰な言語表現を補うかのような活動的な現場主義の最たるものと映る。いや彼にすれば、執筆活動やイベントのプロデュース、アルバム制作などの境界線は存在せず、それらは全て彼の‘闘争’として収斂するものであっただろう。
‘ことはそんなに甘くはない。全体に向かおうとする時、個は常に破片であり、廃墟であり、敵は全体として立ち現われる。直系的論理も運動もことごとく敵を補完するだけであり、沈黙も饒舌も敵を許すだけである。要は敵を内に飼いながら、毒を飲みながら自らの感性のヒエラルキア、理性の整合性を粉砕しつつ、複数の不可視の戦線を創出させることなのだ。ジャズにおいてはジャズミュージシャンの特権性と特権構造をうばいつつ、本来的に快楽主義者でしかないミュージシャンの存在性を照射してゆく事こそ問われなければならない’
「フリージャズ黙示録 解体と非連続の系譜」
コルトレーンやフリージャズが精神レベルで語られた当時、間章はその観念的な理論を代表する批評家であり、いや、むしろ音楽の観念派からも敬遠されるほどの自己への厳しさ、徹底性を持っていたと思う。そんな間章とはさしずめ‘怨念派’であっただろうか。彼はジャズという形態に大げさに言えば近代以降の人間存在が如何に個として屹立できるかという可能性を見出した。詩人としてのスタートから、やがて60年代後期という‘政治の季節’が嫌が負うにも間章に対し個と社会といったテーマを植え付けるに至り、‘外部に対する対峙’という基本姿勢を生んでいったのだろうか。ジャズに見出したアイデンティティー。それは管理と秩序、集団本能という現在の矮小化された存在である人間の問い直し、そこからの反攻の拠点を作る為の賭けであったようだ。従って、アナーキーであることを標榜しながらも快楽主義に陥ることを許容せず、そこの境界に対する意識を研ぎ澄ませ、自己にも他者にもそれを求めてしまう。
私は「ロックマガジン」誌で連載されていた「アナーキズム遊星群」という特異な論評が今でも印象に残っているが、それは氏の生前末期のものであったのだ。間章は1978年、32才で亡くなっている。その3ヶ月前に他界した盟友、阿部薫の後を急いで追ったような、その早い死であった。その阿部薫の死に際しては「私は何度でも何度でも阿部を地獄に突き落とす」と記している。この文章の凄味は如何ばかりか。たった3カ月後には自らをもその地獄
に突き落としたのだから。
*********
その故間章が‘愚にもつかぬ催しもの’と言っていたイベントが昔、あった。
70年代後半から確か90年頃まで毎年行われ、日本のジャズブームに一役、買っていたライブ・アンダー・ザ・スカイ(live under the sky)というジャズの野外イベントがそれだ。
‘愚にもつかぬ催しもの’とはひどい言い方だが間章が言うには何にも不思議ではない。
間章にすれば‘青空の下でジャズの祭典を’等というレイドバックした企画など一喝すべきものでしかないであろう。しかも大資本と結び、ジャズを催すなどというあからさまな商業主義自体、犯罪的とみなしていたかも知れない。これはニューポート・ジャズフェスティバルに対しマックス・ローチやチャールズ・ミンガスがその商業主義的なるを理由に批判を加えていた事に通じるであろうか。
商業主義か否かという問題以前に間章にとってジャズとは娯楽ではなく形而上学であり、存在の問いから発せられる一つの認識の手段であった。従ってライブ・アンダー・ザ・スカイというイベントに賛同する要素など、かけらもないのは当然の事なのである。
それはそうとしてライブ・アンダー・ザ・スカイを私は一回も見に行かなかった。
間章が言うように‘愚にもつかぬ催しもの’と思っていたからか。いや、そうでは全然、ない。私はそこまで偏屈ではない。しかしその理由が何故だか今、思い出せない。私はそれを毎年、テレビのダイジェスト版で観るのが常であった。結局、ただの一度も見に行かなかったというのは自分でも不思議だ。多分、何となく予定が合わなかったり、気分が乗らなかったりした為だろう。私はそれを今、後悔している。
特に87年のライブ・アンダー・ザ・スカイはやはり、行っておくべきであった。
マイルス・デイビス、SXL(サムルノリ、ビル・ラズウェル、シャンカール、ロナル・ドシャノン・ジャクソン、アイーブ・エンディング)ウェイン・ショーター・グループ、ジャック・ディジョネット・スペシャルエディション、ワールド・サクソホン・クァルテット(ジュリアス・ヘンフィル、デビッド・マレイ、オリバー・レイク、ハメット・ブルーイット)、スティーブ・ガッドーガッドギャング、渡辺香津美MOBOといった面々がこの年の出演者であった。凄い顔ぶれだ。
私の好みではガッドギャングと渡辺香津美以外は全て好きなアーティストであり、マイルスは単独のコンサートで観たからいいが、ジャック・ディジョネットスペシャル・エディションを見逃した事は残念であった。
そして私は後日『tribute to john coltrane』というタイトルでCD化された今回のフェスでの特別プログラム‘ジョン・コルトレーンに捧げる’と銘打たれたウェイン・ショーター(ss)、デイブ・リーブマン(ss)、リッチー・バイラーク(p)、エディ・ゴメス(b)、ジャック・ディジョネット(ds)による即席の企画グループの演奏を聴き、これを逃した事も更に悔やんだのである。
************
『tribute to john coltrane』(87)はその‘企画バンド’による演奏の記録である。
ジョン・コルトレーンの‘おたく’、デイブ・リーブマンが濁った音色でソプラノをぐひゃぐひゃと吹きまくる「Mr,P.C」にまず圧倒される。さすがコルトレーン研究の権威を自認するリーブマンの疑似コルトレーンプレイは凄い。そのアドリブ展開はソウルフルにて、ノイジー、その逸脱ぶりは崇拝する故人の継承をアピールするが如きの演奏であろう。
しかしそんなリーブマンのプレイに対抗するのがウェイン・ショーターだ。ショーターは60年代、コルトレーンと互いに影響し合い、ソロアルバムではリズムセクションにエルビン・ジョーンズ、ジミー・ギャリソンを起用するなど、コルトレーンの潜在的な好敵手として同時代を生きたプレイヤーだ。リーブマンに負ける訳にはいかない。リーブマンの先制攻撃のようなソロに対しフリーキーさで勝負する愚を避け、メロディーの解体、アドリブによるアンサンブルの切り崩しと再構築、バンドサウンド全体の構成に意識が向かっている。
表面的な派手さでリーブマンに分があるように見られるが、その深みに於いてショーターが勝るのは当然か。何度も聴けばそう確信する。
「impressions」ではディジョネットのパワーが爆発する。自身のリーダーグループ、スペシャルエディションでは寧ろ独特の空間デザインとも言えるようなドラムによる構築感を持ち味とするが、ここではストレートな突進ぶりを見せ、またもやリーブマンの猛烈なソロを誘発する。そんな周りの熱狂にショーターも時に我を忘れてついつい、つき合ってしまう。ブヒーー!と音を濁らせブロウするショーターはその時、コルトレーンを意識しただろうか。
確かに熱い演奏ではある。
しかしここでの熱さとは‘スリリングではあるが、ある種、予定的なジャズの熱さ、そのレベル以上でも以下でもないという事が自明の了解事項のように露呈してしまっている事も事実だ。企画自体がコルトレーンをタイトルにするハンディもあるだろう。この現代、トップレベルの演奏者の集結をもってしても、コルトレーンへの接近は図れない。ジャズの熱さ以上のサムシングを得られることはない。こうなると通常のジャズ演奏の快楽とは異なるコルトレーン・ミュージックの異常とも言える高揚感覚の正体が逆に知りたくなってくる。コルトレーンの‘突出した’熱さは、それを比較の対象とするには余りにも他の音楽、特に現在のものとはかけ離れた過去のものである事を私達は強く認識するだろう。
勿論、時代がまず違う。60年代とはしばしば喧伝される社会の変革と精神の解放という時代であったと同時に希望の時代であり、‘挫折や敗北以前’の季節とも言えるプレ・ニヒリズムの時代だったと私は思っている。そんな中、ポピュラーミュージックやジャズも社会性や精神性と当然ながらリンクする捉え方をされた。そしてコルトレーンは必然的にそういった捉え方をされる代表格にもなった。‘本人のあずかり知らぬところで’とも付け加えておかねばならないが。結局、‘革命’が大文字であった60年代、‘ジャズ’も大文字だった。
60年代とはイメージするにジャズは大文字のカルチャーだった。それは同じく大文字の
キーワードであった‘革命’と等しく、プレ・ポストモダンに於ける最後の‘夢見られる’時代枠に生じた‘真剣なる’サブカルチャーとして受け止められていたのだろう。挫折前、敗北以前
という時代の空気を私は十分には想像できないが、おそらくはその渦中に様々な‘可能性’への賭けとも言える媒体があり、ジャズもあったということだ。政治という具体ではなくとも、漠然とした変化、改革に人は人生の個的な夢をオーバーラップさせる一種の慣習にも近いメンタリティーが存在した。そういったパターンがあることが音楽によりオーラを持たせるムードを作っていた。だから音楽にも真剣に注意が向き、自ずと演奏者も含む‘ジャズ’なる大きなシーンを生成した。真剣に対峙するという土俵が創出され、それは時代特有のスタイルにもなっていたのではないか。コルトレーンはそうゆう‘聴かれ方’をされた。本人の意向とは異なるにしてもある幸福な相互作用、共振が成立した。それは共犯といってもいいのかもしれない。
ただ、ジャズの‘在り方’とか‘聴き方’などという概念そのものが、いわばコルトレーンの音楽が自身のあずかり知らぬところで単独に生起したような波動であり、そこに基準を置くことの無理が現在の素晴らしい数多のジャズまでも比較論の土俵に無理に押し上げられてしまっている感も拭えない。その意味でもジョン・コルトレーンの特異な感動の質、特別性とはいったい、何であろうかと感嘆の心情で私たちは夢想しないわけにはいかないのだ。
ジョン・コルトレーンを聴くと私は嫌が負うにも、そこに一つの‘部屋’を感じる。それはいわば代替え不可能な特別な部屋であるが、私ならそれを60年代という季節が建造せしめた部屋とは単純に言えない。なぜならそれは正しくコルトレーンだけの部屋であるから。
孤高の批評家でオルガナイザー、間章が求めた高次元な質実はジャズの在り方をすべからく‘闘い’というキーワードの元、厳しく、その基準を峻別されるものだった。その堅苦しさは恐らくは彼自身にある信条を課し、ジャズ演奏家に対する許容と容赦ない批判を循環させる文字通りの運動体としての機能を目論んだものとなる。そんな‘偏狭’な音楽への接し方を崩さないのもコルトレーンの影響を中心とするあの時代の精神を純粋培養する以外に生き方を知らぬことによるものなのかも知れない。もうちょっと気楽になれなかったのか等と余計な事をつい、考えてしまうのは後の私達、ノンポリ世代の概観か。
間章が70年代後期に亡くなったのはある意味、幸福だったのではないか。彼はすでに状況に絶望していた。60―70年代という今からみれば‘闘争的には’豊饒の時代を批判精神たっぷりに生き、かれにとっては唾棄すべき様々な現実を表現者として攻撃的に生きた。間章がもし、80年代を眺めていればどう思うだろう。考えてみるだけで、ある意味、恐ろしい。70年代さえ彼にとっては‘敗北と絶望の季節’だったのだから。日本型資本主義の完成と管理社会の整備、カウンターカルチャーの衰退と文化的に‘白痴化’の進行する80―90年代も尚、あのペースで闘い続ける事ができたであろうか。彼が最後に認めたアーティスト、デレクベイリー、スティーブレイシー(彼等はそれぞれが間章を追悼する作品を残している)と伴走したであろう間章はもしかしたらその過程で、彼等をもやはり葬り去って、縁を切り、孤独の旅を行ったかも知れない。彼ならそんな孤独さえ恐れなかったであろう。
‘北’、‘寒さ’というキーワードを間章は愛読するフェルディナンド・セリーヌから幾度となく援用し、絶えず、カオスに引き寄せられる志向を持つ立場だけがジャズをめぐる可能性の糸口と信じ、いつだって祝祭空間の後の静けさこそを連続的に継続する意義を見出していたのかもしれない。
そんな間章はジャズの表面的な熱狂など、後退的にしか捉えていなかったし、それどころかコミュニティ志向の気配を感じられるものを最も保守的なものと否定していた。彼は何よりも個の極点に立とうしていた。‘感性のアナーキズム’‘極北’といったキーワードが彼を顕わしていた。
しかし改めて彼の著作を読み、思う事は、絶望しながらもニヒリズムに陥らない、その未来展望的な精神の在処であろう。つまり延々と暗黒を書き記すが如き間章の文章、著作は、私の感ずる所、むしろ‘希望の書’であった。しかし彼は希望に至るべく過程の深化を徹底実践する事を選択した。その営為に於いて間章は必然的に迷宮に入り込み、そこから簡単には出ない事を手段とし、またそうしなければ本当の勝利、自由の獲得は果たせない事に厳しく自覚的であったのだろう。従って彼の文章は重苦しいのは確かだがそれでも尚、‘自由’へのアプローチに執着する肯定性の拠点がぎりぎりの崖っぷちで用意されている事は見逃せない。
‘本質的なものはいつも好き嫌いを超えたところに在った。それは選択を許さぬ情け容赦のないもの、ありのままとして在った。アイデンティティーの問題を我々はある意味で決してまのがれ得ないとしても、私には真に発展的にして開かれた人間の自由の可能性はアイデンティティーから自由に離れてアイデンティティーへのこだわりを無くす事から、そして唯一のではなくて様々なアイデンティティーをしなやかに受け入れてゆく事からしか始まらないように思う。私はこの事によって初めて自己破滅をそして順応主義、自己のスタイルへの風化を超えてゆくひとつの認識の地平へ向うができ、行為そのものとしての演奏が真に開放的なものとなり得る地平へ向う事が出来ると思っている’
「ジャズの死滅へ向けて 最終稿」
人一倍、許容性が狭く、誇り高き偏屈者とも言うべき著者がそれでも自らを開かれた存在として機能させるべく苦闘する姿勢が窺える。こういった言説は間章にとって一種の宣言にも似た自己への確認作業である。マニフェストを連発する事で自己顕示欲を満たしながら、返す刀で周囲へ切り込むメッセージとする。理論武装でありながら、象徴的な詩歌のようでもある。客観的には自家中毒なのかもしれないが、読む者に何かひっかかりを常に残すという意味で、やはり、どこか求道的なスタンスを認めざるをえない表現としてのレベルを感じさせる。このスタンスはやはりコルトレーンの求道性にオーバーラップするだろうか 。
‘コルトレーンの一生はまさに巨大な闘いであった。そのかけがいのなさは特に晩年のコードとの対決にあった。確かにコードを無視し、飛び越える事はいかようにも可能だったろうし、多くの当時のプレイヤーはその壁を飛び越す事からフリージャズへ突入して行った。しかしコルトレーンの方法と闘いは他の誰とも違っていた。それはインコードにとどまるのでもアウトコードへ進入するのでもなく、コード的世界と非コード的世界のぎりぎり極限的な領海へ向う事によってコード的世界と非コード的世界を貫き、そこに共に道を開きコードを内側から開放しようという闘いに全てを賭けたのであった。この事の意味はことの他大きい。と言うのはいわばアウトコードから<フリー>で飛び出した者はその事によって大きな自由を得る事はあっても自由の根拠を手にする事はできないし、それは<フリー>内においての可能性を見出す事はできても、その事と<非フリー>の間に具体的な道や可能性を用意できないからなのだ。コルトレーンはこの事に気づいていた。何故、コードの極限までゆく事が必要だったのか。それは根拠のない<フリー>はいつまでも<フリー>ではあり得ないという事につきるだろう。彼はどこまでもこのいわば不可能性に照らされた闘いに全てを捧げた。’
「‘最後’のコルトレーンと惑星空間」
不可能性に賭ける表現とは、もはや手法などではなく、その者の思想、生き様であるだろう。その意味ではコルトレーンと間章は共通の資質を持つ者同士であっただろうか。コルトレーンの音楽を聴くと、確かにそこにうっすらと存在する壁の存在を感じ取る事ができる。軽くポンとは突き破る事のできない限界点、‘不可能性’が背後にあり、その枠の中で音楽絵巻が展開されている。しかし思うのだがその‘不可能性’こそが音楽の快楽要素になっているのも事実だ。色濃いブルースとは何と苦悩に満ちているのだろう。
‘コルトレーンの一生はまさに巨大な闘いであった。そのかけがいのなさは特に晩年のコードとの対決にあった。
間章がこう書くとき、私はインコードとアウトコードのせめぎ合いを意識し安易な逸脱に至らないとするコルトレーンの意思が薬物を絶ってからのいわば、心身の健康を起点とする所から嫌が負うにも直面する命題として立ち現れていた事をイメージする。つまり、単純な話、酩酊や陶酔の状態からは‘せめぎ合い’の意識は生まれない。そこからはストレートなトリップアウトしか生じ得ないからだ。
コルトレーンは壁の存在、‘不可能性’に対し、真に覚醒的、自覚的であった。即興演奏における‘自由’という命題が決してコードアウトやリズムアウトに拠るものではない事に対し絶望し、‘何をすべきか’という孤独な意識に苛まれていたのではないか。それを探しあてる過程の生みの苦しみのように、コードをアウトしたり、インに戻る往復が目的主義によるものではなく、出口を見つける、或いは‘何をもって良しとするか’という至上命題の回答を矢継ぎ早に回答し続けている姿をイメージする。だから単純にアウトな演奏してそのまま流れていくことにはならない、独特の構成感を生んでいるのだと思われる。さらにコルトレーンがフリーキーな演奏の中に瞬間的に‘歌’を歌い、それを差し込むように表現したとき、そのメロディーの破片がとても輝くことをリスナーは知っている。個人的に言えば、私はその‘歌’の瞬間を待っていると言っていい。そんな聴き方を知らず知らずのうち私はしていたと思う。そしてその‘歌’は素晴らしく賛歌的なのだ。
コルトレーンの伝播の理由もそこにあると思っている。単に重く暗いだけならジョン・コルトレーンの音楽がこれほど多くの人々に聴かれる筈がないのは自明の事だ。
***********
87年のlive under the skyにおいて企画された『tribute to john coltrane』
私はこの思いつきのような企画が単独のビデオ作品となった事も知り、見てみた。冒頭でショーターがコルトレーンの思い出を語る。「理論や法則ではなく、スピリットが最も重要なんだ。という事をいつも言われた」と回想するショーター。
ここで熱い演奏を繰り広げたリーブマン、ショーター、ディジョネット等はそれぞれがコルトレーンへの憧憬を有しながら、その高みには決して近つき得ない壁がある事、その相違を認識していた筈だ。熱くスリリングな演奏であるが故に逆にコルトレーンとの距離が浮き彫りになっているという感想は酷であろうか。いや、しかし補足するなら、ここでのリーブマン達は強烈なプレイをしながら、その限界を肌で感じ、狭まる事のない距離に唖然としていたであろう。それを充分、認識しているが故、ここでの音楽世界はある意味、輝いているのも事実だ。‘超えられない壁’を恐らく各人が意識した上でここでの演奏は展開されている。
ディジョネットの突進ぶりはそれを物語っている。彼はこの企画の始まった僅かの時間で瞬間的にその‘壁’を感知したであろう。それが演奏に顕われた。フリーに突入しようが、固有のリズムデザインをアーティスティックに展開しようが、コルトレーンの音楽性の前では色褪せてしまう。どのような技法を採るに関わらず、演奏する態度、その精神性、間章言うところの‘不可能性に照らされた闘い’において何と大きな落差が在ることだろう。そんな想いはディジョネットほどの覚醒したプロなら認識しない筈はあるまい。
しかし一方でここにはリッチー・バイラーク、エディ・ゴメスと言う‘無自覚’な演奏家も競演していた。「naima」でのバイラークの原曲とは大きく異なるリズミカルでアッパーなピアノや「india」の冒頭で繰り広げられるエディ・ゴメスのベースソロもあのジミー・ギャリソンがやるようなダークな世界、重く響くソウルではなく、タッピングでビートを刻むテクニカルなものでこの両者の無頓着な曲芸が益々、コルトレーンとの距離を拡げてしまう結果となっている。
しかし『tribute to john coltrane』にはコルトレーンとの距離を意識する、しないにせよ、楽曲を自分(の限界に)引き寄せて演奏する潔さという意味での肯定的な評価はあると思う。ディジョネットの‘忘我、’ショーターの‘内向性’、リーブマンの‘疑似求道’、バイラーク、ゴメスの‘勘違い’等が一体化した不思議な熱体物のような音楽。個人的には結構、楽しめるものだ。
それでもやはり間章がこれを見たなら、‘愚にもつかぬ催しもの’と両断したであろう事だけは間違いないであろうが。
追記
デイブ・リーブマンによるコルトレーン探求の最大の成果たるアルバムは『john coltrane’s meditations / david liebman ensemble』(96)であろう。コルトレーンの問題作『meditations』(65)をギター、トランペット、オーボエ、キーボード、パーカッションを加えた編成によるリーブマングループが大胆に構築する。リーブマンはテナーに専念し、コルトレーンのボイシングを探るたたかいを展開するが、ここでの演奏は最早、コルトレーンの楽曲を聴く者に忘れさせ、リーブマン達の演奏そのもののレベルのみで聴かせる力が感じられるものだ。その意味でこの作品はコルトレーンを意識せずとも客観的に楽しめる秀作となっている。『meditations』という後期のアヴァンギャルド作品を取り上げる事で通常のグルーブ感覚に拘束される不自由さから逃れ得た結果がこのような自発性溢れる作品となったのか。いやむしろ重要なのはリーブマンのコルトレーン探求が後期コルトレーンの精神性に及ぶにつれ、楽曲解釈のキーを‘理解’からいわば‘愛情’へと回帰した事でその魂とコンセプトにより接近し得たのではないか。
力作となった『john coltrane’s meditations / david liebman ensemble』
強いて言えば本作の欠点は各演奏者の高度な演奏レベルの均質性である。オリジナル『meditations』はエルビン・ジョーンズ、マッコイ・タイナー最後の録音であり、それまでの黄金期を担った両者と彼らとは全く異質な演奏者、ファラオ・サンダース、ラシッド・アリが競演したアルバムであった。コルトレーンによって無理矢理一緒になった四人の意識のずれ。その相違を放置したまま全体が一点に向う危険水位での緊張感とコルトレーンの目指す理想が未完成な領域をそのまま残しながら最終形として作品となった音楽であった。直後に起こるエルビンとマッコイの脱退を予想させるような全体の音の不安定感が逆にスリルある作品となっていた。意図した事ではないが、メンバーの意識のずれが結果的に演奏のエネルギーの好作用したのが『meditations』であった。
これに比べjohn coltrane’s meditations / david liebman ensemble』は各演奏者の均質な演奏レベルによる完成度こそが魅力となっている。リーブマンのリーダーシップとコンセプトの全員への浸透が図られ、その結果、オリジナルでコルトレーンがやろうとした‘理想型’を実現させてくれたのであろうが、その完璧さがある意味でオリジナルを超え、しかしそれ故のアカデミズム一歩手前の‘ジャズの成果主義’をも垣間見せる結果にも繋がっていると言えようか。コルトレーンミュージックに充満したあの‘不安感’‘未達成感’それ故の味わい深さたる要素が結果的に抜け落ちたと感じられるのも事実だ。
でもそれは仕方がない。それは音楽の方法論や技術の問題ではなく、コルトレーンの人間性、性格に由来する内的質実の違いの問題であるのだから。本来的に‘深刻’なコルトレーンを敢えてリーブマンが‘深刻ぶる’ことで接近し得てもそれに何の意味があろうか。
初出「満月に聴く音楽」(2006)収録から改訂
2018年5月











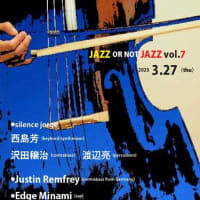
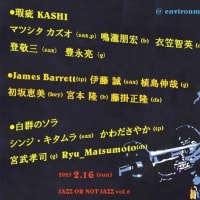












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます