
無惨なり。バウハウス。
再結成の新作にてラストアルバムだという。何のために。よく分からない。これを作るだけの為に25年振りにスタジオに集まった四人。しかしその内容たるや惨憺たるもの。曲も演奏も全く最低。無惨だ。あまりにも。バウハウスは過去の栄光を自ら汚す過ちを犯してしまった。
嘗て、私の暗い青春の1ページを占めたバウハウス。全てのアルバムを愛していた。来日は1983年。その衝撃的なライブは同時代に来日した多くのニューウェーブバンドの中で最も強い印象を私に残している。その年、解散。最高の音楽性とパフォーマンスを誇る偉大なロックバンド、それがバウハウスだった。だからこそ私は、このバンドの正当な再評価、リバイバルを期待してきた。事ある毎に「バウハウスはすごかった」と誰彼構わず伝導したりした。それほど無理解が渦巻いていた。ワンアンドオンリーな個性、類似するバンドがいない為か。フォロワーなき絶対的オリジナリティがバウハウスを巡るあらゆる無理解の源だっただろう。‘ビジュアル系の元祖である’等という捏造、曲解を目にした時、込み上げる情けなさに私は首を横に振った。あとゴスがどうだとか。何なんだ、ゴスとは。
シアトリカルなステージや劇的イメージ以前にバウハウスは確実にミュージシャンだった。
練られた楽曲。物語性豊かなアレンジとアルバム全体の構成美。緊張感溢れる演奏。どれもが一流であり、その表現ビジョンの深さ、一貫性は本物だった。それはヨーロッパの暗黒、神秘主義の表現だったが、楽曲に潜在した欧州歌曲のエッセンスや汎伝統性は子供だましのゴシック等とは次元を異にするものだったのだ。
アルバム『burning from the inside』(83)のナンバー「antonin artaud」を昔からずっと、未だに「アントニンアルタウド」と訳している無知がバウハウスを巡る無理解を象徴している。シュルレアリスムの詩人、演劇家であるアントナンアルトーに関心が向かったバウハウス。アルトーにある狂気や背徳性、神性の表現をバウハウスは獲得しようとした。そんな高次の表現意欲が音楽性に結実したのが各々のアルバムだったのだ。デビッドボウイが嘗てリンゼイケンプに師事し、マイムを学んだのもアントナンアルトーへの関心が契機だったようだ。しかし私はバウハウスの方がよりアルトー的世界を音楽で具現化したと思っている。
デビューシングル「ベラ・ルゴシ・デッド」(79)のイメージフィルムにドイツ表現主義映画「カリガリ博士」が使われていた事を覚えている。イメージを追求する事はグループの重要な要素であっただろう。だが、バウハウスはソングライティングの充実度により、それらを単なるイメージ背景とせず、むしろ内在化させた。そこに深みが生まれ、安っぽさを回避できた。バウハウスの表現ビジョンとはドイツ表現主義やシュルレアリスムに見られる‘内面性の発露’であったのだろう。バウハウスは現在の人間の交錯する魂を原形化したアートを表したかったのだ。幻想やホラー的要素は表現の過程に於いて音楽の外面に付着した、あくまでも副産物だったと感じる。そんな事を強く思い起こさせるのはグループの圧倒的な演奏力が印象深い為だ。それは極めて‘現実的’であった。
その意味で重要なのはアルバムの合間にリリースされたカバーシングル「telegram sam」、「ziggy stardust / third uncle」だった。この3曲の演奏の凄まじさはTレックス、ボウイ、イーノの原曲をパンク世代に再認識させ、それらの持つ楽曲的パワーを知らしめた。そしてバウハウスは自らをそれらに連なる者としてのリアルロックを宣言したのだと思う。従って特筆すべきは表現の演劇性の中に存在した確かな‘ロックビート’であった筈だ。それは内面的質実の深化故に出来上がったバウハウスの堅固な支柱であったと思う。図らずもそれは内面性が欠如し、ビジュアルイメージのみに振り回される数多のバンドがビート感が皆無であった事と好対照を示していた。
内面性の音象化(ビジュアル化)がビートを基盤に成される時、バウハウスの音楽はエンターティメント性を伴う最高のアート作品となった。永遠に聴く事のできる作品性をバウハウスのアルバムは確かに有している。それはクイーン(77年くらいまでの)こそが最もバウハウスに類似するバンドであるという私の確信につながるのだ。両者はいわばメジャー/マイナーという裏表の関係にも似た相似性を示していると感じる。
思わぬ過去回顧の契機となったBAUHAUSの『GO AWAY WHITE』。
凡庸な楽曲と張りのない演奏。私は失望した。作るべきではなかったと思う。その醜態は昨今の再結成ブームの一環のようだ。かつてオールドウェイブの延命を徹底的に批判していたニューウェーブ期のアーティスト達が今、同じ蹉跌を踏む。「‘ヒーローズ’を出した時点で死ねば良かったんだ」と嘗てボウイを批判したロバートスミス(キュアー)が今では自らが、醜悪なリバイバル(サバイバル)を演じる昨今の状況を‘歴史は繰り返す’と看過しても良いのか。周囲の批判が極めて少ないようだ。だから余計、始末に負えない。
衰退した音楽産業という現実の前に、アーティストも取り巻きも音楽ライターも歓迎の意を表す共犯関係にあるのだろう。何故、ちゃんと葬ってやらないのか。私達にできる事は彼等を限りなく無視し、表現に接すれば冷静に批判する事で過去の偉業と明確に区別する事だけだろう。それをいたずらに持ち上げるから皆、成仏できないのである。合掌。
2008.5.15



















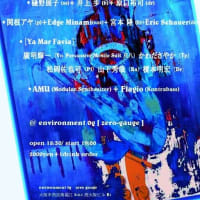






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます