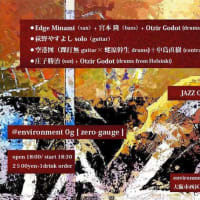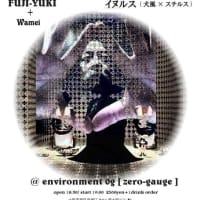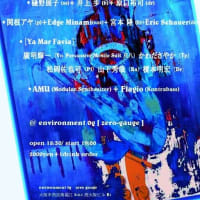70年代には<日本ロック>に関する議論がよくあったと聞く。外来文化であるロックを日本でいかに消化し、オリオジナルに昇華させてゆくか。私が中学の頃も内田裕也と細野晴臣の日本語ロックに関する対談を雑誌で読んだ。それは日本語という非ロックな言語をロックに乗せる正否に関するものだったと記憶する。今ではそんな議論さえない。そんな事にこだわっても仕方ないという空気。或いはそのテーマは既に乗り越えたという勘違い意識の蔓延。またはそんな問題意識そのものが存在しない年代に既に入っているんだろう。しかしその果てに今では奇形なロックもどきの集合的厚みだけが、日本のロックシーン(とも呼びたくはないが)を覆っている。ロックが本来、外来のものであるという自覚すべき基準が欠落している故の脆弱さばかりが目立つ。進みすぎた消費社会に於ける文化の幼稚的土壌のみが商業として成立し得るという悲観的状態は<ロックとは先鋭意識なり>という嘗ての不文律を無効化し、ロックはもはや、時代の一記号として相対化される。
日本語がロックになじまないのは、リズム感の不一致ではなく、言葉の思考性や言語表現の精度を目指す時の音楽上のフォーマットでの違和感だった。松本隆(はっぴいえんど)はそれをクリアしたのだが、フォークロック的フォーマットに限られた中でのサウンドと言葉の融合であった。一方、欧米ロックサウンドへリズム感覚で追いついても、日本語を英語もどきの発声で歌う事でロックへ疑似同化する事しか大多数のものはできていない。卑しい意識と敗残がある。<それらしく見せる>というコンプレックスは独自なロック言語を当然、生み出さず、行き過ぎた商売の泥沼に沈むだけだ。
私にとっての藤圭子ショックはパンクに匹敵するインパクトであり、それはロック的としか言いようのない内面的軋みを昇華させた表現世界だった。いや、これ以上のロックがどこにあると言うのか。藤圭子をきっかけとしてロック的感性で聴ける歌謡曲探求が始まる。結果、ちあきなおみを経て、美空ひばりに到達。頂点を知った。CDを手探りで色々買って聴いていたが、『コロムビア至宝シリーズ 美空ひばり 民謡お国めぐり』を聴いたときの衝撃は大きかった。1962年に発表されたものが2006年になってCD化されたものだが、リズムと言葉の洪水に圧倒され、しかも感情を抑えるミニマムな次元から最大級のこぶしまで爆発させる。凄すぎると思った。内面もビートも総体的に高域に表現される。その力が圧倒的で他に匹敵すべきジャンルすら見つけられない。
日本語をどうやってロックに乗せるのか等というまごまごした話はもはや美空ひばりを聴けば無効である事に気づく。1962年の時点で美空ひばりはロックを難なく体現し、しかもそれすら自分の内側に相対化し、もっと大きな表現の先鋭を顕していた。
『ミソラヒバリ リズム歌謡を歌う1949-1967』はブギやロカビリーやラテンやロックを総なめにしてしまう天才歌手の一端を伺い知る事ができる企画CDである。
「リズム感がいい、というようなものではない。」
湯浅学氏の解説は美空ひばりがリズムで四苦八苦する数多の歌手と違う意識で表現を行っていた事を示唆するものだ。どんなリズムであれ、それは<自分化>すべきもの。できて当たり前。これが美空ひばりの常識である。得てして歌の露出過多に陥る日本歌謡の中でこれほどビートを中核に持った音楽は、ない。
「おそるべき音楽人、美空ひばり。その凄さはまだまだ真に解明されてはいない。」
美空ひばりを<マルチアスリート>と呼ぶ湯浅氏の解説の締めくくりのこの言葉はこの天才歌手を聴き込む必要性を私に今更ながら、確信させた。そして分かったのだが、美空ひばりは現在リリースされているCDだけでは、全くその魅力は掴めないという事。コロムビアレコードからリリースされた昭和30年代後半から少なくとも昭和53年頃までのオリジナルを生み出すサイクルが途切れなかった時期のLPを一つずつ探して聴かねばならない。それだけで50枚以上あるのだが。勿論、一番いいのは順にCD化される事だが、切に願う。